◎ここに一寸解せぬ問題が二つある(中山太郎)
雑誌『郷土研究』第二巻一号および二号(一九一四年一月、二月)から、中山太郎の論文「百済王族の郷土と其伝説」を紹介している。
本日は、その四回目。昨日までに紹介したのは「百済王族の郷土と其伝説(上)」(『郷土研究』第二巻一号、一九一四年一月)で、本日から、「百済王族の郷土と其伝説(下)」(『郷土研究』第二巻二号、一九一四年二月)の紹介に移る。
なお、【 】内は原ルビ。一部に疑問のものもあるが、すべて原文のままである。
百済王族の郷土と其伝説(下) 中 山 太 郎
▲桓武帝の母后と百済王族の栄達 桓武帝の母后新笠姫【にひかさひめ】は、百済王族の系統なる和朝臣【やまとのあそん】高野乙継【たかのおとつぐ】の女で、続紀【しよくき】によると、光仁〈コウニン〉帝潜龍【せんりよう】の時に納【い】れて妃となすとある。此皇后天津日嗣御子【あまつひつぎのみこ】を生み奉りてより、百済王族の一門遽【にわ】かに時めき出し、正一位の極位【きよくゐ】を贈らるゝもの二名、蕃人【はんじん】にして始めて相府【さうふ】に入るもの一名、後宮【こうきう】に召されし女御【によご】一名。遂に百済王族等者朕之外戚也今所以擢一両人加授爵位也との大詔が下るほどの栄達【えいたつ】見るに至つた。日本後紀の筆者〔藤原緒嗣ほか〕をして、中納言従三位和朝臣家麿薨、贈従二位大納言、家麿贈正一位高野朝臣乙継之孫也、其先百済国人也、為人木訥無才学以帝外戚特被擢進、蕃人入相府自此始と驚嘆させ、伴信友【ばんののぶとも】をして「蕃神考【はんしんこう】に京都の平野神社は桓武帝の母后を奉祀【ほうし】せるものなりと考証させるなどの素晴らしい勢【いきほひ】であつた。がこゝに一寸【ちよつと】解【げ】せぬ問題が二つある。一〈ヒトツ〉は桓武帝は百済王等は外戚なりとまで仰せあるにかゝはらず、「神皇正統記」に、日本と韓国と同じ国なりとの意味を記せる文書は桓武帝の朝〈チョウ〉に悉く焼棄せらると云ふことゝ一は百済永継【くだらのながつぐ】は初め藤原内麿〈フジワラノウチマロ〉に嫁し、真夏及び冬嗣の二子を儲け、後に桓武帝の女嬬【によじゆ】となられたことである。解せぬことは強ひて解する必要もないから、此侭にしてソツと片付て置くが、当時列聖の後宮【こうきう】に百済氏を見ること頓【とみ】に加り〈クワワリ〉、桓武帝には、教法教仁貞香の三妃あり、嵯峨帝には、貴命、慶命の二女御あり、仁明〈ニンミョウ〉帝に永慶の一妃あるなど、其の重【おも】なるものである。上〈カミ〉の好むところ、下〈シモ〉の流行をつくり、権門の間にも此の風をなし、御台所【みだいどころ】は百済に限りますよなどと飛んだところで出雲の神をまごつかせ、宮掖鶏障【きうえきけいしよう】の辺り〈アタリ〉頻りに、日百【にちはく】同盟が実行せられたのである。藤原継縄〈フジワラノツグタダ〉妻百済氏賜正四位と続紀にあるのは之が明徴で、川柳子の所謂あの面【つら】とぬかしたと女憤【いきどほ】りと云ふ手合でも、百済と云へば種切れとならんず捌【さば】け方、玉の輿【こし】屋も底を払ふとは目出度〈めでたき〉ことなり。【以下、次回】

















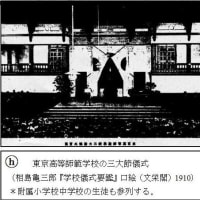
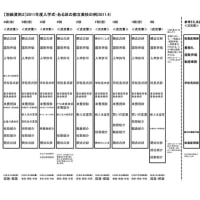
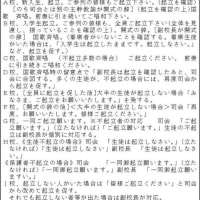








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます