◎狂言『唐人相撲』は日本の相撲とりが唐へ渡る噺
河原宏『伝統思想と民衆』(成文堂、1987)第三章「中世における民族意識と民衆文化」の「二 元寇と神国思想」から、「2 元寇の文芸への反映」の項を紹介している。本日は、その五回目(最後)。
ところで津田左右吉の批判の主要点は、『オディッシウス』の話の中心を占める冒険的航海譚が百合若物語にはないということだが、逍益はそれに答えて漂流譚の部分は切りはなされて御伽草子〈オトギゾウシ〉の『御曹子島渡〈オンゾウシシマワタリ〉』となったとする。
『御曹子島渡』は室町時代の娯楽的読物二十三種を集めた御伽草子に入れられたもので、御曹子源義経が千島へ渡り、鬼の大王から兵法書を手に入れる筋で、途中腰から上は馬、下は人の形をした生物の棲む馬人島、住民すべて裸のはだか島、女だけが住む女【によう】ごの島、小人のいるちいさご島、アイヌ語を用いたゑぞが島などをめぐって行く。ここにもあきらかに当時の海外関心のひろまりが反映している。同時にそれが元寇の余波をうつしていることは、「日本国は神国にてましませば」という神国思想と、「むくり退治のそのために」という詞にもあらわれている。逍遥もこの点で『御曹子島渡』が百合若物語と関係しているのではないか、とのべている。
その他、狂言『唐人相撲〈トウジンズモウ〉』は日本人の相撲とりが唐へ渡り、唐の皇帝を投げ飛ばす噺、謡曲『海士【あま】』では藤原淡海の妹が唐の皇帝の皇后になるなど、素朴ながら視野のひろがり、異国への関心の強さをしめしている。
おそらくこれらの諸作品はいずれも元寇以後、室町時代を通じて倭寇、八幡船〈バハンセン〉、日明貿易など、日本人の海外進出、海外交流の事実をなんらか反映して、単純な中華思想の受容に代る神国意識の下で、前近代ナショナリズムの産物だとみることができよう。
しかしこの時代の神国意識は、一般的にいえばこれまでものべてきたように、近代のそれとは異り武力の誇示や、極端な排外主我の傾向などは含まないものだつた。たとえば応永十五年(一四〇八年)、後小松〈ゴコマツ〉天皇の北山殿〈キタヤマドノ〉行幸の時の連歌には
【一行アキ】
今やすくもろこし船のかよひ来て
あひあふ君ぞ共に久しき
【一行アキ】
とあり、また文明五年(一四七三年)、幕府の連歌始めに
【一行アキ】
ながめやる海は入日を限にて
【一行アキ】
に足利義政の付句〈ツケク〉
【一行アキ】
松浦の沖につゞくもろこし
【一行アキ】
とある。ここによみ込まれている心象風景がいかにも平和で長閑〈ノドカ〉なことはもちろんだが、中国との心理的距離もさまざまな現実の交流を反映して著るしく近しいものになっている。日本の神国思想が、あくまで中国の中華思想を前提に成立している点からいえばそれも当然のことかもしれない。ただそれを、後代の排外的国家主義につながる思想系列の原点として、護教論的方向へ再構成したのは北畠親房〈キタバタケ・チカフサ〉の『神皇正統記〈ジンノウショウトウキ〉』である。〈196~198ページ〉
文中、「藤原淡海」の読みは未詳。この人物のモデルは、淡海公〈タンカイコウ〉のオクリナがある藤原不比等〈フジワラノフヒト〉であろう。

















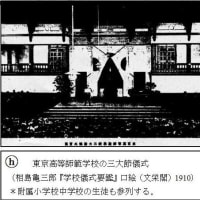
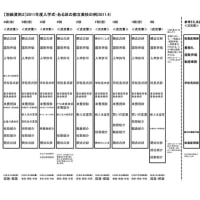
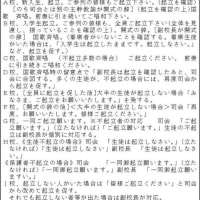








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます