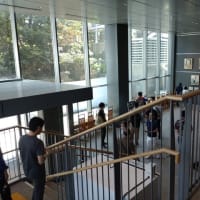行動した順に従うと6日の朝一番に訪れたのがチネテカです。これは前回説明した映像文化をテーマにした10haの大規模再開発の目玉施設といえるでしょう。
フィルムのアーカイブ(シネマテーク、収集保管施設)で付属の映画館(前回紹介した映画館リュミエール)や修復所、図書館を持っています。
案内してくれたのはAnna Fiaccariniさんです。私の耳にはアンナ**(聞き取れず)カリーナと聞こえました。もちろんゴダールの奥さんのアンナカリーナを思い出しました。フィルムアーカイブをアンナカリーナの案内で見学するというのもなかなか得難い体験です。
彼女は私たちが昨年訪ねたパリのシネマテーク(アメリカの売れっ子建築家でスペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館も設計したフランクゲーリーの作品です)にいたこともある研究者です。
チャップリン直筆の絵コンテを説明してくれています(上の写真)。
次の写真を見ればこの映画が「独裁者」であることがわかります。
さてAnna Fiaccariniさんの話から始めます。
いやその前にチネテカの図書館・アーカイブの建築について少々。
この部分は場であったはずです。1階は文献などが並んでいます。
2階にフィルムや絵コンテ、映像や音声テープなどの保管庫があります。
2階からの見降ろしです。
さてAnna Fiaccariniさんの説明です。
チネテカ は1967年に市の図書館に設置された映画に関するアーカイブが発展して出来た市の施設です。
井上ひさしさんの「ボローニャ紀行」などを読むと映画好きの人が作った協同組合がもとになっているものと思っていましたが、チネテカは純然たる市立の機関だそうです。
1995年に図書館から自立した施設としてこの再開発地区に移転してきました。最初は表通りのRiva di Renoに面した古い建物に本部があったようです。もしかしたら今も形式的な本部はReno通り沿いにあるのかもしれません。ちなみにReno通りはRivaという名前が示すように下に川・運河が流れているそうで、私のブログの<2011視察02>で紹介した川(運河?)につながっています。
このアーカイブの特徴はフィルムを集めるだけでなく、脚本、ポスター、撮影を記録する映像、ヴィデオ、映画関係の雑誌、近年はビデオゲームなどあらゆるものをコレクションしていることです。ボローニャ自体の古い写真も収集・公開しています。もちろん中でも有名なのはチャップリンに関するコレクションですが、彼に関する文書だけでも25万点を所蔵しているそうです。遺族も積極的にこのアーカイブに遺品を集中させようとしているようです。もちろん持続的な説得による信頼関係があってのことです。
収蔵品の中心となるフィルムだけでも6万本あるそうですが、それは別の倉庫に保管してあります。
このように充実しているのにはボローニャ大学が1970年代から映画史の研究やフィルム保存に取り組んでいたということも関係しているだろうとのことです。
また冒頭に述べたように、Anna Fiaccariniさんはヨーロッパの他の7つのアーカイブに関係した事があるとのことですがボローニャの一番の特徴は映画を保管する時にもフィルムだけでなく撮影に関関連する文書など周辺資料をきちんと収集することから始めるところだろうと指摘しています。
上の写真は映画監督アレッサンドロ・ブラゼッティに関する資料です。
珍しいものとしてはパゾリーニがアンナマニャーニと演出をめぐって議論している音声なども残っているそうです。またデカメロンのポスターに出ている俳優が実際に映画の中には出てこないのはなぜかなども研究し、今公開されているものが監督自身で公開直前にカットしたものであることなども解明したそうです。
当然黒沢、溝口などの資料もありますよと教えてくれました。
ボローニャは音楽の部門でユネスコの創造都市に認定されていますが、そればかりでなく映像文化に関しても市民の関心が非常に高い都市であるということです。
最後にAnna Fiaccariniさんにこの建物はアルドロッシの設計ですねと話題を向けてみました。建築の設計者など日本の人であれば知らないことが多いので、ちょっと聞いてみたのです。するとこの建物ができたときには彼は死んでいたので正確に言うと彼の事務所の設計ですね、とさらりと回答してくれました。彼女によると入口のロトンダが一番ロッシらしい空間です。私もそれに全く異論がありません。
この後訪れた社会センターの人たちも今度この地区にレンゾピアノ設計のオーディトリアムが計画されているんですよと建築家の名前を普通に会話に登らせていました。やはり自分たちが誇りに思っている美しいまちやまち並みをつくったきたプロフェッションに対して一定の敬意を払っているのでしょう。翻って(一般的な美醜の観点に従えば)決して美しいとはいえない日本の現代都市をつくってきたプロフェッションに日本の人たちが関心を払わないのもむべなるかなというところでしょうか。