『アキレスと亀』
製糸財閥の御曹子・倉持真知寿(吉岡澪皇)は絵を描くのが大好きな男の子。将来は画家を夢見ていたが、父親(中尾彬)の会社が倒産、一家はバラバラになってしまう。
青年になった真知寿(柳憂怜)は画商(大森南朋)の薦めで美術学校に通い、幸子(麻生久美子)という理解ある妻も得て創作活動に励むのだが、いっこうに絵は売れるようにならなかった。
ぐりは4歳のときから絵画教室に通っていた。正確には通わされていた。
母親が絵描きになりたかった夢を娘に投影して、音楽と同じように絵も小さいうちからと思ったのだろうが、いくら田舎のお絵描き教室といえども4歳の生徒なんて他にいるわけがない。教室の方でも持て余して、年長の子どもたちにはきちんとした課題が与えられてる横で、ひとり放ったらかしにされていたのをよく覚えている。
この教室は小学校に入ってすぐに辞めさせられた。辞めさせられた日のことはくっきりと記憶に残っていて、母の日のプレゼントにおかあさんの似顔絵を描きましょうといわれ、ぐりはいつものようにそれを無視して(というか描かなくて良いと判断して)勝手にお姫さまの絵を描いていた。教師もそれを咎めはしなかった。レッスンが終わって母親が迎えに来ると、他の子たちはその場で似顔絵をプレゼントした。ぐりの母親はぐりが描いたお姫さまの絵を見て烈火のごとく怒りだした。具体的な言葉までは覚えていないが、これではなんのために月謝を払って通わせているのかわからないではないかとか、そんなようなことをいったのだろうと思う。ぐりはなんでそんなに怒るんだろう?と不思議に思っていた。
絵画教室を辞めてもぐりを絵描きにしたい野望を諦められない母は、休日ごとにぐりを連れて近隣の地域で催される写生会や展覧会をまわり、ときには自ら写生場所を選んで絵を描かせた。小学生のころ、同級生たちが遊園地や動物園に連れて行かれている行楽日、ぐりは写生をしたり美術展鑑賞をしていた。
ぐりの母は真知寿の父のように「何でも好きなように自由に描け」という人ではなく、ぐりが描いた絵が少しでも気に入らないと無茶苦茶に怒った。ぐりが綺麗だなと思って選んだモチーフは彼女にとっては地味でどうでもいいものばかりで、ぐりが素敵だなと思って用いたタッチは彼女にとっては弱々しくアピール力に欠けていると判断された。子ども時代を通して、母がぐりの絵を褒めたことは一度もない。いつでも叱られ通しだった。スパルタである。
おかげで小中高を通して美術の成績は良かったし、なんだかんだでどうにかこうにか美大には進学したが、気がつけばぐりには自分で描きたいものなんかなんにもなかった。母親に褒められるため、学校でいい成績をとるため、コンクールで入賞するため、入試に合格するためなら絵は描ける。逆に目的がなければ、ぐりには絵を描くことに意味はまったくなかった。
それに気づいたときのショックは、今思い出してもとても淋しい。もしも6歳のときあのお絵描き教室を辞めてなかったらどうなっていただろう、なんてことは想像はしなかったけれど。
子どものころに画家になる夢を持たされた真知寿だが、他者から夢を持たされたという点ではぐりと彼は同じだ。
だが真知寿には「絵を描く目的」がなかった。あえていえば、ただただ好きなものを好きなだけ、画材のある限り描き続けることが目的だった。
映画の中で周囲の人はみんな真知寿の絵を観て「才能がない」というけれど、ぐりはそうは思わなかった。彼のように、心に浮かんだものを湯水のように描き続ける意欲とエネルギーを失わないでいられるのはそれだけで才能だし、とても幸せなことだと思う。少なくとも、ぐりには幸せに見えた。憎しみを感じるほど羨ましかった。こんな風に純粋に絵を描くことを愛せるなんて。絵を描くことにいっさいの迷いを持たずにいられるなんて。
ほんとうは真知寿だって迷ったり苦しんだりしているのかもしれないけど、映画には具体的には描かれていない。おそらく彼のそうした純粋さには、どこまでも黙ってついてきてくれる妻という存在の影響も大きかったのだろう。別のいい方をすれば、彼女がいたから、彼は芸術に必要なだけの孤独や挫折を知らずに過ごしてしまったのだろう。
ストーリー全体としては北野作品で初めてヒットしたという『HANABI』に似ている。あからさまに悲劇的で暴力的だった『HANABI』をネガとして、夫婦愛に悲劇と暴力を暗示したポジが『アキレス〜』といえるかもしれない。
ぐりは北野作品は全部はチェックしてないけど、今回のこの作品に関していえば完成度には若干の不満は残るものの、ストレートでわかりやすくて感動的な映画であるところに間違いはないと思う。ぐり個人としてはそう思うけど、絵を描くことに関心のない観客がどう感じるのかはよくわからない。
1点気になったのは、青年時代のパートと中年時代のパートの両方に薬物による死が登場するところ。直接的な表現ではなく前後の文脈からそう判断したのだが、これはしばしば芸術家がアルコールや薬物などの助けを得て創作するという現実に対する皮肉とも受取れるのだが、実際はどうなんだろう。ぐり的にはそれよりも、昨今目につくようになったまるで女優かミュージシャンのような“ビジュアル系”芸術家ブームを皮肉って欲しかったけどね。結局TVや雑誌でパーソナリティがネタになれば価値がつく、作品そのものの価値を判定することになんか誰もキョーミなーし、みたいな。
それにしても劇中に登場する絵の数がすごい。これ全部たけしが描いたのかー、と思うと労力だけでも圧倒されてしまう。ぐりはたけしの絵って好きでも嫌いでもないんだけど、アレって市場価値としてはどのくらいなんだろね?
製糸財閥の御曹子・倉持真知寿(吉岡澪皇)は絵を描くのが大好きな男の子。将来は画家を夢見ていたが、父親(中尾彬)の会社が倒産、一家はバラバラになってしまう。
青年になった真知寿(柳憂怜)は画商(大森南朋)の薦めで美術学校に通い、幸子(麻生久美子)という理解ある妻も得て創作活動に励むのだが、いっこうに絵は売れるようにならなかった。
ぐりは4歳のときから絵画教室に通っていた。正確には通わされていた。
母親が絵描きになりたかった夢を娘に投影して、音楽と同じように絵も小さいうちからと思ったのだろうが、いくら田舎のお絵描き教室といえども4歳の生徒なんて他にいるわけがない。教室の方でも持て余して、年長の子どもたちにはきちんとした課題が与えられてる横で、ひとり放ったらかしにされていたのをよく覚えている。
この教室は小学校に入ってすぐに辞めさせられた。辞めさせられた日のことはくっきりと記憶に残っていて、母の日のプレゼントにおかあさんの似顔絵を描きましょうといわれ、ぐりはいつものようにそれを無視して(というか描かなくて良いと判断して)勝手にお姫さまの絵を描いていた。教師もそれを咎めはしなかった。レッスンが終わって母親が迎えに来ると、他の子たちはその場で似顔絵をプレゼントした。ぐりの母親はぐりが描いたお姫さまの絵を見て烈火のごとく怒りだした。具体的な言葉までは覚えていないが、これではなんのために月謝を払って通わせているのかわからないではないかとか、そんなようなことをいったのだろうと思う。ぐりはなんでそんなに怒るんだろう?と不思議に思っていた。
絵画教室を辞めてもぐりを絵描きにしたい野望を諦められない母は、休日ごとにぐりを連れて近隣の地域で催される写生会や展覧会をまわり、ときには自ら写生場所を選んで絵を描かせた。小学生のころ、同級生たちが遊園地や動物園に連れて行かれている行楽日、ぐりは写生をしたり美術展鑑賞をしていた。
ぐりの母は真知寿の父のように「何でも好きなように自由に描け」という人ではなく、ぐりが描いた絵が少しでも気に入らないと無茶苦茶に怒った。ぐりが綺麗だなと思って選んだモチーフは彼女にとっては地味でどうでもいいものばかりで、ぐりが素敵だなと思って用いたタッチは彼女にとっては弱々しくアピール力に欠けていると判断された。子ども時代を通して、母がぐりの絵を褒めたことは一度もない。いつでも叱られ通しだった。スパルタである。
おかげで小中高を通して美術の成績は良かったし、なんだかんだでどうにかこうにか美大には進学したが、気がつけばぐりには自分で描きたいものなんかなんにもなかった。母親に褒められるため、学校でいい成績をとるため、コンクールで入賞するため、入試に合格するためなら絵は描ける。逆に目的がなければ、ぐりには絵を描くことに意味はまったくなかった。
それに気づいたときのショックは、今思い出してもとても淋しい。もしも6歳のときあのお絵描き教室を辞めてなかったらどうなっていただろう、なんてことは想像はしなかったけれど。
子どものころに画家になる夢を持たされた真知寿だが、他者から夢を持たされたという点ではぐりと彼は同じだ。
だが真知寿には「絵を描く目的」がなかった。あえていえば、ただただ好きなものを好きなだけ、画材のある限り描き続けることが目的だった。
映画の中で周囲の人はみんな真知寿の絵を観て「才能がない」というけれど、ぐりはそうは思わなかった。彼のように、心に浮かんだものを湯水のように描き続ける意欲とエネルギーを失わないでいられるのはそれだけで才能だし、とても幸せなことだと思う。少なくとも、ぐりには幸せに見えた。憎しみを感じるほど羨ましかった。こんな風に純粋に絵を描くことを愛せるなんて。絵を描くことにいっさいの迷いを持たずにいられるなんて。
ほんとうは真知寿だって迷ったり苦しんだりしているのかもしれないけど、映画には具体的には描かれていない。おそらく彼のそうした純粋さには、どこまでも黙ってついてきてくれる妻という存在の影響も大きかったのだろう。別のいい方をすれば、彼女がいたから、彼は芸術に必要なだけの孤独や挫折を知らずに過ごしてしまったのだろう。
ストーリー全体としては北野作品で初めてヒットしたという『HANABI』に似ている。あからさまに悲劇的で暴力的だった『HANABI』をネガとして、夫婦愛に悲劇と暴力を暗示したポジが『アキレス〜』といえるかもしれない。
ぐりは北野作品は全部はチェックしてないけど、今回のこの作品に関していえば完成度には若干の不満は残るものの、ストレートでわかりやすくて感動的な映画であるところに間違いはないと思う。ぐり個人としてはそう思うけど、絵を描くことに関心のない観客がどう感じるのかはよくわからない。
1点気になったのは、青年時代のパートと中年時代のパートの両方に薬物による死が登場するところ。直接的な表現ではなく前後の文脈からそう判断したのだが、これはしばしば芸術家がアルコールや薬物などの助けを得て創作するという現実に対する皮肉とも受取れるのだが、実際はどうなんだろう。ぐり的にはそれよりも、昨今目につくようになったまるで女優かミュージシャンのような“ビジュアル系”芸術家ブームを皮肉って欲しかったけどね。結局TVや雑誌でパーソナリティがネタになれば価値がつく、作品そのものの価値を判定することになんか誰もキョーミなーし、みたいな。
それにしても劇中に登場する絵の数がすごい。これ全部たけしが描いたのかー、と思うと労力だけでも圧倒されてしまう。ぐりはたけしの絵って好きでも嫌いでもないんだけど、アレって市場価値としてはどのくらいなんだろね?
















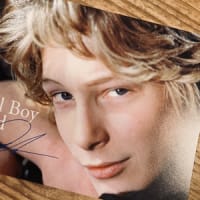



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます