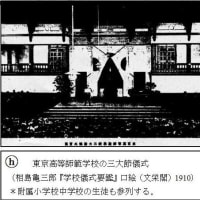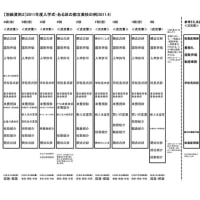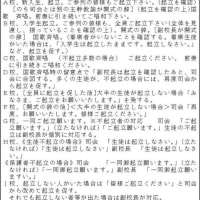◎血液型別かかりやすい病気と浅田一博士
藤田紘一郎氏に『血液型の科学』(祥伝社新書、二〇一〇)という著書がある。そのサブタイトルは「かかる病気、かからない病気」で、その第六章は、「血液型別・かかりやすい病気とその対策」となっている。
同書は、ザッと読んだだけにすぎず、その内容をよく理解しえたわけではないが、「血液型と体質」の相関、あるいは「血液型と疾病〈シッペイ〉」の相関を否定することは、今日の科学においては、かなり難しくなっているという印象を受けた。
こうしたテーマについて論ずる際、忘れてはならないのは、浅田一〈ハジメ〉という学者の名前である。というのは、浅田一は、一九二九年(昭和四)の段階で、早くも、「血液型と疾病」との相関を示唆していたからである。
浅田以前にも、こうした問題に気づいていた研究者がいたことは間違いない。一九二六年(大正一五)の平野林〈ハヤシ〉・矢島登美太〈トミタ〉の論文「人血球凝集反応ニ就テ」は、「身長、体重と血液型との相関関係」、「疾病と血液型との関係」などを調査していたという(松田薫『[血液型と性格]の社会史』一九九一による)。
浅田自身も、おそらくは、平野・矢島論文を含む先行研究によって、「血液型と疾病」の相関に注目したのであろう。しかし、この「相関」について、雑誌などで明確なメッセージを発し、かつ、他の研究者たちを刺激したのは、やはり浅田一という存在だったのではあるまいか。
ここで、浅田の文章を引いておこう。かな遣いなどは、少し直してある。
血液型と気質との間に密接なる関係のあることは、自分の調査した数十人の範囲でははなはだよく適中している。Aらしいと思った人がAでBらしい人はBであった。ところが血液型はこのほか疾病〈シッペイ〉すなわち体質と密接な関係がある。すなわちAB型の人は黴毒〈バイドク〉にかかるとなかなか治りがたい。いくら六〇六〔サルバルサン六〇六号〕を注射してもワ氏反応〔ワッセルマン反応〕がなかなかなくならない。そして変性黴毒たる脊髄癆〈セキズイロウ〉や麻痺性痴呆にもまたAB型が多い。すなわちAB型の人は黴毒に対してよほど警戒せねばならぬ。
O型の人およびB型の人は肺結核にかかりやすいという人が多い。肺結核にかかれば治りにくいというほうがよいかもしれぬ。大阪で結核に対してAO液というのが売出されて居るが、これは血液型の名称でなく有馬、大縄等創始者の名の頭字〈カシラジ〉であるらしい。悪性腫瘍にOが四七・九四%あるという報告がある。
発作性血色素尿症には何型が多いとはっきりわからぬがABが多いという人がある。黴毒と本症と関係があるとすればなおさら面白い。
悪性貧血にはAが四四・二%〔ママ〕
胆嚢〈タンノウ〉病にはOが五三・九一%
慢性潰瘍にはOが五九・三〇%
黄疸〈オウダン〉にはAが四七・九七%
あるという報告がある。
出典は、昨日のコラムでも引用した「最近に於ける血液型の知見の進歩に就て」(一九二九)。文章の末尾には、一五件の「参考文献」が挙げられているので、こうした問題に関心をお持ちの方には、閲覧をおすすめしたい。ただし、現在、そこに挙げられているような「参考文献」が、誰でもすぐ閲覧できる状態にあるのかどうかは不明である。
今日の名言 2012・7・13
◎人間は血液型によって、生まれながらにして免疫力の差があります
寄生虫学の大家で、『笑うカイチュウ』などの著書で知られる藤田紘一郎〈コウイチロウ〉さんの言葉。『血液型の科学』(祥伝社新書、二〇一〇)30ページより。藤田さんによれば、この「免疫力の差」が、結果的に、各血液型の性格を、一定の方向に向かわせているのだという。