◎A・フジモリ氏の両親は九州門徒地帯の出身
昨日、有元正雄氏の『宗教社会史への構想』(吉川弘文館、一九九七)という本から、富山の薬売りの話を紹介した。
同書の冒頭に、次のような話が出てくる。
一九九〇年五月、ペルーの大統領選挙が日本の新聞・テレビなどで大きく取扱われた。アルベルト・フジモリという熊本県からの移民二世が立候補していたからである。彼は選挙スローガンとして「正直・勤勉・技術」の三つを掲げ、ペルーの新しい国作りをこれによって実現しようと訴え、見事に当選した。
ちょうどこのころ、わたくしは真宗の宗教社会史に関する最初の論文を発表し、そのなかで真宗門徒の中心的な徳目は、正直・勤勉・節倹・忍耐の四つであるとしていた(拙稿「真宗門徒宗教社会史序説」)。彼の選挙スローガンと正直・勤勉の二つがダブっているので、彼の両親の宗旨を調べてみるとはたせるかな両親とも真宗門徒であった。A・フジモリの父藤森直一は一九二〇年ペルーに移民し、農園の綿摘み労働者として骨身を惜しまず働き、一九三四年嫁をもらいにいったん帰国し、親戚の井元ムツエと結婚して、ふたたびペルーに渡った。ちなみに、「門徒」〈モント〉というのは、浄土真宗の信者を指す言葉である。
ウィキペディアの「アルベルト・フジモリ」の項は、アルベルト・フジモリ氏の出自について、次のように書いている。
1938年ペルーの首都リマのミラフロレス区で仕立物屋を営む父・直一と母・ムツエの間に生まれる。両親は日本の熊本県飽託〈ホウタク〉郡河内〈カワチ〉村(現・熊本市河内町)出身であり、ペルーに1934年に移住した移民である。彼が誕生すると両親はリマの日本公使館に出生届を提出して日本国籍留保の意志を表したため、フジモリは日本国籍を保有することになった。
河内村は、飽託郡が成立する前は、飽田〈アキタ〉郡に属していた。有元氏の前掲書によれば、この飽田郡は、「九州門徒地帯」に位置づけられ、明治前期における「真宗寺院率」は、四〇%以上であるという。
有元氏が、アルベルト・フジモリ氏の両親の宗旨を、どのようにして調べたかは不明だが、おそらくその通りなのだろう。なお、有元氏が言及されている「真宗門徒宗教社会史序説」というのは、雑誌『思想』一九九〇年五月号(通巻第七九一号)掲載のご自身の論文を指す。

















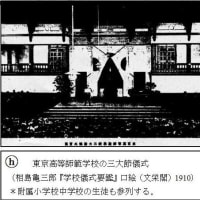
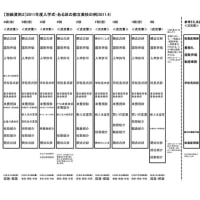
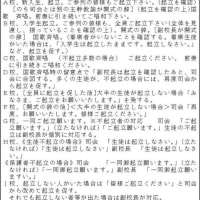








名人物に稲盛和夫氏がいます。彼は特に慎みの徳を説
いていながら、自分ではそれを忘れたのかいかにも聖人
ぶった言動を取り、自己を神格化しています。彼らの共通
点はそんなところにあると思われます。
ょうが、彼が寺社の利益のみに固執しているという点にお
いて「経営の神様」と呼ぶことはできないと思います。
因みに稲盛氏は、『生き方』なる本を出していますが、な
ぜ今さら、生き方を稲盛氏に教えて貰わなければならな
いのでしょうか?彼は、人類共通の生き方なるものを人に
教えることができるのだと思い上がっているとしか考えら
れません。