◎命がけで梵鐘を守った古刹の住職
一昨日、戦争末期には除夜の鐘が鳴らなかったという話を紹介した。これは、「金属供出」といって、軍需品の生産に欠かせない金属を、官公庁あるいは民間に提供させる措置がとられたからである。最初は、任意の供出であったが、一九四一年(昭和一六)には、国家総動員法(一九三八)に基く「金属類回収令」が定められたという。「金属類回収令」は、インターネット上に、その条文がある。
お寺の梵鐘も、もちろんその対象となった。しかし、すべての梵鐘が供出されたわけではない。国宝、国指定重要美術品となっているものは、供出を免れたという。また、中には次のような「例外」もあった。
これは、幣原喜重郎『外交五十年』(読売新聞社、一九五三)の中の一篇「鈴木貫太郎夫妻」に出てくる話である。
戦争中、軍需物資を造るというのでお寺の鐘とか、銅像とかあらゆる金属を民間から取りあげた。村にお寺が一つあり、その寺の釣鐘に白羽の矢が立った。それで村の者が行って、坊さんに釣鐘供出の話をした。坊さんは黙って聞いて居ったが、「それば不可ません〈イケマセン〉。私は承知出来ません。この寺は古い寺で、徳川の何代ごろからのもので、もう三百年も前から今月に至るまで、朝夕に撞くこの鐘の音というものは、実に音と今を繋ぐ一つの連鎖なんです。もしこの鐘を持って行かれたら、もうこの音は聞かれない。うすればこの寺は潰れた〈ツブレタ〉と同じです。そしてそれは私が死んだと同じことです。私としては鐘を供出することは絶対に出来ません」といって、坊さんはどうしても釣鐘を引渡さない。村の者は弱って、われわれが幾ら談判〈ダンパン〉しても、坊さんに言い負かされてしまう。これは鈴木〔貫太郎〕大将に頼んで説諭して貰う外はないというので、ぞろぞろ東京へやって来た。
鈴木君は、どういう事かよく判らんが、一度帰って話を聞いて見ようと、日曜に関宿〈セキヤド〉へ帰って、坊さんを尋ねた。そして「あなたが釣鐘を献納なさらんそうで、村民が県庁に対して申訳ないといつて、私のところへ訴えて来たが、あなたはどういうお考えですか」というと、坊さんは「あなたは私が献納する方がいいとお思いですか」と反問する。鈴木君は、「イヤ、私はその判断をするのじゃない。村の者がいって来たから、それを伝えただけだ」といった。すると坊さんは暫らく黙然と考えていたがつと立って出て行った。いつまで経って帰って来ない。何か不安な気がして、本堂の方へ行って見たら、坊さんは仏像の前へ坐って、短刀を側へ置き、昔風の切腹の様子である。あわや短刀を抜こうとする。鈴木君が飛込む。危ういところで坊さんの一命を取止めた、そうして、「イヤ、あなたの心持ちは判った。私は何も鐘を献納しろといいに来たのじゃない。しかしあなたがそれほど自分の生命を投げ出しても、法を護ろうとする真情は実に神聖なものだ。宜しい。これからは村の者が何といっても、この鈴木が承知しませんから」といって、坊さんをなだめた。
それから彼は村の者を寺へ呼出して、「この坊さんは実に尊い人だ。こんな人は日本に滅多に居らん。この尊い坊さんを、お前らが寄ってたかって殺すようなことになりかけた。今後二度とこんな事を申出てはならん。この鈴木が承知せん」と、厳然と申渡した。坊さんは感動する。村の連中はワアワア泣き出す。それは実に劇的な光景であった。
この鈴木大将というのは、終戦時の首相として知られる鈴木貫太郎のことである。二・二六事件の際、瀕死の重傷を負った鈴木が、夫人のセイキ術によって蘇生したという話は、一一月三〇日のコラムで紹介したことがある。
今日の名言 2012・12・28
◎この鐘の音というものは、実に音と今を繋ぐ一つの連鎖なんです
戦時中に梵鐘の供出に応じようとしなかった古刹の住職の言葉。上記コラム参照。この古刹が何という寺か、この梵鐘は、その後、重要美術品に指定されたのか、などのセンサクは、今回あえておこなわなかった。

















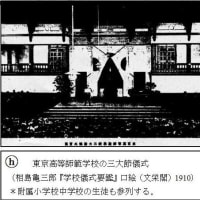
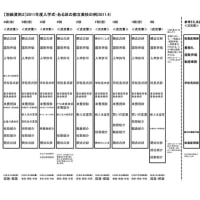
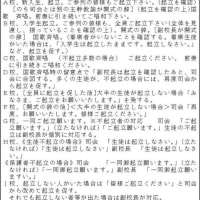








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます