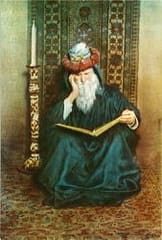2010(平成22)年7月11日、政権交代後初の大形国政選挙となる第22回参議院議員通常選挙の投票が行なわれ、その結果が開票された。
民主党は改選54議席を大きく下回って44議席にとどまり、国民新党も含めた与党の議席数は過半数を割り込んだ。一方、昨年野党に転落した自民党は予想を上回り51議席を確保し改選議席で第1党になった。これで、国会は、衆参各院で多数派となる完全な「ねじれ」状態になった。前自・公政権時の「ねじれ」とは異なり、今の民・国連立政権は衆議院での2/3以上の議席数を確保していないため、今後の政局は前自・公連立政権時代の「ねじれ」以上の大混乱が予測される。いや、「ねじれ」だけでは収まらず、政界再編の波が押し寄せてくるやもしれない・・・。
昨・2009(平成21)年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、子ども手当、高速道路の無料化などを政権公約に掲げて戦い、選挙前の予想を大幅に上回る308議席を獲得し衆議院第一党となった民主党。その民主党を中心とする鳩山由紀夫内閣は当初、70%を超す国民の高い支持率を得てスタートし、発足直後からCO2削減目標の引き上げ、自衛隊インド洋派遣の撤退、公共事業の見直しなどの政策(鳩山由紀夫内閣の政策を参照)を積極的に推し進めたが、首相自身や小沢氏(当時幹事長)の政治資金に関する問題もあり、国会は混乱、8ヵ月間で支持率は20%以下に低下。普天間基地移設問題では自民党政権時代の日米合意をくつがえし基地の県外移設を追い求めたが実現できず、ほぼ自民党の原案に近い状態で米側と決着、そのことに当然のことながら沖縄県民は猛反発している。この首相の迷走と対応のまずさは、社会民主党の連立離脱を招き、鳩山政権の支持率も急速に低下、迫る参議院選を前に人気回復のため、沖縄問題と自らの政治資金問題などの責任をとる形で、強引に小沢幹事長をも道連れにする形で首相の座をおり、2010年6月4日に鳩山内閣総辞職。後任には副首相の菅直人氏が、民主党新代表に指名され、6月8日に菅内閣が発足した。
野党となった自由民主党総裁の谷垣禎一氏からは、衆議院本会議で(著書に書いたことと異なり、与党内での政権たらい回しであり)「言行不一致である」との追及を受けていた。
それは、鳩山政権時代の副総理・国家戦略担当大臣であった当時の彼の著書『大臣 増補版』(岩波新書)の中で「政策的に行き詰ったり、スキャンダルによって総理が内閣総辞職を決めた場合は、与党内で政権のたらいまわしをするのではなく、与党は次の総理候補を決めたうえで衆議院を解散し、野党も総理候補を明確にしたうえで総選挙に挑むべきだろう」・・・と述べていることを言っているのだ。自民党自体がやって来たことを民主党がやったからと言って、「よく言うわ・・・」といった感じではあるが、そのことをさんざん野党時代に非難していたものが、政権交代をし、自らの本でまで非難をするなど、大変立派なことを仰っている以上、菅氏が本当に心底そう思っておられたのであるなら政権移譲時に、何故鳩山氏に解散・総選挙を実施するよう進言しなかったのか・・・と、私も思っている。最も、自民党がしたと同じように、反小沢勢力(以下参考の※1、※2、※3など参照)に担がれて、当然、菅氏が選ばれることが分かっていての形式的な、急な民主党代表選は演じられているが・・・。この菅氏を担いだ半小沢勢力と言われる人達も、本気で菅氏を総裁になる人物、適任者であるからと本気で思って担いでいるとは到底思えず、残り僅か、9月の民主党代表選まで菅氏を担ぎ、その間に自分の名前を売っておき、代表選には総裁候補として争おうと計算づくでやっている人達の心の中は、見え見え・・・だ。
鳩山氏が、小沢氏を道連れにしてまで、菅氏に政権を移譲したのは、あくまでも、この参議院選にどうしても勝ちたいが為であり、鳩山氏・いや小沢氏にとっても、いわば、菅内閣は選挙管理内閣的なものと考えていたはずだ。それを、どう勘違いしたのか、切れ菅からズル菅に変身した彼は、サミットへの参加もあって、急に自分が偉くなったと勘違いしているようだ。
私の記憶では、彼はかっての自民党政権時代に「かいわれ」を食べた大臣ぐらいの存在であり、鳩山政権になってからは、鳩山氏が沖縄問題で苦労しているときには、副首相でありながら、私は何も関係が有りませんといった感じで傍観し、世界の中でも日本だけは、デフレ経済が進行し、円高に株安と深刻な経済状況の中にあるにもかかわらず、財務大臣になってからも、なんの有効な手立てもせず、副首相として、ポスト鳩山の地位を狙い、ただただ失敗をしないことだけを心がけ、官僚は馬鹿だとし公言ていた経済用語もわからない経済音痴は、官僚の力を借りないと何も出来ずに、官僚を使いこなすどころか、官僚は優秀だと褒め称え彼らに利用されながら、虎視眈々と次期首相の座を狙っていた。そして、首相になると、かっての自民党政権と同じような強引な手法で予算を決めるなどの国会運営を行い、選挙にはいるや、選挙前に十分な審議もしないままに唐突な「消費税10%」発言を行いこれを争点化し、それに対する批判が行なわれると、その言い訳にやっきとなっていた。
二人区に2人の民主党候補者が立てたことに対しての小沢批判も有るが、小沢は本気で参議院選に勝ちに行っていた。どんなに立派なことを述べようと、政治の世界、数がなければ何も出来ない。民主党が本当に自分達の理想とする政治を行なおうとすれば、良くても悪くても数を制しない限りは実行できない。小沢はそれを一番良く知っている。
無党派層が民主党離れをした。それが、2人区の組織票を持たない無党派の民主党立候補者が敗れた原因であるが、その原因を作った最大の要因は菅氏の突然の消費税10%論とそれに反発した人達への言い訳や弁解の迷走振りと強引な国会運営である。それが証拠に、鳩山から菅への政権移譲で支持率は相当回復していたのだから・・・。
12日朝日新聞朝刊にも書いてあったが、このような中での選挙でいざ投票となると、誰に投票したら少しは政治がましになるのかと、国民にとって選ぶのにこれほど難しい選挙はなかっただろう。
前回選挙の衆議院選挙で、選挙民の一票が政治を変え、政権交代まで実現することを知ったのだから・・・。その結果が、民主党とズル菅が独走しないようにとブレーキをかけた。
消費税論議をすることが悪いわけではない。もうぼちぼち、方法論は別として消費税率アップなどの増税のこと考えなくてはいけない時期に日本が来ていることぐらいは、日本国民の多くは承知している。しかし、何故10%なのか、消費税論議をする前に、民主党はどれだけ政治や行政改革に取り組み実行したのか・・・。
自動仕分けなど評価の出来ることもあるもののこれといった大きな改革には手をつけていない。子供手当の問題にしても、選挙目当てのバラマキのように、お金がありすぎて困っている鳩山家の孫にまで子供手当を支給するほど日本の財政が豊かではないとを、国民の多くは知っており、増税をしてまでこのような手当を望んではいなかった。本当に困っている人には支給すればよいし、少しでも子供が生み易い環境を作るには、子供手当意外に幾らでも方法論があることを指摘していた。しかし、自分たちが昨年の選挙で約束した「マニフェストを守る」と言う大義名分を建前に、選挙に勝つために役立ちそうなバラマキだけを実行して、選挙のどさくさ紛れに、消費税アップを狙うなどのやり方は、国民を馬鹿にするにも程がある。
去年の選挙で、野党であったが故に財政状況などがわからずに実施が困難となったものについては、そのことを国民に素直に詫びれば良いことである。自分たちの面子を守るだけの為に、膨大な額の税金を使われたのではたまらない。
私も、去年は、民主党に期待したからこそ、1票を入れさせてもらった。しかし、金のありすぎて世間のことも何も分からない人や、経済のことは何も判らず口先だけは達者でただ要領が良いだけの人や、物覚えが良くて東大を出たものの、世間のことはさっぱりの理屈人間ばかりが、選挙に勝ち与党になると、自民党以上の独善的な手法で政治をしようとするなど、勝手なことを黙ってさせるわけにはゆかない。
今、世界の中でも例のないデフレから脱却できずにもがいている日本は経済の活性化なしに、失業問題も福祉も何もあったものではない。次の衆議院選挙まで、3年以上ある。今の小ざかしいだけの人達に好きなように政治を任せ迷走を繰り返していると、日本は本当に沈没しかねないと心配している。もっとリーダーシップのあるものが党を率いるべきである。
(画像は、7月12日記者会見する菅首相、朝日新聞掲載写真をちょっとかいわれでお飾り)、
参考:
※1:民主党内『小沢vs反小沢』勢力図予測:2010参院選候補者編
http://blog.trend-review.net/blog/2010/07/001685.html
※2:なぜここに来て大手マスコミと民主党内反小沢勢力が「小沢幹事長辞任」要求の世論誘導に踏み切ったのか?』
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=228733
※3:「あの人が煽動」小沢側近が“黄門様”渡部氏を痛烈批判
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100219/plt1002191209000-n2.htm
"策士"菅直人が「9月再選後」に狙う「消費税10%増税」選挙
http://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10569119109.html
討論×闘論 " 記事アーカイブ " 「疑似政権交代」か「たらい回し」か
http://blogs.jp.reuters.com/blog/2010/06/02/%E3%80%8C%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9%E4%BA%A4%E4%BB%A3%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%80%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%84%E5%9B%9E%E3%81%97%E3%80%8D%E3%81%8B/
第22回参議院議員通常選挙 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC22%E5%9B%9E%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99
民主党は改選54議席を大きく下回って44議席にとどまり、国民新党も含めた与党の議席数は過半数を割り込んだ。一方、昨年野党に転落した自民党は予想を上回り51議席を確保し改選議席で第1党になった。これで、国会は、衆参各院で多数派となる完全な「ねじれ」状態になった。前自・公政権時の「ねじれ」とは異なり、今の民・国連立政権は衆議院での2/3以上の議席数を確保していないため、今後の政局は前自・公連立政権時代の「ねじれ」以上の大混乱が予測される。いや、「ねじれ」だけでは収まらず、政界再編の波が押し寄せてくるやもしれない・・・。
昨・2009(平成21)年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、子ども手当、高速道路の無料化などを政権公約に掲げて戦い、選挙前の予想を大幅に上回る308議席を獲得し衆議院第一党となった民主党。その民主党を中心とする鳩山由紀夫内閣は当初、70%を超す国民の高い支持率を得てスタートし、発足直後からCO2削減目標の引き上げ、自衛隊インド洋派遣の撤退、公共事業の見直しなどの政策(鳩山由紀夫内閣の政策を参照)を積極的に推し進めたが、首相自身や小沢氏(当時幹事長)の政治資金に関する問題もあり、国会は混乱、8ヵ月間で支持率は20%以下に低下。普天間基地移設問題では自民党政権時代の日米合意をくつがえし基地の県外移設を追い求めたが実現できず、ほぼ自民党の原案に近い状態で米側と決着、そのことに当然のことながら沖縄県民は猛反発している。この首相の迷走と対応のまずさは、社会民主党の連立離脱を招き、鳩山政権の支持率も急速に低下、迫る参議院選を前に人気回復のため、沖縄問題と自らの政治資金問題などの責任をとる形で、強引に小沢幹事長をも道連れにする形で首相の座をおり、2010年6月4日に鳩山内閣総辞職。後任には副首相の菅直人氏が、民主党新代表に指名され、6月8日に菅内閣が発足した。
野党となった自由民主党総裁の谷垣禎一氏からは、衆議院本会議で(著書に書いたことと異なり、与党内での政権たらい回しであり)「言行不一致である」との追及を受けていた。
それは、鳩山政権時代の副総理・国家戦略担当大臣であった当時の彼の著書『大臣 増補版』(岩波新書)の中で「政策的に行き詰ったり、スキャンダルによって総理が内閣総辞職を決めた場合は、与党内で政権のたらいまわしをするのではなく、与党は次の総理候補を決めたうえで衆議院を解散し、野党も総理候補を明確にしたうえで総選挙に挑むべきだろう」・・・と述べていることを言っているのだ。自民党自体がやって来たことを民主党がやったからと言って、「よく言うわ・・・」といった感じではあるが、そのことをさんざん野党時代に非難していたものが、政権交代をし、自らの本でまで非難をするなど、大変立派なことを仰っている以上、菅氏が本当に心底そう思っておられたのであるなら政権移譲時に、何故鳩山氏に解散・総選挙を実施するよう進言しなかったのか・・・と、私も思っている。最も、自民党がしたと同じように、反小沢勢力(以下参考の※1、※2、※3など参照)に担がれて、当然、菅氏が選ばれることが分かっていての形式的な、急な民主党代表選は演じられているが・・・。この菅氏を担いだ半小沢勢力と言われる人達も、本気で菅氏を総裁になる人物、適任者であるからと本気で思って担いでいるとは到底思えず、残り僅か、9月の民主党代表選まで菅氏を担ぎ、その間に自分の名前を売っておき、代表選には総裁候補として争おうと計算づくでやっている人達の心の中は、見え見え・・・だ。
鳩山氏が、小沢氏を道連れにしてまで、菅氏に政権を移譲したのは、あくまでも、この参議院選にどうしても勝ちたいが為であり、鳩山氏・いや小沢氏にとっても、いわば、菅内閣は選挙管理内閣的なものと考えていたはずだ。それを、どう勘違いしたのか、切れ菅からズル菅に変身した彼は、サミットへの参加もあって、急に自分が偉くなったと勘違いしているようだ。
私の記憶では、彼はかっての自民党政権時代に「かいわれ」を食べた大臣ぐらいの存在であり、鳩山政権になってからは、鳩山氏が沖縄問題で苦労しているときには、副首相でありながら、私は何も関係が有りませんといった感じで傍観し、世界の中でも日本だけは、デフレ経済が進行し、円高に株安と深刻な経済状況の中にあるにもかかわらず、財務大臣になってからも、なんの有効な手立てもせず、副首相として、ポスト鳩山の地位を狙い、ただただ失敗をしないことだけを心がけ、官僚は馬鹿だとし公言ていた経済用語もわからない経済音痴は、官僚の力を借りないと何も出来ずに、官僚を使いこなすどころか、官僚は優秀だと褒め称え彼らに利用されながら、虎視眈々と次期首相の座を狙っていた。そして、首相になると、かっての自民党政権と同じような強引な手法で予算を決めるなどの国会運営を行い、選挙にはいるや、選挙前に十分な審議もしないままに唐突な「消費税10%」発言を行いこれを争点化し、それに対する批判が行なわれると、その言い訳にやっきとなっていた。
二人区に2人の民主党候補者が立てたことに対しての小沢批判も有るが、小沢は本気で参議院選に勝ちに行っていた。どんなに立派なことを述べようと、政治の世界、数がなければ何も出来ない。民主党が本当に自分達の理想とする政治を行なおうとすれば、良くても悪くても数を制しない限りは実行できない。小沢はそれを一番良く知っている。
無党派層が民主党離れをした。それが、2人区の組織票を持たない無党派の民主党立候補者が敗れた原因であるが、その原因を作った最大の要因は菅氏の突然の消費税10%論とそれに反発した人達への言い訳や弁解の迷走振りと強引な国会運営である。それが証拠に、鳩山から菅への政権移譲で支持率は相当回復していたのだから・・・。
12日朝日新聞朝刊にも書いてあったが、このような中での選挙でいざ投票となると、誰に投票したら少しは政治がましになるのかと、国民にとって選ぶのにこれほど難しい選挙はなかっただろう。
前回選挙の衆議院選挙で、選挙民の一票が政治を変え、政権交代まで実現することを知ったのだから・・・。その結果が、民主党とズル菅が独走しないようにとブレーキをかけた。
消費税論議をすることが悪いわけではない。もうぼちぼち、方法論は別として消費税率アップなどの増税のこと考えなくてはいけない時期に日本が来ていることぐらいは、日本国民の多くは承知している。しかし、何故10%なのか、消費税論議をする前に、民主党はどれだけ政治や行政改革に取り組み実行したのか・・・。
自動仕分けなど評価の出来ることもあるもののこれといった大きな改革には手をつけていない。子供手当の問題にしても、選挙目当てのバラマキのように、お金がありすぎて困っている鳩山家の孫にまで子供手当を支給するほど日本の財政が豊かではないとを、国民の多くは知っており、増税をしてまでこのような手当を望んではいなかった。本当に困っている人には支給すればよいし、少しでも子供が生み易い環境を作るには、子供手当意外に幾らでも方法論があることを指摘していた。しかし、自分たちが昨年の選挙で約束した「マニフェストを守る」と言う大義名分を建前に、選挙に勝つために役立ちそうなバラマキだけを実行して、選挙のどさくさ紛れに、消費税アップを狙うなどのやり方は、国民を馬鹿にするにも程がある。
去年の選挙で、野党であったが故に財政状況などがわからずに実施が困難となったものについては、そのことを国民に素直に詫びれば良いことである。自分たちの面子を守るだけの為に、膨大な額の税金を使われたのではたまらない。
私も、去年は、民主党に期待したからこそ、1票を入れさせてもらった。しかし、金のありすぎて世間のことも何も分からない人や、経済のことは何も判らず口先だけは達者でただ要領が良いだけの人や、物覚えが良くて東大を出たものの、世間のことはさっぱりの理屈人間ばかりが、選挙に勝ち与党になると、自民党以上の独善的な手法で政治をしようとするなど、勝手なことを黙ってさせるわけにはゆかない。
今、世界の中でも例のないデフレから脱却できずにもがいている日本は経済の活性化なしに、失業問題も福祉も何もあったものではない。次の衆議院選挙まで、3年以上ある。今の小ざかしいだけの人達に好きなように政治を任せ迷走を繰り返していると、日本は本当に沈没しかねないと心配している。もっとリーダーシップのあるものが党を率いるべきである。
(画像は、7月12日記者会見する菅首相、朝日新聞掲載写真をちょっとかいわれでお飾り)、
参考:
※1:民主党内『小沢vs反小沢』勢力図予測:2010参院選候補者編
http://blog.trend-review.net/blog/2010/07/001685.html
※2:なぜここに来て大手マスコミと民主党内反小沢勢力が「小沢幹事長辞任」要求の世論誘導に踏み切ったのか?』
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=228733
※3:「あの人が煽動」小沢側近が“黄門様”渡部氏を痛烈批判
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100219/plt1002191209000-n2.htm
"策士"菅直人が「9月再選後」に狙う「消費税10%増税」選挙
http://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10569119109.html
討論×闘論 " 記事アーカイブ " 「疑似政権交代」か「たらい回し」か
http://blogs.jp.reuters.com/blog/2010/06/02/%E3%80%8C%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%94%BF%E6%A8%A9%E4%BA%A4%E4%BB%A3%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%80%8C%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%84%E5%9B%9E%E3%81%97%E3%80%8D%E3%81%8B/
第22回参議院議員通常選挙 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC22%E5%9B%9E%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99