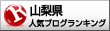昨日の続き、公民館の研修旅行の記録です。
東京スカイツリーを見物した後、バスで向かったのは浅草。
雷門近くの天ぷら屋さん(葵丸進)で昼食をとりました。
表には「45分待ち」という看板が掲げてあり、中にも大勢のお客さんが待っていましたが、団体予約客なのですぐに3階に通され天ぷら定食をいただくことができました。

スケジュールの都合上、浅草には一時間半しかいられないため、食事もそこそこに浅草寺に向かいました。
雷門は天ぷら屋さんから徒歩3分という驚くような近さ。
前にも書きましたが、新装なった雷門の前は、大勢の見物客でいっぱい。
雷門の隣のお店で浅草名物「雷おこし」をお土産に購入。

浅草寺本堂へと続く仲見世通りもけっこうな人出でした。
師走というので来年の干支である大きな絵馬が掲げてあったのでパチリ。
「ああ、来年は還暦だ」という想いがよぎります。

仲見世通りの先には宝蔵門、通称仁王門があります。
この先写真はありませんが、しっかりとお参りをしてきました。

最後の観光場所は江戸東京博物館。
浅草からはものの数分間走っただけで墨田区横綱(両国国技館のすぐ近くです)にある博物館に到着。
バスを降りて一気に6階までエスカレーターで上がります。

6階から5階を含む景色はこんな感じ。
右手にある橋を渡って展示場に向かいます。

橋の右手からは明治時代の新聞社「朝野新聞」の社屋を復元した建物が見えます。
ちょうど今「翔ぶが如く」を読み返しているので、興味を持って写真を撮りましたが、そうでない人には「何のこっちゃ?」の建物かもしれません。

「失われつつある歴史遺産を守るとともに、東京の歴史と文化をふりかえることによって、未来の東京を考える博物館」という趣旨に添い、江戸時代から明治大正昭和にいたる様々な資料が展示されています。
写真は江戸時代の町並みを描いた大きな屏風。

6階は江戸ゾーンでまずは武家屋敷の大きなジオラマが見物客を迎えてくれます。
幕末四賢侯のひとり松平春嶽を生んだ越前松平家の大きな屋敷の模型。
大きな門と言い、壮大な屋根と言い、またたくさんの部屋を持ち、さすがに徳川御家門の屋敷のスケールはすごいです。

隣に展示してあるのが忠臣蔵で有名な松の廊下。
おお、ここで浅野内匠頭が吉良上野介に切りかかったのか!

江戸時代の城下のジオラマも多数展示されています。
ここだけでもゆっくりと時間をかけて眺めたい。

路上の人形たちのアップ。
飾られている人形一つ一つが色々な物語を演じているようで、いくら見ていても見飽きないのですが、時間もないので先へと急ぎます。

江戸時代の商家、農家、工芸品、風俗の模様などをさまざま鑑賞しながら、5階の東京ゾーンへ。
浅草にあった通称「十二階(凌雲閣)」の何十分の一かのミニチュア(と呼ぶにはあまりにも大きい)が目立ちます。
その後、時代は関東大震災を経て太平洋戦争、戦後の復興、高度経済成長の時代の展示と続くのですが、このあたりは本当に駆け足で通り過ぎざるを得ませんでした。残念!
やはり一時間半では足りません。今度またゆっくりと訪れたいと思います。
というわけで、3か所の見物を終わり、バスは予定通り山梨に帰ってきました。
あわただしい旅行でしたが、私にとってはなかなか楽しい旅でした。
東京スカイツリーを見物した後、バスで向かったのは浅草。
雷門近くの天ぷら屋さん(葵丸進)で昼食をとりました。
表には「45分待ち」という看板が掲げてあり、中にも大勢のお客さんが待っていましたが、団体予約客なのですぐに3階に通され天ぷら定食をいただくことができました。

スケジュールの都合上、浅草には一時間半しかいられないため、食事もそこそこに浅草寺に向かいました。
雷門は天ぷら屋さんから徒歩3分という驚くような近さ。
前にも書きましたが、新装なった雷門の前は、大勢の見物客でいっぱい。
雷門の隣のお店で浅草名物「雷おこし」をお土産に購入。

浅草寺本堂へと続く仲見世通りもけっこうな人出でした。
師走というので来年の干支である大きな絵馬が掲げてあったのでパチリ。
「ああ、来年は還暦だ」という想いがよぎります。

仲見世通りの先には宝蔵門、通称仁王門があります。
この先写真はありませんが、しっかりとお参りをしてきました。

最後の観光場所は江戸東京博物館。
浅草からはものの数分間走っただけで墨田区横綱(両国国技館のすぐ近くです)にある博物館に到着。
バスを降りて一気に6階までエスカレーターで上がります。

6階から5階を含む景色はこんな感じ。
右手にある橋を渡って展示場に向かいます。

橋の右手からは明治時代の新聞社「朝野新聞」の社屋を復元した建物が見えます。
ちょうど今「翔ぶが如く」を読み返しているので、興味を持って写真を撮りましたが、そうでない人には「何のこっちゃ?」の建物かもしれません。

「失われつつある歴史遺産を守るとともに、東京の歴史と文化をふりかえることによって、未来の東京を考える博物館」という趣旨に添い、江戸時代から明治大正昭和にいたる様々な資料が展示されています。
写真は江戸時代の町並みを描いた大きな屏風。

6階は江戸ゾーンでまずは武家屋敷の大きなジオラマが見物客を迎えてくれます。
幕末四賢侯のひとり松平春嶽を生んだ越前松平家の大きな屋敷の模型。
大きな門と言い、壮大な屋根と言い、またたくさんの部屋を持ち、さすがに徳川御家門の屋敷のスケールはすごいです。

隣に展示してあるのが忠臣蔵で有名な松の廊下。
おお、ここで浅野内匠頭が吉良上野介に切りかかったのか!

江戸時代の城下のジオラマも多数展示されています。
ここだけでもゆっくりと時間をかけて眺めたい。

路上の人形たちのアップ。
飾られている人形一つ一つが色々な物語を演じているようで、いくら見ていても見飽きないのですが、時間もないので先へと急ぎます。

江戸時代の商家、農家、工芸品、風俗の模様などをさまざま鑑賞しながら、5階の東京ゾーンへ。
浅草にあった通称「十二階(凌雲閣)」の何十分の一かのミニチュア(と呼ぶにはあまりにも大きい)が目立ちます。
その後、時代は関東大震災を経て太平洋戦争、戦後の復興、高度経済成長の時代の展示と続くのですが、このあたりは本当に駆け足で通り過ぎざるを得ませんでした。残念!
やはり一時間半では足りません。今度またゆっくりと訪れたいと思います。
というわけで、3か所の見物を終わり、バスは予定通り山梨に帰ってきました。
あわただしい旅行でしたが、私にとってはなかなか楽しい旅でした。