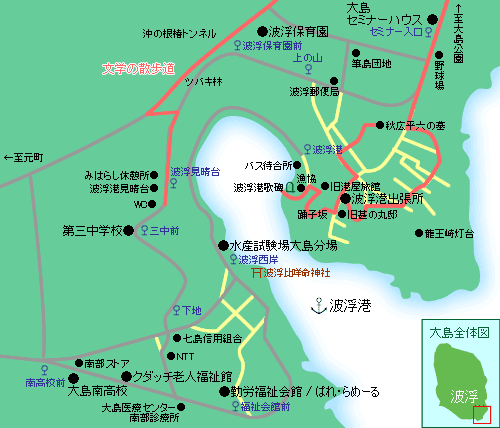今回のイタリア豪華客船の座礁、横転事故で、約4200人もの乗客と乗員が救命ボートで助け出されました。幸いにも港が近かった上、完全に横転するまでにかなり時間があり救命ボートにほぼ全員が乗り移れたのです。しかし11人の死者と21人の行方不明者が出てしまいました。
「救命ボート」を検索すると大小さまざまな種類のボートが写真付きで紹介してあります。そこで大型客船の両側の舷側に吊り下げてある救命ボートの写真を下に示します。
上は日本の豪華客船、「飛鳥」の写真です。そして下は北欧の豪華客船の写真です。
救命ボートの操作は船員がします。しかしその船員が操作方法を知らない場合もあります。今回もあるボートではそんな事態があり、乗客が操作したという報告もありました。
乗客は自分の部屋番号によって乗る救命ボートが決まっています。避難訓練が必ずあり、部屋の救命胴衣を身につけて自分の乗るボートまで迅速に駆けつける訓練をします。そうすると担当の船員が、ボートへの乗り方や海面への降ろし方を説明します。上の写真のように完全密閉式の覆いがついていて乗船口が小さいのです。はたして混乱状態で無事乗り込めるのかが心配になります。乗り込んだ後は船員が船の上から遠隔操作でクレーンのワイヤを伸ばして海面におろします。エンジンを始動させてからフックを外します。その後は急いで本船から離れます。
救命ボートには食料、水、蒸留機、通信機、発煙信号機、GPSなどが積んであり、1週間位の漂流には耐えられます。
上の写真の救命ボートの定員は40名から50名のように見えますが、すし詰めにすると100人近く乗れるそうです。
今回の座礁事故は港が近かったので救命ボートが船と何度か往復して乗客を救ったと報道されています。それが幸運でした。
尚、今回の事故では船が傾いたために、左舷の救命ボートが海へ降ろせず、使うことが出来ませんでした。しかし豪華客船の救命ボートはそのような事態に備えて片方の舷側に吊り下げた救命ボートだけで乗客・乗員の総数を収容出来るようになっているのです。それが国際的な原則です。
荒れる海の上で、傾いた暗い船上で救命ボートに定員通り乗せることは至難のことです。定員まで乗船する前に見切り発車してしまうのは仕方のないことです。
そんな事をいろいろ想像してみると今回の船員による救命ボートの操作は見事だったと思います。一部の船員が操作方法を知らなかったとしても総括的にはよく働いたと感心しています。
しかし30人以上の犠牲者が出たことは残念です。
犠牲者のご冥福をお祈り申し上げます。(終り)