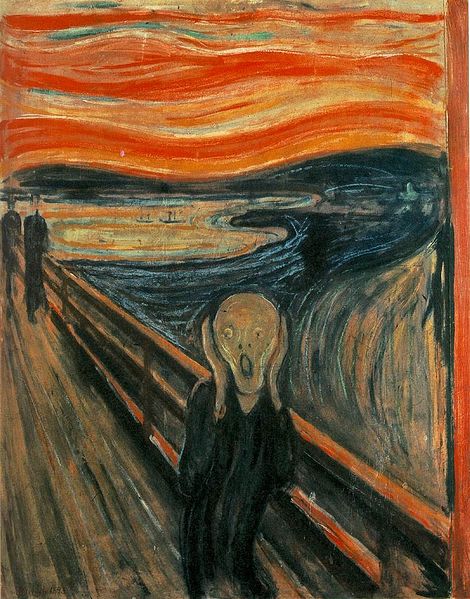八丈島の歴史を調べようとしました。役場へ行って、郷土史の本を見せて下さいと言いました。対応した初老の男性が、それなら是非、民俗資料館へ行ってご覧なさい。そこに全部揃ってますと言います。
そのアドバイスは正解でした。展示されている資料が豊富で、説明文も明快です。かなり研究して書いた文章なのです。
感心して読んでいたら、傍に寄って来る人がいます。地域歴史専門家の細谷昇司氏でした。彼は私が東京に帰った後も、長い間メールで八丈島の詳しい情報を送ってくれた方です。
そのお陰で八丈島の歴史や、人々の考え方がかなり深く分かるようになったのです。尚、細谷昇司さんは「ながれ」という名前でブログ:http://nangare.blog94.fc2.com/
http://blog.goo.ne.jp/zuninrunin/ を書いています。八丈島にご関心のある方は是非ご覧下さい。
以下は、民族資料館で知った島の歴史を簡略に纏めたものです。
約6000年前の縄文時代に島のあちこちに住んでいた人々の遺骨や石器・土器が発掘され、展示してあります。石斧の石は海岸にあるような石ですが、土器に使われた粘土は火山で出来た島には有る筈がない土です。従って縄文人は土器を持って太平洋を渡って本州から来たのです。
大和朝廷のころは形式的には駿河の国へ属していました。
室町時代に、鎌倉公方補佐の関東管領の上杉憲顕が派遣した代官が居ました。
直接的な支配は室町時代末期に北条早雲の家来が代官として大賀卿村の大里に陣屋を作ったころからです。しかし、船旅の危険が大きいためほとんど独立した孤島だったのです。
江戸幕府は早雲の派遣した代官の陣屋跡に島役所を作り、八丈島を江戸幕府の直轄領にして直接統治し始めまたのです。
幕府は、独特の染め方をした絹織物、黄八丈を年貢として納めさせたのです。
江戸時代になって始めての流人は関ヶ原の合戦で敗れた秀吉の家老であった宇喜多秀家とその付き人一行でした。それ以来幕末までに合計1917人の流人が八丈島へやって来たのです。
粗暴犯の他に江戸幕府や仏教界での権力闘争に敗れた政治犯も多かったのです。これらの人々は知的レベルも高く、島の文化へ大きな貢献をしました。
歴史民俗資料館発行の資料解説No.5には20人ほどの流人の名前を記し、島への貢献の内容を説明しています。
カイコと、黄八丈と呼ばれる絹織物を伝えた人、サツマイモを伝えた流人、薩摩焼酎の作り方を伝えた人、詩歌管弦の指導をした風流な流人、などなどの名前を明記して、感謝の言葉が書いてあります。中には大工の棟梁も居て、島でも弟子をとり、多くの大工を育てた人もいます。
これらを総称して「流人文化」といい、八丈島の人々は現在でも誇りにしています。
その「流人文化」のはじめになった宇喜多秀家のお墓参りをした時の記録を下に示します。

上の写真は1606年に八丈島へ流人として到着した宇喜多秀家の御墓です。お墓を訪ねてみると、朝にいけたような瑞々しい切り花が飾ってあります。毎日、切り花を供えている様子です。
秀家の回りにある縁者の小さな墓石の前にも切り花が供えてあります。いったい誰が供えるのでしょう?
秀家は秀吉の一字を貰った五大老の一人で朝鮮出兵で活躍し、帰国後は岡山城の大改修をし、備前・美作57万石の領主でしたが関ヶ原で敗将になってしまいました。八丈島へは長男の孫九郎や前田藩の医師、村田道珍斎や総数13名で到着しました。流罪には正妻の豪姫以外の長男、医師、その他の付き人が許されたのです。その後の差し入れも許され、前田藩による財政援助は明治維新まで続いたのです。
豪姫の実家は前田藩で、実子の居ない秀吉の養女になり、秀吉の重用する秀家の正妻になったのです。
前田藩は秀家存命中は勿論、子孫の宇喜多氏へ、2年毎に白米70俵と35両の現金、衣類、薬品、雑貨などを仕送りしていました。この仕送りは明治2年赦免になり東京へ帰るまで続きました。従って宇喜多秀家は島の人々にとっては感謝、尊敬される存在でした。
宇喜多一族は次第に増え、現在、島には宇喜多という名字の家が沢山あります。そして島の重要な家族として人々に大切にされているのです。
秀家のお墓の前の切り花だけではありません。歴史民俗資料館には宇喜多秀吉の関連資料だけを展示している一つの部屋があります。
八丈島のローカル文化を一言で表せば流人達の持ち込んだ文化を島の人々が大切に育て上げた文化なのです。もっと重要なことは島の人々が江戸幕府によって流された不運な人々をなぐさめ、大切にし、愛して、助けるという精神文化のみゃくみゃくと流れ続いた文化なのです。
江戸幕府から派遣された島の陣屋野の役人も島人の助けが無ければ生きて行けないような絶海の弧島だったのです。江戸時代の帆船では航海が危険過ぎて江戸からの食糧の補給が途絶えがちだったのです。
事実、2009年の1月末に島に渡った私の船も飛行機も欠航続きで、滞在を数日延ばさなければならなかったのです。それが伊豆半島から近い大島や神津島などとの大きな相違でした。伊豆七島と一言で纏めると大きな誤解が起きることを痛感した八丈島への旅でした。
尚、上のお墓の写真は2009年1月末の撮ったものです。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り致します。後藤和弘(藤山杜人)