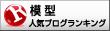気がついたら、藤の花が、盛りの時期を過ぎていました。
毎年、見逃している気がします。
さて。
仕事帰りの道すがら。

屋根やパンタグラフ全体に比べて、碍子が汚れていないことに気がつきました。
撮ったのはこの1枚だけですが、ほかの車輌にも同じような傾向にあります。
考えてみれば、当然ですよね。
付着したものが電気を通しやすい材質だったならば、絶縁という役目を果たせなくなります。
だから、碍子は汚れない、もしくは汚れが付きにくい。
今まで、気がつきませんでした。
で、帰宅して、気になる。

過去にウェザリングした模型です。
これは、汚し過ぎということになるはず。
碍子を、塗り直しました。
あわせて、集電舟のうち、中央付近のつねに架線と接触する部分も塗り直し。

ウェザリングをしたあとで、もういちど塗り直す必要がありそうです。

同じように。


避雷器の碍子も。


古い製品も。


観察が足りなかったなぁ。
以下、追記です。
碍子は、汚れたら拭き取っているのだと教えていただきました。
考えてみれば、そりゃそうですよね。
汚れにくいモノはあっても、汚れないモノは、たぶん世の中にはありません。
絶縁機能を保つために、日々のチェックと掃除をしているひとが、いるはずです。
まだまだ、知らないことばかりです。
ということで、標題も「碍子は汚れない」ではなく
「碍子は汚れていない」が、正しいですね。
敢えて、そのままにしておきますが。
毎年、見逃している気がします。
さて。
仕事帰りの道すがら。

屋根やパンタグラフ全体に比べて、碍子が汚れていないことに気がつきました。
撮ったのはこの1枚だけですが、ほかの車輌にも同じような傾向にあります。
考えてみれば、当然ですよね。
付着したものが電気を通しやすい材質だったならば、絶縁という役目を果たせなくなります。
だから、碍子は汚れない、もしくは汚れが付きにくい。
今まで、気がつきませんでした。
で、帰宅して、気になる。

過去にウェザリングした模型です。
これは、汚し過ぎということになるはず。
碍子を、塗り直しました。
あわせて、集電舟のうち、中央付近のつねに架線と接触する部分も塗り直し。

ウェザリングをしたあとで、もういちど塗り直す必要がありそうです。

同じように。


避雷器の碍子も。


古い製品も。


観察が足りなかったなぁ。
以下、追記です。
碍子は、汚れたら拭き取っているのだと教えていただきました。
考えてみれば、そりゃそうですよね。
汚れにくいモノはあっても、汚れないモノは、たぶん世の中にはありません。
絶縁機能を保つために、日々のチェックと掃除をしているひとが、いるはずです。
まだまだ、知らないことばかりです。
ということで、標題も「碍子は汚れない」ではなく
「碍子は汚れていない」が、正しいですね。
敢えて、そのままにしておきますが。