4月2日(火)
今日見たFacebookから。

「耳が聞こえなくなっても絶望しない社会を作りたい」
難聴の弁護士が指摘する、情報アクセシビリティの課題
聴覚障害者は行動に制限はないんですが、行動の前提となる情報にアクセスできない。
情報アクセシビリティとは
「年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること」
厚生労働省のホームページより
情報アクセシビリティについては、一応法律にも書いてあります。「障害者基本法」の第22条で、これは名宛人が、国及び地方公共団体です。「国とか地方公共団体は、障害者が情報を取得したり、利用したり、自分の意思を表明したり、意思疎通を図ることができるように、いろんな施策を取りなさい」と、書いてあります。
「障害者差別解消法」。こちらは2016年4月1日に施行されて、もうすぐ3年になります。こちらは行政機関だけではなく、事業者も対象になっています。だから、みなさんも他人事ではない法律です。こちらの法律で、(情報アクセシビリティが)どういう位置付けになるかをお話しします。まず、こちらの法律は大原則として、「不当な差別的取扱いの禁止」を定めています。
「障害の社会モデル」と「障害の医学モデル」という考え方
「障害の社会モデル」 ⇒ 障害の解消に向けて取り組む責任は、社会の側にあるという考え方
「障害の医学モデル」 ⇒ 機能の損傷によってもたらされる障害は、自分で取り除くという考え方
最近の障害に対する考え方は「障害の医学モデル」から「障害の社会モデル」に代わってきている。
トンサンは最初っから「障害は環境にある」と言っている。











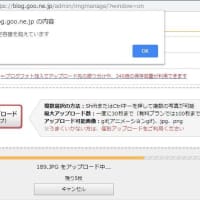








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます