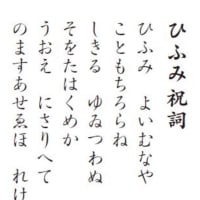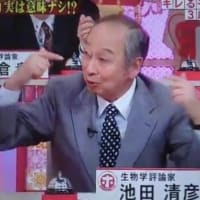卑…身分、地位の低い、下劣、いやしい
弥…ひろくゆきわたる
子…北の方角、ねずみ、子供
つまり、卑しさが広くゆきわたる子供、北にいて下劣で有名となる。
あくまでも中国の魏志倭人伝が正しいとの前提で導き出される日本の古代史である。
これだけでも十分に漢字表記で卑弥呼とすることは日本の恥晒しの歴史となるであろう。田中英道東北大学名誉教授は次の様に書いている。
「偶然的に馬鹿にしていたものを戦後の学者が寄ってたかって万世 一系の天皇家を、疑わせるに足る史料としてきたこと」と問題提起されている。
田中英道

なぜ卑弥呼神社がないのか
――日本のどこにも存在しない「邪馬台国」より
3 「卑弥呼」という名前について
『魏志倭人伝』は、男子の王が七、八十年続いた後に、何年か乱れ た末に、≪乃ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼を曰う。鬼道に事え、能く衆を惑わす≫と記している。ここで注目すべきは、≪一女子を立てて王 となす≫という表現の中に、あくまで男子と男子の戦いの後、卑弥呼が戦いに勝って王の地位についたわけではなく、その男子たちが「共立」して卑弥呼に 「王」を委ねた、という経緯があったことである。つまり戦争の勝利者よりも、巫女のような精神的な権威者を、世の中が必要とした、ということであろう。
しかしその「卑弥呼」の「宮室・楼観を、≪城柵をもて厳かに設 け、常に人有り、兵を持ちて守衛す≫と述べている。ここには決して「共立」されて、安定した生活を送ったわけではない状態があったということだ。つまり 「王」となった以上、防御が必要になった、ということかもしれない。いずれにせよ、この存在は、権威的存在であって、戦いを制することの出来る権力的な存 在ではないことである。これは一見、天皇の存在に似ている。一方で摂政・関白に藤原氏のような実際に政治を執り行う勢力があって、その上に立つ、霊的な権 威の存在であったことである。
しかしこの女王の国は、倭国のひとつ「邪馬台国」であって、「倭 国」の島々がさらに別にあったことを記している。つまり天皇のように、倭国すべてを統一した上の「権威」的存在ではない、ということである。すると、これ 自体、決して、卑弥呼が「倭国」の「王」的存在ではなく、地方政権のひとつであったことになる。
女王卑弥呼が死亡してから、≪更に男王を立てしも、国中服せず。 更々(こもごも)相誅殺し、当時千余人を殺す。復(ま)た卑弥呼の宗女壱与年十三なるを立てて王と為し、国中遂に定まる≫という記述も、この国において は、戦争で国を制するよりも、巫女の家系の子孫を人々が尊敬する、ということを述べていることになる。このような家系を奉るということ自体、『魏志倭人 伝』の作者が、日本の「天皇=スメラミコト」の存在を仄聞して、その精神的権威というものを、このような記述に変えた、と考えられるだろう。しかし、あく まで神武天皇以来の、「倭国」全体の権威を想定したわけではない。
私は学生であった頃、井上光貞東大教授の「国史」の授業を聞いた が、そのとき「卑弥呼」を「ひみこ」と呼ばす、「ひめこ」と呼ぶべきだ、ということを聞いた。氏の『日本国家の起源』にも、「ひめこ」というルビをふって いる。しかしこの「ひめこ」と呼んだのは、江戸時代の九州邪馬台国説の始祖である本居宣長 である。そして井上教授の前の東大教授の坂本太郎氏が、「ひめこ」説を主張し、その根拠に、『元興寺縁起』や『上宮聖徳法王帝説』その他で、漢字仮名書き した人名や神名で「め」と発音すべきところに「弥」の字を使用されている例を数多く出しているからである。それに対し、原田大六氏は、これらの二つの文献 が、「め」という特別な読み方をすべき統一性をもっておらず、やはり「み」と読むべきことを主張している。
いずれにせよ「卑弥呼=ひみこ」というもっともらしい名前から、 延々と論争がはじまったのである。そのもっともらしさとは、この名が「ひのみこ=日皇子」という『古事記』にも、『万葉集』にも出ている言葉と類似してい るからであろう。日皇子は、日の神の子孫であり、日のように輝く御子という意味で、天皇や皇太子、皇子の美称である。天照大御神の皇孫ニニギノミコトが高 天原から芦原中国に降臨した神話にもとづく表現である。≪高照らす 日の皇子は 飛ぶ鳥の 清御原の宮に 神ながら 太敷きまして≫(2一六七)と、地上 への降臨と統治を一連のものとしてとらえている。天皇の神聖性を神話の起源に立ち返って確認し賛美することは、あたかも「ひみこ」の正当性を示しているよ うに錯覚させたのであろう。
『万葉集』では、誰をさすか明らかでない例がある他は、その対象 は天武天皇とその皇子、天武の皇后であった持統天皇に限られている。その意味で、天照大御神の皇祖神化、伊勢神宮の創建、国家神話の体系化などを、あたか も「ひみこ」という言葉が予知していたように、真実性がある、と日本学者が感じてしまったからであろう。
『この「卑弥呼」が「日の皇子」であることは、万世 一系の天皇家を、疑わせるに足る史料として、戦後の学者たちにその捏造性も疑わずに、考察されつづけたことである。ここではっきり言えることは「卑弥呼」 は、「日の御子」を軽蔑した言い方であり、その関連は偶然のことであることだ。』