昨日インタビューしたアンソニー・ルッソは、弟のジョンと共同で映画を撮る、いわゆる兄弟監督である。コーエン、ダルデンヌ、ウォシャウスキー、ファレリー…、今でこそ兄弟監督はたくさんいるが、その嚆矢はイタリアのタビアーニ兄弟ではあるまいか。その兄弟の兄ビットリオが亡くなった。彼らの映画の公開は1980年代のミニシアターブームと重なる。ある意味、そうした時代の波が日本と彼らの映画を結び付けたと言ってもいいだろう。
サルデーニャ島の羊飼いの父子の葛藤を描いた『父パードレ・パドローネ』は77年の映画だが、日本での公開は82年。第二次大戦末期のトスカーナ地方を舞台に、ドイツ軍の撤退によって村を追われた人々の姿を描いた『サン★ロレンツォの夜』と同時期に公開され、こちらは名画座(大井武蔵野館)の二本立てで見た。
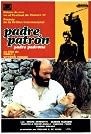
『父パードレ・パドローネ』83.6.21.(初見の際のメモを)
最初は、単なる父子もので、厳格な父親から独立していく息子の自我の確立を描いただけの映画かと思っていたら、これが大間違い。イタリアの片田舎の風土や自然をベースに、残酷、エゴ、ユーモア、愛といった人間が持つ根源的な心情を浮かび上がらせるような映画だった。
結局、この父と子の仲は最後までしっくりしないのだが、陰惨なイメージは浮かんでこない。それどころか、妙な温かさを感じてしまったのは何故なのだろう。
この映画の父親は、日本の古いタイプの親父のように、威張るだけ威張って、決して自分が悪いとは認めない。気に食わなければ平気で子供を殴る。そのくせ妙に情にもろい。子供にとってはやっかい極まりない存在なのだが、その反面、親父が強いというのは息子にとってはうれしいことでもあるわけで…。それが、子供が大きくなるに連れて、強かった父親の弱さや老いを見るようになるのは寂しいことでもある。イタリアという国は何となくその辺りの心情が日本と似ているのかもしれない。
そういえば、ピエトロ・ジェルミの『鉄道員』(56)もそんな映画だったなあ。それにしても日本にこういう頑固親父がいなくなったのはいいことなのか悪いことなのか、などと思ってしまった。
うーん、今から35年前はこんなふうに考えていたのか。
サルデーニャ島の羊飼いの父子の葛藤を描いた『父パードレ・パドローネ』は77年の映画だが、日本での公開は82年。第二次大戦末期のトスカーナ地方を舞台に、ドイツ軍の撤退によって村を追われた人々の姿を描いた『サン★ロレンツォの夜』と同時期に公開され、こちらは名画座(大井武蔵野館)の二本立てで見た。
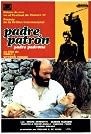
『父パードレ・パドローネ』83.6.21.(初見の際のメモを)
最初は、単なる父子もので、厳格な父親から独立していく息子の自我の確立を描いただけの映画かと思っていたら、これが大間違い。イタリアの片田舎の風土や自然をベースに、残酷、エゴ、ユーモア、愛といった人間が持つ根源的な心情を浮かび上がらせるような映画だった。
結局、この父と子の仲は最後までしっくりしないのだが、陰惨なイメージは浮かんでこない。それどころか、妙な温かさを感じてしまったのは何故なのだろう。
この映画の父親は、日本の古いタイプの親父のように、威張るだけ威張って、決して自分が悪いとは認めない。気に食わなければ平気で子供を殴る。そのくせ妙に情にもろい。子供にとってはやっかい極まりない存在なのだが、その反面、親父が強いというのは息子にとってはうれしいことでもあるわけで…。それが、子供が大きくなるに連れて、強かった父親の弱さや老いを見るようになるのは寂しいことでもある。イタリアという国は何となくその辺りの心情が日本と似ているのかもしれない。
そういえば、ピエトロ・ジェルミの『鉄道員』(56)もそんな映画だったなあ。それにしても日本にこういう頑固親父がいなくなったのはいいことなのか悪いことなのか、などと思ってしまった。
うーん、今から35年前はこんなふうに考えていたのか。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます