秋田市の「竿燈(かんとう)まつり」まであと1か月。
このお祭り(8月に開催されるイベントとしての)の現在の正式表記は「秋田竿燈まつり」。「竿“灯”」ではない。
 秋田竿燈まつり公式サイトの表示
秋田竿燈まつり公式サイトの表示
※公式サイトでは、タイトルは「秋田竿燈まつり」で、その下には「秋田“市”竿燈まつり実行委員会~」とあり、イベント名と実行委員会の名称で「市」の有無が異なる。これは「秋田“市役所内に設置された”竿燈まつり実行委員会」という意味だと思われる。「秋田市秋田竿燈まつり実行委員会」という名称のほうがより正確ではあるのだろう。
ただし、以前の一時期は「竿灯まつり」が公式表記だったことがあった。
「燈」が常用漢字でないために「灯」にしたようだが、本来の表記に戻そうということで再び「燈」に変えられた経緯がある。過去の広報あきたを調べると、おそらく1993(平成5)年から「竿燈」に戻ったらしい。また、確認できた中で最古の1957(昭和32)年には既に「竿灯まつり」となっている。
【4日訂正】コメントでご指摘いただいたように、当用漢字に代わって「常用漢字」の制度ができたのは1981年で、その時に「燈」が「灯」に変わった。それ以前から「竿灯」表記だったので「“燈”が常用漢字でないので“竿灯”表記にした」という理由では、時系列的に合わなくなり、正しい理由ではなかったことになる。
※竿“灯”最後の1992年に、テレビドラマのロケが行われた。
「竿燈」に戻って今年で20年になるようだが、いまだに「竿灯」と表記されることが多い。
さすがに秋田市役所関係では「竿燈」に統一されているが、2010年に紹介した(リンク先中ほど)ように、秋田県庁や地元メディアでさえ、「竿燈」と「竿灯」が混在しているのが見受けられる。
その文書作成者(あるいは情報を公開している組織)が、常用漢字しか使わないという意志を持って「竿灯」に統一しているのならいいが、混在しているのだから、そういうわけではないはず。
パソコンでは「灯」も「燈」もOSやフォントに関わらず表示できてしまい、一部のかな漢字変換システムでは「かんとう」でどちらも候補として表示されてしまうことが原因だと思う。
さて、JTBパブリッシングが「ノジュール」という月刊誌を出しているそうだ。
「50代からの旅と暮らし発見マガジン」で書店では扱わず、定期購読のみ。
 その7月号の広告が、6月29日の新聞に出ていた
その7月号の広告が、6月29日の新聞に出ていた
その第2特集が「一度は見ておきたい日本の夏祭り」。
 いくつかの祭りの名称が掲載されている
いくつかの祭りの名称が掲載されている
秋田の竿燈も出ているが、「竿灯」表記になってしまっている。残念。
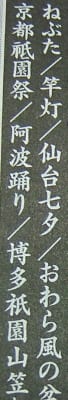 他には、京都“ぎおん”祭と博多“ぎおん”山笠が出ているのだが…
他には、京都“ぎおん”祭と博多“ぎおん”山笠が出ているのだが…
ぎおんの「ぎ」は、「しめすへん」に「氏」。この文字のしめすへんは「ネ」のようなのと「示」の両方とも使われることが多いように感じる。現在のパソコンでは「ネ」のほうは表示できず「祇」だけだが、昔は(ワープロ専用機当時?)は逆に「ネ」で「示」のほうが表示できなかったはず。【4日追記】WindowsではXPまでが「ネ」、7以降で「示」になる模様。
広告では、京都と博多で「ぎ」の文字が違っている。京都は「示」で、博多は「ネ」。あえて文字を変えたということは、公式表記にのっとったのだろうか? でも竿燈は「竿灯」だし…
【4日訂正】よく見たら、新聞広告の京都の「ぎ」は、示に氏の「祇」でもなく、示で氏の下に横棒が1本入る「祗」だった。「祗」は「シ」と読み、「祇」とは別の文字(混同・誤用されることは多い)。したがって「祗園祭」は完全な間違いということになる。(以上訂正。以下は訂正前のまま残します)
確認するためにそれぞれの祭りの公式サイトを見ようとしたが、意外にも京都祇園祭には、明確な公式サイトは存在しないようだ。京都市役所ホームページからリンクされている、京都観光オフィシャルサイトでは、
 「ネ」
「ネ」
他のホームページでは、「示」を使っていたり、ページ内で「ネ」と「示」が混在したりしている。
ホームページで見る限り少なくとも、京都のぎおん祭は必ずしも「示」ではないようだ。
博多のほうは公式サイトがあった。
 「示」
「示」
博多は「示」で統一されている。一部は、いかにも手作業で「示」に変えたような「祇」もある。
 右の小さい「祇」
右の小さい「祇」
トップページ下の問い合わせ先の「博多ぎ園山笠振興会」だけは「ネ」だったけど。
となると、ノジュールの新聞広告は、むしろ公式表記の逆に近い。
また、ノジュール公式ホームページの「最新刊のご紹介」では、博多を「示」と正しく表記している。(京都祇園祭や竿燈は出ていない)
 ノジュール公式ページより
ノジュール公式ページより
新聞広告では他にも、「ねぶた」「阿波踊り」とあるのも引っかかる。「ねぶた」という祭りは各地にあるし、徳島は「阿波おどり」が正当。(ホームページでは「青森ねぶた祭」「阿波おどり」と正しく表記)
どうも本誌は大丈夫で、新聞広告の表記だけに問題があるようだ。
JTBの出版物といえば「るるぶ」をはじめ、観光情報にとても強いイメージがあり、その分野の草分けでもあろう。広告だけとはいえ、それがこうではいただけない。立ち読みできない雑誌だけに、新聞広告の役目は大きいだろうし。
※2015年7月の同誌の広告にも竿燈が出ているが「竿燈まつり」と正式表記になった。
このお祭り(8月に開催されるイベントとしての)の現在の正式表記は「秋田竿燈まつり」。「竿“灯”」ではない。
 秋田竿燈まつり公式サイトの表示
秋田竿燈まつり公式サイトの表示※公式サイトでは、タイトルは「秋田竿燈まつり」で、その下には「秋田“市”竿燈まつり実行委員会~」とあり、イベント名と実行委員会の名称で「市」の有無が異なる。これは「秋田“市役所内に設置された”竿燈まつり実行委員会」という意味だと思われる。「秋田市秋田竿燈まつり実行委員会」という名称のほうがより正確ではあるのだろう。
ただし、以前の一時期は「竿灯まつり」が公式表記だったことがあった。
【4日訂正】コメントでご指摘いただいたように、当用漢字に代わって「常用漢字」の制度ができたのは1981年で、その時に「燈」が「灯」に変わった。それ以前から「竿灯」表記だったので「“燈”が常用漢字でないので“竿灯”表記にした」という理由では、時系列的に合わなくなり、正しい理由ではなかったことになる。
※竿“灯”最後の1992年に、テレビドラマのロケが行われた。
「竿燈」に戻って今年で20年になるようだが、いまだに「竿灯」と表記されることが多い。
さすがに秋田市役所関係では「竿燈」に統一されているが、2010年に紹介した(リンク先中ほど)ように、秋田県庁や地元メディアでさえ、「竿燈」と「竿灯」が混在しているのが見受けられる。
その文書作成者(あるいは情報を公開している組織)が、常用漢字しか使わないという意志を持って「竿灯」に統一しているのならいいが、混在しているのだから、そういうわけではないはず。
パソコンでは「灯」も「燈」もOSやフォントに関わらず表示できてしまい、一部のかな漢字変換システムでは「かんとう」でどちらも候補として表示されてしまうことが原因だと思う。
さて、JTBパブリッシングが「ノジュール」という月刊誌を出しているそうだ。
「50代からの旅と暮らし発見マガジン」で書店では扱わず、定期購読のみ。
 その7月号の広告が、6月29日の新聞に出ていた
その7月号の広告が、6月29日の新聞に出ていたその第2特集が「一度は見ておきたい日本の夏祭り」。
 いくつかの祭りの名称が掲載されている
いくつかの祭りの名称が掲載されている秋田の竿燈も出ているが、「竿灯」表記になってしまっている。残念。
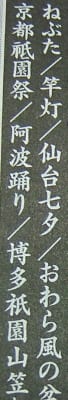 他には、京都“ぎおん”祭と博多“ぎおん”山笠が出ているのだが…
他には、京都“ぎおん”祭と博多“ぎおん”山笠が出ているのだが…ぎおんの「ぎ」は、「しめすへん」に「氏」。この文字のしめすへんは「ネ」のようなのと「示」の両方とも使われることが多いように感じる。現在のパソコンでは「ネ」のほうは表示できず「祇」だけだが、昔は(ワープロ専用機当時?)は逆に「ネ」で「示」のほうが表示できなかったはず。【4日追記】WindowsではXPまでが「ネ」、7以降で「示」になる模様。
広告では、京都と博多で「ぎ」の文字が違っている。京都は「示」で、博多は「ネ」。あえて文字を変えたということは、公式表記にのっとったのだろうか? でも竿燈は「竿灯」だし…
【4日訂正】よく見たら、新聞広告の京都の「ぎ」は、示に氏の「祇」でもなく、示で氏の下に横棒が1本入る「祗」だった。「祗」は「シ」と読み、「祇」とは別の文字(混同・誤用されることは多い)。したがって「祗園祭」は完全な間違いということになる。(以上訂正。以下は訂正前のまま残します)
確認するためにそれぞれの祭りの公式サイトを見ようとしたが、意外にも京都祇園祭には、明確な公式サイトは存在しないようだ。京都市役所ホームページからリンクされている、京都観光オフィシャルサイトでは、
 「ネ」
「ネ」他のホームページでは、「示」を使っていたり、ページ内で「ネ」と「示」が混在したりしている。
ホームページで見る限り少なくとも、京都のぎおん祭は必ずしも「示」ではないようだ。
博多のほうは公式サイトがあった。
 「示」
「示」博多は「示」で統一されている。一部は、いかにも手作業で「示」に変えたような「祇」もある。
 右の小さい「祇」
右の小さい「祇」トップページ下の問い合わせ先の「博多ぎ園山笠振興会」だけは「ネ」だったけど。
となると、ノジュールの新聞広告は、むしろ公式表記の逆に近い。
また、ノジュール公式ホームページの「最新刊のご紹介」では、博多を「示」と正しく表記している。(京都祇園祭や竿燈は出ていない)
 ノジュール公式ページより
ノジュール公式ページより新聞広告では他にも、「ねぶた」「阿波踊り」とあるのも引っかかる。「ねぶた」という祭りは各地にあるし、徳島は「阿波おどり」が正当。(ホームページでは「青森ねぶた祭」「阿波おどり」と正しく表記)
どうも本誌は大丈夫で、新聞広告の表記だけに問題があるようだ。
JTBの出版物といえば「るるぶ」をはじめ、観光情報にとても強いイメージがあり、その分野の草分けでもあろう。広告だけとはいえ、それがこうではいただけない。立ち読みできない雑誌だけに、新聞広告の役目は大きいだろうし。
※2015年7月の同誌の広告にも竿燈が出ているが「竿燈まつり」と正式表記になった。
























当用漢字の時代は「燈」が採用されていて「灯」はなかったので、逆に当用漢字にない字体を使っていたことになりますね。
「灯」が採用されたのは1981年の常用漢字の制定からですね。(「燈」は人名漢字としては存続)
常用漢字がそんなに新しい制度だったとは知りませんでした。
となると、最初は略字的に「灯」を使って、それがいつの間にか正式になってしまったといった事情かもしれません。
「竿燈」表記に戻した時、テレビか何かでその理由として「常用漢字うんぬん」を聞いたような記憶もあります。後付けの理由だったのかもしれません。
そんなわけでまだ実物を見ていないですが、博多じゃなくて福岡ということでしょうか。そして九州新幹線がないと。
公式ホームページで過去のポスターが見られますが、路線図は小さくて見えないのですが、昨年以前はどうだったのでしょうかね。
「竿燈」ですが、明治天皇の秋田行幸の際に、当時の大久保秋田県知事が宮内省に当てた「天覧伺い書」の中で、初めて「竿燈」の表記が用いられました。
この「天覧伺い書」が宮内省に認可された事から、この祭りを「竿燈」と呼ぶようになったのですが、それまでは「ねぶり流し」「ねぶた流し」「竿頭」「竿灯」「作り灯籠」「秋田の七夕」など、様々な呼ばれ方がされていたようです。
殊に「竿灯」ですが、1980年の国の重要無形民俗文化財に指定された際の証書には、「秋田の竿灯」と記されています。
また作られて90年は経つと言われている町内の太鼓にも、「竿灯会」と大書されています。
「かんとう」の名が定着してからも、表記は灯と燈が混在していたのかもしれませんね。手書きで燈を書きにくいとかで。
重要無形民俗文化財のデータベースを検索した所、現在も「秋田の竿灯」のままみたいです。
開催日も5~7日のままですが。(登録当時の情報のまま残すことになっているのかもしれません)
それにしても、いよいよ竿燈まで1週間ですね。
週間予報は悪くなさそう(梅雨が明けるか?)で、今年もいいお祭りになることを願っています。
明治41年、手形練兵場での皇太子殿下(後の大正天皇)台覧臨時出竿の写真には、『秋田名物竿燈七夕』と記されており、大正年間のものと思われる秋田公会堂前での出竿の写真も、『秋田名物竿燈』と記されています。
また、昭和6年の秋田市竿燈会創立趣意書も『秋田市竿燈會』となっており、戦前までは『燈』の字が使われていた様子が伺えます。
しかし、昭和39年に東京オリンピックさよならパーティーに臨時出竿した際、オリンピック東京大会組織委員会から秋田市竿燈会に感謝状が贈られていますが、その宛名は『秋田竿灯殿』となっています。
広く『竿灯』の表記が使われ始めたのは、おそらく戦後なのでしょう。
そんな中でも、世間では他の文字と同様に書きやすい簡単な「灯」にシフトしていったのかもしれません。戦後の時代の流れだったのでしょうか。
コンピュータの普及や本来の表記を重んじる風潮が高まって、「竿燈」に戻ったことになるでしょうか。