前回のハンバーガー自販機の話題、ものすごい大量アクセスをいただいており、びっくり。
今回も土崎の話題で、2つのバス停の表示について(これはアクセスは多くならないでしょう)。
10月から土日が大幅減便された旧国道方面。中央高校・将軍野方面へ2路線が分岐した後、唯一直進する寺内経由土崎線単独のバス停。
 「幕洗川」
「幕洗川」
不思議な名前。坂上田村麻呂が汚れた陣幕を洗ったという伝説にちなむとか。
そういう川は実在しない(はず)。1968年までは寺内の小字だったが、今は土崎港東と土崎港南の各一部になって地名としては消滅。町内会の名称として存続しているようで、土崎港曳山まつりにも出ている。
上の写真は、下り側の表示板。
市営バス時代に設置された(青い部分の下に透けている)もので、バス停名のフォントは「ナール」。
この上り側は、パソコン作成の透明シール角ゴシック体(市営バス末期の設置?)のものだったのが、
 表示板だけ新しくなった
表示板だけ新しくなった
 「幕洗川」
「幕洗川」
最近標準の、太い「スーラ」の中央寄せ。※バス停表示板について直近の記事。
なお、隣の「港南一丁目」は古い手書き文字の表示板だった。未確認だが、いっしょに更新された可能性が高い。
フォント以外に、上下で違いが生じている。
ローマ字の読みが、下りは「MAKUARAIGAWA」、「まくあらいがわ」で、新しい上りは「MAKUARAIGAKA【5日訂正】MAKUARAIKAWA」「まくあらいかわ」。
「川」を「かわ」と読むか「がわ」と読むか、日本語ではよくありがちな問題ではあるが、同じことを指して統一されていないのは、気になる。
個人的には「まくあらいがわ」だと思っていたし、秋田弁としても濁るほうが自然な気がした。少し前にテレビで「幕洗川」をひとことだけ話す場面に遭遇したが、たしか「がわ」だったはず。
バス停の表記では、移管直後の中央交通設置分で、保戸野の「桜町(さくらまち)」を「さくらちょう」してしまっていた。市営バスでもたまに誤った表記のものもあったから、市営バスを全面的に信用もできないけれど…
ところが、秋田市役所(旧?)ホームページの「地名小辞典」や、港まつりの「秋田みなと振興会」ホームページでの町内紹介では、そろって、
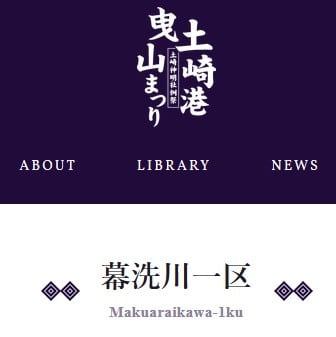 「Makuaraikawa」
「Makuaraikawa」
濁らない「~かわ」となっている。
じゃあ「まくあらいかわ」が正しいのか(だとすれば、中央交通さん疑ってごめんなさい)。バスの車内放送はどうなっているだろう。
もう1つは新国道を越えた場所。9月で廃止されてしまった、土崎駅まで行く神田線のバス停。
 現在は撤去されているかな
現在は撤去されているかな
真ん前にあるお寺の名前が由来のバス停。
これも市営バス設置のナール。一方通行区間なので下り用1つしかないが、当然裏表とも同じ表示。
これは日本語表示に注目。
ぱっと見るとなんとも思わないけれど、落ち着いて見ると、日本語の文字として、ちょっと気になるものがある。
「梅」である。
正しいというか普通のものを見ると分かる。
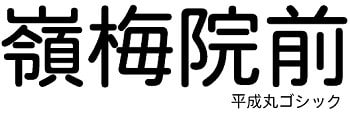 別のフォントですが
別のフォントですが
※この平成丸ゴシックは、ナールと同じ「写研」が作ったフォント。写研はパソコン用フォント発売をかたくなにこばんでいるメーカーなのだが、「平成書体」の開発には関わって、これが唯一のパソコンで使える写研フォントということらしい。機会があればいずれ。
梅の右側・つくりは「毎」だから、右下が右にも下にも突き出ているのが普通。
ところがバス停の表示板はどちらも出ておらず、枠でみるとただの平行四辺形。漢字テストで手書きでこの形にしたら、マルをもらえるだろうか。
カッティングシートが部分的にはがれたようなものでもなさそう。
こういう異体字があるのかとも思ったが、「母」のように点になっているものなどはあるが、この形のものは主な異体字にはなさそう。
そもそも、お寺の表示類は、ごく普通の「嶺梅院」となっている。
調べたら、なんのことはない。ナールの「梅」はこのデザインというだけの話だったようだ。
今はナールは道路の案内標識くらいでしか使われないが、大阪「梅田」の写真を見つけたら、同じ形だったので【3日追記・「青梅」も】。
ナールは、文字の基本の形に比較的忠実なデザインかと思っていたし、平成丸ゴシックはじめ他の丸ゴシック体ではそうなっていないのだから、意表を突かれた。
【3日補足】ナールでは「毎」や「母」も同じ形になっているそうだ。
ちなみにスーラでは、右下は右も下も突き出ているのに加え、左の縦線が下に突き出てもいる。似ているようでそれぞれ特徴があるものだ。
※この後の表示板更新や、「梅」同様のナールの「海」の形について、2020年5月の記事。
今回も土崎の話題で、2つのバス停の表示について(これはアクセスは多くならないでしょう)。
10月から土日が大幅減便された旧国道方面。中央高校・将軍野方面へ2路線が分岐した後、唯一直進する寺内経由土崎線単独のバス停。
 「幕洗川」
「幕洗川」不思議な名前。坂上田村麻呂が汚れた陣幕を洗ったという伝説にちなむとか。
そういう川は実在しない(はず)。1968年までは寺内の小字だったが、今は土崎港東と土崎港南の各一部になって地名としては消滅。町内会の名称として存続しているようで、土崎港曳山まつりにも出ている。
上の写真は、下り側の表示板。
市営バス時代に設置された(青い部分の下に透けている)もので、バス停名のフォントは「ナール」。
この上り側は、パソコン作成の透明シール角ゴシック体(市営バス末期の設置?)のものだったのが、
 表示板だけ新しくなった
表示板だけ新しくなった 「幕洗川」
「幕洗川」最近標準の、太い「スーラ」の中央寄せ。※バス停表示板について直近の記事。
なお、隣の「港南一丁目」は古い手書き文字の表示板だった。未確認だが、いっしょに更新された可能性が高い。
フォント以外に、上下で違いが生じている。
ローマ字の読みが、下りは「MAKUARAIGAWA」、「まくあらいがわ」で、新しい上りは「
「川」を「かわ」と読むか「がわ」と読むか、日本語ではよくありがちな問題ではあるが、同じことを指して統一されていないのは、気になる。
個人的には「まくあらいがわ」だと思っていたし、秋田弁としても濁るほうが自然な気がした。少し前にテレビで「幕洗川」をひとことだけ話す場面に遭遇したが、たしか「がわ」だったはず。
バス停の表記では、移管直後の中央交通設置分で、保戸野の「桜町(さくらまち)」を「さくらちょう」してしまっていた。市営バスでもたまに誤った表記のものもあったから、市営バスを全面的に信用もできないけれど…
ところが、秋田市役所(旧?)ホームページの「地名小辞典」や、港まつりの「秋田みなと振興会」ホームページでの町内紹介では、そろって、
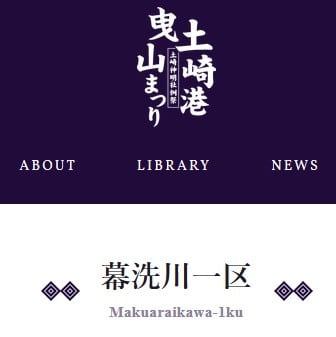 「Makuaraikawa」
「Makuaraikawa」濁らない「~かわ」となっている。
じゃあ「まくあらいかわ」が正しいのか(だとすれば、中央交通さん疑ってごめんなさい)。バスの車内放送はどうなっているだろう。
もう1つは新国道を越えた場所。9月で廃止されてしまった、土崎駅まで行く神田線のバス停。
 現在は撤去されているかな
現在は撤去されているかな真ん前にあるお寺の名前が由来のバス停。
これも市営バス設置のナール。一方通行区間なので下り用1つしかないが、当然裏表とも同じ表示。
これは日本語表示に注目。
ぱっと見るとなんとも思わないけれど、落ち着いて見ると、日本語の文字として、ちょっと気になるものがある。
「梅」である。
正しいというか普通のものを見ると分かる。
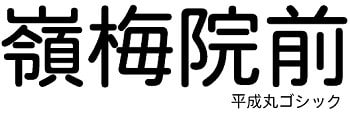 別のフォントですが
別のフォントですが※この平成丸ゴシックは、ナールと同じ「写研」が作ったフォント。写研はパソコン用フォント発売をかたくなにこばんでいるメーカーなのだが、「平成書体」の開発には関わって、これが唯一のパソコンで使える写研フォントということらしい。機会があればいずれ。
梅の右側・つくりは「毎」だから、右下が右にも下にも突き出ているのが普通。
ところがバス停の表示板はどちらも出ておらず、枠でみるとただの平行四辺形。漢字テストで手書きでこの形にしたら、マルをもらえるだろうか。
カッティングシートが部分的にはがれたようなものでもなさそう。
こういう異体字があるのかとも思ったが、「母」のように点になっているものなどはあるが、この形のものは主な異体字にはなさそう。
そもそも、お寺の表示類は、ごく普通の「嶺梅院」となっている。
調べたら、なんのことはない。ナールの「梅」はこのデザインというだけの話だったようだ。
今はナールは道路の案内標識くらいでしか使われないが、大阪「梅田」の写真を見つけたら、同じ形だったので【3日追記・「青梅」も】。
ナールは、文字の基本の形に比較的忠実なデザインかと思っていたし、平成丸ゴシックはじめ他の丸ゴシック体ではそうなっていないのだから、意表を突かれた。
【3日補足】ナールでは「毎」や「母」も同じ形になっているそうだ。
ちなみにスーラでは、右下は右も下も突き出ているのに加え、左の縦線が下に突き出てもいる。似ているようでそれぞれ特徴があるものだ。
※この後の表示板更新や、「梅」同様のナールの「海」の形について、2020年5月の記事。
























Yahoo!で調べてみましたが、「まくあらいかわ」は約8,520,000件、「まくあらいがわ」は約2,980,000件で、濁らない方が優勢ですね。ただし土崎の地名以外もかなりヒットしているようで、あまり参考にはなりませんが。
確かに、秋田県人としては濁った方が発音しやすいです。
また、幕洗川のバス停ですが元々旧国道の市営単独の経路で市営が設置したバス到着ランプ付きの停留所でした。ですので、中央交通に移管のさいに新たに設置したものと思われます。
ご指摘ありがとうございます。
港まつりの町名や地名を紹介する公的なサイトでは、濁らないほうがほとんどのようですので、それが正解で、市営バスは我々のように感覚で濁らせてしまったのかもしれません。
秋田市の地名や河川名の「旭川」は「あさひかわ」と濁らないのはおもしろいですね。岡山市の岡山城・後楽園の前にも旭川が流れていますが、そちらは「あさひがわ」と濁るそうです。
>Unknownさん
山があり(特に運河になる前は)川も近いので、昔はあったのでしょうね。遠くない場所の伽羅橋には、今は川と呼べるか微妙な流れがありますが、昔は違ったのかもしれません。
市営バス時代の幕洗川の記憶はないですが、バスロケ(接近表示)付きでしたが。基本的には移管後も、表示はやめてモノ自体は使い続けています(護国神社前のように)。撤去されたということは、何らかの工事の影響あるいは車がぶつかって壊されたのかもしれません。
>Unknownさん
住居表示の影響もありますが、土崎・寺内の境界で、かつての地名の幕洗川としては広かったのでしょう。嶺梅院の辺りは「清水町」ではないでしょうか。
竿燈もそうですが、町内配置を示した地図があれば、より親しみがわくのになと思っています。
港まつりはいつかはと思いつつ、昼間の止まっているところをちょっとのぞいたことしかありません。
平成の初めには小さな沼が残ってましたし川は現在小路で海善寺脇を通ります。
どちらもカワ発音ですし郷土史で詳しいですよ。
れいばいいん→→りんばいさん、と年配者は以前より呼んでます。
海に近いので、小さな川なんてないと思っていました。なくなってしまったのは惜しいですが。
りんばいさんは、「日本三大弁財天」ですから、檀家でなくても親しむ人も多いのかもしれません。
幕洗川跡は例の解体したスタ-ハウス前の小路で東方向に遡れば突き当たりの空き地が水源でした。
以前は鬱蒼して不思議な感じでした..土崎は名前ついた小路だけて明治初期から50道くらい確認されてます。
東西間を小路と呼ばれ、南北間は通りで明確に区別されてますが先人の知恵に感心します。
私の住まいは本山通りで港地区と将軍野の堺線でりんばいさんから北税務署までの町内です。
言われてみれば、新国道とほぼ平行するものの間隔がとても近く、しかも完全な一直線ではなく、ちょっとおもしろいのが川の名残なのでしょうね。
土崎の地図は、新国道と奥羽本線基準で考えてしまい、方向感覚が狂うことがあるのですが、古くからの道で考えると東西南北が分かりやすいですね。
中央地区でも同じですが、通り・小路の名前を表示したり継承したりしていくことが必要かもしれません。