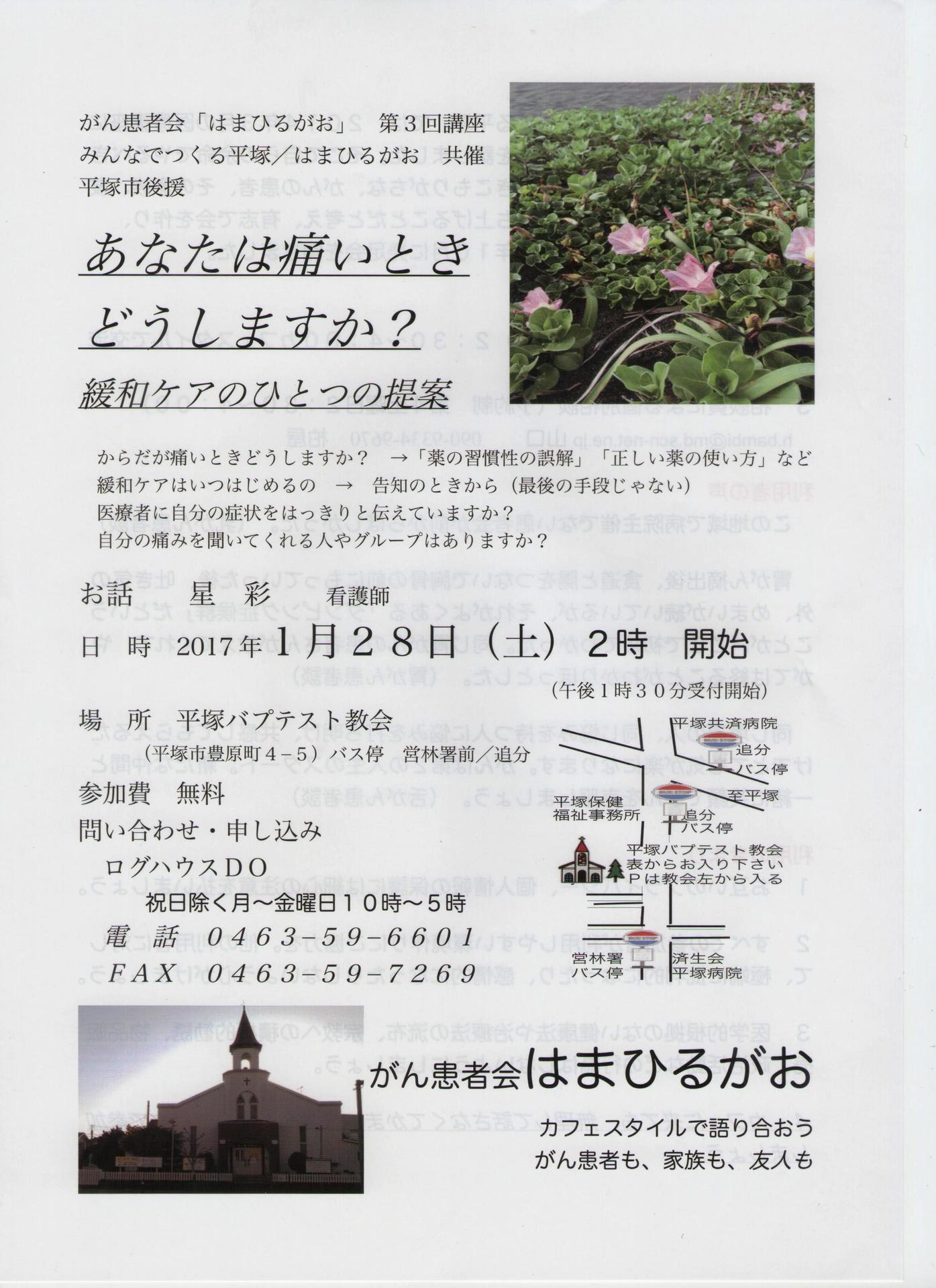牧師室だより 2017年1月29日 他人の靴を履いてみる
「他人の靴を履いてみる」という言葉が英語にあるそうです。人の立場に立って考えるという慣用句です。人の痛みを知るという意味でもあります。痛みは、感性と言ってもいいかもしれません。感性を辞書で引くと、「物事を心で深く感じ取る働き」とあります。それは、一つの出来事について表面的な反応ではなく、一度心でしっかりと受け止めた上で判断することと言えるかもしれません。
ある人が、サーカスの猛獣使いに「ライオンやトラ、クマなどを従わせることができるのはどうしてですか」と聞いたら、猛獣使いはこう答えたと言います。「それは簡単だよ。ゾウはゾウなりに、トラはトラなりに個性を持っている。それぞれ個性に合った使い方をすればいい。それ以外に方法はない」と。同じように、人を成長させたかったら、その人の長所に一番個性が出るのだから、長所を生かして用いることが大切だということです。その長所を見出すには感性を磨く必要があります。
聖書の力を信じるクリスチャンは、自分が行くべき方向を、祈りの中で求めていきます。その中で、それまで自分が思いもしなかったアイデアが与えられたり、覚悟が固まることもあります。その意味で、神に聞くという祈りは、感性を磨き、自分のユニークさや才能を発揮するとても良い方法と言えるでしょう。
あるテーマについて祈り、この方針は神も望むことだという確信を得たら、人間の力がさらに強くなります。神はそういう方法で私たちに責任をとらせて仕事をさせます。だから祈ると決心することができるし、それ以降、心はとてもクリアになるのです。そうした心で行うことは、よき結果に結びつくことが多いものです。
しかし、結果は神にゆだねるもの。神にゆだねるとは、良い結果が出ても自分の手柄としないということです。同じように、悪い結果が出ても人のせいにしないということです。結果を神にゆだねるということは神への信頼、神への祈りから生まれます。