| スタート! |
 |
| 読 了 日 |
2014/02/25 |
| 著 者 |
中山七里 |
| 出 版 社 |
光文社 |
| 形 態 |
単行本 |
| ページ数 |
331 |
| 発 行 日 |
2012/11/20 |
| I S B N |
978-4-334-92857-5 |
上の著者名をクリックすると、著者のページへ移動します。
 昨日、3月16日(日曜日)に、豊岡光生園の保護者会が開催された。正確には会の名称は保護者・家族の会豊岡支部会という。平成25年度最後の会合だ。
昨日、3月16日(日曜日)に、豊岡光生園の保護者会が開催された。正確には会の名称は保護者・家族の会豊岡支部会という。平成25年度最後の会合だ。
豊岡光生園は社会福祉法人・薄光会の中核ともいえる存在の、知的障害者の入所施設である。法人最初の施設で開所後二十数年間は理事長が常駐していたので、法人本部も兼ねていた。
昭和55年開所当時は山間のダム湖のほとりで近代建築を誇っていたが、筑後30年を越す建物は鉄筋コンクリート作りとはいえ、さすがに老朽化を免れず、厳しい財務状況の中で改築のためのプロジェクトチームを発足させた。
プロジェクトチームは設計業者、建築会社との議論を重ねて改築の計画をまとめ上げ、一昨年、平成24年12月から改築が敢行された。
今回の主だった議題はその改築についてだが、1年余の工事期間を終えて、来月、4月20日に豊岡のみならず法人全体のイベントとして竣工式を予定しているので、それについては終了後の別の機会に書くことにする。
さて、保護者・家族の会は元々豊岡光生園を利用する障害児(者)の保護者―主として親たち―によって組織された団体の名称で、当初は施設は1箇所だったから、保護者会と名付けられて保護者会といえば豊岡光生園に入所している園生(当時は入所利用者をそう呼んでいた)の保護者の団体を指していた。
団体は、年数回催される保護者会に参加することや、幾つかの班に分かれて設けられた作業日に、主として細かなメンテナンス作業に従事するといったこと、また園生と一緒に季節ごとのイベント(夏祭り、運動会、クリスマス会等々)を開催する、といった活動をしてきた。そうした活動の中で、保護者同士は自然と絆のような繋がりを培っていった。
 光会はその後豊岡光生園の園生たちが、老後も心置きなく過ごせるようにという目的を以って、安房郡三芳村(現在の南房総市)に特別養護老人ホーム・三芳光陽園を設立開所した。
光会はその後豊岡光生園の園生たちが、老後も心置きなく過ごせるようにという目的を以って、安房郡三芳村(現在の南房総市)に特別養護老人ホーム・三芳光陽園を設立開所した。
さらには地域社会との共生を旗印とする法人は、鴨川市と地元富津市湊に通所施設、鴨川ひかり学園および湊ひかり学園をそれぞれ開園する。
施設が増えるとともに、それぞれの施設の保護者によりそれぞれの保護者会が生まれ、施設独自に活動が始められた。そこで同じ法人内の保護者会の交流を目的に一つの大きな組織に、名前も保護者・家族の会として、豊岡支部会のようにそれぞれの施設においては支部会という名称に変わった。
ところで、自立支援法等の法改正による障害者への対応は、激しいほどの変化を見せて、施設のあり方も利用者の生活により一層寄り添う形に変えざるを得ない状況になった。
その点について詳しく書いていくと、長くなるので省略するが、一言で言えば個別対応を迫られるようになったと言うことか。否、そうした状況は利用者第一をモットーにしているわが薄光会においては、望むところなのだが、いかんせん資金的に余裕のある営みをしているわけではない。
限られた収入の中では十分な介護・支援員を配置したり、個別支援に対応した居住環境を構築することは非常に困難なことなのだ。
 に入所施設において対応の変化を端的に示されたのが、利用者一人当たりの居住面積だ。限られたスペースに立地する施設の中で居住面積を増やすことは不可能に近い。そこで、豊岡光生園では60人だった入所定員を40名に減らして、あまり良い言い方ではないが余剰人員を収納すべく、ケアホーム事業を開始することになる。
に入所施設において対応の変化を端的に示されたのが、利用者一人当たりの居住面積だ。限られたスペースに立地する施設の中で居住面積を増やすことは不可能に近い。そこで、豊岡光生園では60人だった入所定員を40名に減らして、あまり良い言い方ではないが余剰人員を収納すべく、ケアホーム事業を開始することになる。
それらの計画の立案・実行については、実質的なリーダーである幹部職員と、理事長を始めとする法人役員で構成される経営会議が主体となって進められてきた。その結果、現在はケアホームCOCO、ひなたホームズという二つのケアホーム事業が運営されており、ホームの数も7棟となった。
担当職員のたゆまぬ努力は地域社会との交流もスムーズに行われて、次第に障害者の生活や活動が近隣住民に認められるところとなっている。
そうした経過を経てきた保護者・家族の会は、ここ数年の間に新たに入所した利用者の保護者が加わり、またケアホームへの異動となった利用者の保護者とに別れて、全体としての集まりが年2回となった今は、以前ほどの保護者同士のつながりは無くなり、絆は希薄になっている。
古くからの保護者の中には、既に故人となった人も少なくない。そうした状況の中で以前のような保護者の絆を復活させるのは困難なことだ。法の下に保護される反面、厳しい監視下に置かれる社会福祉法人の運営の一端を担ってきた古くからの保護者への対応も、法人として考えるべき課題の一つではないだろうか?
会の終了後そんなことも頭の隅をよぎったのだが、今や、様々な世代が入り混じった状態と、出発時点と異なる社会環境の下では、施設に対する思いもそれぞれに異なるだろうから、簡単ではない。
さて・・・・。
社会福祉法人の一員として何の力にもなれない自分をもどかしく思いながら、数十年の時の流れを振り返ると、様々な、時には激動の時代の中での出来事が去来する。
一方で、世代交代の始まった職員のリーダーたちの若い力が、変革の時代を乗り越えて薄光会の発展と、多くの利用者の生活の安寧を支えていくことだろう、という安心感も生まれる。年寄りの繰言がだいぶ長くなった。
 者・中山七里氏は次々と話題作を発表する傍ら、テレビ番組への出演など目覚しい活躍ぶりだ。 デビュー作の「さよならドビュッシー」を読んだ頃の、その音楽性と巧みな表現力が、この作者は何者なんだろう?と言った謎めいた神秘性は薄れたものの、逆に著者の言葉から編集者の難しい注文に応えて、傑作を物にする職人魂のようなものを感じいる。
者・中山七里氏は次々と話題作を発表する傍ら、テレビ番組への出演など目覚しい活躍ぶりだ。 デビュー作の「さよならドビュッシー」を読んだ頃の、その音楽性と巧みな表現力が、この作者は何者なんだろう?と言った謎めいた神秘性は薄れたものの、逆に著者の言葉から編集者の難しい注文に応えて、傑作を物にする職人魂のようなものを感じいる。
この作者の特徴は、どの作品にも結末の意外性が盛り込まれており、読者の予想をあっさりと裏切る、といったところだ。
多分、と作者の心境を推測すれば、物語を作る過程で、今度はどんな手法で読者を「アッ!」と言わせようか、そんな読者へのサービス精神にあふれる思いで、ストーリー構成を考え進めているのではないか、そんなことを思うのだ。
2年前に読んだ「さよならドビュッシー」の番外編ともいえる「要介護探偵の事件簿」(文庫化に際しては、「さよならドビュッシー前奏曲(プレリュード)」となっている。)、僕はこの1作で作者の虜になってしまい、直ぐその後に「さよならドビュッシー」を読み、ますますその魅力に取り付かれてしまったのだ。
僕にとって10冊目となる本書の舞台は、映画の製作現場だ。だからタイトルの「スタート!」は、勿論監督が発する撮影開始の号令だ。それに従って助監督が打ち鳴らす?のはカチンコと呼ばれる道具だ。
最近では必ずしも監督が「スタート」と言う言葉を発するとは限らず、人によっては「ヨーイ、ハイ」と言ったりすることもあるようだ。海外では大抵「Action=アクション」と言ってるのを耳にする。 映画の製作に関して、一番の課題は資金集めだろう、そうしたことがネックとなって、しばらく製作現場から遠のいていた日本映画界の巨匠・大森宗俊が3年ぶりに暖めていた企画を以って、製作を開始すると言う。
常にコンビを組んできたカメラマンの小森から連絡を受けた助監督の宮藤映一は、再び始まる大森組の製作活動を思い、胸が高鳴るのだった。というのもローコストで安易な映画作りに参加することで、映画への情熱を保ってきたつもりが、試写会の席で耳にするのは、素人の観客から発せられた酷評だったから、腐っていたところなのだ。

 森宗俊が暖めていた企画とは、「災厄の季節」と言うタイトルだ。そして、彼が選んだ脚本家は大方の予想を覆して、売り出し中の若手・六車圭輔だった。陰で天皇とも呼ばれるうるさ型の大森に劣らず、若手ながらこだわりを持つ脚本家が六車だったからだ。
森宗俊が暖めていた企画とは、「災厄の季節」と言うタイトルだ。そして、彼が選んだ脚本家は大方の予想を覆して、売り出し中の若手・六車圭輔だった。陰で天皇とも呼ばれるうるさ型の大森に劣らず、若手ながらこだわりを持つ脚本家が六車だったからだ。
いつも大森組の資金集めに奔走するのは、五社和夫だ。大森組の準備作業であるオールスタッフは、大森監督の自宅で行われるのが通例だ。だが今回はその五社プロ一社の資金では賄いきれずに、製作委員会方式での製作だと言う。
さらには主たる資金提供者である帝都テレビからの横槍で、主演女優や、チーフ助監督の入れ替えを余儀なくされたのだ。脚本の六車は主演女優の入れ替えで、イメージが違うと言うことで急遽書き直しをすることになる。そんなこんなで波乱の幕開けとなった製作現場だが、事件はそれだけでは終わらなかった。
何と殺人事件まで発生する始末だ。
僕は読みながらはるか昔の、黒澤明監督による映画「影武者」(1980年東宝 仲代達矢他)の製作余話を思い出した。作中の大森監督の中にも一部分では黒澤監督のイメージも含まれているが、多分著者は名匠といわれる映画監督の何人かを統合した人物を作り上げたのではないかと思われる。
勿論直接このストーリーが映画「影武者」と似ているわけではない。次々と問題が発生する本編のストーリーが、当初、影武者の武田信玄役に勝新太郎氏で撮影が開始されたのだが、監督と勝氏の間でのいざこざが元で、勝氏の降板ということになり、仲代達矢氏へと主役交代になった経緯などを、思い出させたのだ。
映画ファンならずとも製作現場のリアルな描写は、胸躍る展開だろう。他の作品に比較して、ミステリー味はほんの少し薄い気もするが、終盤の感動のシーンが胸を打つ。

 くほどのスピードで話題作、問題作を発表し続ける著者のエネルギーはどこから出てくるのだろう?と、そのバイタリティあふれる執筆活動にただただ畏敬の念を覚えるばかりだ。
くほどのスピードで話題作、問題作を発表し続ける著者のエネルギーはどこから出てくるのだろう?と、そのバイタリティあふれる執筆活動にただただ畏敬の念を覚えるばかりだ。

 編では前に読んだ短編集で活躍する警視庁捜査一課の刑事・犬養隼人を登場させており、この刑事が登場するストーリーがシリーズの形を作り続けるのか、期待が持てるところだ。
編では前に読んだ短編集で活躍する警視庁捜査一課の刑事・犬養隼人を登場させており、この刑事が登場するストーリーがシリーズの形を作り続けるのか、期待が持てるところだ。










 ばらくブログの更新を怠ってしまった。3日に1冊くらいは読もうと思えばできないことはないのだが、書くとなると簡単ではない。だから一度休んでしまうと、今日は書こう、明日こそ書こうなどと思っている内に、1週間や10日はあっという間に過ぎてしまう。
ばらくブログの更新を怠ってしまった。3日に1冊くらいは読もうと思えばできないことはないのだが、書くとなると簡単ではない。だから一度休んでしまうと、今日は書こう、明日こそ書こうなどと思っている内に、1週間や10日はあっという間に過ぎてしまう。 書は前にいすみ市を訪れた際、古書店・ブックセンターあずまで見つけたものだ。もうこの店に行くこともめったにないだろうと思うと、なんとなく感慨深いものがある。初老のおかみさんや、あまり商売熱心とも見えない若い息子とも、顔なじみになったので少し残念な気もする。
書は前にいすみ市を訪れた際、古書店・ブックセンターあずまで見つけたものだ。もうこの店に行くこともめったにないだろうと思うと、なんとなく感慨深いものがある。初老のおかみさんや、あまり商売熱心とも見えない若い息子とも、顔なじみになったので少し残念な気もする。
 と同様社会福祉法人薄光会の役員(理事)を務めるMKさんから、辞めるのを思いとどまるよう励ましのメールを何度もいただいた。初めて読む人は何の事だかわからないだろうが、先日(4月20日)行われた豊岡光生園の改築の竣工式に於いて、(僕に対する)施設側のちょっとした手違い(だと思われる)から、僕が非常に恥ずかしい思いを抱き、10年来務めた監事職を辞退しようと思ったことに対しての励ましである。
と同様社会福祉法人薄光会の役員(理事)を務めるMKさんから、辞めるのを思いとどまるよう励ましのメールを何度もいただいた。初めて読む人は何の事だかわからないだろうが、先日(4月20日)行われた豊岡光生園の改築の竣工式に於いて、(僕に対する)施設側のちょっとした手違い(だと思われる)から、僕が非常に恥ずかしい思いを抱き、10年来務めた監事職を辞退しようと思ったことに対しての励ましである。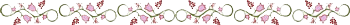
 突に昔の、それも小学生から中学生にかけての、昭和20年代の頃だから大昔といえるだろう、そんな昔を思い出すことが最近になって多くなった。多分歳のせいということもあるだろうが、記憶というものの不思議さを感じる。
突に昔の、それも小学生から中学生にかけての、昭和20年代の頃だから大昔といえるだろう、そんな昔を思い出すことが最近になって多くなった。多分歳のせいということもあるだろうが、記憶というものの不思議さを感じる。 書がそれでも全然面白くなかったかといえば、そんなことはなく登場人物のゲームライターという初めて聞く職業に、興味をひかれた。僕はまだ見たことはないが、ゲームに関する記事を中心とした雑誌があるらしく、本書はそこに寄稿するライターを描いた連作短編集だ。流川映(あきら)という伝説的なライターを目標にする、柵馬朋康を中心としたストーリーが展開される。 途中から作者と思われる詠坂(よみさか)という人物も登場して、柵馬とゲーム論を戦わせたりもする。ファミコンの登場時からの人気ゲーム「マリオブラザース」についての、「穴へはキノコをおいかけて」をはじめとして、映画にもなったドラクエこと「ドラゴンクエスト」について語られる最終作「そしてまわりこまれなかった」まで、ゲームを知っていればもう少し別の楽しみ方もあったかと思われるが、ちょっと残念な気もする。
書がそれでも全然面白くなかったかといえば、そんなことはなく登場人物のゲームライターという初めて聞く職業に、興味をひかれた。僕はまだ見たことはないが、ゲームに関する記事を中心とした雑誌があるらしく、本書はそこに寄稿するライターを描いた連作短編集だ。流川映(あきら)という伝説的なライターを目標にする、柵馬朋康を中心としたストーリーが展開される。 途中から作者と思われる詠坂(よみさか)という人物も登場して、柵馬とゲーム論を戦わせたりもする。ファミコンの登場時からの人気ゲーム「マリオブラザース」についての、「穴へはキノコをおいかけて」をはじめとして、映画にもなったドラクエこと「ドラゴンクエスト」について語られる最終作「そしてまわりこまれなかった」まで、ゲームを知っていればもう少し別の楽しみ方もあったかと思われるが、ちょっと残念な気もする。
 刊本でしかも単行本を買うのはいつ以来だろう?ほんのちょっと少しばかり臨時収入があり、と言っても僕のちょっというのは文字通りほんのわずかな額だ。そうした時に僕のとる行動は子供の頃から決まっており、一つしかない。つまり本を買うことなのだ。
刊本でしかも単行本を買うのはいつ以来だろう?ほんのちょっと少しばかり臨時収入があり、と言っても僕のちょっというのは文字通りほんのわずかな額だ。そうした時に僕のとる行動は子供の頃から決まっており、一つしかない。つまり本を買うことなのだ。
 愛の妻・菜穂子との間に桃子という一人娘もできて、幸せなサラリーマン生活と家庭生活を送っているはずの杉村三郎には、どうしたことか事件が付きまとう。
愛の妻・菜穂子との間に桃子という一人娘もできて、幸せなサラリーマン生活と家庭生活を送っているはずの杉村三郎には、どうしたことか事件が付きまとう。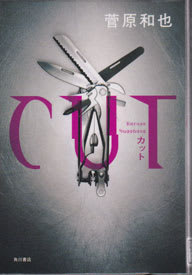
 の中は僕が考えているほど単純ではなく、大部分の人たちにとっては、思うに任せないのが現状ではないかと感じている。僕にすれば、「天下の回りもの」と言われるものが、一向に僕の所には回ってこないのも、その一環ではないか。
の中は僕が考えているほど単純ではなく、大部分の人たちにとっては、思うに任せないのが現状ではないかと感じている。僕にすれば、「天下の回りもの」と言われるものが、一向に僕の所には回ってこないのも、その一環ではないか。 イトルのCUT(カット)が示すように、本書はある意味ではサイコ・キラーの物語だ。
イトルのCUT(カット)が示すように、本書はある意味ではサイコ・キラーの物語だ。
 族館を意味するこの「アクエリアム」というタイトルが、何かしら気になっていた。
族館を意味するこの「アクエリアム」というタイトルが、何かしら気になっていた。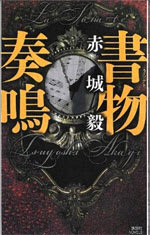
 が逝った。96歳とは言いながら、元気―といっても元気で動き回っていたと言う意味ではなく、病気でなかったと言うことだが―な一人暮らしの日常生活を送っていたから、1昨々日の18日朝、妹からの電話で、母の突然の死を知らされた時は、あまりの急な話に一瞬信じられない思いが湧く。
が逝った。96歳とは言いながら、元気―といっても元気で動き回っていたと言う意味ではなく、病気でなかったと言うことだが―な一人暮らしの日常生活を送っていたから、1昨々日の18日朝、妹からの電話で、母の突然の死を知らされた時は、あまりの急な話に一瞬信じられない思いが湧く。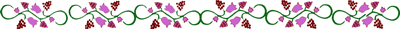
 主となる僕は先に近くの葬儀社に行き葬儀の日程等を打ち合わせる。極々内輪での葬儀なので、通夜は行わず告別式のみ行うこと、葬儀社から市営の火葬場の予約を取ってもらうことなどを依頼する。19日が友引なので、告別式は20日となる。
主となる僕は先に近くの葬儀社に行き葬儀の日程等を打ち合わせる。極々内輪での葬儀なので、通夜は行わず告別式のみ行うこと、葬儀社から市営の火葬場の予約を取ってもらうことなどを依頼する。19日が友引なので、告別式は20日となる。 書人としては、このようなタイトルを見逃すわけには行かないのだが、何と調べたら第1作の「書物狩人」が2010年4月に敢行されて、以下続々とシリーズは続いて、最新刊である本書まで既に8巻が出ているということに、驚いた。
書人としては、このようなタイトルを見逃すわけには行かないのだが、何と調べたら第1作の「書物狩人」が2010年4月に敢行されて、以下続々とシリーズは続いて、最新刊である本書まで既に8巻が出ているということに、驚いた。 んな調査能力や情報の収集能力を見ていると、僕は前に読んだ「インフォメーショニスト」(テイラー・スティーヴンス著 講談社文庫)が思い浮かぶ。もちろん内容は全くの別物だが、お互い依頼人の仕事をこなすために調査や情報の収集に奔走するところが共通の点である。
んな調査能力や情報の収集能力を見ていると、僕は前に読んだ「インフォメーショニスト」(テイラー・スティーヴンス著 講談社文庫)が思い浮かぶ。もちろん内容は全くの別物だが、お互い依頼人の仕事をこなすために調査や情報の収集に奔走するところが共通の点である。
 昨日、3月16日(日曜日)に、豊岡光生園の保護者会が開催された。正確には会の名称は保護者・家族の会豊岡支部会という。平成25年度最後の会合だ。
昨日、3月16日(日曜日)に、豊岡光生園の保護者会が開催された。正確には会の名称は保護者・家族の会豊岡支部会という。平成25年度最後の会合だ。
 光会はその後豊岡光生園の園生たちが、老後も心置きなく過ごせるようにという目的を以って、安房郡三芳村(現在の南房総市)に特別養護老人ホーム・三芳光陽園を設立開所した。
光会はその後豊岡光生園の園生たちが、老後も心置きなく過ごせるようにという目的を以って、安房郡三芳村(現在の南房総市)に特別養護老人ホーム・三芳光陽園を設立開所した。 に入所施設において対応の変化を端的に示されたのが、利用者一人当たりの居住面積だ。限られたスペースに立地する施設の中で居住面積を増やすことは不可能に近い。そこで、豊岡光生園では60人だった入所定員を40名に減らして、あまり良い言い方ではないが余剰人員を収納すべく、ケアホーム事業を開始することになる。
に入所施設において対応の変化を端的に示されたのが、利用者一人当たりの居住面積だ。限られたスペースに立地する施設の中で居住面積を増やすことは不可能に近い。そこで、豊岡光生園では60人だった入所定員を40名に減らして、あまり良い言い方ではないが余剰人員を収納すべく、ケアホーム事業を開始することになる。 者・中山七里氏は次々と話題作を発表する傍ら、テレビ番組への出演など目覚しい活躍ぶりだ。 デビュー作の「さよならドビュッシー」を読んだ頃の、その音楽性と巧みな表現力が、この作者は何者なんだろう?と言った謎めいた神秘性は薄れたものの、逆に著者の言葉から編集者の難しい注文に応えて、傑作を物にする職人魂のようなものを感じいる。
者・中山七里氏は次々と話題作を発表する傍ら、テレビ番組への出演など目覚しい活躍ぶりだ。 デビュー作の「さよならドビュッシー」を読んだ頃の、その音楽性と巧みな表現力が、この作者は何者なんだろう?と言った謎めいた神秘性は薄れたものの、逆に著者の言葉から編集者の難しい注文に応えて、傑作を物にする職人魂のようなものを感じいる。 森宗俊が暖めていた企画とは、「災厄の季節」と言うタイトルだ。そして、彼が選んだ脚本家は大方の予想を覆して、売り出し中の若手・六車圭輔だった。陰で天皇とも呼ばれるうるさ型の大森に劣らず、若手ながらこだわりを持つ脚本家が六車だったからだ。
森宗俊が暖めていた企画とは、「災厄の季節」と言うタイトルだ。そして、彼が選んだ脚本家は大方の予想を覆して、売り出し中の若手・六車圭輔だった。陰で天皇とも呼ばれるうるさ型の大森に劣らず、若手ながらこだわりを持つ脚本家が六車だったからだ。
 瀬隼介氏の名前と作品について知ったのは、実はこの本ではなく「刑事の骨」と言う作品を、最近何処かで紹介されていたのを見たからだ。ところが例によって図書館はどこも貸し出し中なので、処女作である本書を木更津市立図書館で借りてきた。「刑事の骨」はいずれまた、貸し出し中が無くなったら借りて読むことにしよう。
瀬隼介氏の名前と作品について知ったのは、実はこの本ではなく「刑事の骨」と言う作品を、最近何処かで紹介されていたのを見たからだ。ところが例によって図書館はどこも貸し出し中なので、処女作である本書を木更津市立図書館で借りてきた。「刑事の骨」はいずれまた、貸し出し中が無くなったら借りて読むことにしよう。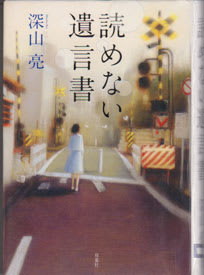
 になるタイトルは、ただメモするだけでなくどこで誰が紹介していたのか、あるいはどこで目にしたのかも書いておけばここでの話題にもなるからいいのだが、つい忘れがちで読書ノートの後ろには、タイトルと著者名だけが列記されている。
になるタイトルは、ただメモするだけでなくどこで誰が紹介していたのか、あるいはどこで目にしたのかも書いておけばここでの話題にもなるからいいのだが、つい忘れがちで読書ノートの後ろには、タイトルと著者名だけが列記されている。 ろ向きの話はさておいて、折角の幸せな気分を取り戻そう。
ろ向きの話はさておいて、折角の幸せな気分を取り戻そう。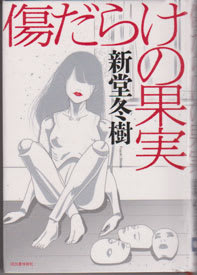
 早、BSイレブンの看板番組となった(多分、僕の独りよがりではないと思う)「宮崎美子のすずらん本屋堂」には、毎回多彩な作家をゲストとして迎え、MCの宮崎美子氏(番組の中で彼女自身は店主と言う言い方をしている)と楽しいトークを繰り広げている。
早、BSイレブンの看板番組となった(多分、僕の独りよがりではないと思う)「宮崎美子のすずらん本屋堂」には、毎回多彩な作家をゲストとして迎え、MCの宮崎美子氏(番組の中で彼女自身は店主と言う言い方をしている)と楽しいトークを繰り広げている。 て、本の話だ。僕はタイトルから想像していたストーリー展開と、大筋のところで合致していたので、その点は逆にちょっとがっかりしたが、最後の一捻りはさすがだ。ただ、テレビ番組の中では宮崎氏が「ノワールの旗手である著者が、新境地の作品・・・」とか言っていたが、僕はこれが初めての新堂氏の作品なので、他の作品との比較は出来ないが、何と言うか手馴れた感じのストーリー構成に思えた。
て、本の話だ。僕はタイトルから想像していたストーリー展開と、大筋のところで合致していたので、その点は逆にちょっとがっかりしたが、最後の一捻りはさすがだ。ただ、テレビ番組の中では宮崎氏が「ノワールの旗手である著者が、新境地の作品・・・」とか言っていたが、僕はこれが初めての新堂氏の作品なので、他の作品との比較は出来ないが、何と言うか手馴れた感じのストーリー構成に思えた。
 に25―26日といすみ市大原へ行くことになって、ブログの更新が予定を遅れた。大原行きは先方で思わぬアクシデントに見舞われ(それも遅れの理由の一つだ)たが、その話はまた後で別の形で書くことにして、今日は去る(2月)23日(日曜日)に、僕が監事を務める社会福祉法人薄光会で行われた評議員会、理事会についての話題を少し書いて見ようと思う。 例年この時期の会合では、当期の第二次補正予算案、次年度の事業計画案が主たる議題である。
に25―26日といすみ市大原へ行くことになって、ブログの更新が予定を遅れた。大原行きは先方で思わぬアクシデントに見舞われ(それも遅れの理由の一つだ)たが、その話はまた後で別の形で書くことにして、今日は去る(2月)23日(日曜日)に、僕が監事を務める社会福祉法人薄光会で行われた評議員会、理事会についての話題を少し書いて見ようと思う。 例年この時期の会合では、当期の第二次補正予算案、次年度の事業計画案が主たる議題である。
 方新に若手の施設長が誕生することには、もろ手を挙げて歓迎したい。
方新に若手の施設長が誕生することには、もろ手を挙げて歓迎したい。 じ文学賞ではあっても、時代の流れとともに選考委員も変わっていくから(近年その交代期間は短くなっているようだ)、それに伴う受賞作の傾向も変化していくことは、避けられないことだろう。
じ文学賞ではあっても、時代の流れとともに選考委員も変わっていくから(近年その交代期間は短くなっているようだ)、それに伴う受賞作の傾向も変化していくことは、避けられないことだろう。
 日までの気象情報では、今日(2月19日)にもまた雪となる予報となっていた。だが南岸低気圧の進路変更に伴って、どうやら再びの雪は免れたようだ。短い間に関東平野の沿岸地帯にこれほどの積もる雪が降るのは極めて珍しいことだ。
日までの気象情報では、今日(2月19日)にもまた雪となる予報となっていた。だが南岸低気圧の進路変更に伴って、どうやら再びの雪は免れたようだ。短い間に関東平野の沿岸地帯にこれほどの積もる雪が降るのは極めて珍しいことだ。
 ころで、本書の「冤罪死刑」というタイトルの意味が、いまいちよく判らないまま読み進むが、何度かその意味をうかがわせる様な事態が起きるにもかかわらず、結局終盤に到るまでその意味は隠されたまま進む。
ころで、本書の「冤罪死刑」というタイトルの意味が、いまいちよく判らないまま読み進むが、何度かその意味をうかがわせる様な事態が起きるにもかかわらず、結局終盤に到るまでその意味は隠されたまま進む。
 画という呼び方で、従来の漫画とは一線を画すようになったのはいつ頃だったのだろうか?
画という呼び方で、従来の漫画とは一線を画すようになったのはいつ頃だったのだろうか? 画編集者の仕事は、漫画家から原稿を受け取るばかりでなく、作品の傾向を示したり、ストーリーのヒントを考えたりと、作者と一体になってプロデュースの一端を担うということのようだ。時には原作者のように筋書きを考えたりもするという。
画編集者の仕事は、漫画家から原稿を受け取るばかりでなく、作品の傾向を示したり、ストーリーのヒントを考えたりと、作者と一体になってプロデュースの一端を担うということのようだ。時には原作者のように筋書きを考えたりもするという。
 評番組で紹介されたミステリーを次々と読めるのは、手元不如意となって仕方なく始めた、図書館通いのおかげだ。懐の寂しいのはあまり歓迎すべきことではないが、古書店めぐりを控えての図書館通いは、新刊でなければ割りと順調にことが運び、読みたい本を読むことができて、心豊かだ。
評番組で紹介されたミステリーを次々と読めるのは、手元不如意となって仕方なく始めた、図書館通いのおかげだ。懐の寂しいのはあまり歓迎すべきことではないが、古書店めぐりを控えての図書館通いは、新刊でなければ割りと順調にことが運び、読みたい本を読むことができて、心豊かだ。
 織が送り込む女性は様々な手段で確保して、若い女子高生から人妻や年配者、果ては妊婦までが登録されて、客の要望に応えている。デリヘルはいくつかのチームで組織されており、チームごとにそれをまとめるリーダーがいる。
織が送り込む女性は様々な手段で確保して、若い女子高生から人妻や年配者、果ては妊婦までが登録されて、客の要望に応えている。デリヘルはいくつかのチームで組織されており、チームごとにそれをまとめるリーダーがいる。