| 烏女 | ||
|---|---|---|
 |
||
| 読 了 日 | 2013/12/12 | |
| 著 者 | 海月ルイ | |
| 出 版 社 | 双葉社 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 323 | |
| 発 行 日 | 2003/12/20 | |
| ISBN | 4-575-23487-7 | |
 年もいよいよ残すところ、今日を含めて3日となった。毎年この時期になると、何か遣り残したことがあるのではないかと、心中穏やかではなくなる。役立たずの年寄りにそんなことは何もないのだが、生来の貧乏性のためだろう。いつも何かに追い立てられているような気になるのだ。
年もいよいよ残すところ、今日を含めて3日となった。毎年この時期になると、何か遣り残したことがあるのではないかと、心中穏やかではなくなる。役立たずの年寄りにそんなことは何もないのだが、生来の貧乏性のためだろう。いつも何かに追い立てられているような気になるのだ。
それと言うのも、実は押し詰まった27日の1昨日になって、ヤフオクにCDと処分せずに残してあったサイン本を出品したのだ。CDはその前にBOOKOFFで幾らくらいで売れるだろうかと、持って行ったら11枚で950円だと言う。僕は内心まあそんなものだろうと、売らずに持ち帰ってネットオークションに出すことにしたのだ。
サイン本のほうは、東京創元社のネット販売でポツポツと買っておいたものが7冊ほどあったので、こちらははなからBOOKOFFでは値段がつかないだろうと思い、同じくネットに出品することにしていた。
BOOKOFFなどでの処分は買い取り価格は安いが、まとめて処分できるのがメリットだ。ネット販売では高く売れるが、一度には売れないからどちら良いかは、そのときの判断だ。

と言うようなこともあって、押し詰まってから出品したものだから、2―3落札の通知などもあり、慌ててメール便で発送手続きなどをしている状態なのだ。
クロネコメール便は近くの7イレブンで済むが、ゆうメールは近くの特定郵便局は閉まっているから、少し離れた本局まで行く必要があって、少しばかりせわしない思いをしている。明けてからゆっくりやればよかったと、後悔しても遅い。
以前ネット販売に入れ込んでいた頃は、もう少し手際がよかったのだが、しばらくやってなかったので、要領が悪くなった。歳をとったせいもあるのだろう。
歳のせいといえば、近頃は割りと得意だと思っていた数独を解くのに、かなりの時間を要するようになった。頭の回転はもともと速い方ではないが、気力の衰えが脳の働きにも影響するのか?体の動きにもそれは現れる。イメージと少しずつずれて行くような気がして、心もとない。
何の話をしてるのかわからなくなってきた。今年最後の無駄話だ。

 分しばらくぶりの著者の作品だと思って、記録をたどったら前回「京都祇園迷宮事件」を読んだのは、2011年の12月だった。2年ぶりとなる本書はホラーを思わせるようなタイトルと表紙だ。
分しばらくぶりの著者の作品だと思って、記録をたどったら前回「京都祇園迷宮事件」を読んだのは、2011年の12月だった。2年ぶりとなる本書はホラーを思わせるようなタイトルと表紙だ。
僕の中では「サスペンスの名手」という認識を著者に対して持っているから、このタイトルと表紙の絵には少々違和感があった。そのため、実はこの本はかなり前に買ってあったにもかかわらず、読むのが遅くなっていたのだ。(と、思っているが、単に僕の気まぐれと言える)
そこいら辺が読書人としては、有ってはならないところなのだが、まあ、これも僕の性分だから仕方がないか?
自分では意識してないが、僕の中にはいろいろと拘りがあるようで、人に対してはそれほどでもない(と自分では思っている)が、自分に対しては拘りというより変なところで完全主義なのかもしれない。
著者の海月ルイ氏は「子盗り」で、もうかなり前になくなったサントリーミステリー大賞の大賞と読者賞をダブル受賞した。2002年のことだから、もう10年以上前のことだ。
感情移入の激しい僕はその「子盗り」を読んで、胸の痛くなるような不安感に襲われて、サスペンス作家として海月氏を強く意識するようになった。だが、僕が好きになる女性作家には寡作な人も多く、海月氏の作品もそれほど多くはないのだ。
多分此の作品で、僕は氏の作品を全部読んでしまったのではないだろうか?
本作は期待したほどのサスペンス性はなかったが、会談めいた部分もあって、それなりに楽しんで読んだ。 子育てや主婦業をこなしながらの著作は楽ではないだろうが、また胸の痛くなるようなサスペンスを期待している。
ここに書くのも今年はこれで最後になった。年々1年の過ぎるのが早く感じられるようになっている。来年はどんな年になるのだろう?
僕のつたない文を読んで下さった皆さん、ありがとうございました。どうぞよいお年をお迎えになってください。そして、また来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
にほんブログ村 |











 説以外にミステリーに関する文献や評論などもたまに読んでいるので、このタイトルも著者の名前も以前から知っていたような気がする。いや、若しかしたらどこかでその年のミステリーベスト10などという記事を見たのかもしれない。
説以外にミステリーに関する文献や評論などもたまに読んでいるので、このタイトルも著者の名前も以前から知っていたような気がする。いや、若しかしたらどこかでその年のミステリーベスト10などという記事を見たのかもしれない。 ョージ・ランバートというのが本編の主人公だ。彼は、公務員の仕事を終えて帰宅すると、台所にガスが充満しており、妻のヒルダが倒れているのを発見する。彼には何がなんだかわからなかったが、どうやらヒルダは自殺らしい。ヒルダとの間にはジェーンという17歳になる娘が居るが、躁うつ病で入院していた。
ョージ・ランバートというのが本編の主人公だ。彼は、公務員の仕事を終えて帰宅すると、台所にガスが充満しており、妻のヒルダが倒れているのを発見する。彼には何がなんだかわからなかったが、どうやらヒルダは自殺らしい。ヒルダとの間にはジェーンという17歳になる娘が居るが、躁うつ病で入院していた。
 月、2013年11月2日が僕の74歳の誕生日で、それを前に1,400冊を読み終えて、どうやら年100冊という目標を達成することが出来た。60歳から始めた此の読書記録も来月2日で丸々14年を経過することになる。
月、2013年11月2日が僕の74歳の誕生日で、それを前に1,400冊を読み終えて、どうやら年100冊という目標を達成することが出来た。60歳から始めた此の読書記録も来月2日で丸々14年を経過することになる。
 て、1400冊目となるこの作品も、BOOKOFFの棚を見ていて見つけた本だ。これを最初に読んだのはいつ頃だっただろう。多分、高校を卒業した後の昭和30年代の半ばだったと思うが、僕のあやふやな記憶では、そのころ僕が読んだ清張作品は光文社から刊行されているカッパノベルスが多かったので、此の作品もそうではないかと思うが、定かではない。
て、1400冊目となるこの作品も、BOOKOFFの棚を見ていて見つけた本だ。これを最初に読んだのはいつ頃だっただろう。多分、高校を卒業した後の昭和30年代の半ばだったと思うが、僕のあやふやな記憶では、そのころ僕が読んだ清張作品は光文社から刊行されているカッパノベルスが多かったので、此の作品もそうではないかと思うが、定かではない。
 ン読本の消化、第2弾だ。
ン読本の消化、第2弾だ。
 人探偵の執念めいた調査のエネルギーがどこから湧いてくるのか?その必然性に疑問を感じると、もういけない。ついていけなくなるのだ。
人探偵の執念めいた調査のエネルギーがどこから湧いてくるのか?その必然性に疑問を感じると、もういけない。ついていけなくなるのだ。
 ブタイトルに「てのひらの闇Ⅱ」とあるが、 残念ながら僕は前に読んだ「てのひらの闇」の内容をまったく覚えていない。記録をたどると、2006年の12月に「てのひらの闇」を読んでおり、 きっかけはドラマを見たことだった。
ブタイトルに「てのひらの闇Ⅱ」とあるが、 残念ながら僕は前に読んだ「てのひらの闇」の内容をまったく覚えていない。記録をたどると、2006年の12月に「てのひらの闇」を読んでおり、 きっかけはドラマを見たことだった。 は読書の途中で、時折作家の博識さに驚くことがある。やはり一つの物語を紡ぎだすためには、それ相応の取材や、資料調べをするのだろうが、作家諸氏のすごいところはそうして得た知識をストーリーに組み立ててしまうところだ。あたかもその道のエキスパートであるがごとく。
は読書の途中で、時折作家の博識さに驚くことがある。やはり一つの物語を紡ぎだすためには、それ相応の取材や、資料調べをするのだろうが、作家諸氏のすごいところはそうして得た知識をストーリーに組み立ててしまうところだ。あたかもその道のエキスパートであるがごとく。
 回見ているわけではないが、書評番組の一つとして見ているのが、Axnミステリーの「早川書房ブックリエ」という番組だ。これは早川書房がベテラン編集者を本(ブック)のソムリエ、ブックリエと呼んで、それぞれの担当している中からその月のお勧め本の紹介をするというものである。
回見ているわけではないが、書評番組の一つとして見ているのが、Axnミステリーの「早川書房ブックリエ」という番組だ。これは早川書房がベテラン編集者を本(ブック)のソムリエ、ブックリエと呼んで、それぞれの担当している中からその月のお勧め本の紹介をするというものである。
 判は欧米の陪審員裁判形式を踏襲することになり、被告・大出俊次をめぐり、検察と弁護側と別れ、それぞれ証人を喚問して、その証言により、陪審員に判断させるというものだ。
判は欧米の陪審員裁判形式を踏襲することになり、被告・大出俊次をめぐり、検察と弁護側と別れ、それぞれ証人を喚問して、その証言により、陪審員に判断させるというものだ。
 の作品は新潮社の月刊誌「小説新潮」に、2002年(平成14年)10月号から2011年(平成23年)11月号まで、実に9年1ヶ月という長期間に及び連載されたあと、第1部が刊行されるまでさらに9ヶ月を経ているから、おおよそ10年という長い年月をかけた一大エンタテインメントだ。
の作品は新潮社の月刊誌「小説新潮」に、2002年(平成14年)10月号から2011年(平成23年)11月号まで、実に9年1ヶ月という長期間に及び連載されたあと、第1部が刊行されるまでさらに9ヶ月を経ているから、おおよそ10年という長い年月をかけた一大エンタテインメントだ。 際には700余ページにも及ぶ内容が、もちろん、そう簡単に片付く話ではなく、落下死体事件は次々と派生的に問題を引き起こし、学校内の教師の勢力図から、PTAの問題、生徒たちの家庭の問題等々へとストーリーを展開させるのだ。
際には700余ページにも及ぶ内容が、もちろん、そう簡単に片付く話ではなく、落下死体事件は次々と派生的に問題を引き起こし、学校内の教師の勢力図から、PTAの問題、生徒たちの家庭の問題等々へとストーリーを展開させるのだ。
 書が出たのはつい この前だという感じがしていたが、もう1年が過ぎようとしていることに、少なからず驚きを感じる。出版業界が不況だと言われていることが嘘のように、次々と新刊が出てくることに、僕などは目まぐるしいほどの思いに駆られる。
書が出たのはつい この前だという感じがしていたが、もう1年が過ぎようとしていることに、少なからず驚きを感じる。出版業界が不況だと言われていることが嘘のように、次々と新刊が出てくることに、僕などは目まぐるしいほどの思いに駆られる。

 庫化されてから急激に売り上げを伸ばしたらしい本書を、古書店で買おうかどうか迷っていた。この読書記録を始めたころ、僕はサイコサスペンスにはまっており、よく「目を覆うような惨劇」などと形容される場面には、あまり抵抗なく入っていける。
庫化されてから急激に売り上げを伸ばしたらしい本書を、古書店で買おうかどうか迷っていた。この読書記録を始めたころ、僕はサイコサスペンスにはまっており、よく「目を覆うような惨劇」などと形容される場面には、あまり抵抗なく入っていける。 み始めてすぐ、やはり図書館で借りたのが正解だった、という思いが湧き上がった。僕が読みたくないと思っていたような、幼児虐待が事細かに描かれるストーリーに、拒絶反応が起こったからだ。
み始めてすぐ、やはり図書館で借りたのが正解だった、という思いが湧き上がった。僕が読みたくないと思っていたような、幼児虐待が事細かに描かれるストーリーに、拒絶反応が起こったからだ。
 し前(6月下旬だったと思うが)の夕方、なんとなくテレビのスイッチを入れると、夕方の番組「ゆうどきネットワーク」(NHK総合テレビで、ウィークデイの17:10ごろからの番組、僕は普段テレビはNHKのニュース番組くらいしか見ないからちゃんねるはいつもNHKになっている)をやっており、メインキャスター山本アナの隣にゲストの女性が座って話をしている。
し前(6月下旬だったと思うが)の夕方、なんとなくテレビのスイッチを入れると、夕方の番組「ゆうどきネットワーク」(NHK総合テレビで、ウィークデイの17:10ごろからの番組、僕は普段テレビはNHKのニュース番組くらいしか見ないからちゃんねるはいつもNHKになっている)をやっており、メインキャスター山本アナの隣にゲストの女性が座って話をしている。
 をとって読むスピードがめっきり遅くなった僕だが、それでも本書は朝から夕方まで1日で読み終わった。最近では珍しい早さだ。読み始めてすぐにその心地よさに酔いながら、ページを繰っていたが、中盤に差し掛かるや急に雲行きが怪しくなる。いや主人公の女性に暗雲がかぶさってくるのだ。表紙のイラスト通り、この大正から昭和初期のロマンを感じさせる、ファッショナブルな女性が主人公だ。造船財閥・八島海運の令嬢八島多江子である。
をとって読むスピードがめっきり遅くなった僕だが、それでも本書は朝から夕方まで1日で読み終わった。最近では珍しい早さだ。読み始めてすぐにその心地よさに酔いながら、ページを繰っていたが、中盤に差し掛かるや急に雲行きが怪しくなる。いや主人公の女性に暗雲がかぶさってくるのだ。表紙のイラスト通り、この大正から昭和初期のロマンを感じさせる、ファッショナブルな女性が主人公だ。造船財閥・八島海運の令嬢八島多江子である。
 月(6月)終わりから今月(7月)初めにかけて、少しの間ブログの更新を怠ってしまったから、遅れを取り戻そうと(そんなことをする必要はまったくないのだが、せめて3日に1冊くらいは読んでおこうと言う気があるから)読書ペースを速めたりしたが、そんなことが長続きするはずもなく、すぐに息切れを起こすのでないだろうか、と危惧しているのだが・・・・。
月(6月)終わりから今月(7月)初めにかけて、少しの間ブログの更新を怠ってしまったから、遅れを取り戻そうと(そんなことをする必要はまったくないのだが、せめて3日に1冊くらいは読んでおこうと言う気があるから)読書ペースを速めたりしたが、そんなことが長続きするはずもなく、すぐに息切れを起こすのでないだろうか、と危惧しているのだが・・・・。 からと言ってリンチをすると言うことになると、それはまったく別の問題だ。つまり秩序が保たれなくなり、大変なことになるのだが、映画やドラマでは時として、日ごろの鬱憤を晴らせるようなリンチのストーリーがもてはやされることもある。今は亡き藤田まこと氏の主演でロングランを記録した必殺シリーズなどがその良い例だ。
からと言ってリンチをすると言うことになると、それはまったく別の問題だ。つまり秩序が保たれなくなり、大変なことになるのだが、映画やドラマでは時として、日ごろの鬱憤を晴らせるようなリンチのストーリーがもてはやされることもある。今は亡き藤田まこと氏の主演でロングランを記録した必殺シリーズなどがその良い例だ。
 分が乗らなくて、ブログの更新に間が空いた。
分が乗らなくて、ブログの更新に間が空いた。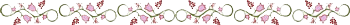
 な理屈っぽい話になった。
な理屈っぽい話になった。
 近と言ってもここ10年?いやもっとかな、ミステリー以外の映画やドラマは見なくなっている。だから、その辺の事情に疎くなったが、昔はドラマなどはミステリーに限らず全般的に好みのものを探してはよく見たものだ。特に脚本家・向田邦子氏の作品はカミさんが好きだったこともあって、付き合ってよく見ていた。
近と言ってもここ10年?いやもっとかな、ミステリー以外の映画やドラマは見なくなっている。だから、その辺の事情に疎くなったが、昔はドラマなどはミステリーに限らず全般的に好みのものを探してはよく見たものだ。特に脚本家・向田邦子氏の作品はカミさんが好きだったこともあって、付き合ってよく見ていた。
 ころで、江戸川乱歩氏は我が国の探偵小説の先駆者というばかりでなく、かのエラリイ・クイーン氏の二人も認めているように、ミステリー書誌研究者としても、収集家としてもその名は高い。
ころで、江戸川乱歩氏は我が国の探偵小説の先駆者というばかりでなく、かのエラリイ・クイーン氏の二人も認めているように、ミステリー書誌研究者としても、収集家としてもその名は高い。