| ジェリコ街の女 THE DEAD OF JERICHO |
||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2022/03/08 |
| 著 者 | コリン・デクスター Colin Dexter |
|
| 訳 者 | 大庭忠男 | |
| 出版社 | 早川書房 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 345 | |
| 発行日 | 1993/03/31 | |
| ISBN | 4-15-077555-9 | |
 ばらく振りのシリーズ作品が続く。2007年3月に読んだ『モース警部最大の事件』に続いて4冊目だ。丁度13年振りとなる。このシリーズはNHKで放送された吹き替え版のドラマで知り、原作を読もうと思ったのだった。この英国ITV制作のドラマはNHKでは、11作までの放送だったと思うが、作品は32作に及んでおり、字幕版としてミステリーチャンネルで放送されたと記憶しているが定かではない。
ばらく振りのシリーズ作品が続く。2007年3月に読んだ『モース警部最大の事件』に続いて4冊目だ。丁度13年振りとなる。このシリーズはNHKで放送された吹き替え版のドラマで知り、原作を読もうと思ったのだった。この英国ITV制作のドラマはNHKでは、11作までの放送だったと思うが、作品は32作に及んでおり、字幕版としてミステリーチャンネルで放送されたと記憶しているが定かではない。
現在僕のDVDレコーダーが故障中なので、検証不可なので確かめようがないのだ。パソコンでも確認できると思ってていたら、再生アプリがなくダメだった。何でもかんでも機械任せはこんな時不便を感じる。
さて、英国推理作家協会賞のシルヴァーダガー賞を受賞した本作は、ドラマで第1作となっているが、コロン・デクスター氏の作品の順番で行くと、第5作にあたるらしい。
僕はドラマの方を先に見ているから、そのダイナミックな作りに興奮を覚えたものだが、原作はそれとは違った趣を感じて、映像とな異なるときめきを感じたのだ。

僕はこのブログの中でも何度かドラマと原作について書いたが、僕が知っている限りでは、原作とは異なるドラマ作りが多いようだ。もちろん監督がその原作をどう読んで、何を訴えようとするかによって、ドラマの方向が決まるのだから、原作と異なる表現があっても当然だとは思うが、視聴者によっては―僕もその一人だ―原作と異なる表現を認めない人もいるようだ。
そんな堅苦しい見方をせず、僕は二通りの表現を、つまりドラマも原作も両方を楽しむことにしている、昔角川春樹氏の映画と原作本の両方を売るといったメディアミックスという手法が話題になって、その手法が多大な観客と読書家を生んだ。僕もその手に乗って大いに楽しんだのだ。特に僕が映像を楽しんだのは、横溝正史氏の金田一耕助シリーズのドラマだった。
このコリン・デクスター氏の作品とは関わりのない話なので、この辺でやめておこう。

 ころでモース警部のシリーズのドラマは、32作も制作されており、原作者のコリン・デクスター氏も、多少制作面でも関わっていたようだが、ドラマの半分くらいはオリジナル脚本のような気がする。
ころでモース警部のシリーズのドラマは、32作も制作されており、原作者のコリン・デクスター氏も、多少制作面でも関わっていたようだが、ドラマの半分くらいはオリジナル脚本のような気がする。
コリン・デクスター氏の原作を全部調べたわけではないが、30作以上のモース警部シリーズは見当たらないのだ。例え原作がなくオリジナル脚本でも、優れたドラマ作りが成されていれば、それはそれで良いのではないかとも思うが、我儘ともいえる視聴者である僕は、原作があってそのストーリーや醸し出される雰囲気が、どの程度映像化されたか、あるいはキャラクターたちが如何にリアルに演じているかが評価できて、面白いドラマになっていれば、観客として満足できるか。
ドラマの話ばかりになったが、本作を読んでいていかにも本格ミステリーを読んでいるのだという、嬉しさが何度も湧いてきた。“探偵はみなを集めて「さて」と言い”なんていう川柳もあるが、やはりミステリーの醍醐味は本格推理だと改めて感じたのだ。
にほんブログ村 |













 作『エンプティ・チェア』を読んだのは、2017年9月末だから、おおよそ4年ぶりのリンカーン・ライムシリーズだ。現在2018年刊行の『カッティング・エッジ』で、14作を数えるシリーズだが、僕は本作でようやく5作目だ。
作『エンプティ・チェア』を読んだのは、2017年9月末だから、おおよそ4年ぶりのリンカーン・ライムシリーズだ。現在2018年刊行の『カッティング・エッジ』で、14作を数えるシリーズだが、僕は本作でようやく5作目だ。
 くのミステリーに描かれる如くに、このシリーズでも気になるところは、リンカーンとアメリア・サックスの関係だ。古くはペリー・メイスンとデラ・ストリートに始まり、国内外を問わず数えきれないほどの、コンビの活躍がミステリーを、いやミステリー以外でも彼と彼女のロマンスが、より一層のストーリーの展開を際立たせている。
くのミステリーに描かれる如くに、このシリーズでも気になるところは、リンカーンとアメリア・サックスの関係だ。古くはペリー・メイスンとデラ・ストリートに始まり、国内外を問わず数えきれないほどの、コンビの活躍がミステリーを、いやミステリー以外でも彼と彼女のロマンスが、より一層のストーリーの展開を際立たせている。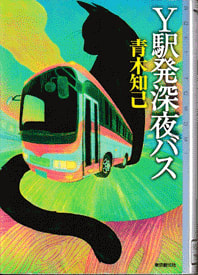
 度もここに書いてきたことだが、僕はタイトルだけで作品を評価してしまうことがある。そしてそれがたまたま僕の好みに合う作品で、面白く読めることがある。
度もここに書いてきたことだが、僕はタイトルだけで作品を評価してしまうことがある。そしてそれがたまたま僕の好みに合う作品で、面白く読めることがある。 のところテレビの番組が、オリンピック放送の為、通常とは異なる編成だから、どちらを見ようかと迷ったり戸惑ったりしている。見なければいいのだが、折角のアスリートたちの活躍を見逃すのもしゃくだ。
のところテレビの番組が、オリンピック放送の為、通常とは異なる編成だから、どちらを見ようかと迷ったり戸惑ったりしている。見なければいいのだが、折角のアスリートたちの活躍を見逃すのもしゃくだ。
 い時からの憧れであったエラリイ・クイーン氏の、国名シリーズの1篇だ。その憧れだった割に僕はまだ今までに、たった3冊しか読み終わってない。いつもの言い訳をすれば、やはり、いろいろと面白い新刊ミステリーが泉のごとくに湧いてくるように、出現するからだ。
い時からの憧れであったエラリイ・クイーン氏の、国名シリーズの1篇だ。その憧れだった割に僕はまだ今までに、たった3冊しか読み終わってない。いつもの言い訳をすれば、やはり、いろいろと面白い新刊ミステリーが泉のごとくに湧いてくるように、出現するからだ。 よいよオリンピックの開催日が近づいてきた。無観客まで想定することにどんな意味があるのだろう?
よいよオリンピックの開催日が近づいてきた。無観客まで想定することにどんな意味があるのだろう?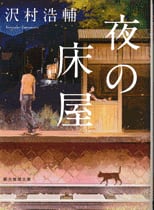
 めてこのタイトルを見た時から気になっていた。それがどれくらい前だったかは忘れたが、発行日からはもう7年も前だと分かり、改めて月日の過ぎる速さを実感する。
めてこのタイトルを見た時から気になっていた。それがどれくらい前だったかは忘れたが、発行日からはもう7年も前だと分かり、改めて月日の過ぎる速さを実感する。
 日はテレビ各局ともに、熱海の土石流の現場取材で大忙しだ。現場取材に招かれた専門家によれば、土石流の起きた頂上付近に行われた「盛り土が土石流を招いた」との見解もあるが、いずれにせよ後からの意見はどうとでも言える。
日はテレビ各局ともに、熱海の土石流の現場取材で大忙しだ。現場取材に招かれた専門家によれば、土石流の起きた頂上付近に行われた「盛り土が土石流を招いた」との見解もあるが、いずれにせよ後からの意見はどうとでも言える。
 、この場合の昔は僕の中学生になったばかりの頃だから、60数年も前になる。その頃の娯楽の王様だった映画の記憶は、田舎の小さな映画館や中の同じく小さな売店などの記憶だ。近ごろ増々記憶力が衰えてきたが、その頃の記憶はうっすらと頭に残っている。
、この場合の昔は僕の中学生になったばかりの頃だから、60数年も前になる。その頃の娯楽の王様だった映画の記憶は、田舎の小さな映画館や中の同じく小さな売店などの記憶だ。近ごろ増々記憶力が衰えてきたが、その頃の記憶はうっすらと頭に残っている。
 日は急に夏が来たかと思うような、穏やかだが暑い日だ。
日は急に夏が来たかと思うような、穏やかだが暑い日だ。
 烈な暑さの続く中、甲子園では高校球児たちのこちらも熱い戦いが続いている。千葉県からは習志野高校が代表として第1戦を勝ち抜いている。僕はプロ野球にはさほどの関心はないが、この夏の高校野球には、ドラマを感じて故郷代表以外にも、その戦いぶりに心を奪われている。
烈な暑さの続く中、甲子園では高校球児たちのこちらも熱い戦いが続いている。千葉県からは習志野高校が代表として第1戦を勝ち抜いている。僕はプロ野球にはさほどの関心はないが、この夏の高校野球には、ドラマを感じて故郷代表以外にも、その戦いぶりに心を奪われている。 年前まで、いや、今からすればおよそ10年前まで、僕の卒業した千葉県立大多喜高等学校の、クラス会「33会」が毎年1回実施されていた。昭和33年卒業ということと、第1回の集まりに33名の参加を見たことからも、33会と名付けられたクラス会は、東大卒のI氏を会長として、気の合った仲間が集うクラス会として、思いのほか長続きした。
年前まで、いや、今からすればおよそ10年前まで、僕の卒業した千葉県立大多喜高等学校の、クラス会「33会」が毎年1回実施されていた。昭和33年卒業ということと、第1回の集まりに33名の参加を見たことからも、33会と名付けられたクラス会は、東大卒のI氏を会長として、気の合った仲間が集うクラス会として、思いのほか長続きした。
 きな作家が多くいるということは、それだけ読書の楽しみが増えるということだ、と思っているが、逆の見方をすれば、読書の方向が定まらないともいえるから、もっとも僕の方向の定まらないのは、自身の気まぐれによるもので、別にもっともらしい理由を付ける必要はないのだが…。
きな作家が多くいるということは、それだけ読書の楽しみが増えるということだ、と思っているが、逆の見方をすれば、読書の方向が定まらないともいえるから、もっとも僕の方向の定まらないのは、自身の気まぐれによるもので、別にもっともらしい理由を付ける必要はないのだが…。 日は、近くのオートバックスで、ブレーキパッドの交換に行ってきた。前々日タイヤ交換の際ブレーキパッドの摩耗が見つかったことにより、交換を余儀なくされたのだ。
日は、近くのオートバックスで、ブレーキパッドの交換に行ってきた。前々日タイヤ交換の際ブレーキパッドの摩耗が見つかったことにより、交換を余儀なくされたのだ。
 国の本格ミステリーを担い、アガサ・クリスティの後継者の一人として、本格推理のほか数多くのサスペンスを書いているルース・レンデル女史。僕はこの名前を見たり聞いたりすると、1985年の事を思い出す。
国の本格ミステリーを担い、アガサ・クリスティの後継者の一人として、本格推理のほか数多くのサスペンスを書いているルース・レンデル女史。僕はこの名前を見たり聞いたりすると、1985年の事を思い出す。

 名な画家の妹で、アンという女が行方不明となって、殺された。犯人はジェフ・スミスだ―そんな匿名の手紙がキングスマーカム署に届いた。ウェクスフォード警部は調査を開始したが、屍体さえ発見されない状況に困惑せざるを得ない。本当に殺人はあったのか?混迷する捜査陣の前に、やがて事件は意外な真相を明らかにする!
名な画家の妹で、アンという女が行方不明となって、殺された。犯人はジェフ・スミスだ―そんな匿名の手紙がキングスマーカム署に届いた。ウェクスフォード警部は調査を開始したが、屍体さえ発見されない状況に困惑せざるを得ない。本当に殺人はあったのか?混迷する捜査陣の前に、やがて事件は意外な真相を明らかにする! 
 27回鮎川哲也賞を受賞した作品。さらに『このミステリーがすごい』、週刊文春のミステリーベスト10、『本格ミステリ・ベスト10』でそれぞれ第1位を獲得したということで、ミステリーファンの間でも高い評価が、口コミで広がった感がある。が、読み終わって僕は半分は好みでなかったこともあって、評判ほどの感銘はなかった。面白くないというわけではないが、途中から山口雅也氏の『生ける屍の死』を連想して、全く異なる内容だが、同じく僕の好みでないという点で、思い出したのだろう。
27回鮎川哲也賞を受賞した作品。さらに『このミステリーがすごい』、週刊文春のミステリーベスト10、『本格ミステリ・ベスト10』でそれぞれ第1位を獲得したということで、ミステリーファンの間でも高い評価が、口コミで広がった感がある。が、読み終わって僕は半分は好みでなかったこともあって、評判ほどの感銘はなかった。面白くないというわけではないが、途中から山口雅也氏の『生ける屍の死』を連想して、全く異なる内容だが、同じく僕の好みでないという点で、思い出したのだろう。 食前に洗濯機に入れておいた洗濯物が洗い終わったので、食後、ハンガーにかけて竿につるす。僕は結婚当初から、主な衣類は自分で選択することにしている。もちろんカミさんに頼むほうが多かったのだが、退職後はすべて自分のものは自分で処理するようになった。
食前に洗濯機に入れておいた洗濯物が洗い終わったので、食後、ハンガーにかけて竿につるす。僕は結婚当初から、主な衣類は自分で選択することにしている。もちろんカミさんに頼むほうが多かったのだが、退職後はすべて自分のものは自分で処理するようになった。

 都の名所案内がごく自然に、ストーリーの中で行われて、そうした説明を聞きながら名所めぐりをしてみたい、そんな風なことを思わせる展開が心地よい。
都の名所案内がごく自然に、ストーリーの中で行われて、そうした説明を聞きながら名所めぐりをしてみたい、そんな風なことを思わせる展開が心地よい。 主が案内する石清水八幡宮へは、ホームズをはじめ松花堂のボランティア5人と、タレントの梶原秋人、真城葵、宮下葵ら一行。
主が案内する石清水八幡宮へは、ホームズをはじめ松花堂のボランティア5人と、タレントの梶原秋人、真城葵、宮下葵ら一行。
 週木曜日から始まった日本女子オープンゴルフの、テレビ中継はNHK・BS1と地上デジタルの両方で、4日間にわたって放送された。昨年の覇者は畑中奈紗選手。史上初というアマチュア、しかも18歳という若い選手の優勝は、女子プロゴルフ界に衝撃を与えるとともに、ゴルフファンを大いに沸かせた。 そしてディフェンディングチャンピオンの畑中選手は、今回も初日5アンダーという好位置で発進。2日目の第2ラウンドでは8アンダーで早くも単独首位に駆け上がった。決勝ラウンドの第3ラウンドからは1オーバーの69名の選手によっての闘いだ。
週木曜日から始まった日本女子オープンゴルフの、テレビ中継はNHK・BS1と地上デジタルの両方で、4日間にわたって放送された。昨年の覇者は畑中奈紗選手。史上初というアマチュア、しかも18歳という若い選手の優勝は、女子プロゴルフ界に衝撃を与えるとともに、ゴルフファンを大いに沸かせた。 そしてディフェンディングチャンピオンの畑中選手は、今回も初日5アンダーという好位置で発進。2日目の第2ラウンドでは8アンダーで早くも単独首位に駆け上がった。決勝ラウンドの第3ラウンドからは1オーバーの69名の選手によっての闘いだ。 月18日に木更津市立図書館からのメールで、予約してあった本書の用意が出来たとのこと。翌日は火曜日で休館日だったので、20日に行って借りてきた。
月18日に木更津市立図書館からのメールで、予約してあった本書の用意が出来たとのこと。翌日は火曜日で休館日だったので、20日に行って借りてきた。
 ラマになったのをみて、8年ほど前に「償い」を読んだ。内容は全く思い出せないのだが、その後本書を買っているくらいだから面白く読んだのだろう。面白い本を読んだ後、同じ作者の本を読みたいと思うのは、誰でも同じだろうと思うが、僕は特にその傾向が強いらしく、BOOKOFFなどで安い文庫本の棚を見て歩きながら、そうした本を探したものだった。
ラマになったのをみて、8年ほど前に「償い」を読んだ。内容は全く思い出せないのだが、その後本書を買っているくらいだから面白く読んだのだろう。面白い本を読んだ後、同じ作者の本を読みたいと思うのは、誰でも同じだろうと思うが、僕は特にその傾向が強いらしく、BOOKOFFなどで安い文庫本の棚を見て歩きながら、そうした本を探したものだった。 部会の役員、と言っても男女合わせて4人だが、話し合いで支部会の欠席者にも会報を郵送することになって、前回から50部を作成することになったから、そうしたことも負担を増す要因となっている。というのは言い訳でしかないか。30部も50部も作る手間はたいして違いがないが、小口を糊付けする製本―ホチキス止めは、時に錆びることもあり、重ねると平にならない、などという理由で僕が独自に考えた方法だ―は1冊ずつの全くの手作業だから、手間も時間もかかるのだ。
部会の役員、と言っても男女合わせて4人だが、話し合いで支部会の欠席者にも会報を郵送することになって、前回から50部を作成することになったから、そうしたことも負担を増す要因となっている。というのは言い訳でしかないか。30部も50部も作る手間はたいして違いがないが、小口を糊付けする製本―ホチキス止めは、時に錆びることもあり、重ねると平にならない、などという理由で僕が独自に考えた方法だ―は1冊ずつの全くの手作業だから、手間も時間もかかるのだ。