| アポロンの嘲笑 | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2014/11/15 |
| 著 者 | 中山七里 | |
| 出版社 | 集英社 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 3341 | |
| 発行日 | 2014/09/10 | |
| ISBN | 978-4-08-771575-0 | |
 昨日11月15日に僕が監事を務める社会福祉法人・薄光会の理事会が招集された。議題 の中に2年に1回行われる役員改選があり、僕の監事としての務めが終わった。
昨日11月15日に僕が監事を務める社会福祉法人・薄光会の理事会が招集された。議題 の中に2年に1回行われる役員改選があり、僕の監事としての務めが終わった。
他にも副理事長のK氏や、理事のO氏も同様に退任され、新たに2名の施設長が理事に就任した。今期は期首4月を前に2名の施設長がその職から離れて、新たに3名の施設長が任命されるなど、組織の構成が刷新されたこともあり、いよいよ法人としての改革の年だという思いを起こさせる。
平成16年から10年以上にわたって務めた監事職ではあるが、何年か前から僕は自分の職務の中で、思いがなかなか届かないということを感じており、職を辞したいと思っていた。そんなことから今回その職を離れることに関しては、何の感慨もわいてこなかった。
7名の理事の中で紅一点の金箱さん(この方は他にも保護者会の役員や、NPOの理事を務めるなど、八面六臂の活躍をしている才媛である)からは、僕の引退を惜しむ言葉をいただいたが、これはあくまで社交辞令として受け取っておいた方がいいだろう。
僕だって惜しまれるほどのことをしていたと、自惚れるほどのことはないのだから。しかし、いつも思うのだが彼女のような人がいる限り、法人が変な方向へと向かうことはないだろうと。貴重な人材だ。

中山七里氏の旺盛な執筆ぶりには驚くばかりだ。僕は何度かテレビ番組に出演した際の氏の話から、彼のことを良い意味で職人作家、あるいは匠だという認識を持っている。
オファーのある出版社の編集者からの注文に応えて、作品を提供するところに物作りの職人、またはレストランのシェフを思い起こさせる。この作家の作品は全作読んでみよう、と思わせるゆえんだ。
この本は昨年9月の発行だから、僕にすればまだ新刊と言っていいが、つい先ごろヤフオクに出品されていたのを見て、手ごろな価格だったので同じ出品者のもう1冊「テミスの剣」と一緒に落札した。
実はこの本の前に10冊ほど読み終わっている本があるのだが、急遽読み終わったばかりの本書の方について書くことにしたのは、読み終わった本がたまると、前の方の本のことを忘れてしまうから、なかな か記事をアップできないのだ
いつもお茶を濁すようなことばかり書いていると、何のための読書記録かわからなくなる。しかし、元来ブログなんて個人の日記だから、何を書こうとかまわないようなものだと、自分に言い訳をしたりして。
長く続けることが何か力になることを期待しているわけでもない。唯々言ってしまえば自己満足に過ぎないのかもしれない。それでも、もう少し先になって、過去ログを見ながら、「馬鹿なことを書いてい るな、アハハ」ということでもいいじゃないか。
そんなことを思いながら書いている。

 書の内容は過去の多くの作品にみられる、終盤の二転三転するどんでん返しではなく、切ない結末になっている。題材は多くの犠牲を伴った東日本大震災にとっている。阪神淡路大震災に直面 して、福島に転居してきた家族のもとに、またもや襲い掛かった原発事故の恐怖と匹敵するような事故が襲い掛かる。
書の内容は過去の多くの作品にみられる、終盤の二転三転するどんでん返しではなく、切ない結末になっている。題材は多くの犠牲を伴った東日本大震災にとっている。阪神淡路大震災に直面 して、福島に転居してきた家族のもとに、またもや襲い掛かった原発事故の恐怖と匹敵するような事故が襲い掛かる。
一家の長男・純一は、妹のかつての恋人だった男を、殺害して収監されていたが、仮釈放で戻ってきた 。原発関連の会社に勤める父親のコネで、どうにか孫請けのそのまた下の作業員になった。仕事の上で親しい間柄になった加瀬邦彦は、奇しくも阪神淡路大震災で奇跡的に助かった少年だった。純一の誘いに乗って彼の家庭を訪れるようになったある時、邦彦が純一を口論の末に殺害するという事件が起こった。
パトカーに乗せられ警察に連行される途中で、辛くも脱出した邦彦が向かった先は厳しく立ち入りが制限された福島第一原発だった。何のために危険な個所に向かうのか?
厳寒の中怪我をおしてまで進む邦彦の命がけの道中と、彼を追う一人の刑事。大昔の米テレビドラマ「逃亡者」を思い起こす。
にほんブログ村 |











 ランスの作家・ピエール・ルメートルの「その女アレックス」を紹介した、東京新聞のコラムでは、他に米国のサスペンス作家のメアリ・H・クラーク氏の「誰かが見ている」と言う彼女の処女作を引き合いに出していた。もちろん僕はまだ彼女の作品は「子供たちはどこにいる」(新潮文庫)しか読んでないので、紹介されていた誘拐事件を描かれる処女作「誰かが見ている」は未読だ。
ランスの作家・ピエール・ルメートルの「その女アレックス」を紹介した、東京新聞のコラムでは、他に米国のサスペンス作家のメアリ・H・クラーク氏の「誰かが見ている」と言う彼女の処女作を引き合いに出していた。もちろん僕はまだ彼女の作品は「子供たちはどこにいる」(新潮文庫)しか読んでないので、紹介されていた誘拐事件を描かれる処女作「誰かが見ている」は未読だ。
 が、彼女の作品は終焉を迎えるに当たっては、またいつも通りの平和な状態が戻って、いわゆるハッピーエンドが多い。そんなことから、大きな不安を抱かせるプロセスを楽しんだ(あるいは怖い思い)のあと、穏やかな日常を取り戻せる、ということで読者は安心して彼女の小説を楽しむのだろう。
が、彼女の作品は終焉を迎えるに当たっては、またいつも通りの平和な状態が戻って、いわゆるハッピーエンドが多い。そんなことから、大きな不安を抱かせるプロセスを楽しんだ(あるいは怖い思い)のあと、穏やかな日常を取り戻せる、ということで読者は安心して彼女の小説を楽しむのだろう。
 月2日、75歳の誕生日で僕の読書記録も満15年を迎える。
月2日、75歳の誕生日で僕の読書記録も満15年を迎える。 訳小説を読むのは随分しばらくぶりだろう。しかも本書は読み終わった日の2日前が発行日となっている新刊だ。それというのも、つい先日(9月12日現在の話だ)東京新聞の文化欄にある「大波小波」と言うコラムで紹介されていたのが本書で、従来の誘拐事件を扱ったものとは趣の異なるミステリーと言ううたい文句に惹かれて、読んでみる気になったのだ。
訳小説を読むのは随分しばらくぶりだろう。しかも本書は読み終わった日の2日前が発行日となっている新刊だ。それというのも、つい先日(9月12日現在の話だ)東京新聞の文化欄にある「大波小波」と言うコラムで紹介されていたのが本書で、従来の誘拐事件を扱ったものとは趣の異なるミステリーと言ううたい文句に惹かれて、読んでみる気になったのだ。
 をとると昔のことを懐かしく思い起こすことが多いといわれる。どうやら僕もその口で、唐突に脈略のないことが頭をよぎる。本書のことも、はるか昔岡田英治、岸田今日子両氏の主演で映画化されたことが頭に浮かんで、当時はそれほど興味があったわけではなかったが、なんとなく頭に残っていたのだろう。 大まかな筋立てとまではいかないが、映画雑誌かなんかで読んだか見たか、アリジゴクの様な砂の中の女につかまって、逃げられなくなった男の物語だ、というくらいの認識はあった。 にもかかわらず僕の気まぐれは、一度読んでおく価値はあるのではないか?などと言う思いを湧きあがらせる。 主演のお二方ともにもうこの世の人ではなくなっているはるか昔の映画のことが気になって、レンタルビデオ店でDVDでもなっていないか探そうと思ったが、その前に原作を読んでおこうと思った。
をとると昔のことを懐かしく思い起こすことが多いといわれる。どうやら僕もその口で、唐突に脈略のないことが頭をよぎる。本書のことも、はるか昔岡田英治、岸田今日子両氏の主演で映画化されたことが頭に浮かんで、当時はそれほど興味があったわけではなかったが、なんとなく頭に残っていたのだろう。 大まかな筋立てとまではいかないが、映画雑誌かなんかで読んだか見たか、アリジゴクの様な砂の中の女につかまって、逃げられなくなった男の物語だ、というくらいの認識はあった。 にもかかわらず僕の気まぐれは、一度読んでおく価値はあるのではないか?などと言う思いを湧きあがらせる。 主演のお二方ともにもうこの世の人ではなくなっているはるか昔の映画のことが気になって、レンタルビデオ店でDVDでもなっていないか探そうと思ったが、その前に原作を読んでおこうと思った。 み終わって、内容は漠然と覚えていたものと、大筋では変わらず不思議な感覚をもたらす、不条理とも言える内容だ。変な言い方だが、読み始めて僕がなぜこの本を今頃になって読もうと思ったのか?が少しずつ分かってきた。 どうということはない、砂の穴にある女の家に泊まったために、抜け出せなくなった男が、その後どうなったのだろうか?ということが心のどこかにずっと残っていたのだということが分かっただけのことだ。 そこに僕はミステリアスな感じを持ったから、一度は読んでおこうと思ったに過ぎない。前述のごとく僕の頭は難しいことは分からないが、それで読後何かを考えさせるこの作品の価値が、今もなお読者を誘うのではないかとちょっぴり感じた。
み終わって、内容は漠然と覚えていたものと、大筋では変わらず不思議な感覚をもたらす、不条理とも言える内容だ。変な言い方だが、読み始めて僕がなぜこの本を今頃になって読もうと思ったのか?が少しずつ分かってきた。 どうということはない、砂の穴にある女の家に泊まったために、抜け出せなくなった男が、その後どうなったのだろうか?ということが心のどこかにずっと残っていたのだということが分かっただけのことだ。 そこに僕はミステリアスな感じを持ったから、一度は読んでおこうと思ったに過ぎない。前述のごとく僕の頭は難しいことは分からないが、それで読後何かを考えさせるこの作品の価値が、今もなお読者を誘うのではないかとちょっぴり感じた。
 はあまりテレビを見ないので、(好きなミステリードラマなどは予約録画して、あとで纏めて見ることが多い)たまたま昨夜テレビつけたら、NHKの報道番組「ニュースウォッチ9」をやっていて、今年のノーベル物理学賞に3人の日本の物理学者が選ばれたというニュースが流れていて驚いた。
はあまりテレビを見ないので、(好きなミステリードラマなどは予約録画して、あとで纏めて見ることが多い)たまたま昨夜テレビつけたら、NHKの報道番組「ニュースウォッチ9」をやっていて、今年のノーベル物理学賞に3人の日本の物理学者が選ばれたというニュースが流れていて驚いた。 田は一人娘の春夏(はるか)を事故で亡くしていた。末永ますみはその娘と生年月日が同じだった。 だが、末永ますみを説諭だけで解放したことが、その後の平田の運命を大きく変えることになる。何かにつけて末永ますみは平田と会おうとするのだ。彼女に暴力をふるうろくでもない男と同棲している彼女を、見捨てておけない平田にやがて、親切が仇になるようなしっぺ返しとも言うような事態が・・・・。
田は一人娘の春夏(はるか)を事故で亡くしていた。末永ますみはその娘と生年月日が同じだった。 だが、末永ますみを説諭だけで解放したことが、その後の平田の運命を大きく変えることになる。何かにつけて末永ますみは平田と会おうとするのだ。彼女に暴力をふるうろくでもない男と同棲している彼女を、見捨てておけない平田にやがて、親切が仇になるようなしっぺ返しとも言うような事態が・・・・。
 年暮れにしばらくぶりで著者の作品を読んで、もう未読の作品は少なくなってきた。それでも精力的に?新しい作品を発表しているから、楽しみだ。読書人であれば、誰でも覚えはあるだろうが、僕は時により一人の作家の作品を続けて読みたくなって、短い期間に読み続けることが過去に幾度かあった。
年暮れにしばらくぶりで著者の作品を読んで、もう未読の作品は少なくなってきた。それでも精力的に?新しい作品を発表しているから、楽しみだ。読書人であれば、誰でも覚えはあるだろうが、僕は時により一人の作家の作品を続けて読みたくなって、短い期間に読み続けることが過去に幾度かあった。

 手の掌や指先が軽い痺れを発して気になる。そんな症状はもう1週間以上続いたろうか?多分6月の階段転落の後遺症だと思うが、今頃になって左手を握ると内側に抵抗感があって、固く握れなくなっている。ドクターは気長に回復を待つように、と言うがいろいろと不都合が出てくると、少しばかり憂鬱になる。
手の掌や指先が軽い痺れを発して気になる。そんな症状はもう1週間以上続いたろうか?多分6月の階段転落の後遺症だと思うが、今頃になって左手を握ると内側に抵抗感があって、固く握れなくなっている。ドクターは気長に回復を待つように、と言うがいろいろと不都合が出てくると、少しばかり憂鬱になる。

 月13日に2階からの階段を転げ落ちて、左腕手首を骨折した後の、経過措置のため今日2度目の通院をした。僕の通う君津中央病院は、国保の直営病院で、近隣の地域では最大の総合病院である。そのためいつも広い駐車場が満杯になるほどの盛況?を見せている。だから、できるだけ近くの駐車場を確保するため早めに出る必要があり、病院へは車で5分ほどだが、今日の予約は10時となっているので、9時過ぎに家を出た。
月13日に2階からの階段を転げ落ちて、左腕手首を骨折した後の、経過措置のため今日2度目の通院をした。僕の通う君津中央病院は、国保の直営病院で、近隣の地域では最大の総合病院である。そのためいつも広い駐車場が満杯になるほどの盛況?を見せている。だから、できるだけ近くの駐車場を確保するため早めに出る必要があり、病院へは車で5分ほどだが、今日の予約は10時となっているので、9時過ぎに家を出た。
 れでも本は読んでみて、初めてその価値がわかるということを、今回も改めて実感した。
れでも本は読んでみて、初めてその価値がわかるということを、今回も改めて実感した。
 じ修復でも、たまに絵画の修復作業などをテレビでやっているのを見るが、それこそ僕のやっている作業などまったく比較にならないほどの根気のいることだと、修復師に尊敬の念を抱く。
じ修復でも、たまに絵画の修復作業などをテレビでやっているのを見るが、それこそ僕のやっている作業などまったく比較にならないほどの根気のいることだと、修復師に尊敬の念を抱く。
 回も同じ事を書いたが、身体の中の暦が当てにならなくなった。まあ、今に始まったことでもないか。著者の「イン・パラダイス」を読んだのがついこの間という感覚だったが、記録をたどったら、もう2年以上前だった。別に驚くにはあたらない、いつものように「Time fly like an allow」を感じるだけだ。
回も同じ事を書いたが、身体の中の暦が当てにならなくなった。まあ、今に始まったことでもないか。著者の「イン・パラダイス」を読んだのがついこの間という感覚だったが、記録をたどったら、もう2年以上前だった。別に驚くにはあたらない、いつものように「Time fly like an allow」を感じるだけだ。 舗における万引きなどを防止、あるいは実行犯を捕捉する保安士の八木薔子がこのシリーズのヒロインだ。
舗における万引きなどを防止、あるいは実行犯を捕捉する保安士の八木薔子がこのシリーズのヒロインだ。


 紙の画像はイラストだとばかり思っていたら、写真だった。内容にピッタリな写真があるはずはないと思うから、特に「池の中での花を抱いた女性の死体」などというシチュエーション・ピクチャーが。
紙の画像はイラストだとばかり思っていたら、写真だった。内容にピッタリな写真があるはずはないと思うから、特に「池の中での花を抱いた女性の死体」などというシチュエーション・ピクチャーが。 はアガサ・クリスティ女史の「スリーピング・マーダー」という作品が好きで、ジョーン・ヒクソン女史がミスマープルに扮したドラマも、数回繰り返し見たほどの好きなシチュエーションである。
はアガサ・クリスティ女史の「スリーピング・マーダー」という作品が好きで、ジョーン・ヒクソン女史がミスマープルに扮したドラマも、数回繰り返し見たほどの好きなシチュエーションである。
 変わらず僕のものぐさは、どこかで紹介された本のタイトルだけしかメモしてないから、どこで誰がどんな風に紹介していたのか、いざこうしてその本を読んだときに、ここでその出典を紹介できないでいる。
変わらず僕のものぐさは、どこかで紹介された本のタイトルだけしかメモしてないから、どこで誰がどんな風に紹介していたのか、いざこうしてその本を読んだときに、ここでその出典を紹介できないでいる。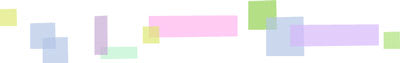
 かな手がかりを追って、謎の解明に向かっていくと、行く先々で新たな謎が浮き上がってくる。そうしたストーリーは過去にも読んだような気もするが、先述のように語り口の上手さが、そうした展開を見せるたびワクワクさせるのだ。
かな手がかりを追って、謎の解明に向かっていくと、行く先々で新たな謎が浮き上がってくる。そうしたストーリーは過去にも読んだような気もするが、先述のように語り口の上手さが、そうした展開を見せるたびワクワクさせるのだ。
 日は朝10時から富津市湊にある、社会福祉法人薄光会の介護施設「太陽(“ひ”と読ませる)のしずく」(ここに一応本部事務所を置いている)で定例の評議員会、理事会が開催された。
日は朝10時から富津市湊にある、社会福祉法人薄光会の介護施設「太陽(“ひ”と読ませる)のしずく」(ここに一応本部事務所を置いている)で定例の評議員会、理事会が開催された。
 国の悪魔なんていうわけのわからないタイトルと、壮大な物語を思わせる表紙のデザインが、僕の興味をひいて読んでみたいという気にさせた。著者の河合莞爾氏は、2012年、「デッドマン」という作品で第32回横溝正史ミステリ大賞を受賞してデビューした作家だそうで、初めての出会いである。
国の悪魔なんていうわけのわからないタイトルと、壮大な物語を思わせる表紙のデザインが、僕の興味をひいて読んでみたいという気にさせた。著者の河合莞爾氏は、2012年、「デッドマン」という作品で第32回横溝正史ミステリ大賞を受賞してデビューした作家だそうで、初めての出会いである。
 しい本を見つけるのは、時々ここに書いているように、テレビの書評番組が多いのだが、たまに読んだ本の後ろにその出版社の簡単な目録が掲載されていることがある。
しい本を見つけるのは、時々ここに書いているように、テレビの書評番組が多いのだが、たまに読んだ本の後ろにその出版社の簡単な目録が掲載されていることがある。
 れっぽい僕は2-3日たてば内容も感動も忘れかねないから、その余韻の残っている内にと思い、珍しく読み終わって直ぐにここに書いているというわけだ。下表のそれぞれのタイトルだけを見ても、その内容が分かるようなものもあるが、そう、全く想像するような内容そのものなのだ。
れっぽい僕は2-3日たてば内容も感動も忘れかねないから、その余韻の残っている内にと思い、珍しく読み終わって直ぐにここに書いているというわけだ。下表のそれぞれのタイトルだけを見ても、その内容が分かるようなものもあるが、そう、全く想像するような内容そのものなのだ。
 近に迫った社会福祉法人薄光会の評議員会、理事会に必要な監事監査報告書をよそに、本を読んだり、ブログの記事を書いたりしてていいのか、と頭の中でもう一人の僕は言うが、そんなことは聞こえないふりをしながらどうでもいいことを優先する。いや、このブログがどうでもいいというわけではないのだが、優先すべきは他にあるということだ。
近に迫った社会福祉法人薄光会の評議員会、理事会に必要な監事監査報告書をよそに、本を読んだり、ブログの記事を書いたりしてていいのか、と頭の中でもう一人の僕は言うが、そんなことは聞こえないふりをしながらどうでもいいことを優先する。いや、このブログがどうでもいいというわけではないのだが、優先すべきは他にあるということだ。 xnミステリーの「BOOK倶楽部」で「このミステリーがすごい!」大賞受賞作として本書が紹介されていた。大森望氏だったか?杉江松恋氏だったか?忘れたが、簡単な説明があったが、その時はあまりにも突飛なタイトルにさして興味を惹かれることもなかったが、他のところでもいくつかの紹介記事が出ているのを見て、衝撃的なタイトルの中身が誘拐劇を描いたものということで、それではとようやく読む気になった。
xnミステリーの「BOOK倶楽部」で「このミステリーがすごい!」大賞受賞作として本書が紹介されていた。大森望氏だったか?杉江松恋氏だったか?忘れたが、簡単な説明があったが、その時はあまりにも突飛なタイトルにさして興味を惹かれることもなかったが、他のところでもいくつかの紹介記事が出ているのを見て、衝撃的なタイトルの中身が誘拐劇を描いたものということで、それではとようやく読む気になった。