| 碧空のカノン | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2021/11/03 |
| 著 者 | 福田和代 | |
| 出版社 | 光文社 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 355 | |
| 発行日 | 2015/09/20 | |
| ISBN | 978-4-334-76962-8 | |
 者・福田和代氏は『TOKYOU BLACKOUT』、『迎撃せよ』の2冊を読んで、気になる作家の一人となった。
者・福田和代氏は『TOKYOU BLACKOUT』、『迎撃せよ』の2冊を読んで、気になる作家の一人となった。
惚れっぽい僕は面白い作品を読むとすぐに惚れこんでしまうのだが、その反対の場合もありつまらないと感じた際には、もう二度とこの作家の作品は読まないだろうという気になる。
だが、そんな思いもその作家がほかの作品で評判になると、また読んでみようかと気が変わるのだ。
そして、面白くないと感じた作品だって、ある時ふと読み返して、なんでこの面白い作品をつまらないと思ったんだろうと、180度見方が変わることもあるのだ。 そんなことだから、僕は人に本を進めることなどできないのだ。面白くて感動したとしても、独りよがりなこともたくさんあったのだと思うが、それでも人一倍数読んでいるから、そうそう独りよがりな事もないだろうと、思ったりもしている。
僕は読書と同じくらい音楽も好きだ。まあ、ジャンルを問わずと言いたいが、若い頃から好きだったのはジャズだ。まだ結婚する前に、カミさんとサンケイホールにアート・ブレイキーとジャズメッセンジャーズの公演に行って、一層ジャズにのめり込むことになった。
一方では当時住んでいた大原町の映画館・富士館で行われた三波春夫ショーや、島倉千代子ショーなどにも行ったことがあって、歌謡曲も好きだった、

そんなことを書いていると切りも際限もなくなってしまいそうだ。
その頃は音楽や映画、特に映画は娯楽の花形だった。という言い方はいろいろある娯楽の中で、映画が突出しての人気だったというような感じだが、そうではなくてそれに匹敵する娯楽が他に無かったのだ。
今はなき日活の大スター・石原裕次郎氏の全盛時代でもあった。いや、話が尽きなくなりそうだから、映画の話はまたの事にしよう。
ユーチューブでたまたま自衛隊音楽隊の「栄冠は君に輝く」の演奏・歌唱を見て、本書が航空自衛隊航空中央音楽隊ノートという副題がついていることから、興味がわいた。アルトサックスを担当する成瀬花音を主人公としたストーリーは、一月後に長野で開催される“ふれあいコンサート”、そこで演奏される曲の楽譜をそろえるよう頼んだ真弓から、楽譜の一部が見当たらないと告げられた。(第一話 ギルガメッシュ交響曲)を始め六つのストーリーから構成されている。

 ょっとそそっかしい所もあるが、努力家の成瀬花音の活躍を描いたストーリーで、僕はミステリーを想像していたら、純然たる自衛隊の音楽活動を描いたものだった。だが、それでも多少は第1話のように、楽譜の紛失事件と言った多少はミステリーっぽいところもあったが・・・。
ょっとそそっかしい所もあるが、努力家の成瀬花音の活躍を描いたストーリーで、僕はミステリーを想像していたら、純然たる自衛隊の音楽活動を描いたものだった。だが、それでも多少は第1話のように、楽譜の紛失事件と言った多少はミステリーっぽいところもあったが・・・。
音楽家の演奏の動画はユーチューブでその多くを見ることが出来て、重宝しているが、僕などはテレビで昔放送された番組がユーチューブで観られることがあり、こちらも重宝している。大橋巨泉氏の司会したジャズ番組や、同様にタモリ氏が司会しているジャズなど、見逃した回などが観られて感激した。
そんなことから、これは前にも書いたかどうか忘れたが、僕はビールはキリン派だが、テレビコマーシャルのサントリー金麦が、以前檀れい氏が担当していたことがあり、僕は彼女のファンなので溌溂として、あるいは茶目っ気を現した彼女の演技に癒されたので、ユーチューブを検索したら、まとめてアップされており、大いに楽しんだ。
こうなると欲しいものは何でもありそうな気もするが、まあ、そういう訳でもない事が後に分かってくる。
またもやなんだか訳の分からない話に終始してしまった。
| # | タイトル |
|---|---|
| 1 | ギルガメッシュ交響曲 |
| 2 | ある愛のうた |
| 3 | 文明開化の鐘 |
| 4 | インジブル・メッセージ |
| 5 | 遠き山に日は落ちて |
| 6 | ラッパ吹きの休日 |
にほんブログ村 |













 昨日(5/7)、木更津市立図書館に『半七捕物帳(四)』と『合唱 岬洋介の帰還』、『ビブリア古書堂の事件手帖~扉子と空白の時~』の3冊を返却の為に訪れた際、以前、恩田陸氏の『蜜蜂と遠雷』の続編だか番外編だかが出たというニュースがあったことを思い出して、本書を借りてきた。館内でパラパラとページを捲っていたら、ページ数も少なく文字フォントのサイズが大きく、行間も空いている。
昨日(5/7)、木更津市立図書館に『半七捕物帳(四)』と『合唱 岬洋介の帰還』、『ビブリア古書堂の事件手帖~扉子と空白の時~』の3冊を返却の為に訪れた際、以前、恩田陸氏の『蜜蜂と遠雷』の続編だか番外編だかが出たというニュースがあったことを思い出して、本書を借りてきた。館内でパラパラとページを捲っていたら、ページ数も少なく文字フォントのサイズが大きく、行間も空いている。 歳の時からたくさんのミステリーを読もうと、手当たり次第に読み漁るといった感じで、本を読み続けてきたが、そのおかげでたくさんの優秀な作家と巡り合うこともできて、僕は幸せな読書生活が出来たと思っている。
歳の時からたくさんのミステリーを読もうと、手当たり次第に読み漁るといった感じで、本を読み続けてきたが、そのおかげでたくさんの優秀な作家と巡り合うこともできて、僕は幸せな読書生活が出来たと思っている。
 事用にExcelで簡単な表を作り、検索関数を使って表引きを設定、従来手書きとゴム印で作成していた配達先名簿を、簡易データベースを活用して、仕事の終了後データを入力(それまでは、事前に手書きをしていた)するように変更、大分時間と手間を省けるようになった。
事用にExcelで簡単な表を作り、検索関数を使って表引きを設定、従来手書きとゴム印で作成していた配達先名簿を、簡易データベースを活用して、仕事の終了後データを入力(それまでは、事前に手書きをしていた)するように変更、大分時間と手間を省けるようになった。
 学中に司法試験に合格しながら、ピアニストへの道を選んだ岬洋介の、たぐいまれな推理力によって、事件解明への展開を描くというと簡単だが、ストーリーはそれほど簡単なものではない。
学中に司法試験に合格しながら、ピアニストへの道を選んだ岬洋介の、たぐいまれな推理力によって、事件解明への展開を描くというと簡単だが、ストーリーはそれほど簡単なものではない。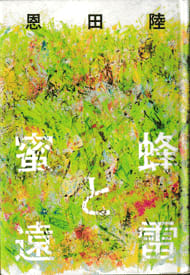
 件もの予約が続いていたので、僕の番はもう少し先になるだろうと思っていたら、存外早く「予約の資料が用意できました」のメールが入った。このところ専ら図書館を利用していて、著者や出版社には申し訳ない気持ちもあるが、何しろ手許不如意も続いており、致し方なし。
件もの予約が続いていたので、僕の番はもう少し先になるだろうと思っていたら、存外早く「予約の資料が用意できました」のメールが入った。このところ専ら図書館を利用していて、著者や出版社には申し訳ない気持ちもあるが、何しろ手許不如意も続いており、致し方なし。 て、本書は若き天才ピアニストたちの、コンサートの模様を描くストーリーだ。コンサートを勝ち抜くための努力や、彼らの演奏の素晴らしさと、行間から音が飛び出しているかのような、描写が感動を呼び起こした作品は、2012年に読んだ中山七里氏の、『さよならドビュッシー』ですでに味わっているが、この作品では少し趣の違った、一流ピアニストを目指す天才たちの、コンサート演奏が繰り広げられて、迫力のある描写が繰り広げられる。
て、本書は若き天才ピアニストたちの、コンサートの模様を描くストーリーだ。コンサートを勝ち抜くための努力や、彼らの演奏の素晴らしさと、行間から音が飛び出しているかのような、描写が感動を呼び起こした作品は、2012年に読んだ中山七里氏の、『さよならドビュッシー』ですでに味わっているが、この作品では少し趣の違った、一流ピアニストを目指す天才たちの、コンサート演奏が繰り広げられて、迫力のある描写が繰り広げられる。
 津市の生活介護施設「太陽(ひ)のしずく」で5月1日、天羽支部会が行われた。天羽支部会と言うのは、社会福祉法人薄光会が運営する「ケアホームCOCO」を利用する障害者の保護者・家族の会の名称で、もともとは入所施設・豊岡光生園の保護者・家族の会に所属していた人たちだが、昨年4月に分割されたものだ。
津市の生活介護施設「太陽(ひ)のしずく」で5月1日、天羽支部会が行われた。天羽支部会と言うのは、社会福祉法人薄光会が運営する「ケアホームCOCO」を利用する障害者の保護者・家族の会の名称で、もともとは入所施設・豊岡光生園の保護者・家族の会に所属していた人たちだが、昨年4月に分割されたものだ。 講談社から2010年にこの作品の単行本が刊行されたとき、テレビの書評番組(番組名は覚えていない)で紹介されたのを見て、記憶の片隅に残っていた。そんなことでBOOKOFFの100円の文庫棚でこの文庫を見かけて買ったものだと思う。
講談社から2010年にこの作品の単行本が刊行されたとき、テレビの書評番組(番組名は覚えていない)で紹介されたのを見て、記憶の片隅に残っていた。そんなことでBOOKOFFの100円の文庫棚でこの文庫を見かけて買ったものだと思う。 書を読み始めて、中山七里氏の「さよならドビュッシー」を読んだ時の感動とは、また趣の異なった感動を覚える。こちらはタイトルからも想像できるように、ドイツ・ロマン派を代表するローベルト・アレクサンダー・シューマンの生涯を描いた作品、ではなくそのシューマンに傾倒する若き天才ピアニスト永嶺修人(まさと)と、その先輩にあたる語り手・里橋優の交流を描いた物語だ。
書を読み始めて、中山七里氏の「さよならドビュッシー」を読んだ時の感動とは、また趣の異なった感動を覚える。こちらはタイトルからも想像できるように、ドイツ・ロマン派を代表するローベルト・アレクサンダー・シューマンの生涯を描いた作品、ではなくそのシューマンに傾倒する若き天才ピアニスト永嶺修人(まさと)と、その先輩にあたる語り手・里橋優の交流を描いた物語だ。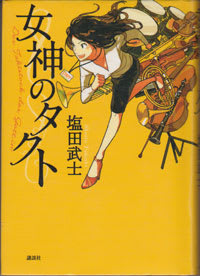
 近テレビの書評番組で知った著者とその作品は、「崩壊」というタイトルだったが、生憎木更津市の図書館には蔵書がなく、「捜査官」、「盤上のアルファ」、「女神のタクト」と並んだ棚から、本書を選んで借りてきた。タイトルと表紙イラストからミュージック・ストーリーと言うことに興味があったからだ。
近テレビの書評番組で知った著者とその作品は、「崩壊」というタイトルだったが、生憎木更津市の図書館には蔵書がなく、「捜査官」、「盤上のアルファ」、「女神のタクト」と並んだ棚から、本書を選んで借りてきた。タイトルと表紙イラストからミュージック・ストーリーと言うことに興味があったからだ。 の作品は裸一貫で起こした稼業を、大企業にまで発展させたオーナー・白石麟太郎が、今は亡き妻のために結成したオーケストラ、「神戸オルケストラ」の再生を期して、たまたま出会った矢吹明菜に、世界的な名声を博す指揮者・一宮拓斗を連れてくるよう依頼する。
の作品は裸一貫で起こした稼業を、大企業にまで発展させたオーナー・白石麟太郎が、今は亡き妻のために結成したオーケストラ、「神戸オルケストラ」の再生を期して、たまたま出会った矢吹明菜に、世界的な名声を博す指揮者・一宮拓斗を連れてくるよう依頼する。
 頃、僕の病気かとも思える買い物症候群が頭をもたげて、そっちこっちから単行本、文庫本の新刊を買いあさって、なお飽き足らずにBOOKOFFへいって中古本をあさる始末だ。
頃、僕の病気かとも思える買い物症候群が頭をもたげて、そっちこっちから単行本、文庫本の新刊を買いあさって、なお飽き足らずにBOOKOFFへいって中古本をあさる始末だ。 アニストで音大の講師も勤める名探偵・岬洋介のシリーズ第3弾である。
アニストで音大の講師も勤める名探偵・岬洋介のシリーズ第3弾である。
 者の「さよならドビュッシー」を読んだ後、同様の音楽ミステリーである本書を続けて読みたいという思いを持つ自分を、どうやらなだめすかして、(そんなことをする必要もないのに…)楽しみを後回しにしていた。
者の「さよならドビュッシー」を読んだ後、同様の音楽ミステリーである本書を続けて読みたいという思いを持つ自分を、どうやらなだめすかして、(そんなことをする必要もないのに…)楽しみを後回しにしていた。 ころがその愛知音大でとんでもない事件が持ち上がったのだ。金庫室とも呼ばれている楽器の収納室から、チェロが盗まれるという事態が発生した。ただのチェロではない、時価2億円のストラディバリウスなのだ。
ころがその愛知音大でとんでもない事件が持ち上がったのだ。金庫室とも呼ばれている楽器の収納室から、チェロが盗まれるという事態が発生した。ただのチェロではない、時価2億円のストラディバリウスなのだ。
 めて読んだ著者の「要介護探偵の事件簿」で、主人公である香月老人のキャラクターに惚れ込んで、その前に登場するという作品ということなので、本書はずっと読みたいと思っていた。
めて読んだ著者の「要介護探偵の事件簿」で、主人公である香月老人のキャラクターに惚れ込んで、その前に登場するという作品ということなので、本書はずっと読みたいと思っていた。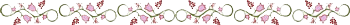
 の物語の凄いところは、まるでピアノの音があふれ出てくるような、演奏の描写である。遥にスパルタ的なピアノレッスンを行う家庭教師・岬洋介の魅力的なキャラクターも加えて、音楽への情熱が語られる。この岬洋介なる人物は、著名な検事を父に持ち、自身も司法試験に優秀な成績を以て合格しているのだが、それをけってピアニストになったという、変わり種だ。
の物語の凄いところは、まるでピアノの音があふれ出てくるような、演奏の描写である。遥にスパルタ的なピアノレッスンを行う家庭教師・岬洋介の魅力的なキャラクターも加えて、音楽への情熱が語られる。この岬洋介なる人物は、著名な検事を父に持ち、自身も司法試験に優秀な成績を以て合格しているのだが、それをけってピアニストになったという、変わり種だ。
 学時代アルバイトで楽団のギター奏者をして、その後、芸能プロデューサーとなり歌手を連れて全国を廻った、という珍しい経歴の著者が4度目にして成し遂げた江戸川乱歩賞受賞作(昭和45年、第16回)である。
学時代アルバイトで楽団のギター奏者をして、その後、芸能プロデューサーとなり歌手を連れて全国を廻った、という珍しい経歴の著者が4度目にして成し遂げた江戸川乱歩賞受賞作(昭和45年、第16回)である。