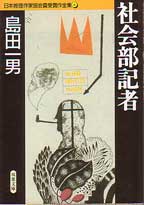| 安全靴とワルツ | ||
|---|---|---|
 |
読了日 | 2021/12/13 |
| 著 者 | 森深紅 | |
| 出版社 | 角川春樹事務所 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 301 | |
| 発行日 | 2012/08/06 | |
| ISBN | 978-4-7584-1184-4 | |
 ての文学作品はミステリーだ。と誰か著名人が言ってたような気がするが、誰だったか思い出せない。
ての文学作品はミステリーだ。と誰か著名人が言ってたような気がするが、誰だったか思い出せない。
まあ、言われてみればもっともだと思わないでもないが、僕はそんな言葉に誘われたわけでもないが、出来るだけ幅広い読書を心掛けてきた。
節操もない読書態度の言い訳かも知れないが、ブログのタイトルが“ミステリー読書”となっているから、従来はあまりとんでもなく見当違いの本は避けてきたつもりだ。しかし、たまにはそうした埒外の本を読みたくなることもあり、なかなか難しいものだ。
所が本書はその埒外と思われた内容が、読み進むうちに次第に面白さを増してきた。自動車メーカーの現場の仕事がいかにも即した内容であらわされており、さもありなんと思わせたのだ。
少し前の時代に、いや少しではないか、“企業戦士”と言う言葉が幅を利かせていた。本書を読んでいると、主人公の坂本敦子が正にその企業戦士だ。運の良さもあるが本人の予期せぬ人事考課が、スムーズな昇格を引き寄せるさまが、心地よく響く。
女性と言うことだけでなく、人として企業人として業務に向き合う姿勢が、何とも読んでいて引き寄せられるのだ。

大分ゆっくりの読書スピードだが、12月中に読み終えて相沢沙呼氏の『INVERT 城塚翡翠倒叙集』を読みたいものだ。
前作の『mediumメディウム 霊媒探偵城塚翡翠 』に圧倒されるような読後感を味わったので、k遺体が大きいのだ。
この『安全靴とワルツ』は積ン読本の消化だが、いつか読もうと思って買った本が、知らぬ間に300いや400冊はあるだろうか?読もうと思って買うのだが、買ってしまえばいつでも読めるということで、読まずに溜まってしまうのだ。もう何度同じことを書いただろう?
どうしても手許に有る本は後回しになって、新しい本を先に読みたくなる。そうして積ン読本が増えていくのだ。最近はこれ以上増やすことが無いように、書店や古書店に行くことを控えている。行けば1冊くらいは良いだろうと手を出してしまうのだ。まあ、それでも資金は手元不如意ということもあって、欲しくても経済的に余裕がないから、1冊でもおいそれと手は出せない。

 い頃は金が有ろうと無かろうと、何とか工面して本を買っていた時もあり、一番の思い出は中学生の頃だ。昼食代としていくらかの小使いを貯めては空きっ腹を我慢して、文庫本に変えていた。
い頃は金が有ろうと無かろうと、何とか工面して本を買っていた時もあり、一番の思い出は中学生の頃だ。昼食代としていくらかの小使いを貯めては空きっ腹を我慢して、文庫本に変えていた。
お蔭で成長期の栄養不良が成長をストップさせたのだろう。痩せて背も伸びなかったのはそのせいだと思っている。今頃そんなことを振り返っても、何にもならないのは分かっているが、僕の暗い青春前期の苦い思い出は尽きない。
そんな暗い青春を抜け出して、明るい未来が待っていたかというと、そんなことはなく相変わらず僕の生活は黒から灰色に変わったくらいだ。だが、そうは言うものの、そうしたことは僕の思いの中だけで、客観的にはどうやら世間一般と同様に幸せな家庭生活を送っている。
近づいている人生120年時代に向かって、生き延びるかどうかは分からないが、昨年脳梗塞を患ったにも拘らず、割と元気に過ごせているのは幸せか?それとも不幸せなのか?
今日は3月18日金曜日で燃えるゴミの日、指定の袋に入れた1週間分のごみを集積所に運んだ。いつのころからかそれが僕のルーチンとなっている。
福島、宮城を襲った震度6強の地震は、我が木更津地方をもちょっと長い横揺れをもたらした。23時36分と遅い時間だっただけに、寝ていた人も多かったのではないか。僕もまだ寝付いてはいなかったが、布団の中だった。少し長い揺れに驚いて、すぐにテレビをつけると、震源は福島県沖だと分かり、東北新幹線の脱線事故、高速道の日いび割れなどの被害を及ぼしたことが分かった。
東日本大震災から11年を迎えて、再び大きな地震に見舞われた東北地方の人々に何とも言えない気の毒な思いだ。
にほんブログ村 |













 約してあった本の順番が回ってきたとの連絡メールが、9月4日の日曜日に市原市立図書館から入った。少し前に木更津より市原の方が、予約の順番が回ってくるのが早い、という実績があって僕はネットで市原市立図書館の方に、本書の予約を入れておいたのだ。
約してあった本の順番が回ってきたとの連絡メールが、9月4日の日曜日に市原市立図書館から入った。少し前に木更津より市原の方が、予約の順番が回ってくるのが早い、という実績があって僕はネットで市原市立図書館の方に、本書の予約を入れておいたのだ。 にも書いたことがあるが、ミステリーの探偵役に付いて、あらゆる職種が出きったのではないか、そういう人もいて、ミステリー作家の題材探しも大変だなと、本書を読んでいてそんなことを思った。もう探偵をこなす職業はないのではないか、そんな意見に対してまだまだありますよ、といった具合に今回の主人公が初めて聞く“家裁調査官”ということで、探せば探偵になる人物はいくらでもあるのではないか、そんな気にもさせられる。
にも書いたことがあるが、ミステリーの探偵役に付いて、あらゆる職種が出きったのではないか、そういう人もいて、ミステリー作家の題材探しも大変だなと、本書を読んでいてそんなことを思った。もう探偵をこなす職業はないのではないか、そんな意見に対してまだまだありますよ、といった具合に今回の主人公が初めて聞く“家裁調査官”ということで、探せば探偵になる人物はいくらでもあるのではないか、そんな気にもさせられる。
 の本を知ったのは昨年早くに、NHKBSで放送された「週刊ブックレビュー」で、ゲストの誰かがお勧めの1冊として紹介していたのを見てからだ。と思う?
の本を知ったのは昨年早くに、NHKBSで放送された「週刊ブックレビュー」で、ゲストの誰かがお勧めの1冊として紹介していたのを見てからだ。と思う? て本書の舞台は、玄武書房という中堅の出版社、そこで企画された大きなプロジェクトが、「大渡海」という日本語辞書の出版だった。日本語という言葉の海原を渡るための舟が、辞書ということで名づけられた「大渡海」だが、それにかかる費用と、時間は半端なものではなく、会社の方針で何度か中止となりかける。
て本書の舞台は、玄武書房という中堅の出版社、そこで企画された大きなプロジェクトが、「大渡海」という日本語辞書の出版だった。日本語という言葉の海原を渡るための舟が、辞書ということで名づけられた「大渡海」だが、それにかかる費用と、時間は半端なものではなく、会社の方針で何度か中止となりかける。
 xnミステリーで定期的に放送している講談社の「リブラリアンの書庫」という番組で、著者が出演して本書に関するインタビューに答えていた。図はその時の番組あてに書いた著者のサインだ
xnミステリーで定期的に放送している講談社の「リブラリアンの書庫」という番組で、著者が出演して本書に関するインタビューに答えていた。図はその時の番組あてに書いた著者のサインだ 人公・花森心平の何とも心もとない様子は、これでも大卒なのかと!と言いたいほどだ。しかしそんなキャラクターだからこそ、その後の活躍が浮き彫りにされるのか?
人公・花森心平の何とも心もとない様子は、これでも大卒なのかと!と言いたいほどだ。しかしそんなキャラクターだからこそ、その後の活躍が浮き彫りにされるのか?