| ニャン氏の童心 | ||
|---|---|---|
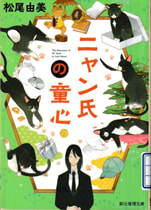 |
読了日 | 2021/05/04 |
| 著 者 | 松尾由美 | |
| 出版社 | 東京創元社 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 264 | |
| 発行日 | 2017/02/24 | |
| ISBN | 978-4-488-43908-8 | |
 盆休みが明けて僕の仕事(メール便の配達業)が、再び始まった。休み明けの仕事は結構たくさんあって、その仕分けや読み込みに、時間がかかった。仕事がたくさんあるのは大いに歓迎するところだが、だんだん体力も衰えて、自分が考えているよりずっとスタミナの消費速度は上がっているようで、目に見えて疲れがたまってくようだ。
盆休みが明けて僕の仕事(メール便の配達業)が、再び始まった。休み明けの仕事は結構たくさんあって、その仕分けや読み込みに、時間がかかった。仕事がたくさんあるのは大いに歓迎するところだが、だんだん体力も衰えて、自分が考えているよりずっとスタミナの消費速度は上がっているようで、目に見えて疲れがたまってくようだ。
少し前までは、まだまだ働けるという気がしていたのに、それはずいぶん前のような気がしている。まだ81歳で、弱音を吐くには早すぎるのではないかと、思うが実際には弱音ではなく本音なのだ。
せめて85歳くらいまでは頑張ってみようと思うが、この細い体がもつかどうか、保証の限りではないというのが本当のところだ。

しかし新型コロナの勢いは、僕の体力、気力とは反対に、増々その勢いを増すばかりだ。
政府の施策の失敗ばかりを責めるだけでは、解決しないだろう。あまり言いたくはないが、究極のところ自助努力が求められている。“自分の命は自分で守る”しかないのだ。わが木更津市の感染者数は1,000人を超えて、少しずつではあるが毎日その数を上乗せしている。どこで誰が感染をしているのだろうと思うが、人それぞれ事情は異なり一概にその行動を責めるわけにはいかないのだろう。
僕の場合をいえば、前にも書いたが、ワクチンの接種には何の副作用もなく、接種後の生活に一遍の不都合もなかった。運が良かったのか、それとも体質の問題か?若い人たちの間には、副作用を恐れてワクチン接種を拒む人が多いと聞く。そのために感染者が増えているというのなら、それは本末転倒と言うか、いや、意味合いが少し異なるか?誰のためのワクチン接種かに、はき違えがあるのか?
問題は簡単ではないが、いずれにしても感染を食い止めて、一日でも早い日常を取り戻すために。何をすれば、良いのか、何をしてはならないのか、誰しもが考えるときだろう。

 の知らない間にニャン氏のシリーズは3巻出ていて、木更津市立図書館に蔵書としてあるから、いつでも読めるらしい。松尾由美氏の短編はちょっとした日常の謎を扱う短編が楽しいから、読みたいという読書欲を満たせる。 タイトルから推測すれば、多分猫が探偵役を果たすのだろう。
の知らない間にニャン氏のシリーズは3巻出ていて、木更津市立図書館に蔵書としてあるから、いつでも読めるらしい。松尾由美氏の短編はちょっとした日常の謎を扱う短編が楽しいから、読みたいという読書欲を満たせる。 タイトルから推測すれば、多分猫が探偵役を果たすのだろう。
猫とミステリーは切っても切れない縁があり、化け猫などの怪奇譚や探偵役やその助手役など、多くのミステリーにも登城して、活躍ぶりを示している。
僕が中学生の頃に発足した、江戸川乱歩賞の公募第1作が仁木悦子女史の『猫は知っていた』もそうした猫を絡ませたミステリーだったのではないか。僕はそれにより女性ミステリ作家が誕生したことに、驚きと喜びを同時に味わったものだった。(実際はそれ以前にも女性ミステリ作家はいて、僕が知らないだけだったのだが・・・・)
今では、エドガー・アラン・ポウ氏の『黒猫』を引き合いに出すまでもなく、猫が絡むミステリーは数限りなくある。我が国でも赤川次郎氏の三毛猫ホームズ―残念ながら僕このシリーズを読んでないから、何とも言えないが…―をはじめ、たくさんの猫探偵が活躍しているらしい。
最近の犬猫ペットのブームともいえることも、こうしたミステリーがもてはやされる要因か。
中堅の出版社・プラタナス書房で働く編集者、田宮宴は港区に事務所を構える童話作家、ミーミ・ニャン吉氏の所へ1年くらい通っていた。田宮の相手をするのはいつも秘書の丸山だった。
彼がミーミ・ニャン氏の言葉を田宮に伝えるのだが、いつもそばには、タキシードをまとい、蝶ネクタイをした政争の紳士を思わせる様な柄の猫がいた。多分その猫が実はミーミ市ではないかと思わせるのだが、確たる証拠はない。
しかし第1巻の『ニャン氏の事件簿』から、いつも丸山の隣に鎮座する猫がニャン氏であることを想像させており、いよいよ本書の中ほどで、丸山がの事実を明かして、ニャン氏の正体が知れることになる。
| タイトル | 号 | 発行年月 |
|---|---|---|
| 袋小路の猫探偵 | Vol.85 | 2017年10月 |
| 偽りのアプローチ | Vol.86 | 2017年12月 |
| 幸運の星の下に | Vol.87 | 2018年2月 |
| 金栗庵の悲劇 | Vol.88 | 2018年4月 |
| 猫探偵と土手の桜 | Vol.89 | 2018年6月 |
| ニャン氏のクリスマス | Vol.90 | 2018年8月 |
にほんブログ村 |













 々僕はこの作者の新作が出ていないかを、Amazonなどで探してみている。
々僕はこの作者の新作が出ていないかを、Amazonなどで探してみている。 日は朝からどんよりとした曇り空で、気温は割と高めなのだが、温かさを感じないのは、お天気のせいか。
日は朝からどんよりとした曇り空で、気温は割と高めなのだが、温かさを感じないのは、お天気のせいか。
 年7月の「悲嘆の門」以来だから、著者の作品を読むのは1年2カ月ぶりか。
年7月の「悲嘆の門」以来だから、著者の作品を読むのは1年2カ月ぶりか。 ァンタジーと呼ばれる物語や、映像作品はたくさんあって中でも、英国の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中の読者や視聴者の絶大な人気を誇っている。わが国でも国際アンデルセン賞を受賞したことで、一躍時の人ともなった上橋菜穂子氏の作品が人気を集めており、NHKで「精霊の守り人」シリーズがドラマ化された。
ァンタジーと呼ばれる物語や、映像作品はたくさんあって中でも、英国の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中の読者や視聴者の絶大な人気を誇っている。わが国でも国際アンデルセン賞を受賞したことで、一躍時の人ともなった上橋菜穂子氏の作品が人気を集めており、NHKで「精霊の守り人」シリーズがドラマ化された。
 日の日曜日は薄光会の保護者・家族の会の定例役員会があって、午前中太陽のしずくに行ってきた。毎回のことだが、社会福祉法人薄光会は、富津市湊に本拠を構える法人で、富津市を中心として、鴨川市、南房総市などに知的障害者の入所施設、通所施設、あるいは特別養護老人ホームなどを展開している。
日の日曜日は薄光会の保護者・家族の会の定例役員会があって、午前中太陽のしずくに行ってきた。毎回のことだが、社会福祉法人薄光会は、富津市湊に本拠を構える法人で、富津市を中心として、鴨川市、南房総市などに知的障害者の入所施設、通所施設、あるいは特別養護老人ホームなどを展開している。 当なミーハーの僕でも、以前ならこのシリーズ作品には、それほど興味を示さなかったのではないか、そんな感じを持っている。だが、ミーハーなるがゆえに、国際アンデルセン賞なるものに興味が湧いて、ネットで検索したところ、「小さなノーベル賞」といわれるほど多田愛奈影響力を持つ賞で、「児童文学への永続的な寄与」に対する表彰だとのこと。
当なミーハーの僕でも、以前ならこのシリーズ作品には、それほど興味を示さなかったのではないか、そんな感じを持っている。だが、ミーハーなるがゆえに、国際アンデルセン賞なるものに興味が湧いて、ネットで検索したところ、「小さなノーベル賞」といわれるほど多田愛奈影響力を持つ賞で、「児童文学への永続的な寄与」に対する表彰だとのこと。
 曜日21日から3日間にわたって繰り広げられた、LPGAツアー第8戦・フジサンケイレディスクラシックをテレビ観戦しながら、勝負の厳しさを改めて感じた。野球は筋書きのないドラマだといわれるが、それは野球に限ったことではないだろう。スポーツ競技に共通していえることではないかと思う。
曜日21日から3日間にわたって繰り広げられた、LPGAツアー第8戦・フジサンケイレディスクラシックをテレビ観戦しながら、勝負の厳しさを改めて感じた。野球は筋書きのないドラマだといわれるが、それは野球に限ったことではないだろう。スポーツ競技に共通していえることではないかと思う。 をあけながらもシリーズ3冊目となった。いつ頃だったか忘れたが、ヤマダ電機のポイントでシリーズ4冊をまとめて交換したから、このあともう1冊「虚空の旅人」が残っている。
をあけながらもシリーズ3冊目となった。いつ頃だったか忘れたが、ヤマダ電機のポイントでシリーズ4冊をまとめて交換したから、このあともう1冊「虚空の旅人」が残っている。
 こ1週間ほど左足のふくらはぎ上部が鈍い痛みを放っている。どこかにぶつけたとか変な座りかたをしたとか、そういった覚えがなく、原因がわからない。医師に見せるほどではないが(そういう素人判断が、大事になる元なのだが)、気になっていた。
こ1週間ほど左足のふくらはぎ上部が鈍い痛みを放っている。どこかにぶつけたとか変な座りかたをしたとか、そういった覚えがなく、原因がわからない。医師に見せるほどではないが(そういう素人判断が、大事になる元なのだが)、気になっていた。 昨日と昨日はヤマハ・レディースオープンがあって、夢中でテレビ観戦をしていたから、おかげで少々テレビ疲れだ。それほど夢中にならなくてもよさそうなものだが、自分ではゴルフをしないのに、僕はテレビ観戦だけであたかも自分がプレイしているような疲れを感じてしまう。
昨日と昨日はヤマハ・レディースオープンがあって、夢中でテレビ観戦をしていたから、おかげで少々テレビ疲れだ。それほど夢中にならなくてもよさそうなものだが、自分ではゴルフをしないのに、僕はテレビ観戦だけであたかも自分がプレイしているような疲れを感じてしまう。
 日で3月も終わりだというのに、曇ってうすら寒い陽気はまるで逆戻りしたみたいだ。
日で3月も終わりだというのに、曇ってうすら寒い陽気はまるで逆戻りしたみたいだ。 更津市立図書館へ「国を救った数学少女」を借りに行ったときに、知念実希人氏の棚に本書と「黒猫の小夜曲(セレナーデ)」が並んでいるのを見て、一緒に借り出した。
更津市立図書館へ「国を救った数学少女」を借りに行ったときに、知念実希人氏の棚に本書と「黒猫の小夜曲(セレナーデ)」が並んでいるのを見て、一緒に借り出した。
 り人」シリーズ第2作。僕のほんのわずかな拘り、のようなものが、シリーズ第1作「精霊の守り人」を読んだ後、シリーズ前作を読んでみようという気を起こした。近くのヤマダ電機のポイントが少し残っていたから、本書と次作「夢の守り人」の文庫と交換してきた。
り人」シリーズ第2作。僕のほんのわずかな拘り、のようなものが、シリーズ第1作「精霊の守り人」を読んだ後、シリーズ前作を読んでみようという気を起こした。近くのヤマダ電機のポイントが少し残っていたから、本書と次作「夢の守り人」の文庫と交換してきた。 しい環境のカンバル王国は、食物を栽培することもかなわず、20年に一度の山の国王との交歓によるルイシャと言う青光石をもらい、多くの食物を手に入れるしかないのだ。
しい環境のカンバル王国は、食物を栽培することもかなわず、20年に一度の山の国王との交歓によるルイシャと言う青光石をもらい、多くの食物を手に入れるしかないのだ。
 る25日金曜日、月に一度の検診日で薬丸病院に行ってきた。前回の「迎撃せよ」のところでは、息子のことを書いたので、長くなるから通院については書かなかった。僕の血圧の高い状態は昨年秋からのことで、取り立ててどこか具合が悪いということではないが、血圧が高いということはいろいろと不都合をもたらす要因となるから、毎日朝晩の血圧測定と内服薬は欠かさず行っている。加えて、月に一度血圧管理手帳を携えて、医師の検診を仰ぐということが続いている。
る25日金曜日、月に一度の検診日で薬丸病院に行ってきた。前回の「迎撃せよ」のところでは、息子のことを書いたので、長くなるから通院については書かなかった。僕の血圧の高い状態は昨年秋からのことで、取り立ててどこか具合が悪いということではないが、血圧が高いということはいろいろと不都合をもたらす要因となるから、毎日朝晩の血圧測定と内服薬は欠かさず行っている。加えて、月に一度血圧管理手帳を携えて、医師の検診を仰ぐということが続いている。 がこの作品に惹かれる一つの要因は、女性が主人公と言うところだ。女性の著者が女性の読者を対象に?、女性・主人公の活躍を描く、というとその昔一世を風靡した3F作品を思い浮かべるが、本書がそれと違うところは、老若男女を問わず楽しめるエンタテインメントだというところだ。
がこの作品に惹かれる一つの要因は、女性が主人公と言うところだ。女性の著者が女性の読者を対象に?、女性・主人公の活躍を描く、というとその昔一世を風靡した3F作品を思い浮かべるが、本書がそれと違うところは、老若男女を問わず楽しめるエンタテインメントだというところだ。
 原すなお氏は、まだ読んではいないが「青春デンデケデケデケ」が第105回直木賞を受賞したことで、その名を知った。僕はそれより、安楽椅子探偵の名作として知られる、「ミミズクとオリーブ」のシリーズ作品の方で、なじみ深い。
原すなお氏は、まだ読んではいないが「青春デンデケデケデケ」が第105回直木賞を受賞したことで、その名を知った。僕はそれより、安楽椅子探偵の名作として知られる、「ミミズクとオリーブ」のシリーズ作品の方で、なじみ深い。 れから何年かして、東京創元社から文庫で「わが身世にふる、じじわかし」というタイトルで、シリーズの続編が出て、やれうれしやと買って読んだのが2007年だから、すでに8年の歳月が過ぎている。
れから何年かして、東京創元社から文庫で「わが身世にふる、じじわかし」というタイトルで、シリーズの続編が出て、やれうれしやと買って読んだのが2007年だから、すでに8年の歳月が過ぎている。
 昨日(10月15日)、9月29日以来18日ぶりで、病院に行った。本来は10月12日で処方された降圧剤が切れるから、行くはずだったけれど、祝日で病院は休みだったのがもとで、ずるずると延びてしまったのだ。血液検査、尿検査の結果血圧の高いのは、何らかの病が原因ではないことがわかり、一安心。ドクターも確たる原因はわからないが、ちょっとしたストレス等も原因となるから気を付けるように、とのことだ。
昨日(10月15日)、9月29日以来18日ぶりで、病院に行った。本来は10月12日で処方された降圧剤が切れるから、行くはずだったけれど、祝日で病院は休みだったのがもとで、ずるずると延びてしまったのだ。血液検査、尿検査の結果血圧の高いのは、何らかの病が原因ではないことがわかり、一安心。ドクターも確たる原因はわからないが、ちょっとしたストレス等も原因となるから気を付けるように、とのことだ。 代を超越したSFのような作品だ。売れっ子ともいえる著者の作品は初めてだが、いずれ一つは読んでみたいと思っていた作家だ。たくさんある著作のどれから読んだらいいか? そんなことを考えていて、手を付けるのが少々遅くなった。いや、そんなことはないか。
代を超越したSFのような作品だ。売れっ子ともいえる著者の作品は初めてだが、いずれ一つは読んでみたいと思っていた作家だ。たくさんある著作のどれから読んだらいいか? そんなことを考えていて、手を付けるのが少々遅くなった。いや、そんなことはないか。 かし地下鉄の駅は当たり前の話だが、階段を地下に降りて行かなければならない。そして再び階段を上って地上に出た時に時代を隔てた別の世界が待っているなど、ロマンチックであると同時に恐怖でもある。
かし地下鉄の駅は当たり前の話だが、階段を地下に降りて行かなければならない。そして再び階段を上って地上に出た時に時代を隔てた別の世界が待っているなど、ロマンチックであると同時に恐怖でもある。
 れの22日(平成26年)にしばらくぶりでいすみ市大原に行ってきた。菩提寺の瀧泉寺(りゅうせんじ)に供米料を納めるのが目的だ。先年はおふくろが3月18日に心臓発作で亡くなって、何かと寺とのかかわりが多かった。
れの22日(平成26年)にしばらくぶりでいすみ市大原に行ってきた。菩提寺の瀧泉寺(りゅうせんじ)に供米料を納めるのが目的だ。先年はおふくろが3月18日に心臓発作で亡くなって、何かと寺とのかかわりが多かった。
 インベーダー・ゲームに嵌ってゲームセンターやゲーム機の置いてあるスナックや喫茶店に入り浸ったものだ。ほんの短い期間であったが、苦も無く10面消せるようになって止めた。単純なゲームだったが、それだけに人を夢中にさせる何かがあった。
インベーダー・ゲームに嵌ってゲームセンターやゲーム機の置いてあるスナックや喫茶店に入り浸ったものだ。ほんの短い期間であったが、苦も無く10面消せるようになって止めた。単純なゲームだったが、それだけに人を夢中にさせる何かがあった。 近は何度も書いているように、細々と続いてはいるものの、読書量も以前に比べれば圧倒的に少なくなって、BOOKOFFなどの古書店に行くことも全くと言っていい程なくなった。
近は何度も書いているように、細々と続いてはいるものの、読書量も以前に比べれば圧倒的に少なくなって、BOOKOFFなどの古書店に行くことも全くと言っていい程なくなった。
 の作品が単行本で出た時、どこか例えばBSイレブンの「宮崎美子のすずらん本屋堂」とかで、紹介されたのを見たような気がする。が、気になるタイトル、と言うかいいタイトル―読書意欲をそそるタイトル―だな、と思った。しかし、多分僕の好みではないだろうと、例によって僕の思い込みが強く、強いて読もうという気にはならなかった。
の作品が単行本で出た時、どこか例えばBSイレブンの「宮崎美子のすずらん本屋堂」とかで、紹介されたのを見たような気がする。が、気になるタイトル、と言うかいいタイトル―読書意欲をそそるタイトル―だな、と思った。しかし、多分僕の好みではないだろうと、例によって僕の思い込みが強く、強いて読もうという気にはならなかった。
 咫烏(ヤタガラス)の世界(山内:やまうち)で、世継ぎである若宮のきさき選びが始まる、というのがスタートだ。
咫烏(ヤタガラス)の世界(山内:やまうち)で、世継ぎである若宮のきさき選びが始まる、というのがスタートだ。
 神的に何とはなく落ち着かない日々を送っている。そのせいかブログの記事が書けなくて、更新がすすまないでいる。それでも読む方は夜寝る前の時間に少しずつ読んでいるから、ここに書いてない本をすでに数冊読み終わってはいるのだが。
神的に何とはなく落ち着かない日々を送っている。そのせいかブログの記事が書けなくて、更新がすすまないでいる。それでも読む方は夜寝る前の時間に少しずつ読んでいるから、ここに書いてない本をすでに数冊読み終わってはいるのだが。 記のように本書は連作短編集の形をとっているが、一つずつが完結していないところもあって、全体を通して長編ともいえるのではないか。喫茶店「エメラルド」を舞台に、「貴方の不思議、解きます」ということで、隠れ家的探偵の活躍を描くストーリーだ。店長の上倉真紘、その弟で高校生のオーナー・上倉悠貴、そして就活中だがなかなか内定のとれない女子大生の小野寺美久がウェイトレスのアルバイトをしているというのが、レギュラーメンバーである。驚くほどの美形だが極めつけの毒舌家の悠貴が探偵役をこなす。
記のように本書は連作短編集の形をとっているが、一つずつが完結していないところもあって、全体を通して長編ともいえるのではないか。喫茶店「エメラルド」を舞台に、「貴方の不思議、解きます」ということで、隠れ家的探偵の活躍を描くストーリーだ。店長の上倉真紘、その弟で高校生のオーナー・上倉悠貴、そして就活中だがなかなか内定のとれない女子大生の小野寺美久がウェイトレスのアルバイトをしているというのが、レギュラーメンバーである。驚くほどの美形だが極めつけの毒舌家の悠貴が探偵役をこなす。