| あなたのいない記憶 | ||
|---|---|---|
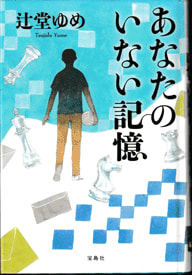 |
読了日 | 2020/11/04 |
| 著 者 | 辻堂ゆめ | |
| 出版社 | 宝島社 | |
| 形 態 | 単行本 | |
| ページ数 | 334 | |
| 発行日 | 2016/11/05 | |
| ISBN | 978-4-8002-6237-0 | |
 ログへの投稿が大分日を開けてしまった。これが初めての事ではないが、毎度毎度の不規則な投稿は、余計に自分のいい加減さをひけらかしているようだから、少し改めようとは思いながらもなかなか直らない。
ログへの投稿が大分日を開けてしまった。これが初めての事ではないが、毎度毎度の不規則な投稿は、余計に自分のいい加減さをひけらかしているようだから、少し改めようとは思いながらもなかなか直らない。
いよいよと言った感じのアメリカ大統領選挙が始まって(投票は昨日11月3日だった)、テレビは各局選挙一色かと思ったが、そうでもなく日常の番組を流しているところが多い。
まあ、それはそうだ、いくら影響を及ぼすとはいえ、他国の首長選挙に一日中関わっているわけにもいかないだろう。しかし僕にとっても大いなる関心事で、現職、対抗馬の争いは他の何よりも興味がある。
それでも興味があるといった程度で、僕の生活に直接響くものではないが・・・。
しかし、良きにつけ悪しきにつけドナルド・トランプ氏の存在感は何物にも勝っている。そんな姿を見ていると、前回のヒラリー・クリントン氏との選挙戦の時のように、バイデン氏の有利とされている州も、ふたを開けてみればひっくり返って、けっきょくはトランプ氏の再選、てな結果になるのかどうか?僕にはわからないが、案外そんなところに落ち着く可能性もある、のではないか?そんなことも考えられるのだ。

ふと、思い出してAmazonで著者の作品を検索、タイトルに惹かれて図書館で借りてきた。 初めて彼女の作品と出逢ったのは、もう3年も前の事で宝島社の「このミス大賞」の優秀作品に選ばれたデビュー作『いなくなった私へ』というファンタジックなミステリーだった。もう内容はすっかり忘れたが、僕の好みの内容だったことだけが頭に残っている。
東大卒の才媛と言うことからもデビュー作に惹かれた一因だったが、今や東大在学中の秀才たちが、テレビのクイズ番組で活躍しており、視聴者を喜ばせている。昔は東大を出て大蔵省(現在の財務省)の官僚になるのが、一つの出世の道と考えられていた時代もあり(現在も相変わらずの様相か)、時代の変遷を感じる。
まあ、いろいろあるが僕にとっては、その才能を活かして面白いミステリーを生みだしてくれることを大いに歓迎するところだ。
歳をとったせいなのだろうが、近ごろと言うか大分前から、ミステリーに対して昔のようなときめきを感じなくなってきている。情報過多の時代だからか?様々な情報が入り乱れる中、過剰ともいえる出版社の広告やキャッチコピーが、新作ミステリーへの勧誘を邪魔しているような気がしてならない。
僕の個人的な思いかもしれないが、否、ここでは全く僕の個人的な思いを書いているのだが、それでもたまに新作ミステリーを読んで、衝撃とも言える面白さを感じることもあるから、ミステリー読書をやめられないでいるのだ。

 きな作家の作品を次々と漁るように読むのは、決して落胆することがない、という安易な思いがあるからだが、一つには新たな作者の作品が自分の好みに合うかどうかが分からないということにも起因する。
きな作家の作品を次々と漁るように読むのは、決して落胆することがない、という安易な思いがあるからだが、一つには新たな作者の作品が自分の好みに合うかどうかが分からないということにも起因する。
だから、思いがけず初めての作家の作品が、面白く読めた時には望外の喜びを感じるのだろう。めったに無いことだが。
先月(9月)に出版社の広告がメールマガジンで何度か続いているのが気になって、2作続けて読んだが、期待していた程でなかったが、多分それは僕の受け入れ方が、時期に合わなかったからではないかと思っている。
過去に何度かそういうことがあって、全く駄作だと思っていた作品を、気を取り直して何か月か、あるいは何年かしてから読み直して、その面白さを認識したということがあった。
それこそが読書の醍醐味だ。
にほんブログ村 |












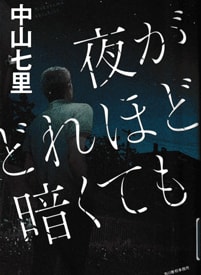
 月11日に予約申し込みをして、ようやく順番が回ってきた5冊の内の1冊が本書だ。 相変わらず人気の高い中山氏だが、それにも増してその旺盛な執筆振りに、唯々驚くほかない。何にしても身体に気を付けて、面白い物語の紡ぎ手を長く保ってほしい。
月11日に予約申し込みをして、ようやく順番が回ってきた5冊の内の1冊が本書だ。 相変わらず人気の高い中山氏だが、それにも増してその旺盛な執筆振りに、唯々驚くほかない。何にしても身体に気を付けて、面白い物語の紡ぎ手を長く保ってほしい。
 日はもう10月も半ばに差し掛かった14日だ。僕の怠け癖がまた出て、ブログへの投稿が2か月も間があいてしまった。この本を読み終わったのは8月31日で、当然の事ながら僕はほとんどその内容を忘れている。ノートの記録はメモ程度の事しかないから、この記事を書くため図書館でもう一度本書を借りてきた。 とは言えざっと読んだところで、記事を書けるわけでもないのだが、それでもブロガーとしての最低限のマナーだという、僕の矜持もあって・・・などときれいごとを言ってられない、2か月も投稿を放っておいたのだから。 そんなことは僕にとって珍しいことでもなく、特に図書館で借りて読んだ本の時は、往々にして同様の事が発生する。近ごろは特に多くなっている。3回に1回程度同じことを書いているような気がして、全くお恥ずかしい。
日はもう10月も半ばに差し掛かった14日だ。僕の怠け癖がまた出て、ブログへの投稿が2か月も間があいてしまった。この本を読み終わったのは8月31日で、当然の事ながら僕はほとんどその内容を忘れている。ノートの記録はメモ程度の事しかないから、この記事を書くため図書館でもう一度本書を借りてきた。 とは言えざっと読んだところで、記事を書けるわけでもないのだが、それでもブロガーとしての最低限のマナーだという、僕の矜持もあって・・・などときれいごとを言ってられない、2か月も投稿を放っておいたのだから。 そんなことは僕にとって珍しいことでもなく、特に図書館で借りて読んだ本の時は、往々にして同様の事が発生する。近ごろは特に多くなっている。3回に1回程度同じことを書いているような気がして、全くお恥ずかしい。
 日(9月14日 月曜日)いすみ市大原の親戚から訃報が知らされた。何と、僕の中学の同級生が亡くなったというのだ。正に青天の霹靂とはこういうことをさすのだと感じた。
日(9月14日 月曜日)いすみ市大原の親戚から訃報が知らされた。何と、僕の中学の同級生が亡くなったというのだ。正に青天の霹靂とはこういうことをさすのだと感じた。 0年も前は今では大昔だ。
0年も前は今では大昔だ。
 うだいぶ前に書いた文章の内容が、少し古い印象を与えるかもしれない。それでも新型コロナウィルスの感染状況は、依然としてその勢いを止めることがなく、不気味な感じを現し続けている。
うだいぶ前に書いた文章の内容が、少し古い印象を与えるかもしれない。それでも新型コロナウィルスの感染状況は、依然としてその勢いを止めることがなく、不気味な感じを現し続けている。 し時間が経てば自分のバカさ加減がよくわかるが、なかなかその時点では分からないから厄介なのだ。いやいや、厄介だ、では済まされないのだ。絶えずここで告白しているように、僕はあまり裕福ではなくどちらかと言えば貧乏と言える部類に入る。
し時間が経てば自分のバカさ加減がよくわかるが、なかなかその時点では分からないから厄介なのだ。いやいや、厄介だ、では済まされないのだ。絶えずここで告白しているように、僕はあまり裕福ではなくどちらかと言えば貧乏と言える部類に入る。 て本作品は、自殺を防止することを目的とした、NPOの活動を描いた物語なのだが、一方ではコンピュータアプリケーションによる、集団自殺へ導くということを企てる者もいて、世は複雑怪奇。
て本作品は、自殺を防止することを目的とした、NPOの活動を描いた物語なのだが、一方ではコンピュータアプリケーションによる、集団自殺へ導くということを企てる者もいて、世は複雑怪奇。
 時は新たに本を買うことを控えており、NETの広告やAmazon、あるいはヤフオクなどの閲覧もしないようにしていた。ところがいつの間にかそうしたことも忘れて、ヤフオクの出品に面白い本が出ていないか、Amazonの中古本に興味のある本がないか、などと毎日見ている。
時は新たに本を買うことを控えており、NETの広告やAmazon、あるいはヤフオクなどの閲覧もしないようにしていた。ところがいつの間にかそうしたことも忘れて、ヤフオクの出品に面白い本が出ていないか、Amazonの中古本に興味のある本がないか、などと毎日見ている。 のところ東京都の新たな新型コロナウィルス感染者の増加と、西日本、特に九州地方の豪雨災害のニュースで、もちきりのテレビ放送に何と言って良いか?災害被害者への思いが胸をつぶす。
のところ東京都の新たな新型コロナウィルス感染者の増加と、西日本、特に九州地方の豪雨災害のニュースで、もちきりのテレビ放送に何と言って良いか?災害被害者への思いが胸をつぶす。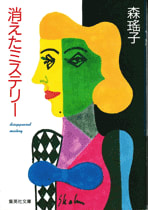
 々思っていることだが、僕がまだ知らない面白いミステリーは、そっちこっちに有って、それらの本は、 じれったい様に読まれるのを待っている。
々思っていることだが、僕がまだ知らない面白いミステリーは、そっちこっちに有って、それらの本は、 じれったい様に読まれるのを待っている。 つて、江戸川乱歩氏が雑誌“宝石”の立て直しを図った折に、探偵作家以外の多くの作家に探偵小説を書くことを勧めていた、ことを思い起こす。
つて、江戸川乱歩氏が雑誌“宝石”の立て直しを図った折に、探偵作家以外の多くの作家に探偵小説を書くことを勧めていた、ことを思い起こす。
 月21日から5月3日まで、なんと12日もかかってようやく読み終えた。1冊の本を2週間近くもかかって読んだのは、今までにないことだが、数ページ読んでは一休みと言ったことを繰り返せばこうなる、ということを改めて確認しても、何の役にも立たない。
月21日から5月3日まで、なんと12日もかかってようやく読み終えた。1冊の本を2週間近くもかかって読んだのは、今までにないことだが、数ページ読んでは一休みと言ったことを繰り返せばこうなる、ということを改めて確認しても、何の役にも立たない。 日は息子の入所している福祉施設から、正確には施設利用者(主として知的障碍者)の、保護者の団体である天羽支部から、昨年度の決算報告並びに、今年度の予算案だった。
日は息子の入所している福祉施設から、正確には施設利用者(主として知的障碍者)の、保護者の団体である天羽支部から、昨年度の決算報告並びに、今年度の予算案だった。
 邪鬼な傾向のある僕は、従来なら決して手にすることのない本だ。
邪鬼な傾向のある僕は、従来なら決して手にすることのない本だ。 曜日(16日)のニュースで、アメリカのGMS(ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア)、JCペニーが連邦破産法(日本の民事再生法にあたる)を申請したという報道があった。
曜日(16日)のニュースで、アメリカのGMS(ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア)、JCペニーが連邦破産法(日本の民事再生法にあたる)を申請したという報道があった。
 和初期の探偵小説を思わせるような、ちょっと不気味な感じのするタイトルだ。中山七里氏の作品は本書で44冊目となった。それでもまだ、未読の新刊が数冊残っている。
和初期の探偵小説を思わせるような、ちょっと不気味な感じのするタイトルだ。中山七里氏の作品は本書で44冊目となった。それでもまだ、未読の新刊が数冊残っている。
 月24日図書館からのメールに気付き開くと、「予約の資料が用意できました」という、本書の順番が回ってきた知らせだった。あいにく当日は火曜の休館日だったので翌25日に行って借りてきた。
月24日図書館からのメールに気付き開くと、「予約の資料が用意できました」という、本書の順番が回ってきた知らせだった。あいにく当日は火曜の休館日だったので翌25日に行って借りてきた。
 書の帯に、“この小説、凄すぎてコピーが書けません。とにかく読んでください!”とあり、ネタバレ厳禁!!の表示も。僕は単純にタイトルに惹かれて買ったのだが、“ルビンの壺”については、表紙のイラストでお分かりのように、二人の人物の向かい合った顔の影絵が示すように、壺の形を示している。
書の帯に、“この小説、凄すぎてコピーが書けません。とにかく読んでください!”とあり、ネタバレ厳禁!!の表示も。僕は単純にタイトルに惹かれて買ったのだが、“ルビンの壺”については、表紙のイラストでお分かりのように、二人の人物の向かい合った顔の影絵が示すように、壺の形を示している。 ーヒーを飲みながらミステリーを読むには絶好の環境だ。僕のように何にも予定はなく、出かけるところもない年寄りにはいいかもしれないが、若くてエネルギーを持て余す若者には、緊急事態宣言による外出自粛はつらいことかもしれない。
ーヒーを飲みながらミステリーを読むには絶好の環境だ。僕のように何にも予定はなく、出かけるところもない年寄りにはいいかもしれないが、若くてエネルギーを持て余す若者には、緊急事態宣言による外出自粛はつらいことかもしれない。
 故ミステリー作家は、誘拐事件に惹かれるのだろう?そして、飽きずに次々と作品を生み出すのだろう。そんな疑問を何回かここに書いてきた。最も割に合わない犯罪と言われる“誘拐”。それは実際の事件の経過を見ても分かるように、誘拐事件の99%あるいはそれ以上、犯人側から見たら不成功に終わっているからだ。
故ミステリー作家は、誘拐事件に惹かれるのだろう?そして、飽きずに次々と作品を生み出すのだろう。そんな疑問を何回かここに書いてきた。最も割に合わない犯罪と言われる“誘拐”。それは実際の事件の経過を見ても分かるように、誘拐事件の99%あるいはそれ以上、犯人側から見たら不成功に終わっているからだ。
 近、と言ってもつい先ごろの事なのに、日時も場所も忘れた。
近、と言ってもつい先ごろの事なのに、日時も場所も忘れた。

 誨師(きょうかいし)というのがこの物語の主人公だ。教誨師とは死刑囚に宗教を教え諭す仕事だ。
誨師(きょうかいし)というのがこの物語の主人公だ。教誨師とは死刑囚に宗教を教え諭す仕事だ。 れにしても新型コロナウィルスの勢いは、いまだとどまるところを知らない。
れにしても新型コロナウィルスの勢いは、いまだとどまるところを知らない。
 日、3月11日は9年前に起こった東日本大震災の日だ。 今でもあの日のテレビで見た映像は忘れることのできない衝撃的なものだった。実際に被害にあった人、身近で大切な人を失った人は、どんな日々を送ってきたのだろうかと、その心の中は想像することさえ出来ないでいるが、僕は昭和20年3月の東京大空襲を思い出す。当時5歳だった僕はほんの一部分しか覚えていないのだが、まだ1歳だった弟を背にしたお袋に手を引かれて、火の海の中を隅田公園に逃れたことが、鮮明に頭に浮かぶことから、まったく事情は異なるが東日本大震災のさ中にいた人たちの、どうしようもなかった気持ちが多少なりとも、分かるような気もするのだ。
日、3月11日は9年前に起こった東日本大震災の日だ。 今でもあの日のテレビで見た映像は忘れることのできない衝撃的なものだった。実際に被害にあった人、身近で大切な人を失った人は、どんな日々を送ってきたのだろうかと、その心の中は想像することさえ出来ないでいるが、僕は昭和20年3月の東京大空襲を思い出す。当時5歳だった僕はほんの一部分しか覚えていないのだが、まだ1歳だった弟を背にしたお袋に手を引かれて、火の海の中を隅田公園に逃れたことが、鮮明に頭に浮かぶことから、まったく事情は異なるが東日本大震災のさ中にいた人たちの、どうしようもなかった気持ちが多少なりとも、分かるような気もするのだ。 馬区石神井のハイツ長谷川というマンションの一室で、老人の死体が発見された。
馬区石神井のハイツ長谷川というマンションの一室で、老人の死体が発見された。