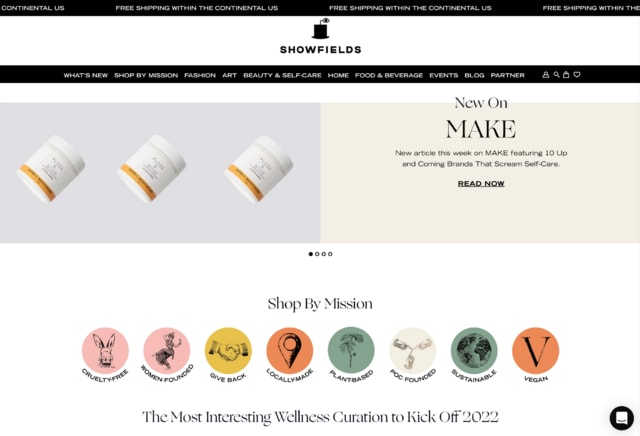すでに社長のポストを奪われたのだから責任はないと思う。だが、その結果を招いた一端は、もちろん当人にある。大塚家具の大塚久美子元社長とヤマダデンキ吸収合併の件だ。報道によると、店舗やIDCは存続するが、法人は消滅することになるという。
ここに至った経緯を改めて振り返る必要はないだろう。メディアは大塚家具が迷走した背景に創業者である父勝久氏と息女久美子氏の「親子げんか」があるように伝えるが、それは大衆を惹きつけるネタに過ぎない。むしろ、家具業界が抱える構造的な問題が大塚家具にも例外なくのし掛かり、追い詰められていったということだ。
時代に変化に取り残された大塚家具
家具という商品はどんな性格のものか。かつての日本には、軽くて女性でも持ち運べることから、結婚時には桐箪笥を主体にした「婚礼家具」を新婦側が嫁入り道具として持たせる習わしがあった。昭和期にも家具専門店はこの習慣(洋服箪笥、衣装箪笥、整理箪笥の婚礼3点セット)を販売戦略に組み込み、家電などとセットにしてマーケティングを展開していた。
高度成長期に入ると、結婚だけでなく就職や転勤、進学と、人の移動が家具の需要に影響した。単身生活ではそれほど多くの家具は必要ない。学生の下宿生活では3段ボックスやファンシーケースがあれば十分だった。結婚では核家族化が進んだが、いきなり一戸建てに住めるわけではない。社宅やアパート暮らしなら、揃えられる家具やインテリアは限られた。家庭では子供が生まれ成長するに従って、求められるアイテムも変わっていったのである。


やがてバブル景気に突入すると住宅需要の盛り上げとリンクして、メディアは家具&インテリアをこぞって特集した。専門のスタイリストが雑誌の特集ページで紹介するのは、外国製を主体にした高価格・高感度なもの。中でも、デンマーク生まれの「Yチェア」やイタリア製の「マッキントッシュ」のように所有することで価値を生む家具も登場した。
バブルが崩壊し平成不況が長引くと一転、所得やライフステージに合わせた商品提案がなされるようになった。一つは途上国で製造することで低価格を実現したもの。もう一つがセコハン(中古)の家具である。しかし、こうしたトレンドが家具専門店を苦しめることになった。品揃えには広大なスペースが必要になるため、都市部の店舗では高額な家賃負担が経営を圧迫した。生き残りをかけてローコストな郊外展開にシフトしたものの、仕入れて安売りするだけではコストを吸収できず、閉店するところが相次いだ。
裏を返せば、消費生活の変化と所得の伸び悩みで、高価な家具を一生に渡って使う様式や価値観が変わってしまったのだ。ファミリー層がマンションで暮らし始めると、収納が充実しているためタンスは必要ではなくなり、売れるのはテーブルセットやソファ、ベッド、カップ&ローボードと限られた。若年層は家具&インテリアに対するセンスが向上したことで、中古の家具やインテリアでもおしゃれにコーディネートしてみせた。
そんな状況下でも、大塚家具は高級家具を販売するためにお客一人一人に販売員を付かせるマンツーマン接客を続けた。しかし、大多数の消費者はそんな手法を望まなくなっていた。自分のライフスタイルに合うデザインや機能を備えれていれば、産地やブランド、品質には拘らない。マスで売れる家具・インテリアは完全にトレードオフの商品になってしまった。ただ、ベッドだけは高齢社会を反映し、介護機能付きで高額なものにシフトし始めている。

もっとも、ユーザーが家具選びの主導権を握れば、プロフェッショナルな接客は必要ない。それを逆手に取ったのが「ニトリ」や「イケア」、「無印良品」である。自ら製造して販売することでデザインや機能性、品質を限定的にし、セルフで自由に選んでもらうこと(組み立ても)で、低価格を実現した。こうして彼らが完全に家具・インテリア市場のボリュームゾーンを制圧したのである。
戦略転換を模索したものの、ミッションを欠いた
もちろん、国立難関校の一橋大学を卒業し、経営コンサルタントまで務めた大塚久美子氏がそうした構造変化に気づいていないわけがない。メディアで伝えられた「高級ではなく、売りやすい中級も扱う」「お父さんのやり方は古いのよ」などの「反抗」にはその一端が見られる。だが、企業経営はまず確固とした方針が必要で、経営者にはそのミッションがある。戦略転換を進めるには、それを打ち立てなければならない。その上で、戦術としての商品政策、販売手法が生きてくるのである。
ところが、大塚久美子氏は経営者としてミッションを果たさなかった。しかも、売上げ不振を十分に補えるだけの代替戦略を構築し、銀座や博多での広大な店舗展開など高コスト体質を改めたかと言えば、そんなことはない。つまり、久美子氏が新たな経営方針をしっかり示さず、判断のタイミングを見失ったことがヤマダ電機への身売り、そして会社の消滅につながったのである。


家具・インテリアの市場を俯瞰すると、ハイグレードのジャンルに入るインポート家具では、イタリアの「カッシーナイクスシー」、デンマークの「ボーコンセプト」、英国の「コンランショップ」など欧米のブランドが浸透している。これらは品質の良さだけでなく、デザイン性や感度でも優れており、価格対価値では大塚家具を凌駕している。マーケットは小さいが、一定数の富裕層がターゲットだ。


中級でも「アクタス」「タイムレスコンフォート」「ダブルデイ」などのインテリアショップが顧客を捉えている。その手法はリビングやキッチンなどの雑貨で集客し、お客が逆に売場にディスプレイされた家具に魅了されて購入するシダクション商法。「フランフラン」のように都会で一人暮らしをする女性に特化した業態もある。売り方、見せ方の妙というか、家具だけをだだっ広く並べて、販売員が張り付いて接客してきた大塚家具とは大きな違いである。
もちろん、低価格の家具・インテリアは、アウトレット店を含めいくらでもある。中古業態の「ハードオフ」や「セカンドストリート」も、家具の買取や販売(カッシーナイクスシーのようなブランドはセコハンでも高値で取引)も行っているし、環境保護を考えるSDGsが叫ばれ、新品でなくてもいい価値観が市民権を得たのも事実だ。加えて日本は毎年のように台風や豪雨、地震が発生し、被害が多発している。家具が売れる環境にはあるのだが、破損するのは高級品も同じだから、売れ筋はなおさら低価格品やセコハンになっていく。
大塚家具が中級品の販売を拡大したところで、どれだけのお客を捕捉できたか。競合の状況を見れば、かなり厳しかっただろう。筆者が住む福岡の大川市は家具産地として有名だが、海外製の低価格品に押されて厳しい状況にある。その打開策として「コントラクト(請負)」部門の拡充を行っている。木造住宅の建具や造り付け家具、ビルや店舗の内装で特別仕様に近い家具などをハウジングメーカーや建設会社から受注するものだ。大塚家具も一部で乗り出していたようだが、目に見えた成果は出せていなかった。
家具需要を活性化させたいのなら、一度購入したら終わりではなく、買い替えを促す方法もありだと思う。高級家具は品質も良いのでセコハンでも売れるし、リフォームにも耐えられる。模様替えなどのキャンペーンを張って、そうした商品の買取と再販の仕組みを整えることも必要だった。並行して、子供たちに家具の魅力を知ってもらうために製造現場の見学会を開催するとか、手作り=オーダー家具に親しんでもらうためにDIYのワークショップを開くとか。少しでも販売につなげていくやり方は色々と考えられたはずだ。
万策を尽くすこともなく、救いの手をヤマダ電機に一本化したことが果たして正解だったのか。高級家具の販売と家電の安売り大手。外から見ればあまりに企業の格や文化が違うように見える。それとも、仕入れコストできるだけを安くするためにメーカーに圧力をかける体質は共通していたのか。どちらにしても、家電の売上げが頭打ちで住宅設備などに活路を見出そうとするヤマダ電機に、大塚家具がうまく飲み込まれたのは確かだ。
家電の購入はネット通販でも十分だが、家具はサイズや使い勝手も購入の条件になるから、現物を見なければならない。消費者側が家具選びの主導権を握る中で、ヤマダ電機とてどこまで家電との相乗効果を発揮できるかは未知数だ。大塚家具を生かすも殺すも、家具を必要とするお客をいかに集客するかにかかっている。果たしてヤマダ電機にそれができるかである。
今思えば、経営はつくづくクリエイティブだと思う。時代の変化を読み、需要を喚起するビジネスを創造できるかだからだ。美人で秀才で凛とした大塚久美子氏には酷な言い方かもしれないが、彼女にはその能力がなかったということである。
ここに至った経緯を改めて振り返る必要はないだろう。メディアは大塚家具が迷走した背景に創業者である父勝久氏と息女久美子氏の「親子げんか」があるように伝えるが、それは大衆を惹きつけるネタに過ぎない。むしろ、家具業界が抱える構造的な問題が大塚家具にも例外なくのし掛かり、追い詰められていったということだ。
時代に変化に取り残された大塚家具
家具という商品はどんな性格のものか。かつての日本には、軽くて女性でも持ち運べることから、結婚時には桐箪笥を主体にした「婚礼家具」を新婦側が嫁入り道具として持たせる習わしがあった。昭和期にも家具専門店はこの習慣(洋服箪笥、衣装箪笥、整理箪笥の婚礼3点セット)を販売戦略に組み込み、家電などとセットにしてマーケティングを展開していた。
高度成長期に入ると、結婚だけでなく就職や転勤、進学と、人の移動が家具の需要に影響した。単身生活ではそれほど多くの家具は必要ない。学生の下宿生活では3段ボックスやファンシーケースがあれば十分だった。結婚では核家族化が進んだが、いきなり一戸建てに住めるわけではない。社宅やアパート暮らしなら、揃えられる家具やインテリアは限られた。家庭では子供が生まれ成長するに従って、求められるアイテムも変わっていったのである。


やがてバブル景気に突入すると住宅需要の盛り上げとリンクして、メディアは家具&インテリアをこぞって特集した。専門のスタイリストが雑誌の特集ページで紹介するのは、外国製を主体にした高価格・高感度なもの。中でも、デンマーク生まれの「Yチェア」やイタリア製の「マッキントッシュ」のように所有することで価値を生む家具も登場した。
バブルが崩壊し平成不況が長引くと一転、所得やライフステージに合わせた商品提案がなされるようになった。一つは途上国で製造することで低価格を実現したもの。もう一つがセコハン(中古)の家具である。しかし、こうしたトレンドが家具専門店を苦しめることになった。品揃えには広大なスペースが必要になるため、都市部の店舗では高額な家賃負担が経営を圧迫した。生き残りをかけてローコストな郊外展開にシフトしたものの、仕入れて安売りするだけではコストを吸収できず、閉店するところが相次いだ。
裏を返せば、消費生活の変化と所得の伸び悩みで、高価な家具を一生に渡って使う様式や価値観が変わってしまったのだ。ファミリー層がマンションで暮らし始めると、収納が充実しているためタンスは必要ではなくなり、売れるのはテーブルセットやソファ、ベッド、カップ&ローボードと限られた。若年層は家具&インテリアに対するセンスが向上したことで、中古の家具やインテリアでもおしゃれにコーディネートしてみせた。
そんな状況下でも、大塚家具は高級家具を販売するためにお客一人一人に販売員を付かせるマンツーマン接客を続けた。しかし、大多数の消費者はそんな手法を望まなくなっていた。自分のライフスタイルに合うデザインや機能を備えれていれば、産地やブランド、品質には拘らない。マスで売れる家具・インテリアは完全にトレードオフの商品になってしまった。ただ、ベッドだけは高齢社会を反映し、介護機能付きで高額なものにシフトし始めている。

もっとも、ユーザーが家具選びの主導権を握れば、プロフェッショナルな接客は必要ない。それを逆手に取ったのが「ニトリ」や「イケア」、「無印良品」である。自ら製造して販売することでデザインや機能性、品質を限定的にし、セルフで自由に選んでもらうこと(組み立ても)で、低価格を実現した。こうして彼らが完全に家具・インテリア市場のボリュームゾーンを制圧したのである。
戦略転換を模索したものの、ミッションを欠いた
もちろん、国立難関校の一橋大学を卒業し、経営コンサルタントまで務めた大塚久美子氏がそうした構造変化に気づいていないわけがない。メディアで伝えられた「高級ではなく、売りやすい中級も扱う」「お父さんのやり方は古いのよ」などの「反抗」にはその一端が見られる。だが、企業経営はまず確固とした方針が必要で、経営者にはそのミッションがある。戦略転換を進めるには、それを打ち立てなければならない。その上で、戦術としての商品政策、販売手法が生きてくるのである。
ところが、大塚久美子氏は経営者としてミッションを果たさなかった。しかも、売上げ不振を十分に補えるだけの代替戦略を構築し、銀座や博多での広大な店舗展開など高コスト体質を改めたかと言えば、そんなことはない。つまり、久美子氏が新たな経営方針をしっかり示さず、判断のタイミングを見失ったことがヤマダ電機への身売り、そして会社の消滅につながったのである。


家具・インテリアの市場を俯瞰すると、ハイグレードのジャンルに入るインポート家具では、イタリアの「カッシーナイクスシー」、デンマークの「ボーコンセプト」、英国の「コンランショップ」など欧米のブランドが浸透している。これらは品質の良さだけでなく、デザイン性や感度でも優れており、価格対価値では大塚家具を凌駕している。マーケットは小さいが、一定数の富裕層がターゲットだ。


中級でも「アクタス」「タイムレスコンフォート」「ダブルデイ」などのインテリアショップが顧客を捉えている。その手法はリビングやキッチンなどの雑貨で集客し、お客が逆に売場にディスプレイされた家具に魅了されて購入するシダクション商法。「フランフラン」のように都会で一人暮らしをする女性に特化した業態もある。売り方、見せ方の妙というか、家具だけをだだっ広く並べて、販売員が張り付いて接客してきた大塚家具とは大きな違いである。
もちろん、低価格の家具・インテリアは、アウトレット店を含めいくらでもある。中古業態の「ハードオフ」や「セカンドストリート」も、家具の買取や販売(カッシーナイクスシーのようなブランドはセコハンでも高値で取引)も行っているし、環境保護を考えるSDGsが叫ばれ、新品でなくてもいい価値観が市民権を得たのも事実だ。加えて日本は毎年のように台風や豪雨、地震が発生し、被害が多発している。家具が売れる環境にはあるのだが、破損するのは高級品も同じだから、売れ筋はなおさら低価格品やセコハンになっていく。
大塚家具が中級品の販売を拡大したところで、どれだけのお客を捕捉できたか。競合の状況を見れば、かなり厳しかっただろう。筆者が住む福岡の大川市は家具産地として有名だが、海外製の低価格品に押されて厳しい状況にある。その打開策として「コントラクト(請負)」部門の拡充を行っている。木造住宅の建具や造り付け家具、ビルや店舗の内装で特別仕様に近い家具などをハウジングメーカーや建設会社から受注するものだ。大塚家具も一部で乗り出していたようだが、目に見えた成果は出せていなかった。
家具需要を活性化させたいのなら、一度購入したら終わりではなく、買い替えを促す方法もありだと思う。高級家具は品質も良いのでセコハンでも売れるし、リフォームにも耐えられる。模様替えなどのキャンペーンを張って、そうした商品の買取と再販の仕組みを整えることも必要だった。並行して、子供たちに家具の魅力を知ってもらうために製造現場の見学会を開催するとか、手作り=オーダー家具に親しんでもらうためにDIYのワークショップを開くとか。少しでも販売につなげていくやり方は色々と考えられたはずだ。
万策を尽くすこともなく、救いの手をヤマダ電機に一本化したことが果たして正解だったのか。高級家具の販売と家電の安売り大手。外から見ればあまりに企業の格や文化が違うように見える。それとも、仕入れコストできるだけを安くするためにメーカーに圧力をかける体質は共通していたのか。どちらにしても、家電の売上げが頭打ちで住宅設備などに活路を見出そうとするヤマダ電機に、大塚家具がうまく飲み込まれたのは確かだ。
家電の購入はネット通販でも十分だが、家具はサイズや使い勝手も購入の条件になるから、現物を見なければならない。消費者側が家具選びの主導権を握る中で、ヤマダ電機とてどこまで家電との相乗効果を発揮できるかは未知数だ。大塚家具を生かすも殺すも、家具を必要とするお客をいかに集客するかにかかっている。果たしてヤマダ電機にそれができるかである。
今思えば、経営はつくづくクリエイティブだと思う。時代の変化を読み、需要を喚起するビジネスを創造できるかだからだ。美人で秀才で凛とした大塚久美子氏には酷な言い方かもしれないが、彼女にはその能力がなかったということである。