昨年からにわかにクローズアップされている「売らない店」。最初に手掛けたのが丸井だ。D2C(ダイレクト・トゥー・コンシューマー)のテナントを誘致し、各店はショールームに徹し接客のみで対応する。来店客は商品をECで購入するが、その決済に丸井のエポスカードを使ってもらうことで、同社は手数料と購買データを得る戦略だ。
一例を挙げると、新宿マルイでは1階に「b8ta(ベータ)」をリーシングした。同店は最新家電などの体験ができる施設で、商品は売らない。来店客は展示された商品を実際に手に取って確認するだけで、購入は基本的に専用の通販サイトで行う。
丸井側は天井に取り付けたAIカメラで来店客の動向を撮影し、商品前に立った時間やスタッフが商品説明を行った回数、販売までに漕ぎ着けた割合などを記録する。こうしたデータをテナント企業にフィードバックして、マーケティングや商品開発にも生かしてもらうわけだ。丸井は百貨店から定期借家契約のSC(ショッピングセンター)に転換している。売らない店舗の導入は、従来の歩率家賃とは違った収益確保の資金石となる。
J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋東京店も昨年10月、D2C企業のショールームに特化した「明日見世」を開設した。婦人服フロアの一角に約20のブランドを展開するもので、スタッフは商品説明を行うだけで販売はしない。来店客は商品に付いたQRコードをスマートフォンで読み取り、ブランドのサイトからECで購入する。大丸側はからD2C企業から出店料を得るだけだ。将来的には松坂屋の名古屋店や大丸の梅田店などでも導入するという。
大丸松坂屋は、新興企業のD2Cブランドは資金的に脆弱で実店舗を持てないところが多く、店頭で接客など小売りのノウハウもないと見る。そこで、D2C企業に対してコストをかけず、消費者との直接の接点をもつ場を提供する。D2Cブランドは個性的で、若者が好む傾向が強い。百貨店の顧客とはリンクしないのに誘致する背景には、既存とは異なる客層へのアプローチがあり、小売業からテナントビルへの脱皮を鮮明にする。
また、接客サービス後のプロセス、販売をスムーズにデジタル化すれば、コンビニと同じく24時間顧客に対応できる。ウィズコロナであることも含め、店舗での滞留時間は制限されているわけで、それに代わる接点をいかに確保するかが小売業の新たな視点とも言える。
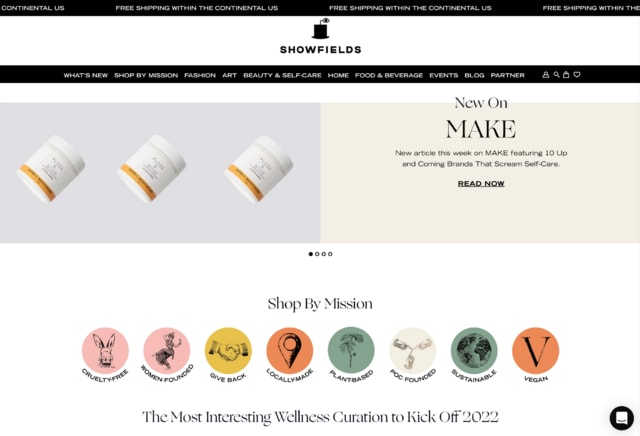
いよいよ今夏には米国発の売らない百貨店「SHOWFIELDS(ショーフィールズ)」が日本に上陸する。2017年の創業からわずか5年で、ニューヨークのノーホーなど3店舗を展開。こちらも商品を体験してもらうのみだが、本家米国ではコロナ禍もあって急成長を遂げている。日本では化粧品や衣料に限定し、20ブランドほどの出店を募集中だ。
店内にはAIカメラを設置して来店客の買い物行動や滞留時間を分析。そのデータを出店企業の商品開発などに活かしてもらうスタイルも同じだ。まずは東京都内(出店候補は銀座や表参道)に50坪〜100坪程度で出店する。日本1号店では半年程度のデモンストレーション後に、SC内や路面にニューヨークと同じ350坪程度の常設店を出店する計画という。
セレクション感度やブランドを選り抜く目
では、ショーフィールズの通販サイト(https://showfields.com)で展開されている2022年春夏のアイテムから、D2Cセレクションのポイントを探ってみたい。ファッションアイテムでまず注目なのは、「Dauntless」。ニューヨークでは動物を傷付けたり殺したりしないサスティナブルレーベルとして最も注目を集めるブランドだ。

中でも「Sam Gabardine Sand」のアウターは、肩にエポレットをつけたトレンチ風のデザインだが、素材にはフェイクシルクのギャバジンを使い、ヌードカラーの生地はインナーが透けて見えるトランスペアレント。大手アパレルには思いもつかないような企画で、価格も136ドルといたってリーズナブルだ。春風の中、摩天楼の下を闊歩するワーキングウーマンが好みそうな奇抜なテイストこそ、D2Cアパレルの真骨頂とも言える。

「Hangover Hoodies」のパーカー(64.99ドル)は、シルクスクリーンによるハンドメイドプリント。スウェット地へのカラープリントは今やインクジェットプリントが主流。だが、インクジェットではデザインしたロゴや絵柄をPCでデータ化さえすれば量産は容易なのだが、プリント可能な位置やサイズが決まってくる。
ところが、シルクスクリーンは色の分だけ版と刷りが必要になるものの、アナログ感のベタっとした印字や絵柄が打ち出せ、手作業ゆえにプリント位置やサイズを選ばない。Hangover Hoodiesのバックプリントも位置を微妙にウエスト寄りに下げている。そのため、受注生産のようで注文から納期までに2週間ほど。こうした手法も量産を避けるD2Cブランドならではと言える。


ファッショングッズでは以下の2点が目をひいた。まずニューヨークでアートアドバイザーを務める「Maria Brito」と政治的解放やジェンダーフリーを訴えるフランス系ブラジル人のデュオ「Assume Vivid Astro Focus」がコラボしたラップ(大判のショール)だ。
いろんな糸で織り込んだコットンジャカードで大胆な幾何学柄を表現。ヘムは織り糸によるカラフルなフリンジ処理だ。手の込んだ作りなので価格は高額になるが、それでもショーフィールズはアートコレクター向けに大幅に割引した(300ドル)と説明する。こうしたアイテムは作り手の活動内容やイデオロギーを打ち出す要素を持つことから、一般の流通ルートに乗る商品とはコスト感覚や売価設定も変わってくる。それもD2Cブランドだから可能なのだ。


「Lindsay Albanese」のドロップハットホルダー(55ドル)は、脱いだ帽子をバッグのストラップに留め付けるレザーアクセ。荷物が多い旅行などでハンズフリーになれる必須アイテムとも言える。ショーフィールズのサイトではベストセラーというから、アイデアグッズであることもD2Cのポイントと言えそうだ。
どのアイテムもショーフィールズが持ち前のセレクト感度とブランドを見抜く目で選り抜いている。こうした方向性を見るとD2Cブランドとは言え、何でもかんでも誘致すればいいわけではないことがわかる。
AIカメラで分析したお客の動向はあくまでマーケティングや商品開発の手段にすぎない。目的は百貨店から離れていったお客の呼び戻しや新たな客層の開拓すること。そのためには日本店でも、米国本家と同様に来店客の購買意欲をそそるセレクションが実現できるか。かつて伊勢丹が誘致したバーニーズが名ばかりでお客を呼べずに売却先が転々とした点を反面教師にし、D2Cブランド側にも商品開発力が問われるのは言うまでもない。
振り返ると筆者の記憶には、取引先のマネージャーや幹部連中が販売スタッフを叱咤・鼓舞する姿が今も残る。彼らがお題目のように発していたフレーズは、「売る気度アップ」「売ろう!売る!売れ!」「売りまくって、ケルンを積もう」等々だった。あまりに殺伐としてギスギスした現場を少し引いたところから眺めていたが、あれから数十年、彼らが存命なら「売らない店が小売りの新たな軸になりつつある」ことをどう思われるだろうか。
最近、この手の報道に触れるたびに、メディアにはかつてアパレル小売りのラインにいた方々にも取材してほしいと思う。丸井の青井浩社長やJ・フロントリテイリングの好本達也代表執行役社長が危機意識から発想を変えようというのは理解できる。だが、果たして中小のチェーン店にそれが可能なのかも考えていく必要がある。
また、ECのプラットフォーマーと同じく自らD2C企業を運営するより、テナント集めに専念した方が儲かると考えるところが出てくるだろう。百貨店やSCデベロッパーも既存業態はレッドオーシャンの中にあるから、各社が売らない店の比率を上げる戦略にシフトするのは時間の問題だ。
コラムアップの前日には、セブン&アイHDが傘下の百貨店「そごう・西武」を売却する方向で調整に入っているとのニュースが流れた。ただ、日本の百貨店で買収に応じるところはなさそうで、それだけ百貨店事業が斜陽、行き詰まりの業種だというのを物語る。売却には海外の企業やファンドが応じるかもしれないが、不成立となれば都心立地というロケーションを活かしたデベロッパー事業に転換するしかないないだろう。
となると、今度はD2C企業やテナントの取り合いになったり、D2C企業がより厳しい目で選別されていくことになる。大事なことは、売らない店やデータ分析のためのハード整備よりも、お客が「買いたくなる物」をいかに提供できるか。それにかかっているのである。
一例を挙げると、新宿マルイでは1階に「b8ta(ベータ)」をリーシングした。同店は最新家電などの体験ができる施設で、商品は売らない。来店客は展示された商品を実際に手に取って確認するだけで、購入は基本的に専用の通販サイトで行う。
丸井側は天井に取り付けたAIカメラで来店客の動向を撮影し、商品前に立った時間やスタッフが商品説明を行った回数、販売までに漕ぎ着けた割合などを記録する。こうしたデータをテナント企業にフィードバックして、マーケティングや商品開発にも生かしてもらうわけだ。丸井は百貨店から定期借家契約のSC(ショッピングセンター)に転換している。売らない店舗の導入は、従来の歩率家賃とは違った収益確保の資金石となる。
J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋東京店も昨年10月、D2C企業のショールームに特化した「明日見世」を開設した。婦人服フロアの一角に約20のブランドを展開するもので、スタッフは商品説明を行うだけで販売はしない。来店客は商品に付いたQRコードをスマートフォンで読み取り、ブランドのサイトからECで購入する。大丸側はからD2C企業から出店料を得るだけだ。将来的には松坂屋の名古屋店や大丸の梅田店などでも導入するという。
大丸松坂屋は、新興企業のD2Cブランドは資金的に脆弱で実店舗を持てないところが多く、店頭で接客など小売りのノウハウもないと見る。そこで、D2C企業に対してコストをかけず、消費者との直接の接点をもつ場を提供する。D2Cブランドは個性的で、若者が好む傾向が強い。百貨店の顧客とはリンクしないのに誘致する背景には、既存とは異なる客層へのアプローチがあり、小売業からテナントビルへの脱皮を鮮明にする。
また、接客サービス後のプロセス、販売をスムーズにデジタル化すれば、コンビニと同じく24時間顧客に対応できる。ウィズコロナであることも含め、店舗での滞留時間は制限されているわけで、それに代わる接点をいかに確保するかが小売業の新たな視点とも言える。
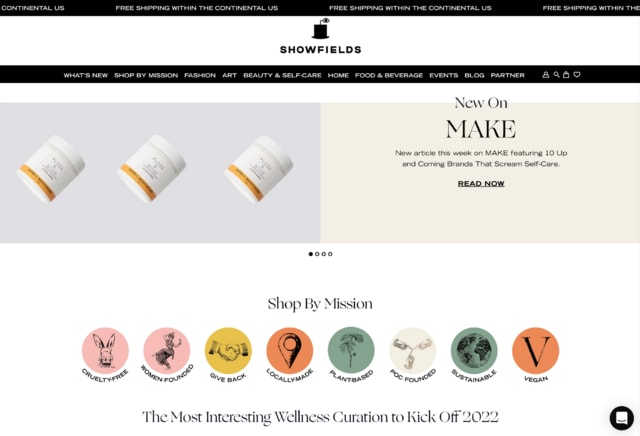
いよいよ今夏には米国発の売らない百貨店「SHOWFIELDS(ショーフィールズ)」が日本に上陸する。2017年の創業からわずか5年で、ニューヨークのノーホーなど3店舗を展開。こちらも商品を体験してもらうのみだが、本家米国ではコロナ禍もあって急成長を遂げている。日本では化粧品や衣料に限定し、20ブランドほどの出店を募集中だ。
店内にはAIカメラを設置して来店客の買い物行動や滞留時間を分析。そのデータを出店企業の商品開発などに活かしてもらうスタイルも同じだ。まずは東京都内(出店候補は銀座や表参道)に50坪〜100坪程度で出店する。日本1号店では半年程度のデモンストレーション後に、SC内や路面にニューヨークと同じ350坪程度の常設店を出店する計画という。
セレクション感度やブランドを選り抜く目
では、ショーフィールズの通販サイト(https://showfields.com)で展開されている2022年春夏のアイテムから、D2Cセレクションのポイントを探ってみたい。ファッションアイテムでまず注目なのは、「Dauntless」。ニューヨークでは動物を傷付けたり殺したりしないサスティナブルレーベルとして最も注目を集めるブランドだ。

中でも「Sam Gabardine Sand」のアウターは、肩にエポレットをつけたトレンチ風のデザインだが、素材にはフェイクシルクのギャバジンを使い、ヌードカラーの生地はインナーが透けて見えるトランスペアレント。大手アパレルには思いもつかないような企画で、価格も136ドルといたってリーズナブルだ。春風の中、摩天楼の下を闊歩するワーキングウーマンが好みそうな奇抜なテイストこそ、D2Cアパレルの真骨頂とも言える。

「Hangover Hoodies」のパーカー(64.99ドル)は、シルクスクリーンによるハンドメイドプリント。スウェット地へのカラープリントは今やインクジェットプリントが主流。だが、インクジェットではデザインしたロゴや絵柄をPCでデータ化さえすれば量産は容易なのだが、プリント可能な位置やサイズが決まってくる。
ところが、シルクスクリーンは色の分だけ版と刷りが必要になるものの、アナログ感のベタっとした印字や絵柄が打ち出せ、手作業ゆえにプリント位置やサイズを選ばない。Hangover Hoodiesのバックプリントも位置を微妙にウエスト寄りに下げている。そのため、受注生産のようで注文から納期までに2週間ほど。こうした手法も量産を避けるD2Cブランドならではと言える。


ファッショングッズでは以下の2点が目をひいた。まずニューヨークでアートアドバイザーを務める「Maria Brito」と政治的解放やジェンダーフリーを訴えるフランス系ブラジル人のデュオ「Assume Vivid Astro Focus」がコラボしたラップ(大判のショール)だ。
いろんな糸で織り込んだコットンジャカードで大胆な幾何学柄を表現。ヘムは織り糸によるカラフルなフリンジ処理だ。手の込んだ作りなので価格は高額になるが、それでもショーフィールズはアートコレクター向けに大幅に割引した(300ドル)と説明する。こうしたアイテムは作り手の活動内容やイデオロギーを打ち出す要素を持つことから、一般の流通ルートに乗る商品とはコスト感覚や売価設定も変わってくる。それもD2Cブランドだから可能なのだ。


「Lindsay Albanese」のドロップハットホルダー(55ドル)は、脱いだ帽子をバッグのストラップに留め付けるレザーアクセ。荷物が多い旅行などでハンズフリーになれる必須アイテムとも言える。ショーフィールズのサイトではベストセラーというから、アイデアグッズであることもD2Cのポイントと言えそうだ。
どのアイテムもショーフィールズが持ち前のセレクト感度とブランドを見抜く目で選り抜いている。こうした方向性を見るとD2Cブランドとは言え、何でもかんでも誘致すればいいわけではないことがわかる。
AIカメラで分析したお客の動向はあくまでマーケティングや商品開発の手段にすぎない。目的は百貨店から離れていったお客の呼び戻しや新たな客層の開拓すること。そのためには日本店でも、米国本家と同様に来店客の購買意欲をそそるセレクションが実現できるか。かつて伊勢丹が誘致したバーニーズが名ばかりでお客を呼べずに売却先が転々とした点を反面教師にし、D2Cブランド側にも商品開発力が問われるのは言うまでもない。
振り返ると筆者の記憶には、取引先のマネージャーや幹部連中が販売スタッフを叱咤・鼓舞する姿が今も残る。彼らがお題目のように発していたフレーズは、「売る気度アップ」「売ろう!売る!売れ!」「売りまくって、ケルンを積もう」等々だった。あまりに殺伐としてギスギスした現場を少し引いたところから眺めていたが、あれから数十年、彼らが存命なら「売らない店が小売りの新たな軸になりつつある」ことをどう思われるだろうか。
最近、この手の報道に触れるたびに、メディアにはかつてアパレル小売りのラインにいた方々にも取材してほしいと思う。丸井の青井浩社長やJ・フロントリテイリングの好本達也代表執行役社長が危機意識から発想を変えようというのは理解できる。だが、果たして中小のチェーン店にそれが可能なのかも考えていく必要がある。
また、ECのプラットフォーマーと同じく自らD2C企業を運営するより、テナント集めに専念した方が儲かると考えるところが出てくるだろう。百貨店やSCデベロッパーも既存業態はレッドオーシャンの中にあるから、各社が売らない店の比率を上げる戦略にシフトするのは時間の問題だ。
コラムアップの前日には、セブン&アイHDが傘下の百貨店「そごう・西武」を売却する方向で調整に入っているとのニュースが流れた。ただ、日本の百貨店で買収に応じるところはなさそうで、それだけ百貨店事業が斜陽、行き詰まりの業種だというのを物語る。売却には海外の企業やファンドが応じるかもしれないが、不成立となれば都心立地というロケーションを活かしたデベロッパー事業に転換するしかないないだろう。
となると、今度はD2C企業やテナントの取り合いになったり、D2C企業がより厳しい目で選別されていくことになる。大事なことは、売らない店やデータ分析のためのハード整備よりも、お客が「買いたくなる物」をいかに提供できるか。それにかかっているのである。















