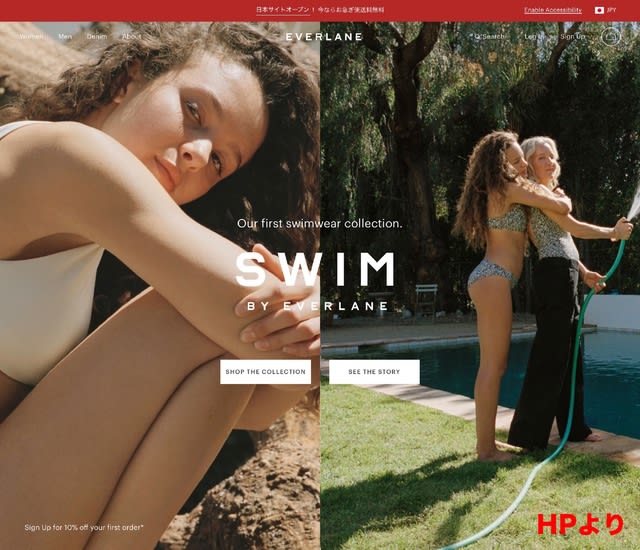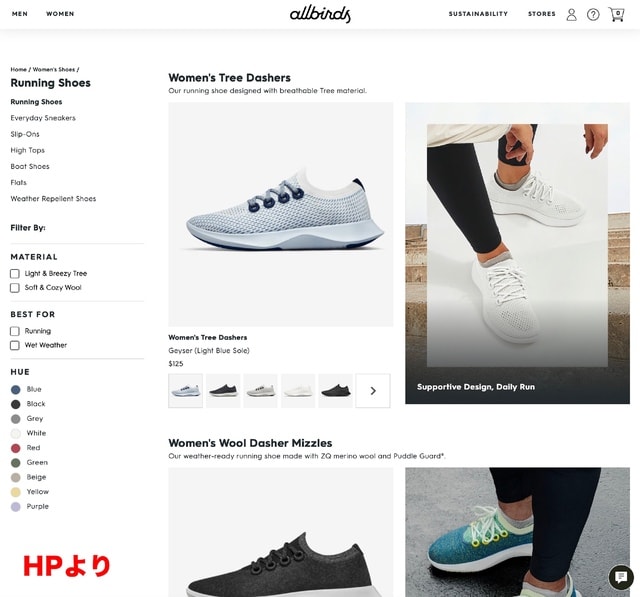福岡の中心部に事務所を構えて25年目に入った。中央区の大名界隈は様変わりする一方、ずっと同じ場所で営業を続けている店舗もある。大名1丁目と2丁目を分ける通りに立つ古いビルの1階にあった「イシイ学生服」もその一つだ。


「あった」と書いたのは、昨年夏に閉店し東区で新装オープンしたからだ。それでも、筆者が大名に来てから20年以上、この地で営業を続けていた。西区にも店舗を構えているので、2店体制は維持されたまま。少子化と言われながらも、改めて学生服需要の底堅さを感じる。同店のHPには「創業100年」とある。まさに福岡では老舗の学生服専門店。そこで、今回は学生服というアパレルとその環境について論じてみたい。
振り返ると、友人の実家も都内でイシイ学生服と同じ専門店を営んでいた。過去に何度か訪れたことがあるが、店には工場から届いたばかりの制服が学校別に仕分けされ、ハンガーラックに掛かっていたのをよく目にした。店主の親父さんが生粋の江戸っ子で根っからの商売人。学生服のことを色々と教えてくれた。
以下が今も記憶に残る親父さんの一言である。
○私立の幼稚園から養護(現:支援)学校、公立高校まで200校以上扱っているよ
○うちが販売した制服なら、見ただけでどこの学校かわかるさ
○高校は合格発表後に採寸して、1週間で縫製、仕上げを行わなければならない
○受注し製造、販売すれば終わりでなく、万が一のために備蓄もしている
○縫い子さんは専用工場に30名以上、他には20数名の外注さんを抱えている
○みんな40代以上のベテラン、仕事も早くイレギュラーサイズもこなしてくれる
ざっとこんなところだ。男子学生向けの「学ラン」はほぼ既製のものがあり、オーダーする必要はない。だが、幼稚園児の制服や女子学生のセーラー服は園や学校によってデザインが異なり、基本パターンにそってオーダーを受け付ける。しかも、上着の形、スカーフの色、ラインの数、イニシャル、ディテールなどが違うため、縫製スタッフは外注を含め学校ごとに担当を決めているとも言ってた。
また、私学ではブレザースタイルの制服が定着。そのため、人気デザインの制服には受験生が集中するから、競走倍率のアップに伴い偏差値が上がるとも。これらはすべて今から30年以上前に聞いた話だ。その親父さんも十年前に亡くなり、長男である友人が後を継いだ。
外注スタッフは80歳代だが、後任が見つからない
一昨年、その友人に会う機会があり、経営状況について聞いてみた。すると、学生服自体の市場は堅調な反面、「縫製スタッフの高齢化が懸念材料だ」とポツリ。これは学生服に限らず、国内の縫製業界全般に言えること。構造的な問題でもある。
ただ、学生服は価格競争に巻き込まれるファッション衣料とは違い、店側の言い値がほぼ定価となり、お客である学生側(代金を支払うのは親)にもすんなり受け入れられる。販売店も安売りはしないから、収益のバランスは崩れない。もちろん、格差社会の広がりで、貧困家庭では代金を一括で支払えないところもあり、分割払いなどで対処しているという。
縫製スタッフの高齢化はどうか。親父さんから話を聞いた時、スタッフの大半は40代でバリバリの現役だった。空前の好景気で、工賃にも値上げ圧力がかかりそうだが、それはなかったという。逆に親父さんは外注さんへの型紙や素資材の持ち込みから、製品の受け取り、スケジュール管理、スタッフ家族への配慮(こ姉弟は割引)まで、いろんな気遣いをしていた。

ところが、時が経ち、スタッフは高齢者が多くなり、外注さんには80代もいるとか。高い技術力と長年の経験があるので、生活のためというより認知症の防止になればとの自戒から、賃金に関係なく仕事を続けてくれるが、一人また一人とリタイアしている。並行して若手の採用や育成も行なっているが、制服のような単純作業は専門学校卒にはなかなか務まらない。これも「いつかはパリコレ」との夢を煽る教育の弊害だろうか。
だから、技術者採用の間口を洋裁に関心がある30代の主婦パートにも広げている。だが、こちらはいきなり縫製作業を頼むわけにはいかない。下働きをしてもらいながら少しずつ技術を習得させているが、好きな服が作れるわけではないため、辞めていくものも少なくないと。勤めに出た方が楽に稼げるしねとも。都内でそういう状況なのだから、地方ではなおさら大変ではないかと思う。
学校によってデザインがまちまちのセーラー服が減り、既成パターン・規格サイズのブレザースタイルが増えていることがせめてもの救いだが、セーラー服がゼロになることはない。ブレザースタイルでも注文者の体型と学校ごとのレギュレーションに則って、ジャケットの袖丈やボトムの裾などを微調整する。成長期で大きめを購入する男子生徒への対応も不可欠。それらにはお直しの技術が必要になる。
また、幼稚園児の制服はファミリー層の好みを意識してか、ギャザーやタック、パイピングなどを施したおしゃれなデザインになっており、その分仕様も複雑になるから、やはり技術力のあるスタッフでないと務まらないと。抜本的な解決策がない中で、友人はシニアの技術者には「できる範囲でいいですから、ボチボチやってください」と、発注量を減らしながらイレギュラーや備蓄分をお願いしていると、語っていた。
学生服も単納期のパターンオーダーに移行するか
今やスーツの世界では、ITを駆使したCtoM(Customer to Manufactory)による海外生産・単納期のパターンオーダースーツに移りつつある。学生服にもこのシステムが導入されれば、国外で生産され始めるのも時間の問題だろう。ところで、先日、ファッションライターの南充浩さんが、ご自身のSNSで以下のようなコメントをされていた。
「先日お会いした制服販売店は、ファッションビルに2店舗、イオンとIYに4店舗あるだけでなく、ネット通販も開始。さらに縫製工場も持っていてOEM生産もやっているという。学生服という特殊なジャンルなので大企業にはなれないとは思うが、新しい切り口にチャレンジしているので、楽しみな企業ではある」(冒頭部分は割愛し、残りは原文のまま)
実に楽観的な意見である。前出のような学生服の内部事情をまで細かく取材されているわけでもないだろうし、構造的な問題をどう解決すべきかというソリューションまで考えてあるわけではないから、無理もない。
だが、知人は別の見方をしていた。「学生服の世界は海外生産の量産服とは違い、縫製という仕事に誇りをもち、スキルと経験をもった国内在住のシニア技術者抜きには語れない。その方々からは自分が気づいていないことを数多く学べた」と語る。
また「世間では高齢者が直言すると老害だの、やがて死ぬから若者の声に耳を傾けろという書き込みを目にする。しかし、うちの仕事をしてもらっている80代のベテランスタッフの中には、月に30万円以上も稼ぐ人がいるので、こちらも税務面までサポートする。そんな人が縫った学生服は着心地がいいのか、注文者からの引き合いも多い」と、言い切った。
80代で月収30万円以上とは驚く。しかも、これは純然たる工賃だから学生服の売上げに換算すれば、相当な額になるはずだ。コロナ禍の今、感染した高齢者は死亡する傾向が強い。彼らの死は寿命でもあり、死期が近い高齢者より先が長い若者を助ける国民世論を形成すべきとの意見がある。今は有事だから、それも一理あるだろう。
しかし、平時ならどうなのだろう。稼げる高齢者と稼げない若者とは、75歳を過ぎても億の収入を得るタモリと吉本の売れない若手芸人を天秤にかけるようなもの。助けるとか、助けないとかの議論は置いといても、能力があって生産性が高く社会、経済に貢献しているのは明らかに前者。若手芸人は有能なタモリを超えてから、引退論を口にしろということだ。
そう言えば、コムデギャルソンやヨウジヤマモトといったデザイナーブランドの特殊加工を担っているのも、その多くはシニア技術者である。アパレルは多かれ少なかれ、卓越した技術と豊富な経験を持ち、銭金関係なく仕事に誇りを持つシニア層に支えられてきた。それも肝に命じておくべきではないか。学生服のことを考えて、改めてそう実感した。


「あった」と書いたのは、昨年夏に閉店し東区で新装オープンしたからだ。それでも、筆者が大名に来てから20年以上、この地で営業を続けていた。西区にも店舗を構えているので、2店体制は維持されたまま。少子化と言われながらも、改めて学生服需要の底堅さを感じる。同店のHPには「創業100年」とある。まさに福岡では老舗の学生服専門店。そこで、今回は学生服というアパレルとその環境について論じてみたい。
振り返ると、友人の実家も都内でイシイ学生服と同じ専門店を営んでいた。過去に何度か訪れたことがあるが、店には工場から届いたばかりの制服が学校別に仕分けされ、ハンガーラックに掛かっていたのをよく目にした。店主の親父さんが生粋の江戸っ子で根っからの商売人。学生服のことを色々と教えてくれた。
以下が今も記憶に残る親父さんの一言である。
○私立の幼稚園から養護(現:支援)学校、公立高校まで200校以上扱っているよ
○うちが販売した制服なら、見ただけでどこの学校かわかるさ
○高校は合格発表後に採寸して、1週間で縫製、仕上げを行わなければならない
○受注し製造、販売すれば終わりでなく、万が一のために備蓄もしている
○縫い子さんは専用工場に30名以上、他には20数名の外注さんを抱えている
○みんな40代以上のベテラン、仕事も早くイレギュラーサイズもこなしてくれる
ざっとこんなところだ。男子学生向けの「学ラン」はほぼ既製のものがあり、オーダーする必要はない。だが、幼稚園児の制服や女子学生のセーラー服は園や学校によってデザインが異なり、基本パターンにそってオーダーを受け付ける。しかも、上着の形、スカーフの色、ラインの数、イニシャル、ディテールなどが違うため、縫製スタッフは外注を含め学校ごとに担当を決めているとも言ってた。
また、私学ではブレザースタイルの制服が定着。そのため、人気デザインの制服には受験生が集中するから、競走倍率のアップに伴い偏差値が上がるとも。これらはすべて今から30年以上前に聞いた話だ。その親父さんも十年前に亡くなり、長男である友人が後を継いだ。
外注スタッフは80歳代だが、後任が見つからない
一昨年、その友人に会う機会があり、経営状況について聞いてみた。すると、学生服自体の市場は堅調な反面、「縫製スタッフの高齢化が懸念材料だ」とポツリ。これは学生服に限らず、国内の縫製業界全般に言えること。構造的な問題でもある。
ただ、学生服は価格競争に巻き込まれるファッション衣料とは違い、店側の言い値がほぼ定価となり、お客である学生側(代金を支払うのは親)にもすんなり受け入れられる。販売店も安売りはしないから、収益のバランスは崩れない。もちろん、格差社会の広がりで、貧困家庭では代金を一括で支払えないところもあり、分割払いなどで対処しているという。
縫製スタッフの高齢化はどうか。親父さんから話を聞いた時、スタッフの大半は40代でバリバリの現役だった。空前の好景気で、工賃にも値上げ圧力がかかりそうだが、それはなかったという。逆に親父さんは外注さんへの型紙や素資材の持ち込みから、製品の受け取り、スケジュール管理、スタッフ家族への配慮(こ姉弟は割引)まで、いろんな気遣いをしていた。

ところが、時が経ち、スタッフは高齢者が多くなり、外注さんには80代もいるとか。高い技術力と長年の経験があるので、生活のためというより認知症の防止になればとの自戒から、賃金に関係なく仕事を続けてくれるが、一人また一人とリタイアしている。並行して若手の採用や育成も行なっているが、制服のような単純作業は専門学校卒にはなかなか務まらない。これも「いつかはパリコレ」との夢を煽る教育の弊害だろうか。
だから、技術者採用の間口を洋裁に関心がある30代の主婦パートにも広げている。だが、こちらはいきなり縫製作業を頼むわけにはいかない。下働きをしてもらいながら少しずつ技術を習得させているが、好きな服が作れるわけではないため、辞めていくものも少なくないと。勤めに出た方が楽に稼げるしねとも。都内でそういう状況なのだから、地方ではなおさら大変ではないかと思う。
学校によってデザインがまちまちのセーラー服が減り、既成パターン・規格サイズのブレザースタイルが増えていることがせめてもの救いだが、セーラー服がゼロになることはない。ブレザースタイルでも注文者の体型と学校ごとのレギュレーションに則って、ジャケットの袖丈やボトムの裾などを微調整する。成長期で大きめを購入する男子生徒への対応も不可欠。それらにはお直しの技術が必要になる。
また、幼稚園児の制服はファミリー層の好みを意識してか、ギャザーやタック、パイピングなどを施したおしゃれなデザインになっており、その分仕様も複雑になるから、やはり技術力のあるスタッフでないと務まらないと。抜本的な解決策がない中で、友人はシニアの技術者には「できる範囲でいいですから、ボチボチやってください」と、発注量を減らしながらイレギュラーや備蓄分をお願いしていると、語っていた。
学生服も単納期のパターンオーダーに移行するか
今やスーツの世界では、ITを駆使したCtoM(Customer to Manufactory)による海外生産・単納期のパターンオーダースーツに移りつつある。学生服にもこのシステムが導入されれば、国外で生産され始めるのも時間の問題だろう。ところで、先日、ファッションライターの南充浩さんが、ご自身のSNSで以下のようなコメントをされていた。
「先日お会いした制服販売店は、ファッションビルに2店舗、イオンとIYに4店舗あるだけでなく、ネット通販も開始。さらに縫製工場も持っていてOEM生産もやっているという。学生服という特殊なジャンルなので大企業にはなれないとは思うが、新しい切り口にチャレンジしているので、楽しみな企業ではある」(冒頭部分は割愛し、残りは原文のまま)
実に楽観的な意見である。前出のような学生服の内部事情をまで細かく取材されているわけでもないだろうし、構造的な問題をどう解決すべきかというソリューションまで考えてあるわけではないから、無理もない。
だが、知人は別の見方をしていた。「学生服の世界は海外生産の量産服とは違い、縫製という仕事に誇りをもち、スキルと経験をもった国内在住のシニア技術者抜きには語れない。その方々からは自分が気づいていないことを数多く学べた」と語る。
また「世間では高齢者が直言すると老害だの、やがて死ぬから若者の声に耳を傾けろという書き込みを目にする。しかし、うちの仕事をしてもらっている80代のベテランスタッフの中には、月に30万円以上も稼ぐ人がいるので、こちらも税務面までサポートする。そんな人が縫った学生服は着心地がいいのか、注文者からの引き合いも多い」と、言い切った。
80代で月収30万円以上とは驚く。しかも、これは純然たる工賃だから学生服の売上げに換算すれば、相当な額になるはずだ。コロナ禍の今、感染した高齢者は死亡する傾向が強い。彼らの死は寿命でもあり、死期が近い高齢者より先が長い若者を助ける国民世論を形成すべきとの意見がある。今は有事だから、それも一理あるだろう。
しかし、平時ならどうなのだろう。稼げる高齢者と稼げない若者とは、75歳を過ぎても億の収入を得るタモリと吉本の売れない若手芸人を天秤にかけるようなもの。助けるとか、助けないとかの議論は置いといても、能力があって生産性が高く社会、経済に貢献しているのは明らかに前者。若手芸人は有能なタモリを超えてから、引退論を口にしろということだ。
そう言えば、コムデギャルソンやヨウジヤマモトといったデザイナーブランドの特殊加工を担っているのも、その多くはシニア技術者である。アパレルは多かれ少なかれ、卓越した技術と豊富な経験を持ち、銭金関係なく仕事に誇りを持つシニア層に支えられてきた。それも肝に命じておくべきではないか。学生服のことを考えて、改めてそう実感した。