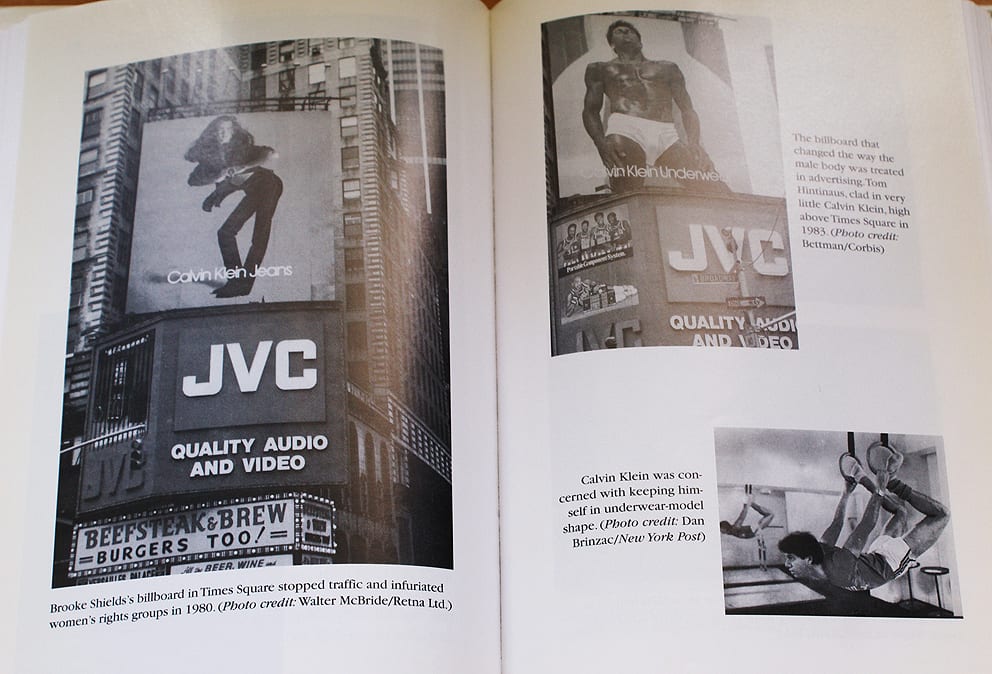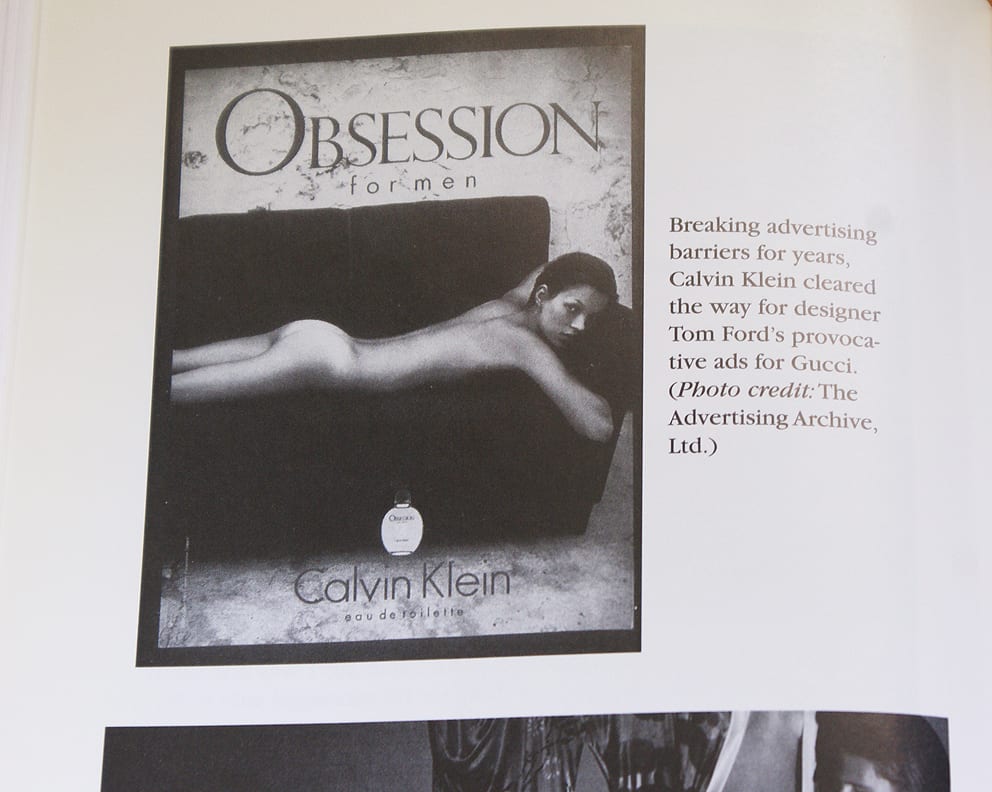昨年後半から外国人観光客によるインバウンド消費が減少している。これに支えられていた百貨店は、2016年7月の免税総売上高(協会加盟84店舗)が約146億3000万円で、前年同期比の79%まで落ち込んだ。一般物品の売上高(同)がさらに67.6%まで落ち込んでいるところをみると、外国人頼みの政策は一時しのぎに過ぎず、日本人客を蔑ろにした結果は惨憺たる有り様だ。
結局、百貨店は長年の懸案である構造改革や中長期的な戦略構築を先送りにしただけで、このツケは決して小さくないということを意味する。かといって、今の百貨店は新しいことをやるにしても手詰まり状態だし、お客に振り向いてもらうにはマーケットがあまりに成熟している。衣料品は完全にSCやネット通販に持って行かれているし、デパ地下商品だって売上げの核、収益源になる商材が次々と生まれ、ヒットする保証はない。
伊勢丹のように商品開拓に積極的なところもあるが、委託販売、消化仕入れのままで利益を確保するのは容易ではない。マスで売れる価格帯がある程度決まってきた中、自店の粗利益を確保するには原価率を圧縮せざるをえず、そうせずに十分な利益をとるには売価を上げなくてはならない。商品の質を下げれば、勝ち目はないし、価格を上げれば勝負の舞台に上がれない。
目が肥えたお客に対し、百貨店が自前で価格に見合う以上の価値=お値打ち商品を提供できることなど不可能に近いのだ。伊勢丹は全国の製造メーカーに割って入って、商品開発から手掛けていこうとのSPA脱皮への姿勢も示したが、具体的な商品づくりは見て来ない。その前提としてお客がどんな商品を欲しているのか、まだまだマーケティングの段階なのだろう。
そんな取り組みを先鋭化するわけでもないだろうが、三越伊勢丹がこのほど東京・青山に会員制サロン「サード ペイジ(3rd_PAGE)」をオープンすると発表した。百貨店のサテライト業態なんか今さら珍しくもないが、サードペイジは新規事業としてエムアイカード会員に限定という。しかも月会費として1万円が徴収されるので、上顧客を対象にする考えなのだろう。
お客は月会費を払っても観劇会招待や応分の割引が付くわけではないが、 旅や絵画、文化、伝統、ライフスタイル、食、車、スポーツなどを切り口に、会員でなければ体験できないセミナーやワークショップ、コンシェルジュサービスが提供されるという。
従来、百貨店がメーンターゲットとしてきた団塊世代〜60代はすでに定年退職、またはリタイアが近い。この層は欧米からエコノミックアニマルと揶揄されるほど、がむしゃらに働いてきた人々が大半だ。そのため、男性は時間的、経済的にゆとりを持っても、これといって「やること」を見つけるのは簡単ではない。サロンは富裕層の中でそうした層にアプローチし、新たなライフスタイルを提案する試みとみえる。
百貨店が団塊世代をターゲットに設定しても、主に狙ってきたのは女性だ。しかし、女性を対象とする商品やサービスは、ファッションからコスメや健康食品、趣味、レジャーまで有り余るくらい溢れている。平日の夕方、都市部にある百貨店のレディスフロアを見ると実に閑散としている。これは三越や伊勢丹も例外ではない。
もはやファッション衣料、特に百貨店向けのNBアパレルでは集客できなくなっているのだ。そうした状況を踏まえて、中高年の女性に新たな商品やサービスを提案するのは、至難の業と気づき始めたのではないか。
反面、これまでメーンで狙って来なかった大人の男性客。特に中高年にはアプローチする価値は十分にあるということだ。従来、商品の購入はほとんど妻任せだったが、いつ先立たれるか、三行半を突きつけられるかわからない。その時に備えて、自分でも何か前向きになれることを持っておこう。そうした啓蒙から始めようということか。
身近でできる旅行やスポーツ、美術館巡りからドライブ、そして料理や絵画、陶芸などといった趣味まで、今までは商品を提供するモノ消費だったが、それを体験型の「コト消費」に変えていく。その先に再度商品の購入があれば儲け物。上顧客を対象にした気の長いマーケティングになりそうだが、そうしたウォンツを喚起するしか、百貨店は新しい市場を掘り起こせないとの判断だと思う。
団塊世代は日本で初めてジーンズを穿き、Tシャツを着て海外旅行し、VANジャケットでクラブに通った層とも言われる。しかし、こうした最新のカルチャー、ファッショントレンドを謳歌したのは一部の人々に限られる。大半は一生懸命働いて車を買い、その先に結婚、マイホームという人生だったはずだ。だからこそ、眠っていた余暇願望に火を付け、消費へと駆り立てる。これが百貨店にとってサバイバル作戦の一つであるのも間違いない。
しかし、この世代は生きても、あと10年かそこらだ。その次はどうするのかという課題もある。次世代の50代は男性でも情報感度が高く、バブル景気と平成不況の両方を経験している。ファッションもVAN世代のような一つのトレンドで括るのは難しく、アメカジからトラッド、DCブランド、インポートまでと幅広い。車はポルシェやベンツに乗るし、国産車の良さをわかっている。趣味も音楽から釣り、トライアスロンにまで触れるなど、多種多彩のスタイル、嗜好が混在している。
リストラされた人も少なくなく、生活防衛に必死になっている。そこまで貧困ではないが、カネをかけるところとかけないところのメリハリをつける。パソコンを自由に使いこなし、ネットショッピングか実店舗での購買かどちらが得かを見極める目をもつ。妻に付き合って百貨店も一通りチェックはするが、価格と価値を比較して「この程度ならショッピングセンターでいいか」と、自分で選ぶ合理性をもつ。商品の価値を価格が高いか安いか、ブランドかノンブランドかの絶対的価値では捉えない。それだけに百貨店が攻略するには非常に難しいと思われる。
そして、40代以下の男性になると、ほとんど百貨店では買い物していないはずだ。というか、百貨店がターゲットにしてきていないのだから、どうしようもない。おそらくここから下の階層では新規でマーケットを掘り起こすのは非常に難しいと思う。20年先、百貨店は大人の男性客は完全に諦めるのか。それとも何かの企てが考えられるのか。
そのためにもマーケティングリサーチは待ったなしだ。50代以下の男性がどんな商品やサービスを求め、消費行動に出るのか。その攻略が百貨店として無理との判断なら思いきって諦め、他の業態に任せるのか。非常に難しい選択を強いられることになる。
翻って三越伊勢丹のサードペイジは、東京・青山の一等地に出店する。上顧客を対象とした会員制サロンとは言え、それなりにコストはかかると思う。ビジネスとしてペイするかどうかのシミュレーションはしていると思うが、百貨店としてサバイバルマーケティングへの投資もあるだろう。はたしてその答えが見つけられるのかどうか、注目される。
他の業態で思い出したが、渋谷パルコが閉館し、3年後に再オープンすることが決まった。こちらもいろいろと模索が続いているようで、新しい渋谷パルコは新たな東京カルチャーの発信拠点に据える一方、地方店は足下商圏の深耕に軸足を置く市場対応型のように見える。渋谷店は採算度外視で最先端の流行を発信し、ローカル店は収益を生み出せる稼ぎ手にしていく戦略なのだろう。
当然、大人の男女をターゲットにするのは地方店ということだ。7月に開業した「仙台パルコ2」は、「オトナ考えるPARCO。」との触れ込みで、店づくりからテナントリーシング、接客サービスまで大人に合わせている。パルコ=若者という偏向した概念を変えるべく、本来の幅広い客層対応の一環として、パルコとともに成長した50代をメーンターゲットに設定する。
フロア構成は1階に飲食店街に置き、牛タンやカレーの良い「匂い」で人々を集客する仕掛けだ。シャワー効果ならぬ、噴水効果とでも言うのだろうか。2〜5階にはビューティ関連を充実させ、オーガニック、漢方、アロマなどをキーワードにした商品やサービスを提供している。50代、特に大人の女性がいちばん関心があるものだ。本来なら百貨店が提供するのだが、仙台駅前にはないことからパルコがそれを担うということか。
それにしても、すでに百貨店のようにテナントを集め、委託販売、消化仕入れのビジネスでは難しいということでもある。たとえ大人狙いでもマーケットの変化を見極めながら、パルコがもつ定期借家契約によるテナント集積、お得意の編集力やイメージ戦略をシンクロしてコンセプトを際立たせることが重要なのだ。
一方でこう考えることもできる。都市部では百貨店にしても、駅ビルやSCにしても大人向けに売るモノがなくなっているのではないか。特にパルコのような業態がこだわって探し出し、売っていくようなファッションが見当たらないとも言える。だから、手っ取り早く体験やコト消費に走る傾向が強くなっているのではないか。パルコが8月26日、青山にオープンした「バイパルコ」も、若者向けとは言え、自らラボラトリーと宣言するようにモノを売ることの限界から、カルチャー発信で消費を喚起しようかと、模索しているようにも映る。
しかし、本当にそれでいいのだろうか。多く売ることばかり考えた小売り発想の終着地。売れるものを作るマーケットインの限界点。そうしたビジネスが都市部ではいい加減陳腐化してしまったのではないだろうか。ECもこれまでは「いかに売るか」で成長してきたが、ここに来て「何を売るか」を見つけられないところは、頭打ちになっている。
マスで売れる商品が出尽くしてしまったからこそ、そうした商品を捨てたところにもマーケットは出現するかもしれない。 サロンやラボラトリーとは言わず、「今のマスマーケットはつまらん」と思っているお客と共同で、積極的にもの作りを進めていく試みも、必要な気がするが。デザイナーが作ったTシャツならそれで良いのか。その辺を考え直さないと、変わらないと思う。
大人にとって自分にあったファッションとは何ぞや。それが市場で見つからないのなら、思いきって作れないか。お仕着せのオーダーメードではなく、お客自ら素材やデザインを決める服や雑貨づくり。それが体験できるような取り組みも重要だと思う。有りものでは売るものがなくなりつつあるのだから、ないモノを作ることにも目を向ける。できるできないは別にして、百貨店が都市のインフラとして前向きに取り組んでこそ、本当にレボリューションできるのではないだろうか。
結局、百貨店は長年の懸案である構造改革や中長期的な戦略構築を先送りにしただけで、このツケは決して小さくないということを意味する。かといって、今の百貨店は新しいことをやるにしても手詰まり状態だし、お客に振り向いてもらうにはマーケットがあまりに成熟している。衣料品は完全にSCやネット通販に持って行かれているし、デパ地下商品だって売上げの核、収益源になる商材が次々と生まれ、ヒットする保証はない。
伊勢丹のように商品開拓に積極的なところもあるが、委託販売、消化仕入れのままで利益を確保するのは容易ではない。マスで売れる価格帯がある程度決まってきた中、自店の粗利益を確保するには原価率を圧縮せざるをえず、そうせずに十分な利益をとるには売価を上げなくてはならない。商品の質を下げれば、勝ち目はないし、価格を上げれば勝負の舞台に上がれない。
目が肥えたお客に対し、百貨店が自前で価格に見合う以上の価値=お値打ち商品を提供できることなど不可能に近いのだ。伊勢丹は全国の製造メーカーに割って入って、商品開発から手掛けていこうとのSPA脱皮への姿勢も示したが、具体的な商品づくりは見て来ない。その前提としてお客がどんな商品を欲しているのか、まだまだマーケティングの段階なのだろう。
そんな取り組みを先鋭化するわけでもないだろうが、三越伊勢丹がこのほど東京・青山に会員制サロン「サード ペイジ(3rd_PAGE)」をオープンすると発表した。百貨店のサテライト業態なんか今さら珍しくもないが、サードペイジは新規事業としてエムアイカード会員に限定という。しかも月会費として1万円が徴収されるので、上顧客を対象にする考えなのだろう。
お客は月会費を払っても観劇会招待や応分の割引が付くわけではないが、 旅や絵画、文化、伝統、ライフスタイル、食、車、スポーツなどを切り口に、会員でなければ体験できないセミナーやワークショップ、コンシェルジュサービスが提供されるという。
従来、百貨店がメーンターゲットとしてきた団塊世代〜60代はすでに定年退職、またはリタイアが近い。この層は欧米からエコノミックアニマルと揶揄されるほど、がむしゃらに働いてきた人々が大半だ。そのため、男性は時間的、経済的にゆとりを持っても、これといって「やること」を見つけるのは簡単ではない。サロンは富裕層の中でそうした層にアプローチし、新たなライフスタイルを提案する試みとみえる。
百貨店が団塊世代をターゲットに設定しても、主に狙ってきたのは女性だ。しかし、女性を対象とする商品やサービスは、ファッションからコスメや健康食品、趣味、レジャーまで有り余るくらい溢れている。平日の夕方、都市部にある百貨店のレディスフロアを見ると実に閑散としている。これは三越や伊勢丹も例外ではない。
もはやファッション衣料、特に百貨店向けのNBアパレルでは集客できなくなっているのだ。そうした状況を踏まえて、中高年の女性に新たな商品やサービスを提案するのは、至難の業と気づき始めたのではないか。
反面、これまでメーンで狙って来なかった大人の男性客。特に中高年にはアプローチする価値は十分にあるということだ。従来、商品の購入はほとんど妻任せだったが、いつ先立たれるか、三行半を突きつけられるかわからない。その時に備えて、自分でも何か前向きになれることを持っておこう。そうした啓蒙から始めようということか。
身近でできる旅行やスポーツ、美術館巡りからドライブ、そして料理や絵画、陶芸などといった趣味まで、今までは商品を提供するモノ消費だったが、それを体験型の「コト消費」に変えていく。その先に再度商品の購入があれば儲け物。上顧客を対象にした気の長いマーケティングになりそうだが、そうしたウォンツを喚起するしか、百貨店は新しい市場を掘り起こせないとの判断だと思う。
団塊世代は日本で初めてジーンズを穿き、Tシャツを着て海外旅行し、VANジャケットでクラブに通った層とも言われる。しかし、こうした最新のカルチャー、ファッショントレンドを謳歌したのは一部の人々に限られる。大半は一生懸命働いて車を買い、その先に結婚、マイホームという人生だったはずだ。だからこそ、眠っていた余暇願望に火を付け、消費へと駆り立てる。これが百貨店にとってサバイバル作戦の一つであるのも間違いない。
しかし、この世代は生きても、あと10年かそこらだ。その次はどうするのかという課題もある。次世代の50代は男性でも情報感度が高く、バブル景気と平成不況の両方を経験している。ファッションもVAN世代のような一つのトレンドで括るのは難しく、アメカジからトラッド、DCブランド、インポートまでと幅広い。車はポルシェやベンツに乗るし、国産車の良さをわかっている。趣味も音楽から釣り、トライアスロンにまで触れるなど、多種多彩のスタイル、嗜好が混在している。
リストラされた人も少なくなく、生活防衛に必死になっている。そこまで貧困ではないが、カネをかけるところとかけないところのメリハリをつける。パソコンを自由に使いこなし、ネットショッピングか実店舗での購買かどちらが得かを見極める目をもつ。妻に付き合って百貨店も一通りチェックはするが、価格と価値を比較して「この程度ならショッピングセンターでいいか」と、自分で選ぶ合理性をもつ。商品の価値を価格が高いか安いか、ブランドかノンブランドかの絶対的価値では捉えない。それだけに百貨店が攻略するには非常に難しいと思われる。
そして、40代以下の男性になると、ほとんど百貨店では買い物していないはずだ。というか、百貨店がターゲットにしてきていないのだから、どうしようもない。おそらくここから下の階層では新規でマーケットを掘り起こすのは非常に難しいと思う。20年先、百貨店は大人の男性客は完全に諦めるのか。それとも何かの企てが考えられるのか。
そのためにもマーケティングリサーチは待ったなしだ。50代以下の男性がどんな商品やサービスを求め、消費行動に出るのか。その攻略が百貨店として無理との判断なら思いきって諦め、他の業態に任せるのか。非常に難しい選択を強いられることになる。
翻って三越伊勢丹のサードペイジは、東京・青山の一等地に出店する。上顧客を対象とした会員制サロンとは言え、それなりにコストはかかると思う。ビジネスとしてペイするかどうかのシミュレーションはしていると思うが、百貨店としてサバイバルマーケティングへの投資もあるだろう。はたしてその答えが見つけられるのかどうか、注目される。
他の業態で思い出したが、渋谷パルコが閉館し、3年後に再オープンすることが決まった。こちらもいろいろと模索が続いているようで、新しい渋谷パルコは新たな東京カルチャーの発信拠点に据える一方、地方店は足下商圏の深耕に軸足を置く市場対応型のように見える。渋谷店は採算度外視で最先端の流行を発信し、ローカル店は収益を生み出せる稼ぎ手にしていく戦略なのだろう。
当然、大人の男女をターゲットにするのは地方店ということだ。7月に開業した「仙台パルコ2」は、「オトナ考えるPARCO。」との触れ込みで、店づくりからテナントリーシング、接客サービスまで大人に合わせている。パルコ=若者という偏向した概念を変えるべく、本来の幅広い客層対応の一環として、パルコとともに成長した50代をメーンターゲットに設定する。
フロア構成は1階に飲食店街に置き、牛タンやカレーの良い「匂い」で人々を集客する仕掛けだ。シャワー効果ならぬ、噴水効果とでも言うのだろうか。2〜5階にはビューティ関連を充実させ、オーガニック、漢方、アロマなどをキーワードにした商品やサービスを提供している。50代、特に大人の女性がいちばん関心があるものだ。本来なら百貨店が提供するのだが、仙台駅前にはないことからパルコがそれを担うということか。
それにしても、すでに百貨店のようにテナントを集め、委託販売、消化仕入れのビジネスでは難しいということでもある。たとえ大人狙いでもマーケットの変化を見極めながら、パルコがもつ定期借家契約によるテナント集積、お得意の編集力やイメージ戦略をシンクロしてコンセプトを際立たせることが重要なのだ。
一方でこう考えることもできる。都市部では百貨店にしても、駅ビルやSCにしても大人向けに売るモノがなくなっているのではないか。特にパルコのような業態がこだわって探し出し、売っていくようなファッションが見当たらないとも言える。だから、手っ取り早く体験やコト消費に走る傾向が強くなっているのではないか。パルコが8月26日、青山にオープンした「バイパルコ」も、若者向けとは言え、自らラボラトリーと宣言するようにモノを売ることの限界から、カルチャー発信で消費を喚起しようかと、模索しているようにも映る。
しかし、本当にそれでいいのだろうか。多く売ることばかり考えた小売り発想の終着地。売れるものを作るマーケットインの限界点。そうしたビジネスが都市部ではいい加減陳腐化してしまったのではないだろうか。ECもこれまでは「いかに売るか」で成長してきたが、ここに来て「何を売るか」を見つけられないところは、頭打ちになっている。
マスで売れる商品が出尽くしてしまったからこそ、そうした商品を捨てたところにもマーケットは出現するかもしれない。 サロンやラボラトリーとは言わず、「今のマスマーケットはつまらん」と思っているお客と共同で、積極的にもの作りを進めていく試みも、必要な気がするが。デザイナーが作ったTシャツならそれで良いのか。その辺を考え直さないと、変わらないと思う。
大人にとって自分にあったファッションとは何ぞや。それが市場で見つからないのなら、思いきって作れないか。お仕着せのオーダーメードではなく、お客自ら素材やデザインを決める服や雑貨づくり。それが体験できるような取り組みも重要だと思う。有りものでは売るものがなくなりつつあるのだから、ないモノを作ることにも目を向ける。できるできないは別にして、百貨店が都市のインフラとして前向きに取り組んでこそ、本当にレボリューションできるのではないだろうか。