キャンディーズ「春一番」がカラオケから抹殺されていた
穂口雄右氏の行動、僕は支持します。
-----以下、記事よりの一部抜粋----
穂口氏が語る。
「『春一番』『夏が来た!』の2曲は私が作詞作曲しているため、一人の判断でファンの皆さんに安心して低価格で楽しんでいただけるよう、自己管理としました」
ところが、こうした穂口氏の対応に周囲の反応はさまざまだった。NHKはすぐに年間契約に合意したものの、ソニーグループが「春一番」の音楽配信を止めるなどの措置を講じた。
つまり、カラオケなどでキャンディーズの一部の楽曲が、歌えなくなってしまっているのだ。
だが、穂口氏が、このタイミングで音楽業界に一石を投じたのには理由があると言う。
「テレビ局が特定の曲を優先的に放送してヒット曲を作り出したり、CDに『握手券』をつけることで、作品の完成度とは無関係に売り上げを伸ばそうとする業界の体質に疑問を感じました。そうしたことが可能なのも、広告代理店系列の音楽出版社がJASRACが管理する多くの楽曲の著作権を取得しているからです。音楽著作権を1社で20万曲も集め、これを武器にアーティストや楽曲の囲い込みをやっている。こうした行為は音楽産業を衰退させるだけです」
(中略)
そして、穂口氏は著作権および著作隣接権の濫用こそが、著作権の法の精神に反していると主張するのだ。
「この条文の中でも『これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ』が重要で、著作権を盾にして国民の楽しみを奪う行為は、著作権法の立法の精神に反する行為と言っても過言ではないでしょう。著作権者や著作隣接権者は、国民が著作物を楽しむための多様な手段に対して、著作物の利用を公正に許諾し提供する義務があります。著作隣接権の既得権を過剰に行使して、文化や技術の発展を妨害する行為は慎まなければなりません。著作権は文化や技術の発展に寄与することを目的とした権利であることは間違いありません。したがって、レコード協会の行動は著作権法の立法の精神を踏みにじる暴挙と断言できます」
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数 10,500 突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼ミュージックソムリエ・ベーシック養成講座 第1期 9月29日(土)スタート!!!
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

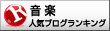 音楽 ブログランキングへ
音楽 ブログランキングへ
 マーケティング・経営 ブログランキングへ
マーケティング・経営 ブログランキングへ
穂口雄右氏の行動、僕は支持します。
-----以下、記事よりの一部抜粋----
穂口氏が語る。
「『春一番』『夏が来た!』の2曲は私が作詞作曲しているため、一人の判断でファンの皆さんに安心して低価格で楽しんでいただけるよう、自己管理としました」
ところが、こうした穂口氏の対応に周囲の反応はさまざまだった。NHKはすぐに年間契約に合意したものの、ソニーグループが「春一番」の音楽配信を止めるなどの措置を講じた。
つまり、カラオケなどでキャンディーズの一部の楽曲が、歌えなくなってしまっているのだ。
だが、穂口氏が、このタイミングで音楽業界に一石を投じたのには理由があると言う。
「テレビ局が特定の曲を優先的に放送してヒット曲を作り出したり、CDに『握手券』をつけることで、作品の完成度とは無関係に売り上げを伸ばそうとする業界の体質に疑問を感じました。そうしたことが可能なのも、広告代理店系列の音楽出版社がJASRACが管理する多くの楽曲の著作権を取得しているからです。音楽著作権を1社で20万曲も集め、これを武器にアーティストや楽曲の囲い込みをやっている。こうした行為は音楽産業を衰退させるだけです」
(中略)
そして、穂口氏は著作権および著作隣接権の濫用こそが、著作権の法の精神に反していると主張するのだ。
「この条文の中でも『これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ』が重要で、著作権を盾にして国民の楽しみを奪う行為は、著作権法の立法の精神に反する行為と言っても過言ではないでしょう。著作権者や著作隣接権者は、国民が著作物を楽しむための多様な手段に対して、著作物の利用を公正に許諾し提供する義務があります。著作隣接権の既得権を過剰に行使して、文化や技術の発展を妨害する行為は慎まなければなりません。著作権は文化や技術の発展に寄与することを目的とした権利であることは間違いありません。したがって、レコード協会の行動は著作権法の立法の精神を踏みにじる暴挙と断言できます」
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数 10,500 突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼ミュージックソムリエ・ベーシック養成講座 第1期 9月29日(土)スタート!!!
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。


























