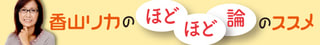【森達也 リアル共同幻想論】
◆連合赤軍がうらやましい。
中枢の意志を過剰に忖度する周辺。そして周辺の意志を過剰に忖度する中枢。互いに忖度し合いながら集団は暴走する。一人称の主語を喪うからだ。
連合赤軍やオウムだけではない。ナチスやポルポトや大日本帝国など、すべての組織共同体が引き起こす壮大な失敗の背景には、この負のメカニズムが絶対に働いている。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
「空気に支配された、組織内意思決定のジレンマ」と名づけてみたい。
このあたりが落とし所だろう。
さすが、森達也さん!
森恒夫は一度、運動から脱落した経緯もあって、自分の弱さ(それが正常だと考えるが・・・)を自分で見ない、他人から見られないために“過激化”していったことはよく知られている。
そんな森恒夫が、永田洋子から相談を受け、「処刑すべし!」と言ったら、「本当にやっちゃたよ・・・(汗)」と。
それで、後戻りのできない破滅へのスパイラルへ。
森や永田に支配され一方的に強制されたのではなく、むしろ自分たちが森や永田を相互作用的に追い込んだ要素もあるのかもしれないと語りながら、元兵士たちはつらそうだ。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
「支配され一方的に強制されたのではなく」「相互作用的に追い込んだ要素もある」が重要なポイントだ。
そして、見事に連合赤軍とオウム真理教の暴走に共通しているわけだ。
一方、オウムのほうでは、1990年、熊本地検にブチ切れた麻原が過激なことを言って、それを上祐が止めた。
それは、一対一のインフォーマルな場(お風呂のガラス越し)だったからこそ可能だったわけで、他の幹部のいるフォーマルな会議の場だったら、さすがに上祐でも言えなかった、という話は象徴的だ。
少しだけ苦笑しながらそう言ったあとに上祐は、「もしも他の幹部たちがいたら、制止はなかなかできません。より過激なことを提案するほうが修行になるかのような雰囲気がありました。麻原と(自分をも含む)側近たちとの相互作用によって、事件がエスカレートしたことは確かです」とつぶやいた。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
連合赤軍、オウム真理教という、世の中から見ればごくごく少数のカルト集団の悲劇は、戦前のわが国そのものの悲劇でもあったことを忘れてはならないだろう。
戦後、極東軍事裁判によってA級戦犯とされた日本国の指導者たちの気持ちを想像するに、「何で俺が???」だったのではないだろうか?
つまり、「責任の所在」というものが曖昧だったことである。
「俺に責任があるんだとしたら、あいつとこいつだって・・・」。
当時の軍幹部の方のインタビューを多く見聞するに、「なぜ、破滅にいたったのかわからない・・・」という答えばかりだ。
そりゃそうだろう、「犯人」とは「空気(感)」だったわけだから。。。
一方で、東南アジアはじめ海外では、敵国の捕虜や住民を自らの手で殺害した中堅幹部たちが「戦犯」として処刑され、命令を下した上級幹部達の命が助かったという、悲喜劇も少なくなかったという。
われわれは、マスコミ報道の論調を自然に自らの「思考のフレーム」としてしまうものだ。
森達也さんは、こう言う。
当時の多くのメディアは、指導者の位置にいた森恒夫と永田洋子の2人が、異常な支配欲や権勢欲、さらには嫉妬や保身や残忍な加虐趣味など個人的な欲望を燃料にしながら、他のメンバーたちの心身を支配して互いに殺し合う閉塞的な状況を作りあげたなどと解釈し、裁判も大筋としては、そうした構図に合わせるかのように進行した。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】2ページ目より)
そんなマスコミを通じて流布された「思考フレーム」を、刷り込まれるものだから、過去の失敗は「教訓」として乗り越えられないのではないだろうか?
そして、、、忘れたころに同じ失敗を繰り返す。
規模の大小を問わずに。
前回、連合赤軍とオウムに関連した記事の中で、私が主張していることだが、カルト集団の構成員は、そんな特殊な人達ではなく、ごく普通の人達なのだ。
さらにいえば、ほとんどの犯罪の加害者もそうだ (弁護してるわけではないからね)。
ところが、マスコミ論調によって形成された「思考フレーム」とは、「世間」から外れた存在を「異質な他者」として排除し、人々の“覗き趣味”に訴え興味をひくようセンセーショナルな性格を持っているのだ。
これでは、教訓の意味を活かしきれないわけで、何の問題解決にも至らない。
森さんが導かれた結論は、「すべての組織共同体が引き起こす壮大な失敗の背景」にある「負のメカニズム」。
これを私は、「空気に支配された、組織内意思決定のジレンマ」と呼ぶ。
***************************************
▼私へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数7,800突破しました!
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

◆連合赤軍がうらやましい。
中枢の意志を過剰に忖度する周辺。そして周辺の意志を過剰に忖度する中枢。互いに忖度し合いながら集団は暴走する。一人称の主語を喪うからだ。
連合赤軍やオウムだけではない。ナチスやポルポトや大日本帝国など、すべての組織共同体が引き起こす壮大な失敗の背景には、この負のメカニズムが絶対に働いている。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
「空気に支配された、組織内意思決定のジレンマ」と名づけてみたい。
このあたりが落とし所だろう。
さすが、森達也さん!
森恒夫は一度、運動から脱落した経緯もあって、自分の弱さ(それが正常だと考えるが・・・)を自分で見ない、他人から見られないために“過激化”していったことはよく知られている。
そんな森恒夫が、永田洋子から相談を受け、「処刑すべし!」と言ったら、「本当にやっちゃたよ・・・(汗)」と。
それで、後戻りのできない破滅へのスパイラルへ。
森や永田に支配され一方的に強制されたのではなく、むしろ自分たちが森や永田を相互作用的に追い込んだ要素もあるのかもしれないと語りながら、元兵士たちはつらそうだ。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
「支配され一方的に強制されたのではなく」「相互作用的に追い込んだ要素もある」が重要なポイントだ。
そして、見事に連合赤軍とオウム真理教の暴走に共通しているわけだ。
一方、オウムのほうでは、1990年、熊本地検にブチ切れた麻原が過激なことを言って、それを上祐が止めた。
それは、一対一のインフォーマルな場(お風呂のガラス越し)だったからこそ可能だったわけで、他の幹部のいるフォーマルな会議の場だったら、さすがに上祐でも言えなかった、という話は象徴的だ。
少しだけ苦笑しながらそう言ったあとに上祐は、「もしも他の幹部たちがいたら、制止はなかなかできません。より過激なことを提案するほうが修行になるかのような雰囲気がありました。麻原と(自分をも含む)側近たちとの相互作用によって、事件がエスカレートしたことは確かです」とつぶやいた。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】4ページ目より)
連合赤軍、オウム真理教という、世の中から見ればごくごく少数のカルト集団の悲劇は、戦前のわが国そのものの悲劇でもあったことを忘れてはならないだろう。
戦後、極東軍事裁判によってA級戦犯とされた日本国の指導者たちの気持ちを想像するに、「何で俺が???」だったのではないだろうか?
つまり、「責任の所在」というものが曖昧だったことである。
「俺に責任があるんだとしたら、あいつとこいつだって・・・」。
当時の軍幹部の方のインタビューを多く見聞するに、「なぜ、破滅にいたったのかわからない・・・」という答えばかりだ。
そりゃそうだろう、「犯人」とは「空気(感)」だったわけだから。。。
一方で、東南アジアはじめ海外では、敵国の捕虜や住民を自らの手で殺害した中堅幹部たちが「戦犯」として処刑され、命令を下した上級幹部達の命が助かったという、悲喜劇も少なくなかったという。
われわれは、マスコミ報道の論調を自然に自らの「思考のフレーム」としてしまうものだ。
森達也さんは、こう言う。
当時の多くのメディアは、指導者の位置にいた森恒夫と永田洋子の2人が、異常な支配欲や権勢欲、さらには嫉妬や保身や残忍な加虐趣味など個人的な欲望を燃料にしながら、他のメンバーたちの心身を支配して互いに殺し合う閉塞的な状況を作りあげたなどと解釈し、裁判も大筋としては、そうした構図に合わせるかのように進行した。
(黒字は引用部分、【森達也 リアル共同幻想論】2ページ目より)
そんなマスコミを通じて流布された「思考フレーム」を、刷り込まれるものだから、過去の失敗は「教訓」として乗り越えられないのではないだろうか?
そして、、、忘れたころに同じ失敗を繰り返す。
規模の大小を問わずに。
前回、連合赤軍とオウムに関連した記事の中で、私が主張していることだが、カルト集団の構成員は、そんな特殊な人達ではなく、ごく普通の人達なのだ。
さらにいえば、ほとんどの犯罪の加害者もそうだ (弁護してるわけではないからね)。
ところが、マスコミ論調によって形成された「思考フレーム」とは、「世間」から外れた存在を「異質な他者」として排除し、人々の“覗き趣味”に訴え興味をひくようセンセーショナルな性格を持っているのだ。
これでは、教訓の意味を活かしきれないわけで、何の問題解決にも至らない。
森さんが導かれた結論は、「すべての組織共同体が引き起こす壮大な失敗の背景」にある「負のメカニズム」。
これを私は、「空気に支配された、組織内意思決定のジレンマ」と呼ぶ。
***************************************
▼私へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数7,800突破しました!
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。