角川「短歌」8月号の座談会「流行る歌、残る歌」は、いい企画だった。
大辻隆弘、俵万智、斉藤斎藤、北山あさひの4氏に、今後残るであろう作品を10首あげてもらい、それぞれ残る理由を述べていく、というものであった。
4氏の「残る歌の条件」と、選んだ作品をごく簡単にまとめると……。
<俵万智>
残る歌の条件
・歌そのものの力で、すでに多くの読者を獲得している
・時代の刻印がある
・ツイッターで見た人がいいな思って広がっていく。今だからこその残り方
選んだ歌(10首選のなかから1首掲出)
告白は二択を迫ることじゃなく我は一択だと告げること
関根裕治
<斉藤斎藤>
・一発で耳に残る歌
・構造がしっかりしている歌
・人間の普遍的な生活様式に根ざしている歌
雨の降りはじめが木々を鳴らすのを見上げる 熱があるかもしれない
阿波野巧也
<北山あさひ>
・その人にしか詠めないものが詠まれている歌
産めば歌も変わるよと言いしひとびとをわれはゆるさず陶器のごとく
大森静佳
<大辻隆弘>
・言葉の新しさ
・生と死という人間の本質をぐっとつかんでいる歌
椅子に深く、この世に浅く腰かける 何かこぼれる感じがあって
笹川諒
座談会では、こんな感じで、各々が「残る歌の条件」と「残る歌」10首をあげて、この後、縦横に議論が展開していくのであった。
さて、この4氏のあげた「残る歌の条件」ならびに10首選(本稿では1首だけ掲出)、これを読んで、読者の皆さんはどう思われたであろうか。
筆者の意見は、こうである。
4氏のあげた「残る歌の条件」、これ、要は、4氏それぞれが考えている「いい歌」の基準なのだ。
つまり、俵万智であれば、俵が考えている「いい歌」というのは、歌そのものの力ですでに多くの読者を獲得していたり、時代の刻印があったり、ツイッターで見た人がいいなと思って広がっていったり、というのが基準となっているのだ。
斉藤斎藤なら、一発で耳に残ったり、構造がしっかりしていたり、人間の普遍的な生活様式に根ざしていたり、というのが、氏の考える「いい歌」の基準といって、差し支えないだろう。
そう考えるならば、4氏のいう「いい歌」の基準は、てんでばらばらなのがわかるだろう。
だからこそ、議論する意義があるといえるのだけれど、それはともかく、ここではっきりといえることは、短歌の世界で「いい歌」の絶対的な基準というのは存在しない、ということだ。
つまり、「時代の刻印」がある歌が「いい歌」だといえるし、「一発で耳に残る歌」が「いい歌」だともいえるし、「生と死という人間の本質をぐっとつかんでいる歌」が「いい歌」だともいえるのだ。もうね、どうにでも言えるのである。
そういうわけで、4氏の選んだ10首も、てんでばらばらということになる。
試しに、これを読んでいらっしゃる皆さんも、皆さんが考える「残る歌」10首を選んでみたらよい。これ、やってみたらすぐにわかるが、何らかの基準がないと選びようがないし、そして、そうやって選んだ「残る歌」というのは、とりもなおさず自分が思う「いい歌」とイコールになろう。そうりゃそうだ。自分が「いい歌」と思わない歌を残そうなんて思うわけがないのだから。
さて、ここまでの議論で明らかになった、短歌の世界に「いい歌」の基準は存在しない、ということ。
これ、実は、ものすごく「いい」ことだ。
なぜなら、自分で基準をつくれるということなのだから。
つまり、いい歌かそうでないかは他人が決めるものではない。自分で決めるものなのだ。それが短歌の世界なのである。
自分で作った「いい歌」の基準で他人の歌を読んで、自分で作った「いい歌」の基準で自分の歌を詠めばいい。
なんて素敵な文芸ジャンルなのだろうと、つくづく思う。
ちなみに、なぜ短歌の世界には「いい歌」の基準がないか分かるだろうか。
これは、いわゆる純粋読者がいないせいなのだ。
つまり、他者による評価軸がないせいなのだ。
これ、例えば小説世界とかテレビや映画のシナリオ世界といった、純粋読者が多数を占める文芸ジャンルだったら、「いい」作品の最大の評価基準というのは、売れるかどうか、という点になるだろう。
そうなると、作る側は、どうにかして売れる作品を作るようになる。
言い換えれば、売れるために作品を作る、ということだ。
一方、純粋読者のいない短歌の世界に住んでいる私たち歌人は、売れるために歌を詠んじゃいないだろう。だって、そもそも売れないのだから。
そりゃあ、短歌が今よりも大衆受けしてメジャーになるのは嬉しいことに違いない。けど、歌人が、歌人じゃない人にも短歌を読んでもらいたい、なんて言い出して、実際にそうした歌を詠みだすと、間違いなく大衆迎合的な創作活動に陥るから、やめた方がいいと私は思う。
短歌の世界は、純粋読者がいないから、「いい」のである。










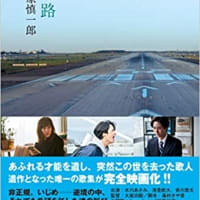
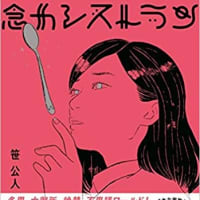
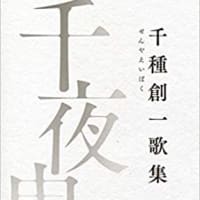
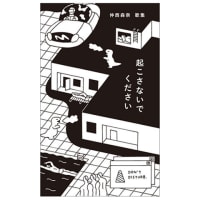
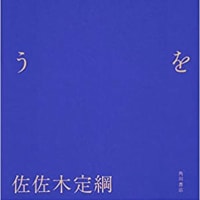
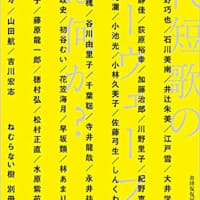

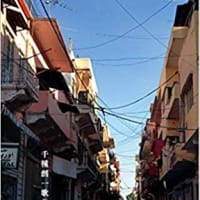

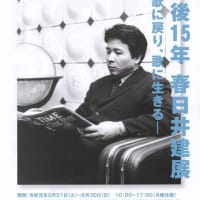
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます