或る女性歌人の方とご一緒に仕事をした時、話題が若い世代の歌人たちのことになった。将来が楽しみな才能も少なくないが、全般的に見ると、若い歌人たちの作品は「ほそい」のだと彼女は評された。ご自身も長いキャリアを持ち、大いに活躍しておられる方なので、批評眼もまた確かだと思われたが、その「ほそい」という表現が、私にとっては面白かった。
ほそいとは、丈に比べて幅が狭い、短いということだと思う。またウエストがほそいといえば痩せていることだし、ほそい声は小さく弱々しい声だ。「ほそい作品」あるいは「ふとい作品」とはどういう意味だろうか。
この詩集は何よりも、時間と記憶をめぐる「ほそい歌」であると言えるだろう。「ほそい」と言うのは、繊細な感覚でなければ捉えることのできない、瞬時に飛び去る幽かな光を追っているから。それ故に、そっと身に寄り添うひそやかさと、もの狂おしいなつかしさを伴っている。
わたしは走らない、ただ光を跳ぼうとした。非常階段の錆は展翅されたまま、
雑居ビル群の谷の虚ろでしきりとざらついて、掻き消える、・・・鎖された暗い
窓が翻りたくて、鳴く、ルウ、ルウ、と。
千駄ヶ谷、神宮前、茅屋
。いっせいに
溶けあって漂流する色彩、何いろだろうわたしの、だれかの、後ろ姿の裏側で。
反転する路地の迷彩、千駄ヶ谷、神宮前、茅屋、あれは、時間の沖。
現代詩からの引用で恐縮だが、「ほそい」と述べている書評とその作品を例にあげてみた。ここで評者は、「ほそい」とは繊細な感覚を持ち、その感覚で捉えた幽かな存在の追求をしていること、と説明しているようだ。だが、作品の稀に見る繊細さを好ましいとしながらも、ある種のもどかしさを強く感じているように思える。ほそさは、特徴の一つであって、必ずしも最上の賛辞ではないということかもしれない。
田中ましろ歌集「かたすみさがし」も、繊細な感性で編まれた一冊である。父の病と向き合った連作「告げられる冬」「抗う、そして春」の言葉は地上から屹立し、生の彼方の光に触れている。
とりどりの線でこの世とつながってしずかに隆起している身体
抗うという名の薬さらさらと流れ落ちたり父のからだに
冬の日の死に近づいた人の目にひかりを入れる医師のゆびさき
雨の予感いま信号は明滅を終えてしずかに姿勢をただす
一首目、色分けされたチューブが病人の生命を維持している。治療は苦しいだろうに、病人は静かだ。筋肉も骨もある身体の厚みが厳かでさえある。二首目は、点滴の袋に記された薬剤の名前、抗◯◯剤など。病に抗う父のための薬剤も、抗う性質を持つ。三首目では、清らかな精神が聖性をもたらす。臨終に近い病人の瞳孔をさりげなく調べ、生を確認する医師。「目にひかりを入れる」のは、実際にはペンライトで照らしたのだろうが、「冬の日」が横たわる人と医師を包み、恩寵としての光を目の中に降ろしたようにも感じられる。誠実そうな医師の「ゆびさき」にも光が宿る。四首目、心電図モニターに心拍が表示されなくなる。起伏のない直線が画面に流れるばかり。「しずかに姿勢をただす」のは、心臓の停止を告げるこの直線なのか、死者に礼をする医師たちか。歌人は窓の外に、雨の接近を察知している。深い悲しみと葛藤にありながらも、繊細な感性は微かな湿度の変化に気づいてしまう。雨と共に近づいて来るのが人生の試練であることにも気づいている。
若い書き手にとって、死は遠い。年長者の領域に生息する未知に過ぎない。人の生死を司る神は更に虚構の領域のキャラクターの一つなのだろうか。
神さまも発見されてしまったしもう絶対と呼ぶものがない
八月の蛇口すべてが空をむき神様さえも撃ちぬくように
3階の窓から空に向け飛ばす輪ゴム 神さま僕はここだよ
ビー玉をのぞけば大きくなる瞳 神様よこれが僕のいのちだ
神が虚構のものであるように、作者にとって、世界も時に虚構だ。そこでは驚くほど言葉は自由に飛翔し、鮮やかな抒情の軌跡を描き出す。
飛びはねて影を地面に置き去れば刹那ふたりになるわたしたち
ストライク投げても受け止めないくせにミットかまえて「恋」なんて言う
祈りだけ置いていきます朝の陽を浴びてしずかに開く仕組みの
壊れゆくもの美しく朝焼けにふたりひとつの窓開けはなつ
用心していても、つい感心感動させられてしまう。三首目、例えば八木重吉(1898~1927)の詩「このあかるさのなかへ/ひとつの素朴な琴をおけば/秋の美しさに耐えかねて/琴はしづかに鳴りいだすだろう」などと比較すれば、いにしえの言葉がどれほど遥かな距離を旅してここに到達したかが想像される。人の世に祈りは変わらずあっても、「しずかに開く仕組み」を内蔵した言葉はもはや素朴とは言えない。旅人は成長して、別の相貌をそなえたのだ。そして四首目の「壊れゆくもの」が何と多くを意味していることか。夜、闇、そして時間、生命・・。歌集タイトルの「かたすみ」とは謙虚な表現であって、新しい場所から新しい歌が生まれているのだ。
前述の女性歌人の方が「私にはわからない」と述べられたのが、堂園昌彦「やがて秋茄子へと到る」(港の人)であった。詩集を刊行している出版社が歌集を出したことが新鮮で、私も興味深く読んだ歌集である。(光森裕樹歌集「鈴を産むひばり」も読みたかったが・・)
秋茄子を両手に乗せて光らせてどうして死ぬんだろう僕たちは
生きるならまずは冷たい冬の陽を手のひらに乗せ手を温める
手に乗せる歌二首。前の歌は、艶やかに実って美味しげな茄子を両手に乗せ、死を想うという意表をつく組み合わせである。生の象徴である食とその対極の死。茄子の紺色の奥に漆黒の宇宙を見つけ、人の生の儚さを悟ったのかもしれない。死が艶々と手のひらで一個の実としてある光景は恐ろしくもある。歌集のタイトルがこの歌から取られたのだとすれば、やがて訪れる死を前提に生きよと私たちは何を手渡されているのだろうか。
同じ手のひらに陽を乗せると、それは身体を温め、心を支える行為になる。すなわち生きるということだ。だが、陽を手に取ることはできず、陽自体も冷たいという二重の不可能性をこの歌は突きつけてくる。現代の明るい社会の生き難さを思う。
手のひらといえば、二冊の受賞詩集が思い出される。
手のひらに西瓜の種を載せている撃たれたような君のてのひら
手のひらで冷えた卵をあっためているときふいに土けむりたつ
・・・私にとって、詠うことは自らの手を燃やすような静けさの行為である。幼い頃から、怒りや悔しさが兆すとどういうわけか心よりまずてのひらが痛んだ。てのひらにこそ、<私>が在ると信じていた。
二首はどちらも小さなものを守るように手のひらに載せている。いずれは西瓜の実になり、鳥になる生命と銃撃という対立が衝撃的である。戦火が目の前に迫る緊迫感がありながら、映像のような遠さでもある。
大森氏の文章は歌集のあとがきより。手のひらに自分自身が宿っている感覚があり、詠うことは、その手を燃やす静けさの行為だという。創造をする精神は、その創作に先立って、なんらかの傷を負っていると洞察した詩人が過去におり、また、「詩集をまとめることは私の生涯に、またひとつ傷を負うことかもしれない。(中略)この詩集という傷口をとおして深く届きたい。」(岡島弘子「つゆ玉になる前のことについて」あとがき)と書いた詩人もいた。創作とは、作者が再び傷を負うことでもある。自らの手のひらを燃やしながら静謐であること。世界の静けさそのものであること。手には自身が宿っている。燃えながら世界を掴んで差し出した時、その手はほそい、と言われるだろうか。いや、おそらくは誰からも言われまい。
ほそいとは、丈に比べて幅が狭い、短いということだと思う。またウエストがほそいといえば痩せていることだし、ほそい声は小さく弱々しい声だ。「ほそい作品」あるいは「ふとい作品」とはどういう意味だろうか。
この詩集は何よりも、時間と記憶をめぐる「ほそい歌」であると言えるだろう。「ほそい」と言うのは、繊細な感覚でなければ捉えることのできない、瞬時に飛び去る幽かな光を追っているから。それ故に、そっと身に寄り添うひそやかさと、もの狂おしいなつかしさを伴っている。
(中本道代 杉本徹詩集「ルウ、ルウ」書評 交野が原77号 2014年9月)
わたしは走らない、ただ光を跳ぼうとした。非常階段の錆は展翅されたまま、
雑居ビル群の谷の虚ろでしきりとざらついて、掻き消える、・・・鎖された暗い
窓が翻りたくて、鳴く、ルウ、ルウ、と。
千駄ヶ谷、神宮前、茅屋
。いっせいに
溶けあって漂流する色彩、何いろだろうわたしの、だれかの、後ろ姿の裏側で。
反転する路地の迷彩、千駄ヶ谷、神宮前、茅屋、あれは、時間の沖。
(杉本徹「ルウ、ルウ」冒頭)
現代詩からの引用で恐縮だが、「ほそい」と述べている書評とその作品を例にあげてみた。ここで評者は、「ほそい」とは繊細な感覚を持ち、その感覚で捉えた幽かな存在の追求をしていること、と説明しているようだ。だが、作品の稀に見る繊細さを好ましいとしながらも、ある種のもどかしさを強く感じているように思える。ほそさは、特徴の一つであって、必ずしも最上の賛辞ではないということかもしれない。
田中ましろ歌集「かたすみさがし」も、繊細な感性で編まれた一冊である。父の病と向き合った連作「告げられる冬」「抗う、そして春」の言葉は地上から屹立し、生の彼方の光に触れている。
とりどりの線でこの世とつながってしずかに隆起している身体
抗うという名の薬さらさらと流れ落ちたり父のからだに
冬の日の死に近づいた人の目にひかりを入れる医師のゆびさき
雨の予感いま信号は明滅を終えてしずかに姿勢をただす
一首目、色分けされたチューブが病人の生命を維持している。治療は苦しいだろうに、病人は静かだ。筋肉も骨もある身体の厚みが厳かでさえある。二首目は、点滴の袋に記された薬剤の名前、抗◯◯剤など。病に抗う父のための薬剤も、抗う性質を持つ。三首目では、清らかな精神が聖性をもたらす。臨終に近い病人の瞳孔をさりげなく調べ、生を確認する医師。「目にひかりを入れる」のは、実際にはペンライトで照らしたのだろうが、「冬の日」が横たわる人と医師を包み、恩寵としての光を目の中に降ろしたようにも感じられる。誠実そうな医師の「ゆびさき」にも光が宿る。四首目、心電図モニターに心拍が表示されなくなる。起伏のない直線が画面に流れるばかり。「しずかに姿勢をただす」のは、心臓の停止を告げるこの直線なのか、死者に礼をする医師たちか。歌人は窓の外に、雨の接近を察知している。深い悲しみと葛藤にありながらも、繊細な感性は微かな湿度の変化に気づいてしまう。雨と共に近づいて来るのが人生の試練であることにも気づいている。
若い書き手にとって、死は遠い。年長者の領域に生息する未知に過ぎない。人の生死を司る神は更に虚構の領域のキャラクターの一つなのだろうか。
神さまも発見されてしまったしもう絶対と呼ぶものがない
八月の蛇口すべてが空をむき神様さえも撃ちぬくように
3階の窓から空に向け飛ばす輪ゴム 神さま僕はここだよ
ビー玉をのぞけば大きくなる瞳 神様よこれが僕のいのちだ
神が虚構のものであるように、作者にとって、世界も時に虚構だ。そこでは驚くほど言葉は自由に飛翔し、鮮やかな抒情の軌跡を描き出す。
飛びはねて影を地面に置き去れば刹那ふたりになるわたしたち
ストライク投げても受け止めないくせにミットかまえて「恋」なんて言う
祈りだけ置いていきます朝の陽を浴びてしずかに開く仕組みの
壊れゆくもの美しく朝焼けにふたりひとつの窓開けはなつ
用心していても、つい感心感動させられてしまう。三首目、例えば八木重吉(1898~1927)の詩「このあかるさのなかへ/ひとつの素朴な琴をおけば/秋の美しさに耐えかねて/琴はしづかに鳴りいだすだろう」などと比較すれば、いにしえの言葉がどれほど遥かな距離を旅してここに到達したかが想像される。人の世に祈りは変わらずあっても、「しずかに開く仕組み」を内蔵した言葉はもはや素朴とは言えない。旅人は成長して、別の相貌をそなえたのだ。そして四首目の「壊れゆくもの」が何と多くを意味していることか。夜、闇、そして時間、生命・・。歌集タイトルの「かたすみ」とは謙虚な表現であって、新しい場所から新しい歌が生まれているのだ。
前述の女性歌人の方が「私にはわからない」と述べられたのが、堂園昌彦「やがて秋茄子へと到る」(港の人)であった。詩集を刊行している出版社が歌集を出したことが新鮮で、私も興味深く読んだ歌集である。(光森裕樹歌集「鈴を産むひばり」も読みたかったが・・)
秋茄子を両手に乗せて光らせてどうして死ぬんだろう僕たちは
生きるならまずは冷たい冬の陽を手のひらに乗せ手を温める
手に乗せる歌二首。前の歌は、艶やかに実って美味しげな茄子を両手に乗せ、死を想うという意表をつく組み合わせである。生の象徴である食とその対極の死。茄子の紺色の奥に漆黒の宇宙を見つけ、人の生の儚さを悟ったのかもしれない。死が艶々と手のひらで一個の実としてある光景は恐ろしくもある。歌集のタイトルがこの歌から取られたのだとすれば、やがて訪れる死を前提に生きよと私たちは何を手渡されているのだろうか。
同じ手のひらに陽を乗せると、それは身体を温め、心を支える行為になる。すなわち生きるということだ。だが、陽を手に取ることはできず、陽自体も冷たいという二重の不可能性をこの歌は突きつけてくる。現代の明るい社会の生き難さを思う。
手のひらといえば、二冊の受賞詩集が思い出される。
手のひらに西瓜の種を載せている撃たれたような君のてのひら
手のひらで冷えた卵をあっためているときふいに土けむりたつ
(山崎聡子「手のひらの花火」)
・・・私にとって、詠うことは自らの手を燃やすような静けさの行為である。幼い頃から、怒りや悔しさが兆すとどういうわけか心よりまずてのひらが痛んだ。てのひらにこそ、<私>が在ると信じていた。
(大森静佳「てのひらを燃やす」)
二首はどちらも小さなものを守るように手のひらに載せている。いずれは西瓜の実になり、鳥になる生命と銃撃という対立が衝撃的である。戦火が目の前に迫る緊迫感がありながら、映像のような遠さでもある。
大森氏の文章は歌集のあとがきより。手のひらに自分自身が宿っている感覚があり、詠うことは、その手を燃やす静けさの行為だという。創造をする精神は、その創作に先立って、なんらかの傷を負っていると洞察した詩人が過去におり、また、「詩集をまとめることは私の生涯に、またひとつ傷を負うことかもしれない。(中略)この詩集という傷口をとおして深く届きたい。」(岡島弘子「つゆ玉になる前のことについて」あとがき)と書いた詩人もいた。創作とは、作者が再び傷を負うことでもある。自らの手のひらを燃やしながら静謐であること。世界の静けさそのものであること。手には自身が宿っている。燃えながら世界を掴んで差し出した時、その手はほそい、と言われるだろうか。いや、おそらくは誰からも言われまい。










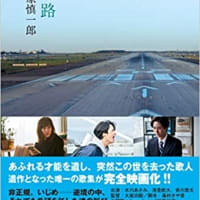
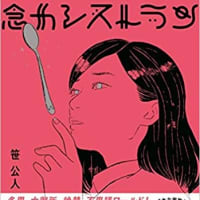
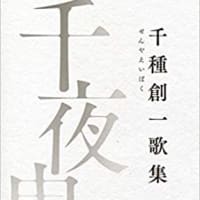
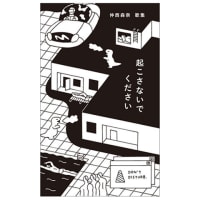
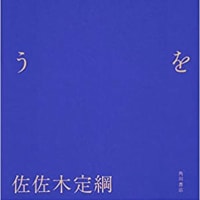
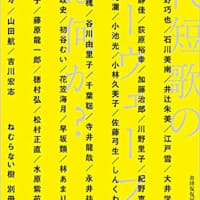

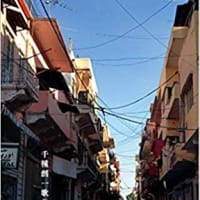

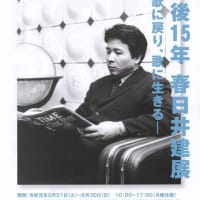
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます