◎ポスターも作成
“天高く馬肥ゆる秋”と言いますが、第7回の「『資本論』を読む会」の開催日も、天高く秋晴れの好天日でした。
ところが“紅一点”のクミさんは季節外れのインフルエンザに罹ったとかでお休み。寂しい開催となりました。
おまけに、われわれ以外には、会場を使う人も少ないのか、全体にガランとして侘しさがつのります。
今回、我が「『資本論』を読む会」はポスターを作成しました(写真参照)。というのはどうやら図書館の掲示板にポスターを貼り出してもらえそうだとピースさんが提案したからです。さっそく、埼玉の「所沢・『資本論』を読む会」のポスターが迫力があるので利用させてもらうことにし、連絡して送ってもらい、それを加工してつくりました。なかなかよいポスターが出来たと思ったのですが、残念ながら、図書館の掲示板には掲載できないとのことでした。掲載するのは、図書館が後援したり、支援する団体に限っているのだそうです。しかしわれわれの案内ビラを入れる箱を作ってくれるなど協力的なので、作ったポスター(A4)もそこに入れていたところ、さっそく無くなっていたので、持ち帰る人があったのだと思います。
今後も案内ビラとポスターを裏表に印刷して、ボックスに入れておくことにしました。
◎金やダイヤモンドは価値どおりに支払われていない?
今回は第16パラグラフから第1節の終わりまで進みました。テキストに入る前に、前回の「報告」に関連して、「抽象的人間労働」の概念について、それは歴史的なものなのか、それとも歴史貫通的なものなのか、という議論が行われたのですが、これは次の第2節でも必ずと言ってよいほど議論になる問題なので、ここではその報告は割愛します。
今回はテキストは比較的進捗したのですが、それはあまりゴチャゴチャした議論が無かったからでもあります。しかしそのなかでも議論になったのは17パラグラフでした。
ここではマルクスは《ある一つの商品の生産に必要とされる労働時間が不変であれば、その商品の価値の大きさは不変のままであろう。しかし、その労働時間は、労働の生産力が変動するたびに、それにつれて変動する》と述べて、《労働の生産力》を規定する諸事情については色々とあるとしながら、とりわけ、(1)《労働者の熟練の平均度》(2)《科学とその工学的応用可能性との発展段階》(3)《生産過程の社会的結合》(4)《生産手段の規模とその作用能力》(5)《自然諸関係によって、規定される》としています。
まずここで、上げられている生産力を規定する五つの事情について、それぞれ具体的にはどういうものが考えられるかについて議論になりました。例えば、「協業」や「分業」などによる生産力のアップはどれに入るのか、という問題がピースさんから出され、それはやはり(3)に入るのではないかということになりました。しかし、それに対しては亀仙人から、コンビナートなどのようなさまざまな産業分野が有機的に結合されるような場合はどうか、という質問も出されました。後者も(2)や(4)の要素もあるように思うが、どちらかというと(3)に入る感じがするが、しかしそうなると両者はかなり内容的に違う感じもするわけで、果たしてどう考えたらよいのかという疑問だったと思います。これは未解決です。
次にマルクスは価値の大きさを規定する労働時間は生産力によって規定されるとし、その生産力を規定する事情はさまざまあるとしながら、そのあとにそのことの例として書いていること--《たとえば、同じ量の労働でも、豊作の時には八ブッシェルの小麦に表され、凶作の時にはただ四ブッシェルの小麦に表されるにすぎない。同じ量の労働でも、豊かな鉱山では貧しい鉱山でよりも多くの金属を供給する、等々》--は、すべて(5)の《自然諸関係》に関連するものばかりではないか、その点、展開としては疑問がある、との指摘がありました(ただこれについては、そのあとの議論のなかでマルクスが《もしもほんのわずかの労働で石炭をダイヤモンドに変えることに成功すれば、ダイヤモンドの価値はレンガの価値以下になりうる》と述べている例は(2)の《科学とその工学的応用可能性との発展段階》に該当するだろうとの指摘はありました)。
さらに問題になったのは、そのあとでマルクスが金とダイヤモンドの例を上げて述べていることです。まず引用しておきましょう。
《ダイヤモンドは地表にはめったにみられないので、その発見には平均的に多くの労働時間が費やされる。そのため、ダイヤモンドはわずかな体積で多くの労働を表すことになる。ジェイコブは、金がかつてその全価値を支払われたことがあるかどうかを、疑っている。このことは、ダイヤモンドにはいっそうよくあてはまる。エッシュヴェーゲによれば、一八二三年の時点で、ブラジルのダイヤモンド鉱山の過去八〇年間の総産出高は、ブラジルの砂糖農園またはコーヒー農園の一年半分の平均生産物の価格にも達していなかった。ダイヤモンドの総産出高がはるかにより多くの労働を、したがって、より多くの価値を表していたにもかかわらず、そうだったのである。》(全集版s.54-55)
つまりダイヤモンドは小さな体積で多くの労働を表し、だから小さなダイヤでも恐ろしく高いものだが、しかしマルクスがここで述べていることは、そういうことだけではなく、だから実際には、ダイヤモンドはその価値どおりには支払われたためしはない、ということのようである。つまりダイヤモンドは実際に売買されているよりももっと高価なものなのだ、とでも言いたいかである。
しかしこれは果たして事実なのかどうかがまず疑問として出されました。そして、もしそれが事実なら、それは生産力が商品の価値を規定する例としては、むしろダイヤモンドは例外だということではないのか、それともここでマルクスが言いたいのは、ダイヤモンドの価格はその価値から乖離して売買されているということであろうか、もしそうならそれはどんな理由によるのか、ただ価値があまりにも膨大すぎるからなのか、そもそもそんなことをここで論じる意義が果たしてあるのか、という疑問が出されました。この疑問も解決されていません。
◎価値であることなしに、使用価値である、商品であることになしに、有用である
次は最後の第18パラグラフが問題になりました。まず引用しておきましょう。
《ある物は、価値であることなしに、使用価値でありえる。人間にとってのその物の効用が労働によって媒介されていない場合がそれである。たとえば、空気、処女地、自然の草原、原生林などがそうである。ある物は、商品であることなしに、有用であり、人間労働の生産物でありえる。自分の生産物によって自分自身の欲求を満たす人は、たしかに使用価値を作りだすが、商品を作りだしはしない。商品を生産するためには、彼は、使用価値を生産するだけでなく、他人のための使用価値を、社会的使用価値を、生産しなければならない。》(s.55)
ここでまず最初に《ある物は、価値であることなしに、使用価値でありえる》例として、マルクスは《人間にとってのその物の効用が労働によって媒介されていない場合がそれであり。たとえば、空気、処女地、自然の草原、原生林などがそうである》と説明しているが、しかしその説明だとむしろ〈ある物は、労働生産物であることになしに、使用価値でありえる〉とすべきではないのか、という意見が出されました。
というのは、その次にマルクスは《ある物は、商品であることなしに、有用であり、人間労働の生産物でありえる》と述べているからです。つまり今度は労働生産物であり、有用なものだが、商品ではない、すなわち価値ではないものを例として上げています。だから順序としては、まず最初に使用価値はあるが、労働生産物ではないもの、そしてその次は労働生産物であり、使用価値ではあるが、価値でないものを上げるというのが順序としてはよい様に思うというのです。
しかしこれに対しては、マルクスはここでは《ある物が、価値である》とは、そもそもどういう場合かを論じるために書いているのであって、だから最初から《ある物が、価値であることなしに、……》と書きはじめているのは、これでよいのだ、という意見もでました。
またエンゲルスが先に引用した文章に続けて、次の様な注を挿入していることについても少し意見がでました。
《(しかも、ただ単に他人のためというだけではない。中世の農民は、封建領主のために年貢の穀物を生産し、僧侶のために十分の一税の穀物を生産した。しかし、年貢穀物も十分の一税穀物も、それらが他人のために生産されたということによっては、商品にはならなかった。商品になるためには、生産物は、それが使用価値として役立つ他人の手に、交換を通して移譲されなければならない)》(同)
ここでマルクスは《商品を生産するためには、彼は、使用価値を生産するだけでなく、他人のための使用価値を、社会的使用価値を、生産しなければならない》と述べているだけであって、《他人のための使用価値を、社会的使用価値を、生産》したもの、その生産物はすべて商品になるとは言っていないのだから、エンゲルスの注は不要である、との意見がでました。しかし他方で、まあエンゲルスが注で書いているように、「誤解」を取り除くためなのだから、別に良いのではないかという意見もでました。
全体に議論としては淡白でしたが、これは天気が良すぎたからか、まあ、こんな学習会もあるということです。











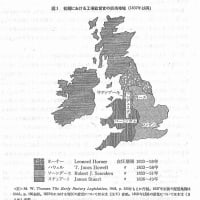
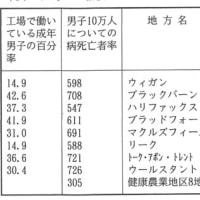
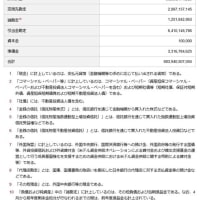

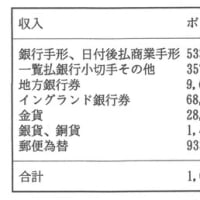
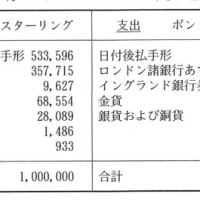
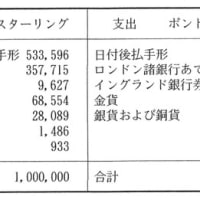
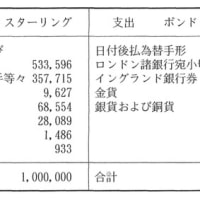
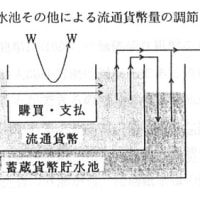







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます