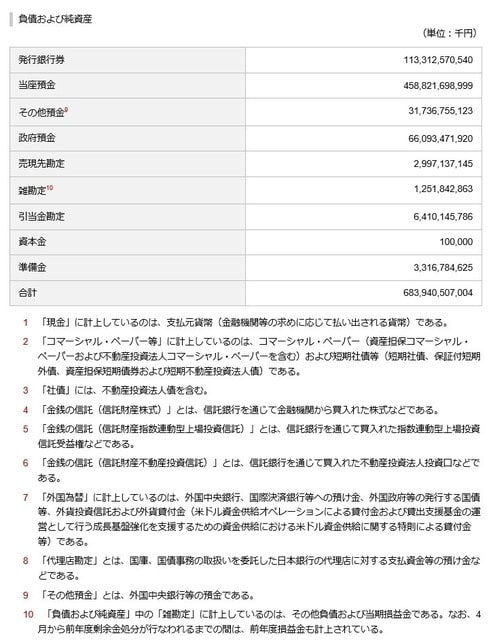『資本論』学習資料No.23(通算第73回)(2)
◎第10パラグラフ(商品生産が発展すれば、支払手段としての貨幣の機能は商品流通の部面を超える)
【10】〈(イ)商品生産が或る程度の高さと広さとに達すれば、支払手段としての貨幣の機能は商品流通の部面を越える。(ロ)貨幣は契約の一般的商品となる(104)。(ハ)地代や租税などは現物納付から貨幣支払に変わる。(ニ)この変化がどんなに生産過程の総姿態によって制約されているかを示すものは、たとえば、すべての貢租を貨幣でり立てようとするローマ帝国の試みが二度も失敗したことである。(ホ)ボアギユベールやヴォバン将軍たちがあのように雄弁に非難しているルイ14世治下のフランス農村住民のひどい窮乏は、ただ租税の高さのせいだっただけではなく、現物租税から貨幣租税への転化のせいでもあった(105)。(ヘ)他方、アジアでは同時に国家租税の重要な要素でもある地代の現物形態が、自然関係と同じ不変性をもって再生産される生産関係にもとづいているのであるが、この支払形態はまた反作用的に古い生産関係を維持するのである。(ト)それは、トルコ帝国の自己保存の秘密の一つをなしている。(チ)ヨーロッパによって強制された外国貿易が日本で現物地代から貨幣地代(*)への転化を伴うならば、日本の模範的な農業もそれでおしまいである。(リ)この農業の窮屈な経済的存立条件は解消するであろう。
(*) 第三版および第四版では、金納地代〔Goldrente〕となっている。〉
(イ) 商品生産がある程度の高さと広さとに達すると、支払手段としての貨幣の機能は、商品流通の部面をのり越えてひろがっていきます。
支配手段は単純な商品流通のなかから自然発生的に生まれてくる、流通手段とは違った別の形態規定性を帯びた(よって違った機能を果たす)貨幣でした。しかしそれが商品生産がある程度の高さと広さになると、商品流通の部面を乗り越えて広がって行くというのです。つまり商品流通とは直接関係がない場合の「支払い」に貨幣が使われるということです。例えば「税金を支払う」というようなケースです。税金そのものは商品流通とは直接には関係のない事柄ですが、そうした場合にも支払手段の貨幣の機能が拡張してくるということです。
(ロ) 貨幣は契約のさいに一般的に用いられる商品となるのです。
〈一般的商品〉というのは、貨幣も商品であり、他の諸商品が特殊的商品であるのに対応して、貨幣は一般的商品だという意味で使われます。『経済学批判』には〈金と銀は貨幣としては、その概念上一般的商品である〉(全集第13巻135頁)という一文が見られます。しかしでは〈貨幣は契約の一般的商品となる〉とはどういうことでしょうか。実はこの言葉そのものはベーリの言葉をそのままマルクスが使っているのです。『批判』の関連する部分を抜粋してみましょう。そこでは注のなかでベーリの一文が紹介されています。
〈一般的支払手段としては、貨幣は契約の一般的商品となる。--はじめはただ商品流通の領域の内部でだけだが*。けれども貨幣のこの機能の発展につれて、他のすべての支払の形態はしだいに貨幣支払に解消していく。貨幣が排他的支払手段として発達している程度は、交換価値が生産をどれだけ深くまた広くとらえているかという程度を示している。
* ベーリ、前掲書、3ページ。「貨幣は契約の一般的商品である。すなわち、将来履行されるべき大多数の財産契約を結ぶのに用いられるものである。」〉 (全集第13巻122頁)
これを見ますと、『批判』では『資本論』とは異なり、〈一般的支払手段としては、貨幣は契約の一般的商品となる〉と述べたあと、〈はじめはただ商品流通の領域の内部でだけだが。けれども貨幣のこの機能の発展につれて、他のすべての支払の形態はしだいに貨幣支払に解消していく〉と述べています。つまりそれまでの現物での支払に代わって貨幣での支払になっていくことについて述べています。そしてベーリは〈すなわち、将来履行されるべき大多数の財産契約を結ぶのに用いられるものである〉と述べています。だからここで〈一般的商品〉というのは、諸契約において、将来の契約の履行に際して払われるべき貨幣だという意味ではないでしょうか。
またここには原注(104)がついていますが、それを見るとD・デフォーの『公信用に関する一論』からの引用がありますが、そこには〈取引の過程は、……販売と支払に変わって、すべての売買契約が……いまでは貨幣での価格にもとづいて定められる〉とあります。つまり売買契約が貨幣価格にもとづいて定められるという意味が貨幣が一般的商品になるという意味だとも分かります。
(ハ) 地代や租税などは現物納付から貨幣支払に変わります。
だから地代や租税もそれまでの現物による納付から貨幣による納付に変わっていくということです。
日本の場合、江戸時代には幕藩体制のもと年貢という形で米による物納が決められていました(ただし一部は畑作などの場合は金・銀による納付もあったようです)、それが明治維新の地租改正によって年貢は地租に改正され、貨幣形態による納入が義務づけられたのです(地租は土地収益から算定された地価の100分の3とされた)。この地租改正によって、農民の負担が強化され、地主や農民の激しい反対を招いたと言われています(地租改正反対一揆)。そして地租の重圧から自作農民の急速な没落を招き、地租軽減は自由民権運動における中心的な要求になったと言われています。戦後の1947年に地租法は廃止され、代わって固定資産税に変わりました。(『世界大百科事典』)。
(ニ) こうした変化が生産過程の総姿態によって制約されていることを示すのは、たとえば、すべての貢租を貨幣でり立てようとするローマ帝国の試みが二度も失敗したことです。
物納を金納に変えるためには、農民など生産者は少なくとも生産物を商品として販売し、貨幣を入手する必要があります。つまりそれだけ商品経済が発展していることが前提されるのです。だからそれは「生産の一般的状態」(フランス語版)に依存しているのです。
『資本論』第3巻の第47章「資本主義的地代の生成」には、次のような一文があります。
〈本来の現物経済では、たとえば古代ローマの多くの大所有地でもカール大帝の荘園でもそうだったように、また(ヴァンサール『労働の歴史』を見よ)全中世をつうじて多少ともそうだったように、農業生産物は全然流通過程にはいらないか、またはその非常にわずかな部分がはいるだけであり、また、生産物中の土地所有者の収入を表わしている部分でさえも相対的にごくわずかな部分が流通過程にはいるだけであるが、このような現物経済が行なわれているところでは、大所有地の生産物も剰余生産物もけっしてただ農業労働の生産物だけから成っているのではない。それには同様に工業労働の生産物も含まれている。家内手工業労働や製造労働は、その基礎をなしている農業の副業として、この現物経済の基礎である生産様式の条件なのであって、ヨーロッパの古代や中世でもそうだったし、また今日でもその伝統的な組織がまだ破壊されていないインドの共同体ではそうである。〉 (全集第25巻b1008-1009頁)
つまりローマ帝国の時代にはもちろん、中世になっても農業生産物は全然流通過程には入らないか、わずかな部分がはいるだけだったというわけですから、そのような状態で、貢租を貨幣でり立てようとしても失敗するのは当然だったといえるわけです。
なおこの部分はむかし大阪市内でやっていた『資本論』を学ぶ会でも議論したことがありましたので、その「学ぶ会ニュース」№47(2000.11.1)から紹介しておきましょう。
【まず、最初のところ(第10パラグラフ)では、支払手段としての貨幣の機能が、商品流通の部面以外にも及ぶことが指摘され、地代や租税などが現物納付から貨幣支払いに転化することが述べられています。そこでまず問題になったのが〈この転化が生産過程の総姿態によってどんなに強く制約されるかは、たとえば、あらゆる公課を貨幣で取りたてようとしたローマ帝国のこころみが二度にわたって失敗したことで証明されている〉という部分の〈ローマ帝国のこころみ〉とはどのようなものだったのかということです。これも実際には古代ローマの経済を研究しなければ分かりませんが、例によってマルクス自身が他のところで同じ問題を論じていないか調べてみました。しかし残念ながら、それを直接具体的に論じているところは見つけることは出来ませんでした。ただ第3巻の第47章「資本制的地代の発生史」の「第4節 貨幣地代」を見ると、現物納付が貨幣支払いに転化するためには〈生産過程の総姿態〉に〈強く制約される〉理由らしきものが分かるのではないかと思います。
〈直接生産者は、このばあいには(貨幣地代の場合には--引用者)、自分の土地所有者(これが国家であれ私人であれ)にたいし、生産物でなく生産物の価格を支払わねばならない。だから、現物形態での生産物の超過分では、もはや間に合わない。それは、この現物形態から貨幣形態に転形されなければならぬ。直接的生産者は従来通り自分の生活維持手段の少なくとも最大部分をみずから生産し続けるとはいえ、彼の生産物の一部分はいまや商品に転形--商品として生産--されねばならなぬ。だから、全生産様式の性格が多かれ少なかれ変化される。全生産様式が、社会的関連からの独立性・離脱性を失う。生産費--これには今や多かれ少なかれ貨幣支出が入り込む--の関係が決定的となる〉 (青木版1122~3頁)
つまり地代や租税を貨幣形態で支払うためには現物を一旦商品として販売しなければなりませんが、そのためにはそれだけの商品経済そのものの発展が--そしてそれだけの生産力の発展が--前提されるということです。同じ所でマルクスは次のようにも述べています。
〈労働の社会的生産力の一定の発展なしにはこうした転形がいかに完遂されがたいかは、ローマ帝国のもとで失敗したこうした転形の種々なる試みにより、この地代のうち少なくとも国税として実存する部分を一般的に貨幣地代に転形させようとしたが現物地代に逆戻りしたことによって、証明される。こうした移行困難は、例えば、革命前にフランスでは貨幣地代が従来の諸形態の残滓によって混和、混合されていたことを見ればわかる〉 (同1123~4頁)。
以前にも紹介したことがありますが、マルクスは古代ローマの経済に関しては、デュロ・ド・ラ・マルの『ローマ人の経済学』から抜粋ノートを作っています。それは『マルクス資本論草稿集』第2巻の「雑」の中に見ることができますが、そのマルの著書から上記の問題に関連するように思える部分をついでに重引しておきましょう。
〈「国家の収入は、国有地からのもの、現物での貢納、賦役、また商品の輸出入に際して支払われる、あるいはある主の食料品の販売に関して徴収される、金納の税などからなっていた。そうしたやり方は、オスマン帝国においてもなお、ほとんど変化なしに存在していた。独裁官スラの時代には、また7世紀の終わりでさえも、ローマ共和国は、年々4000万フランしか徴収していなかったのであって、西暦697年……。1780年にトルコのサルタンの収入は、ピアストル銀貨による貨幣納では、たった3500ピアストル、すなわち7000万フランであった。……ローマ人とトルコ人は、その収入の最大の部分を現物で徴収していた。ローマ人の場合には、穀物の10分の1、果物の5分の1、トルコ人の場合には、生産物の2分の1から10分の1までさまざまであった」〉 (同草稿集2巻716頁)
このようにローマ帝国では金納されたのは、商品の輸出入やある種の食料品の販売に関して徴収される税に限られ、それ以外のものはほとんど物納であったことが分かります。】
(ホ) ボアギユベールやヴォバン将軍たちがあのように雄弁に非難しているルイ14世治下のフランス農村住民のひどい窮乏は、租税が高かったせいだけではなく、現物租税から貨幣租税に変えられたせいでもありました。
ボアギュベール(1646-1714)は『資本論辞典』によればフランスの経済学者で『富、貨幣、租税の本質に関する論究』などの著作で〈ブルボン絶対王政治下における重商主義および高利資本に寄生された半封建的租税制度によって窮乏してゆくフランス農村社会をえがき,絶望的なかたちで分解されつつあった小農民(分益農)の立場から‘ルイ14世の官廷や彼の徴税務負人や彼の貴族などの盲目的破壊的な黄金欲'を攻撃し,財政・租税制度の改革を主張した〉(550頁)ということです。ヴォパン将軍(1633-1704)については詳し説明は見いだせませんでしたが、フランスの軍事技術者で、『国王十分一税の構想』などでコルベール重商主義に反対したという説明があります。
『要綱』には次のようなマルクスの抜粋ノートがあります。MEGAの注解とともに紹介しましょう。
〈ルイ14世、15世、16世治下のフランスでは、農村の住民にはまだ、政府に納めるべき現物税があった。(オジエ。)
(1) 〔注解〕マリ・オジエ『公信用ならびに古代より現代にいたるその歴史について』、パリ、1842年、128、129ページ。オジエの原文では、次のようになっている。--「ルイ14世、ルイ15世、さらにルイ16世の時代になってさえもなお、現物税が……まだ存在していた。……93年以前には、……政府にたいして現物税を納めていた農村の住民がいたのである……。」--マルクスはこの箇所を、彼の抜粋ノート「完成された貨幣制度」の15ページによって引用している。〉 (草稿集②789頁)
つまりオジエによればルイ14世(在位1643-1715)、15世(同1715-1774)、さらに16世(同1774-1792)の時代になっも、現物税が存在していたということですから、それだけ商品経済が十分には発達していなかったということでしょう。だからもっとも商品経済の発展が遅れていたであろうルイ14世の時代に、現物租税を強制的に貨幣租税に変えたということはそれだけ農民には過酷な負担を強いることになったということではないでしょうか。
この部分も先の学ぶ会ニュースで取り上げていますので、紹介しておきます。
【つぎに問題となったのは、ルイ14世治下の租税の過酷さを告発した人物としてマルクスが上げているボワギュベールとヴォバン将軍についてです。前者については『資本論辞典』にも出てきますが、後者はどういう人物なのかさっぱり分からなかったのです。だからそれを調べてみました。まずボワギュベールについて『辞典』を持参していない人のために少し紹介しておきましょう。
〈ボアギュベール(1646-1714)、フランスの経済学者。1678年にルゥアンの裁判官職につき、コルベールの重商主義を攻撃した主著が筆禍をひきおこしてオーヴェルニュに追放された等のほか、経歴はあまりあきらかでない。……ブルボン絶対王政治下における重商主義および高利資本に寄生された半封建的租税制度によって窮乏していくフラン農村社会をえがき、絶望的なかたちで分解されつつあった小農民(分益農)の立場から“ルイ14世の官廷や彼の徴税請負人や彼の貴族などの盲目的破壊的な黄金欲”を攻撃し、財政・租税制度の改革を主張した。……マルクスは、イギリスにおけるペティとともに、フランスにおける古典派経済学のはじまりとして高く評価している。……(以下、略)〉
つぎはヴォバン将軍ですが、これはなかなか見つけることが出来ませんでした。青木版『資本論』の人名索引を引くと、わずかに〈フランスの天才的軍事技師、コーベル主義の反対者〉とあるのみです。これではなぜヴォバン将軍がボアギュベールと一緒に紹介されているのか分かりません。ようやく京大西洋史研究室編『西洋史辞典』に次のような説明を見つけ出しました。
〈ヴォーバン(1633-1707)、フランスの築城家、軍人、経済学者。貧困貴族の生まれ、10歳で孤児となり、土地の司祭の手で育てられた。フロンドの乱では反乱軍に属したが、1655年来ルイ14世の技師となり、築城に従事、のち軍人としても活躍、結局300余りの要塞の築城と補強に従い、50余の要塞の攻囲戦を指揮した。1699年科学アカデミー名誉会員となり、1703年元帥、引退後『王室の10分の1税』を著し、当時租税の負担が下層階級にのみ負わされていく不合理を説き、租税請負人、特権階級の反省を求め、税の平等を要求した。このため1707年逮捕され、著書は焼き捨てられ、失意の中に死す。重農主義者の先駆として有名。他に築城に関する著書がある〉
つまり二人とも重農主義者であり、その社会的な地位をなげうってでも、過酷な重税にあえぐ農民の窮状を告発し、それに寄生する特権階級を攻撃した勇気ある経済学者たちであったことが分かります。】
(ヘ)(ト) 他方、アジアでは、自然諸関係と同じ不変性をもって再生産される生産諸関係という基礎のうえで地代は現物形態をとっており、この形態が同時に国税の重要な要素ともなっているのですが、現物形態というこの支払形態が、反作用的に、古い生産形態を維持しているのです。この支払形態がトルコ帝国の自己保存の秘密の一つとなっています。
それに対して、アジアでは、現物経済が生産関係の自然と同じ不変性の基礎になっているのですが、そこでは地代は現物形態をとっていて、この形態が国税の重要な要素になっているということです。そしてそれがまた反作用として働いて生産形態を古いままに維持することになっているということです。『資本論』の第3部第47章「資本主義的地代の生成」第3節「生産物地代」のなかで、マルクスは次のように述べています。
〈生産物地代の形態が生産物や生産そのものの一定の種類に結びづけられているということによって、この形態には農業と家内工業との結合が不可欠だということによって、農民家族がこうしてほとんど完全な自給自足を保っていることによって、市場からも自分の外にある社会部分の生産や歴史の動きからも農畏家族が独立していることによって、要するに現物経済一般の性格によって、この形態は、静止的な社会状態の基礎をなすのにまりたくふさわしいものであって、それはわれわれがたとえばアジアで見るとおりである。〉 (全集第25巻b1020頁)
つまり地代が現物形態をとっているということは、商品経済が未発展で、生産物のほとんどが商品とはならず自給自足的な村落共同体のなかで人々は生活しているということです。そうしたものが生産関係の安定性や不変性の基礎になっているということです。しかしそこでは人格的な従属関係にもとで、剰余労働は生産物地代として搾取されているのですが、そうした社会的関係そのものがそうしたものに支えられているということでもあるわけです。オスマン帝国の支配も、そうした剰余労働を現物の貢納として収奪はするものの、それ以外は自給自足的な安定した村落共同体のそのままにさせることが、むしろ帝国の安定になっていたということでしょうか。マルクスは同じところで〈この形態の地代の場合には、剰余労働を表わす生産物地代は、けっして農村家族の全超過労働を汲み尽くすとはかぎらない。むしろ、生産者には、労働地代の場合に比べて、超過労働をする時間をもつためのより大きな余地が与えられており、この超過労働の生産物が彼自身のものであることは、彼の最も不可欠な必要を充たす彼の労働の生産物が彼のものであるのと同様である。〉(同上)と述べています。つまり農民は彼にとって必要不可欠な生活手段である生産物を自分のものとするだけではなくて、それ以上の超過労働の余地が与えられており、その生産物が彼自身のものになったというのです。もちろん、それが後には農民のなかに貧富の格差を生させ、彼らの間に搾取者と非搾取者との対立が生まれてくる余地でもあるのですが、しかしそれはまた別の話だとマルクスは述べています。
(チ)(リ) 日本で、ヨーロッパによって押しつけられた外国貿易が現物地代から貨幣地代への転化をもたらすならば、日本の模範的な農業はおしまいです。この農業の狭隘な経済的存立条件はなくなることでしょう。
この部分はフランス語版では次のようになっています。
〈ヨーロッパが日本に授けた自由貿易が、この国で現物地代から貨幣地代への転換を惹き起こすならば、この国の模範的な農業は、このような革命に抵抗するには余りにも狭隘な経済条件に服しているから、万事休すである。〉 (江夏・上杉訳122頁)
日本の封建的土地所有についてマルクスは『資本論』第1部第7篇「資本の本源的蓄積」の注192)で、次のように述べています。
〈192 日本は、その土地所有の純封建的な組織とその発達した小農民経営とをもって、たいていはブルジョア的偏見にとらわれているわれわれのすべての歴史書よりもはるかに忠実なヨーロッパ中世の姿を示している。〉 (全集第23巻b938頁)
この注192)がついている本文は次の一文です。
〈ヨーロッパのどの国でも、封建的な生産は、できるだけ多くの家臣のあいだに土地を分割するということによって特徴づけられている。封建領主の権力は、どの君主のそれとも同様に、彼の地代帳の長さにではなく彼の家臣の数にもとついていたし、またこの家臣の数は自営農民の数にかかっていた(192)。〉 (全集第23巻b937頁)
つまりマルクスの目には当時の日本の封建制度は中世社会の模範的な姿を示していたということですが、それが外国から開国を迫られ、それによって外国貿易が現物地代から貨幣地代への転化を促すなら、こうした典型的な封建制度の経済的基礎はなくなるだろうと予測しているわけです。
日本では明治維新以前からすでに貨幣経済の発展が見られまれしたが、しかし実際に地代が年貢という形での現物(米)地代から貨幣地代に変わったのは、すでに見ましたように、明治維新の地租改正によります。しかし明治維新は、まさにペリーの来航に象徴されるように外国からの開国の強制に始まる動乱の一結果です。日本における封建社会の崩壊はマルクスの予測どおりだったといえるでしょう。
◎原注104
【原注104】〈104 「取引の過程は、財貨と財貨との交換、または引渡しと受取りから、販売と支払に変わって、すべての売買契約が……いまでは貨幣での価格にもとづいて定められる。」(〔D・デフォー著〕『公信用に関する一論』、第3版、ロンドン、1710年、8ページ。)〉
この原注は〈貨幣は契約の一般的商品となる〉という一文に付けられたものです。すでに見たように、この一文そのものがベーリの述べているものをそのままマルクスが使っているもののようです。
このD・デフォーの著書では、〈取引の過程〉、つまり商品の売買が、〈財貨と財貨との交換〉、つまり物々交換、〈または引渡しと受取りから〉、商品の引き渡しと貨幣の受け取りから、〈販売と支払に変わっ〉たと述べています。つまり取引が、物々交換から商品の販売と購買に変わり、さらに支払手段としての貨幣の機能にもとづいて、商品の販売と支払に変わったとその過程が述べられ、その結果〈すべての売買契約が……いまでは貨幣での価格にもとづいて定められる〉となっています。これ自体は果たして商品流通を超えた支払を意味しているのかどうかはこのままでは分かりませんが、すべての支払が貨幣によってなされるようになったという意味ともとれます。
◎原注105
【原注105】〈105 「貨幣は万物の死刑執行者となった。」財政技術は「この禍いに満ちたエキスを得るためにおそろしく多量の財貨や商品を蒸発させた蒸溜器である。」「貨幣は全人類に戦いを宣する。」(ボアギユベール『富、貨幣、租税の本質に関する論究』、デール編『財政経済学者』、パリ、1843年、第1巻、413、419、417、418ページ。)〉
この原注は〈ボアギユベールやヴォバン将軍たちがあのように雄弁に非難しているルイ14世治下のフランス農村住民のひどい窮乏は、ただ租税の高さのせいだっただけではなく、現物租税から貨幣租税への転化のせいでもあった〉という一文につけられたものです。だからまさにボアギュベールの著書からの引用からになっています。
『経済批判・原初稿』では原注ではなく、〈ボアギユベールは、ペティがイギリス経済学に対して占めているのとまったく同一の重要な地位をフランス経済学に対して占めており、重金主義の熱烈な反対者の一人であるが、彼は、貨幣が他の諸商品に対する排他的な価値として、つまり支払手段(彼は特に租税の支払手段のことを考えている)および蓄蔵貨幣として現われるさまざまな諸形態について貨幣を把握している。(価値が貨幣という姿の独自の定在をもつことは、他の諸商品が価値を相対的に喪失すること、つまり他の諸商品の相対的な地位低下として現われる。)〉(草稿集③76頁)という一文に続いて、ボアギュベール著作集から長い引用が行われています。そのなかに今回の原注にも紹介されている次のような一文がマルクス自身の解説付きで見ることができます。
〈商品を貨幣に転化するために商品の価格を下げること(商品をその価値以下で販売すること)が、いっさいの窮乏の原因なのである。(同書第5章を見よ。)そして以上の意味をこめて彼は、「貨幣はいっさいの物の死刑執行人となってしまった」(同書、413ページ)と言うのである。彼は、貨幣をふやす財政術を「このいまわしい要約をつくりだすためにものすごい量の財貨や商品を蒸発させてしまう蒸留器」にたとえている。(419ページ。)貴金属の価値を下げることによって、「商品それ自身がその正当な価値を回復させられるであろう。」同書、422ページ。「貨幣は……全人類に宣戦を布告する。」(417-418ページ)〉 (草稿集③78-79頁)
これを見ると、ボアギュベールが〈「貨幣は万物の死刑執行者となった。」〉というのは、〈商品を貨幣に転化するために商品の価格を下げること(商品をその価値以下で販売すること)が、いっさいの窮乏の原因なのである〉という意味で、それ以上の意味を込めて言われたものであることが分かります。また〈財政技術は「この禍いに満ちたエキスを得るためにおそろしく多量の財貨や商品を蒸発させた蒸溜器である。」〉という場合の〈財政技術〉というのは、〈貨幣をふやす財政術〉のことを意味していること、それを〈ものすごい量の財貨や商品を蒸発させてしまう〉、つまりそれらを犠牲にして貨幣を増やそうとすることを〈蒸溜器〉に例えていることが分かります。〈「貨幣は全人類に戦いを宣する。」〉という一文も〈「貨幣は……全人類に宣戦を布告する。」〉となっています。貨幣は全人類を犠牲にするほどに忌まわしいものだということでしょうか。
◎第11パラグラフ(支払手段の必要量は支払周期の長さに正比例する)
【11】〈(イ)どの国でも、いくつかの一般的な支払時期が固定してくる。(ロ)それらの時期は、再生産の別の循環運行を別とすれば、ある程度まで、季節の移り変わりに結びついた自然的生産条件にもとづいている。(ハ)それらはまた、直接に商品流通から生ずるのではない支払、たとえば租税や地代などをも規制する。(ニ)社会の全表面に分散したこれらの支払のために一年のうちの何日間かに必要な貨幣量は、支払手段の節約に周期的な、しかしまったく表面的な撹乱をひき起こす(106)。(ホ)支払手段の流通速度に関する法則からは次のことが出てくる。(ヘ)すなわち、その原因がなんであろうと、すべての周期的な支払について、支払手段の必要量は支払周期の長さに正比例する、ということである(107)。
* 第一版から第四版まで、反比例、となっている。〉
(イ)(ロ) どの国でも、若干の支払時期がしだいに固定して、一般的に行われるようになります。それらは、一部は--再生産上このほかの諸循環を別としてのことですが--、季節の移り変わりに結びついた生産の自然的諸条件にもとづいています。
日本にも「五・十日(ごとび)」とか「五十払い」という言葉がありますが、毎月の5日、10日、15日、20日、25日と30日か月末を決済日とする習慣です。そのために道路が混み合ったりします。つまり支払時期が商習慣として固定してくるということです。日本の「五・十日(ごとび)」には〈赤山禅院の五日講に由来するとの説がある。赤山明神の祭日に当たる五日に参詣して懸け取りに回るとスムーズに集金できるという謂われより。〉(ウィキベデア)との説明がありますが、理由ははっきりしません。
ここでは季節の移り変わりと結びついた生産の自然条件にもとづくと書かれています。農業の場合などは収穫期と結びついて支払時期が決まってくるということでしょうか。
(ハ) それらはまた、直接に商品流通から生ずるのではない支払、たとえば租税や地代などをも規制します。
そしてそうした生産の自然条件によって決まる支払時期というものは、直接には商品流通にもとづくものではないもの、例えば租税や地代などの支払をも規制するということです。地代などは農業の収穫期と結びついているのはよく分かりますが、租税もそうした商品流通から生じる支払時期に規制されてその納税期間や時期が決まってくるということでしょう。
(ニ) これらの支払は社会の全表面に散らばって行われているのですが、一年のうちの何日間かは、そうした支払が集中するので、こうした日々の支払に必要な貨幣量は、支払手段の節約に周期的な攪乱を、ただし、まったく表面的でしかない撹乱をひき起こします。
諸支払いが集中するということは、すでに見ましたように、相殺によって支払手段の節約をもたらしました。しかしこれは商品流通における話です。支払手段の流通が商品流通の枠を超えた場合、支配が集中することは必ずしも相殺をもたらすとは限らないのです。例えば、租税や地代の支払が集中したからといってそれらが相殺されるということはありません。だからこうした支払いの集中は相殺による支払手段の節約に周期的な攪乱をもたらすというわけです。
マルクスは『資本論』第3部では国債の利子支払と納税とが支払手段としての貨幣量に及ぼす影響について次のように論じています(ただし大谷氏が「流通〔Circulation〕」と訳しているところは「通貨」と訳すべきところが多いので、内容に即してそのように訳しています)。
〈通貨〔Circulation〕の,事業の状態にはかかわりのない{したがって公衆の必要とする額が同じままでの}現実の膨張または収縮は,ただ技術的な諸原因から生じるだけである。たとえば,租税支払いの期日には銀行券(と鋳貨)が普通の程度を越えてイングランド銀行に流れ込んで,事実上通貨〔Circulation〕を,それの必要にはおかまいなしに収縮させる。国債の利子が払い出されるときにはその逆になる。〉 (大谷『マルクスの利子生み資本論』第4巻111頁)
こうしたことから現実の商品流通とはかかわりのない貨幣の流通量の増減が生じるのですが、それが攪乱にならないように、イングランド銀行は租税支払の期日の前には追加的な貸付を行うと指摘されています。また国債の利子の支払日には商品流通に必要な貨幣量以上の通貨が出まわりますが、それらは銀行に預金され、だからそれだけ銀行の準備金が増えるわけが、そのために利子率が下がるのだと説明されています。
(ホ)(ヘ) 支払手段の流通速度についての法則からは、次のことが出てきます。すなわち、すべての周期的な支払について、どんな出所から支払われたかにかかわりなく、支払手段の必要量は支払周期の長さに正比例する、ということです。
〈支払手段の流通速度〉というのは、ある期間のあいだに同じ貨幣片が何回支払手段として通流するのかということです。しかしこの速度は二つの事情によって制約されました。一つは債権者と債務者との関係の連鎖です。もう一つは支払期限のあいだの時間の長さでした。つまり支払手段が周期的に流通する場合、その周期の長さが、支払手段の必要量に関係してくるということです。その周期が短ければ、同じ貨幣量が一定期間のあいだ何回も使われるために、全体として必要な貨幣量は減ります。そしてその反対に周期が長ければ、その分、貨幣量が増えることになります。例えば日給制と月給制とを考えた場合、日給だと支払った日のあと、短い期間に貨幣がすぐに還流してきて、次の日かあるいは数日のうちに再び同じ貨幣を給与として支払うことができますが、月給制だと支払われた貨幣が還流してくるのは一カ月以上あとになってからになります。だから前者に比べて後者の方が支払手段としての貨幣の必要量は増えるわけです。マルクスはそれを〈支払手段の必要量は支払周期の長さに正比例する〉と述べています。
ところでこの部分も学ぶ会ニュースで取り上げていますので、紹介しておきます。
【つぎに第11パラグラフの最後に出てくる「正比例」が、1版から4版までは「反比例」となっており、戦後の多くの版本でマルクスの「誤記」として「正比例」に改められたことについて、果たしてどちらが正しいのか議論がありました。まず当該のパラグラフを紹介しておきましょう。
〈どの国でも一定の一般的な支払い期限が固定している。これらの支払い期限は、再生産の他の諸循環を度外視すれば、一部は、季節の移りかわりに結びついた生産の自然諸条件に基づいている。これらの支払い期限は、租税、地代などのような、直接には商品流通から発生するのではない諸支払いをも規制する。社会の表面全体に散らばっているこれらの支払いのために一年のうちの一定の諸期日に必要とされる貨幣の総量は、支払手段の節約に、周期的な、しかしまったく表面的な、撹乱を引きおこす。支払手段の通流速度に関する法則の帰結として、どんな期限をもつ支払いであろうと、すべての周期的支払いにとって必要な支払手段の総量は、諸支払い期間の長さに正比例する〉
下線の「正比例」は少なくとも第1版から第4版までは「反比例」あるいは「逆比例」となっていたのです。果たしてマルクスは勘違いをしたのか、それとも戦後の翻訳者の方が間違った解釈をマルクスに押しつけているのか、どうなのでしょうか?
学習会での議論の最終的な結論は、戦後の諸版のとおり「正比例」が正しいのではないかという結論になりました。それはこの部分についている注107のペティの説明--マルクスが「みごとに答える」と評価している--をよく検討してみれば分かります。ペティは「年4000万フランを調達するのに600万の金で足りるか」という質問に、「足りる」と答え、その理由を年4000万の支払いだが、それを毎週という短い周期で支払うならば、4000÷52(1年は52週)で、約77万、つまり100万あればよいと説明しています(実際のペティの説明は「100万の貨幣の40/52」などと説明していますが、これは要するに週に100万ずつ支払えば52週では5200万支払えるから4000万なら十分支払えるといいたいのです)。そしてまた四半期ごと(3カ月ごと)の支払いなら1000万が必要とも説明(これは4000÷4=1000)し、だから諸支払いが1週間と13週間(=四半期)のあいだのさまざまな期限で行われるなら、両者の平均としてほぼ550万と計算しています。
つまりペティは、周期的支払いの「諸支払い期間」が短ければ短いほど、「必要な支払手段の総額」は少なくてすむと説明しているわけです。だからペティの説明どおりに理解するならば、やはり「正比例」が正しいことになり、マルクスの「誤記」だと解釈した方が良いように思えるのです。
ところで、しかしこうした結論に異論をとなえている御仁が存在することも紹介しておきましょう。それは『資本論』の翻訳ではその「厳密さ」が評価されている長谷部文雄です。青木書店版の『資本論』では当該箇所は「逆比例」となっており、それに長谷部の次のような長い訳者注がついています(長いので一部省略)。
〈この場合の問題は、Lange der Zahlungsperiodenという言葉を、支払い周期(1週間目とか3カ月目というような、支払い期限と支払期限との間隔)の長さと解するか、支払期間(1日間とか1週間とかいう、その間に支払いが行われるべき期間)の長さと解するかに依存するのであって、前者が大となれば、支払総額が大となるが故に支払手段の必要分量はこれに正比例し、また後者が大となれば、支払手段の流通速度が大となるが故に支払手段の必要分量はこれに逆比例する。しかるに、マルクスの本文における「支払手段の流通速度に関する法則からして……周期的な支払にとっては」という前置きからすれば、右の言葉は「支払期間の長さ」と読むべきであり、比例関係は「逆」でなければならぬと思われる〉 (276頁)
しかし長谷部のいうような「支払期間」なるものは、少なくともペティの説明のなかでは全く行われていないのであって、やはり長谷部の理解には無理があるように思えるのですが、どうでしょうか?】
◎原注106
【原注106】〈106 1826年の議会の調査委員会でクレーグ氏は次のように述べている。「1824年の聖霊降臨節には、エディンバラの諸銀行にたいする銀行券の需要が莫大な額にのぼり、11時には銀行の手もとには1枚の銀行券も残ってはいなかった。そこであちこちのどの銀行に借りにやっても手に入れることはできなかった。ついに取引の多くはただ紙券だけですまされた。ところが、3時にはすべての銀行券が、それを出した銀行に返されていた。それはただ手から手へ渡されただけだった。」スコットランドでは銀行券の実際の平均流通高は300万ポンド・スターリングよりも少ないにもかかわらず、1年間のいくつかの支払日には、銀行業者の手もとにある銀行券が全部ひっくるめて約700万ポンドも動員される。このような時期には、銀行券は一つの独特な機能を果たさなければならない。そして、それを果たせば、銀行券を出したそれぞれの銀行に流れて帰るのである。(ジョン・フラートン『通貨調節論』、第2版、ロンドン、1845年、86ぺージ、注。〔岩波文庫版、福田訳、115-116ページ。〕)理解を助けるためにつけ加えれば、スコットランドでは、フラートンの著書が出た当時は、預金にたいして小切手ではなく銀行券だけが発行されたのである。〉
この原注は〈社会の全表面に分散したこれらの支払のために一年のうちの何日間かに必要な貨幣量は、支払手段の節約に周期的な、しかしまったく表面的な撹乱をひき起こす〉という一文につけられたものです。
実は、この注は、最後の〈理解を助けるためにつけ加えれば、スコットランドでは、フラートンの著書が出た当時は、預金にたいして小切手ではなく銀行券だけが発行されたのである。〉という一文はマルクスのものですが、それ以外の最初の鍵括弧の部分とそのあとの鍵括弧のない部分も含めてすべてフラートンの『通貨調節論』からの抜粋です。だからとりあえず、参考のためにその少し前からその部分をフラートンの著書から紹介しておきましょう(ただし改造社版・阿野季房訳から、一部現代用語に変えました)。
このマルクスの引用している部分はフラートンの著書の〈地方銀行業者の発券高はもっぱら当該地方における地方的取引と消費との程度によって規制され、その変動は生産と価格との変動にともなっている。そして地方銀行業者は、彼らの発券高をこのような商取引ならびに消費の範囲が規定する限度以上に増大させようとしても、余分の紙券は直ちに間違いなく彼らの手に還流するからそれは不可能であり、反対に発券高を無理に減少させようとしても、その空隙は前の場合とほとんど同じように確実に他の何らかの源泉から補充されるからやはり目的を達することは出来ない、というのであった〉(108頁)という本文につけられた注のなかの一部です。その注では各年代の議会の委員会の証言への参照指示のあと幾つかの証言が紹介されているのですが、そのなかに次のような一文があります。
〈銀行券のうち、公衆の手にとどまり通貨として機能しているように考えられる部分は、賃金やその他の日常支出のような少額の支払に必要とされる分である。それ以上のものはすべて他の諸銀行に払い込まれるか、または直ちに発行銀行の手許に還流してしまう』。なお、一時的ないし地方的需要にもとづいて個人銀行券の過剰発行が行われる場合があっても一旦この需要がやむとそれが如何に容易にまた迅速に是正されるかという事実についての最も際立った例証は、恐らく、1826年の委員会においてギブスン・クレイグ氏(Mr.Gibson Craig)が述べた逸話のうちにこれを見いだしうると思われる(報告書268頁参照)。すなわちクレイグ氏は次のごとく言っている。『1824年の聖霊降臨祭の月曜日に、エディンバラでは銀行券に対する膨大な需要があったので、11時にはもはや1枚もわれわれの手許には残らなかった、そこで融通を得るためいろいろな銀行に順次人をやったが、一枚もえられなかった、かくて多くの取引はただ仮証書によってのみ処理されることになった。しかるに午後3時となるや一切の銀行券がそれを発行した各銀行に戻ってきた! 要するに、これらの銀行券は手から手へ転々して行ったに過ぎないのである』。〔以下第2版への追加--訳者〕これはこの種の現象の例としては唯一のものでは決してない。私がもっとも信頼すべき筋から確かめたところによれば、スコットランドにおける銀行券の実際の流通高は平均して300万ポンドを割っているにもかかわらず毎年数回は各銀行業者の所有する約700万ポンドからの紙券がことごとく活動させられることが起こるとのことである。これらの場合それらの紙券はただ単独の特別な役割を果たすのであり、一旦、この役割をはたしてしまえばそれはもとの各銀行へと還流する。〉 (109-110頁)
ここで言われている〈聖霊降臨節〉というのは別名「ペンテコステ」というらしいですが、キリスト教の復活祭につぐ祭日の一つのようです。よく分からないのですが、日本の「五・十日(ごとび)」が〈赤山禅院の五日講に由来するとの説がある。赤山明神の祭日に当たる五日に参詣して懸け取りに回るとスムーズに集金できるという謂われより。〉(ウィキベデア)との説明がありましたが、聖霊降臨祭もそのお祭り日に支払が集中したのかも知れません。あるいはお祭りに供える貨幣が膨大だったのかも知れません。いずれにせよ、そのために支払手段の流通量が増えて、11時には銀行券が銀行からなくなってしまったのが、午後の3時にはすべて銀行に返されていたということです。つまり支払手段としての機能を果たした銀行券はすぐに銀行に預金され還流したということのようです。
なおマルクスは〈理解を助けるためにつけ加えますと、フラートンの著書が出た当時のスコットランドでは、預金にたいして、小切手ではなくて銀行券だけが発行されたのです〉と補足しています。つまり銀行に口座をもつ顧客がそれを利用する場合、小切手で支払うというケースはスコットランドには無かったということです。だから預金を利用しようとする顧客は、それをただ銀行券で引き出して使うしか方法がなかったということなのです。だから一時的に支払手段に対する大きな需要が生じたら、銀行から銀行券がなくなってしまうというような異常な事態が生じたということでしょう。
◎原注107
【原注107】〈107 「もし一年当たり4000万を調達する必要があるとすれば、産業が必要とする回転と流通とのために、同じ600万」(の金)「でこと足りるだろうか?」という問いにたいして、ペティは、いつものような巧妙さで次のように答えている。「私は、足りる、と答える。というのは、支出は4000万だから、もし回転が、たとえば土曜ごとに受け払いをしている貧しい職人や労働者のあいだで見られるように、毎週というような短い周期であるならば、100万の貨幣の40/52でもこれらの目的が達せられるだろうからである。しかし、もし周期が、わが国の地代支払や租税徴収の慣例どおりに、四半期であるならば、その場合には1000万が必要であろう。それゆえ、一般に諸支払が1週間から13週間までのまちまちの周期でなされるものと想定すれば、40/52百万に1000万を加えたものの半分は550万だから、550万あれば十分である。」(ウィリアム・ペティ『アイルランドの政治的解剖、1672年』、ロンドン版、1691年、13、14ページ。〔岩波文庫版、大内・松川訳『租税貢納論』、183-184ぺージ。〕)〉
これは〈すなわち、その原因がなんであろうと、すべての周期的な支払について、支払手段の必要量は支払周期の長さに正比例する、ということである〉という一文につけられた原注です。ペティの著書からの抜粋からほぼなっています。この問題は、すでに先に紹介した学ぶ会ニュースのなかで、その解説らしきものがありました。もう一度、その部分だけを紹介しておきましょう。
【ペティは「年4000万フランを調達するのに600万の金で足りるか」という質問に、「足りる」と答え、その理由を年4000万の支払いだが、それを毎週という短い周期で支払うならば、4000÷52(1年は52週)で、約77万、つまり100万あればよいと説明しています(実際のペティの説明は「100万の貨幣の40/52」などと説明していますが、これは要するに週に100万ずつ支払えば52週では5200万支払えるから4000万なら十分支払えるといいたいのです)。そしてまた四半期ごと(3カ月ごと)の支払いなら1000万が必要とも説明(これは4000÷4=1000)し、だから諸支払いが1週間と13週間(=四半期)のあいだのさまざまな期限で行われるなら、両者の平均としてほぼ550万と計算しています。】
ペティの主張の説明としてはこれで十分ではないでしょうか。
◎第12パラグラフ(支払手段の準備金)
【12】〈(イ)支払手段としての貨幣の発展は、債務額の支払期限のための貨幣蓄積を必要にする。(ロ)独立な致富形態としての貨幣蓄蔵はブルジョア社会の進歩につれてなくなるが、反対に、支払手段の準備金という形では貨幣蓄蔵はこの進歩につれて増大するのである。〉
(イ) 支払手段としての貨幣の発展は、支払期限に債務額を支払うために貨幣を蓄積することを必要にします。
商品流通においては勿論、それ以外においても支払うためには、その期限までに貨幣を準備しなければなりません。その貨幣をどのように入手するかに係わらず、支払うに必要な一定額になるまで、それまでの期間のあいだ貨幣を積み立てておく必要が生じます。これは流通手段の場合のように、商品を販売して入手した貨幣をいっぺんに別の商品の購入に支出するのではなく、いろいろな商品の購入に宛てるために、一時的に保持しているのとは違った性格の貨幣です。流通手段の場合には一時的に保持しているものは鋳貨準備金といって流通貨幣の一部分ですが(流通を技術的に一時止めているだけの貨幣)、支払のための準備金は、蓄蔵貨幣の一種で、流通から引き上げられた貨幣なのです。
(ロ) 自立的な致富形態としての蓄蔵貨幣形成は、ブルジョア社会が進歩するのにつれてなくなっていきますが、それとは反対に、支払手段の準備ファンドという形態での蓄蔵貨幣形成はブルジョア社会の進展につれて増大していきます。
もともと蓄蔵貨幣というのは、流通から引き上げられて蓄蔵される貨幣であって、それ自体が絶対的な価値として富の象徴のようなもので、“黄金熱”がそれを代表しています。こうした蓄蔵貨幣は、資本主義の初期のころ重商主義や重金主義の時代(歴史的には黄金を世界に探し求めた大航海時代がそれにあたります)に発達したものです。しかし資本主義が発展してくると、こうした蓄蔵貨幣の役割は姿を消して行きます。その代わりに支払のための準備としての蓄蔵貨幣の役割が増大してくるのです。
しかし現代ではこうした蓄蔵貨幣そのものも銀行の預金になり、金の現物としてはほぼ中央銀行の金庫に眠るだけのものになっています。預金は預金者にとっては準備金という性格を持っていますが、社会的に見ると、それはすぐに銀行から貸し出されて、ただ帳簿上の記録としてあるだけの架空なものです。だから蓄蔵貨幣とはいえません。
このパラグラフについてはより詳しい説明がなされている『経済学批判』から参考のために紹介しておきましょう。
〈諸支払は、それとしてまた準備金を、支払手段としての貨幣の蓄積を必要とする。こういう準備金の形成は、もはや貨幣蓄蔵の場合のように流通そのものにとって外的な活動としても、また鋳貨準備の場合のように鋳貨のたんなる技術的停滞としても現われないで、むしろ貨幣が将来の一定の支払期日に手もとにあるように、だんだんに積み立てられなければならない。だから致富として考えられている抽象的形態での貨幣蓄蔵は、ブルジョア的生産の発達につれて減少するのに、交換過程によって直接に必要とされる貨幣蓄蔵は増加する、というよりはむしろ、一般に商品流通の領域内で形成される蓄蔵貨幣の一部分が、支払手段の準備金として吸収される。ブルジョア的生産が発達していればいるほど、この準備金はますます必要な最小限度に限られる。ロックは利子率の引下げについての彼の著作で、彼の時代のこの準備金の大きさについて興味ある説明をあたえている。この説明から、銀行制度が発達しはじめたばかりの時代に、イギリスでは支払手段の貯水池が一般に流通していた貨幣のどれほど大きな部分を吸収していたかがうかがい知られる。〉 (全集第13巻125頁)
(以上で、「b 支払手段」は終わりです。【付属資料】は(3)に掲載。)