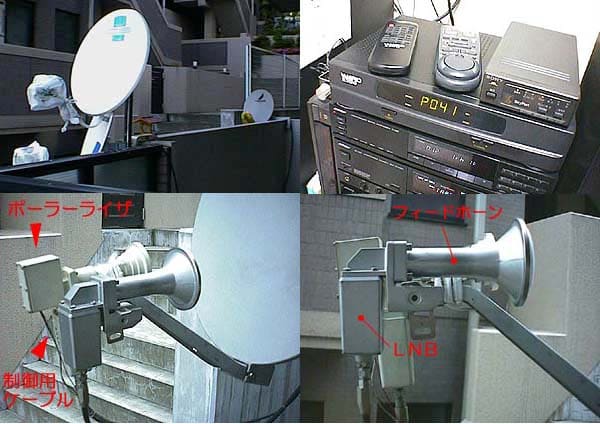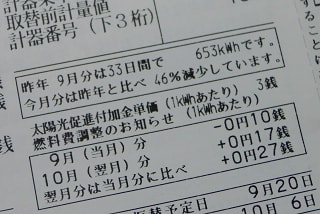車のバッテリー交換をして5年半使ったバッテリーはソーラーシステムへ転用。その前にサルフェーションの除去と内部低抵抗の改善を試みる。前から興味のあったパルス充電器(6A)を精進。パルス充電前の開放電圧は12.3Vだった。パルス充電を10時間ほどかけてみたところ電圧は13.7Vに改善。残念ながら内部抵抗値は測定できない。ついでに5年間放置していたソーラー充電用バッテリーをチェック。マイナス端子に恐ろしいほどのサルフェーションが蓄積していた。これはもう廃棄確定。

東日本大震災より13年。輪番停電の苦労を思い出し緩んだ気分を引き締める。発動発電機も試運転しなければと思う。