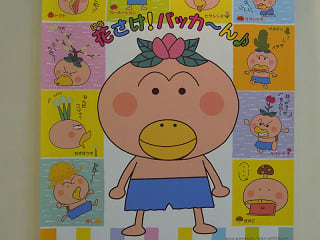日比谷公園の噴水横にある売店。映画のセットと見紛うばかりの完璧な昭和風情を頑なに通している。カウンターにはダイヤル式675型のピンク電話や地球儀?。「フィルム」の看板も今となっては懐かしい。店の奥には絶版アイテムがふつうに積まれているかも知れない。
鉄道フェスティバルということでやんわりと業務命令を受けお付き合い。ワシが電GOを企画してから15周年となるのだ。三連休の初日は日比谷公園でお仕事となる。告白すると鉄道フェスティバルなるものは今回が初参加。無料イベント盛りだくさんを想像していたのだけれど、会場の殆どは電鉄会社の物販、しかも長蛇の列。人気の阪急電鉄ブースなどは日比谷公園の長辺を埋める長さの行列が出来ていた。聞けば開演二日前から並ぶ人もいたようだ。折角家族や恋人をひきつれて来ても物販のテントだけでは不満ブーブーではないか。業界が揃っているのだからライブスチームを走らせたりちょっとした機材の展示などひと工夫あってもよさそうに思う。不景気で広告宣伝費は削減方向だとは思うが、鉄道への理解を深めるイベントにしては商魂ばかりが目立つイベントでありました。ざーんねん!
TV取材を受ける新製品とワシの代表作「初代電GO!」も会場隅に展示されていた。
業界の夏の祭典、アミューズメントマシンショーも無事終わりました。今年の新製品もお陰さまで評判良かったのでホッと一安心。再来週はロンドンで次なる仕事が待ってマス。
業界の夏の祭典、アミューズメントマシンショーも無事終わりました。今年の新製品もお陰さまで評判良かったのでホッと一安心。再来週はロンドンで次なる仕事が待ってマス。
実験企画から三年目、ようやく製品化にこぎ着けました。まあ、途中おさぼりで中断してたのだけれど。今年の年末に出荷です(ようやく情報解禁)。ビデオにメカトロ、プライズにメダル。なんでもやります、やらせてください。これが業務用アミューズメント製品企画の醍醐味です。
ホレホレ
ホレホレ
仕事の移動でJR相模線を利用した。この線は今や開発著しい橋本駅と東海道線茅ヶ崎駅を結ぶローカルな単線。いまでもタブレット交換が行われ鉄道マニアの注目を集めている(ウソ)。で、数年ぶりに利用して扉扱いが乗客の押しボタン(半自動スイッチ)操作というのに気づく。車外、車内に開閉ボタンがありそれで開け閉めするのだ。地元の乗客は慣れたもので扉を開けて乗車しご丁寧に車内のボタンで閉めの操作まで行っている(因みに閉め操作は車掌室より一斉操作で行う)。平日の昼間は1時間に2本程度の運行密度であり乗客もまばらとなればそれで十分かも知れない。そして何より今の季節は車内冷房の冷気が逃げないのでありがたい。折角冷えた車内も駅での扉開閉の度にリセットされることが回避される。実に省エネではないか。この「ボタン式半自動」システムは寒冷地仕様として採用されているが、他の路線でも積極的に取り入れてもいいのかも知れない。因みに小田急新宿駅でも厳冬時、停車時間の長い車両では手動式扱いにして暖気の流出を防いでいる。
今日は新宿の本社でミーティングがあり昼前に小田急で移動。長椅子の端に座れたので肘掛に頬杖をついて惰眠を決め込む。途中の駅で親父が乗り込んできてドア横に立ち、ワシのことなどお構いなしで尻でグイグイと肘を押しのけて肘掛に腰を預けやがった。見れば60歳前後のいい歳。この暑いなか顔の真横に親父の尻。こういう厚顔無恥な親に育てられた子供もまたモンスターペアレントとして自己主張が強く他人の迷惑も省みず損得勘定だけで生きているのだろうなあと思う。まったくつまらん人生だと思うのだがそれこそが大きなお世話というものか。注意する気にもならない、逆ギレされるのがオチ。こういう輩には関らないことが一番なのだ。
仕事で開発製作中の業務用ゲーム機のBGMがサウンド部門よりアップデートされた。早速試作筐体にセットしてエージング。筐体部屋から時折BGMが聴こえてくる。開発部屋の他プロジェクトメンバーから「あの曲はなんだ?!」「一度聴くと頭から離れない」とのクレーム殺到。何を隠そうワシもそう思ってました。そのうちにこの新製品が日本全国の大型スーパーの子供用ゲームコーナーに並ぶ予定。ショッカーよろしく日本中のお子様を恐怖のズンドコに叩き込んでやる。この曲はカリキュラマシーンとゲバゲバと霊感ヤマカンとイエイエを足して割ったような曲なのだ。この稼業こういう楽しみがないとね。にひひ
カリキュラマシーン
ゲバゲバ90分
霊感ヤマカン第六感
イエイエ
未だに車でカセットテープを聴いているライフスタイルではあるけれど、そろそろカセットテープも心許なくなってきた。そこで“紙ジャケ”なるCDを買ってみた。“紙ジャケ”とは当時のLPをCDに焼き直したものをしてそう呼ぶのだと思っていたら本当にボール紙の「紙ジャケット」だった。装丁、歌詞冊子もLP時代のものをスケールダウンしたまま。ご丁寧にもCD袋までLP時代の内袋を模していた。まあこれはこれで面白い。で、買ったCDは中島みゆき。高校、大学時代に聴いていたものを今でも繰り返し聴いている。但し最近の彼女のものは一切聴かないし興味もない。彼女の感性が最高に研ぎ澄まされていたのはやはり25年ほど昔だと思うのだ。人は10歳で人格が決まると言われているが、ワシの嗜好は20歳でとまってしまった。この軽薄、幼稚にして短絡的な世の中では70~80年代への憧憬も許されるだろう。
人生初のハンモック体験。先ずは横座りして体重を預けながら両足を乗せる。前後にモソモソ動き重心位置の調整。転覆することもなく案外簡単に寝転ぶことができた。体重は分散化され面で支えれらながらも網目が浮遊感を演出している。涼しく爽やかな風の抜ける木立は日差しを遮りとてつもなく心地よい。この環境ならどんな分厚い哲学書でも読破できそうだ。気分はもうムーミン谷のジャコウネズミさん。そしてつぶやくのはこの台詞「無駄ぢゃ無駄ぢゃ」あくせく働くのが嫌になる瞬間でもある。
東京ビッグサイトの帰り閉館時間迫る「船の科学館」に飛び込む。今年9月いっぱいで展示公開が休止となるのだ。この科学館は昭和の雰囲気を色濃く残す展示スタイルでたいそう気に入っていた。なかでも青函連絡船の羊蹄丸内部はラーメン博物館よろしく昭和30年冬の青森駅が再現されており素敵な空間を演出していた。船内には出入り自由の映画館もあり青函連絡船に関連した映画が一日中かけられている。観客はいつも数えるほど。科学館の中は懐かしくも心地よい昭和の時間が流れているのだ。この雰囲気はかつての大阪市立電気科学館、京都伏見の青少年科学センターそして大阪弁天町の交通科学館と同じもの。バブル期を境に訳のわからぬプランナーによって多くの展示館、科学館が、下世話で低俗幼稚な展示スタイルへと改悪され破壊されるなかにあって、今では数えるほどとなった貴重な存在のひとつであったのだ。しかしそれも9月で見納め。船を模った本館はリニューアルするらしいが、青函連絡船はスクラップとの噂も。維持管理費を考えると相当な負担であることは容易に想像できる。しかし折りしも機械遺産に認定された連絡船、できればこのまま保存を続けて欲しいと願う。大宮の交通博物館に移設なんて駄目かしら。皆さんもこの夏休み昭和最後の船の科学館を是非ご見学ください。今なら特別料金200円で見学できます。
車のポジションランプが球切れ。予備球は持っていたので交換しようとするもバッテリーを降ろさねば作業できないことが判明。面倒なので先送り。こういう箇所の交換は整備性をもっと考慮して欲しいものだ。ソアラの時もフォグの球交換は一苦労だったことを思い出す。
自分にとってカゲロウは不吉な知らせとなっている。学生時代に実家のベランダにカゲロウがウドンゲと呼ばれる卵を産卵しているのを見つけ翌日親戚に不幸があった。数年後またカゲロウを見つけて一度は追い払うも戻ってきて産卵。数日後に祖父が他界。そんなことが3度ほど続くと偶然では済ませられなくなった。元々「優曇華の花」は三千年に一度しか咲かないとされ、優曇華の花が咲くと100人の人に見てもらい厄払いするような迷信を母から聞いた。現に子供の頃、街路樹に張り紙がしてあり「優曇華の花が咲きました、どうか見てください」と優曇華の花(たぶんカゲロウの卵)が貼り付けられているのを見た記憶がある。稀有な出来事をして「盲亀の浮木、優曇華の花」との諺もあるくらいだ。
今朝出勤の途中でウドンゲではないけれど壁にとまるカゲロウを見つける。一瞬不吉な予感と胸騒ぎがするも急いでそれを否定しその場を去った。そして今夜、親友の悲報を聞く。なんとも遣り切れない気分になる。
今朝出勤の途中でウドンゲではないけれど壁にとまるカゲロウを見つける。一瞬不吉な予感と胸騒ぎがするも急いでそれを否定しその場を去った。そして今夜、親友の悲報を聞く。なんとも遣り切れない気分になる。