江戸幕府の軍艦「咸臨丸」が幕末に渡米してから150年を記念して、県の歴史愛好家の会「讃岐龍馬会塩飽(しわく)社中」は、同船に水夫として乗り込んだ塩飽諸島出身の35人の功績をたたえる石碑を同諸島の櫃石(ひついし)島(坂出市)に建立。26日、子孫を招いて、除幕式を行う。同会の丸野忠義会長は「日本の船として初めて太平洋横断に成功した咸臨丸で、塩飽の人々が果たした役割は大きく、その歴史を語り継ぎたい」と話している。
咸臨丸に乗り込んだ50人の水夫のうち35人が同諸島の本島、広島、高見島、櫃石島、牛島、佐柳(さなぎ)島、瀬居島の7島の出身者だった。
塩飽の人々は古くから瀬戸内海の海運を担い、江戸時代は中期まで幕府の御用船方として城米の輸送など重要な役割を果たした。操船技術に長けていたことから、幕府の徴用を受けて咸臨丸に乗り込んだ。
しかし、咸臨丸の航海での塩飽の人々の活躍は全国的にはあまり知られておらず、「過酷な航海を支えた塩飽の人々に光をあてたい」と、歴史愛好家ら約25人が2002年、会を結成。子孫や、墓を訪ねる調査などを進めてきた。漁港跡地に建てられる石碑は花こう岩で高さ2メートル、幅2・5メートル。太平洋の荒波を進む咸臨丸の写真を転写し、「郷土の誇りとして その名を永く 後世に伝えん」とする文字と、水夫35人の氏名を刻む。
同会は04年6月、佐柳島出身で、同船の水夫で後に海援隊士となり坂本龍馬と行動を共にした佐柳高次(1835~91)を顕彰する石碑を同島に建てている。除幕式には大阪や櫃石島から水夫の子孫3人が訪れる予定で、子孫の1人で大阪市港区在住の藤本増夫さん(59)は「水夫たちの活躍は歴史の闇に埋もれている。全員の名を記した碑を故郷に建てることは意義があり、誇りに思う」と話している。
6/8 読売新聞
よければクリックしてください。 人気ブログランキングへ 一日一回クリックしてもらえたらうれしいです。
大阪龍馬会携帯版HPはこちらです。 大阪龍馬会HPはこちらです。 NHKドラマスタッフブログはこちらです 龍馬伝のHPはこちら
咸臨丸に乗り込んだ50人の水夫のうち35人が同諸島の本島、広島、高見島、櫃石島、牛島、佐柳(さなぎ)島、瀬居島の7島の出身者だった。
塩飽の人々は古くから瀬戸内海の海運を担い、江戸時代は中期まで幕府の御用船方として城米の輸送など重要な役割を果たした。操船技術に長けていたことから、幕府の徴用を受けて咸臨丸に乗り込んだ。
しかし、咸臨丸の航海での塩飽の人々の活躍は全国的にはあまり知られておらず、「過酷な航海を支えた塩飽の人々に光をあてたい」と、歴史愛好家ら約25人が2002年、会を結成。子孫や、墓を訪ねる調査などを進めてきた。漁港跡地に建てられる石碑は花こう岩で高さ2メートル、幅2・5メートル。太平洋の荒波を進む咸臨丸の写真を転写し、「郷土の誇りとして その名を永く 後世に伝えん」とする文字と、水夫35人の氏名を刻む。
同会は04年6月、佐柳島出身で、同船の水夫で後に海援隊士となり坂本龍馬と行動を共にした佐柳高次(1835~91)を顕彰する石碑を同島に建てている。除幕式には大阪や櫃石島から水夫の子孫3人が訪れる予定で、子孫の1人で大阪市港区在住の藤本増夫さん(59)は「水夫たちの活躍は歴史の闇に埋もれている。全員の名を記した碑を故郷に建てることは意義があり、誇りに思う」と話している。
6/8 読売新聞
よければクリックしてください。 人気ブログランキングへ 一日一回クリックしてもらえたらうれしいです。
大阪龍馬会携帯版HPはこちらです。 大阪龍馬会HPはこちらです。 NHKドラマスタッフブログはこちらです 龍馬伝のHPはこちら











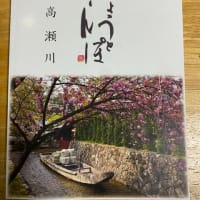

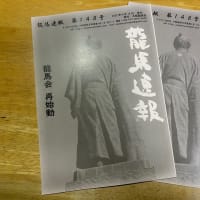

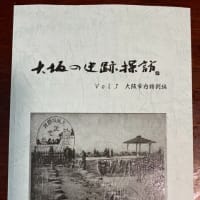


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます