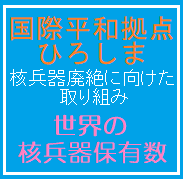第26回・議院内閣の仕組み
を読みました。
内閣の仕組み、ちょっと難しくて私には理解できません。
憲法上、政党の活動について規制がないということは、
私たち国民がしっかり意識して、
私たちにとって不利にならないように政治の動きを見ていく必要があると言うこと。
アメリカの大統領制のように直接的な関わりではない代わりに、
私たちの声を国会で、少数派の声を含めて充分に議論されるべき。
内閣はその国会に対して責任を負う・・・
次は
第27回・議院内閣制と権力分立06-09-13UP
を読んでみます。
心配事が取り越し苦労でありますように。
を読みました。
内閣の仕組み、ちょっと難しくて私には理解できません。
憲法上、政党の活動について規制がないということは、
私たち国民がしっかり意識して、
私たちにとって不利にならないように政治の動きを見ていく必要があると言うこと。
アメリカの大統領制のように直接的な関わりではない代わりに、
私たちの声を国会で、少数派の声を含めて充分に議論されるべき。
内閣はその国会に対して責任を負う・・・
次は
第27回・議院内閣制と権力分立06-09-13UP
を読んでみます。
心配事が取り越し苦労でありますように。