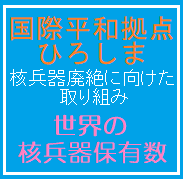第16回・「国民投票法について(その3)」 を読みました。
国民投票法が作られなかったことは立法不作為ではない。
(ちょっと解釈が難しいけど)
・・【正論】百地章 速やかに国民投票法の制定を (イザ!):産経新聞社
“あくまでも国民が望んだときに、
国民の代表として改憲の発議をすることができる”
本当に国民が憲法を理解し、改正を望んでいるのだろうか?
改憲を否定し、そのための手続法も作らせないということも、
改憲を肯定することと同じように、国民主権を行使していると言える。
次は
第17回・「国家と個人」06-06-14UP
を読んでみます。
心配事が取り越し苦労でありますように。
国民投票法が作られなかったことは立法不作為ではない。
(ちょっと解釈が難しいけど)
・・【正論】百地章 速やかに国民投票法の制定を (イザ!):産経新聞社
“あくまでも国民が望んだときに、
国民の代表として改憲の発議をすることができる”
本当に国民が憲法を理解し、改正を望んでいるのだろうか?
改憲を否定し、そのための手続法も作らせないということも、
改憲を肯定することと同じように、国民主権を行使していると言える。
次は
第17回・「国家と個人」06-06-14UP
を読んでみます。
心配事が取り越し苦労でありますように。
imktj