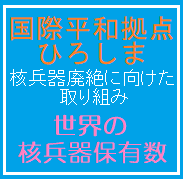「薬物依存症には刑罰ではなく治療が必要なことを知って欲しい」
松本俊彦氏
(国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部部長)
2019年12月7日
有料会員にならないと見られない番組ですが、
とても興味深い内容なので印象に残ったことをメモし羅列します。
カッコ内は個人的な感想です。
-------------------------------------------------------------------------
依存症とは。
自分の大事なものランキングの一番上に来るもの、
それが薬物などになってしまうと(大事な人を裏切ってしまうなどの)価値観の転倒が起こってしまう。
「依存症」というと「依存」が悪いものという誤解が生じるかもしれないが、依存そのものは悪い事ではない。
(例えば、一日の終わりに美味しく酒を飲み、リフレッシュして、翌日はまた仕事に出る、というようなこと=酒に依存しつつ生活を維持している)
いそん【依存】
( 名 ) スル
〔「いぞん」とも〕
①他のものにたよって成立・存在すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館) |
依存症の人は結果的に生活できなくなってしまっているから、もはや「依存」ではない=病気「依存症」ということ。
依存症か依存症でないかのラインは・・・
依存性物質を繰り返し使っていると体が慣れて増えていく
急にやめるとリバウンドで離脱症状
依存症の医学的根拠

身体依存自体はあまり問題ではない。
問題は精神依存。
依存症と言われるもの=その社会にとって害なもの。
医学的概念では説明できない部分がある。
日本では、お酒とたばこは合法。
ギャンブルも。
「麻薬」とは何か?

実は独自の定義はない。(!)

定義すると、酒やたばこも対象になる。
多幸感?陶酔感?依存性?
(強いて言えば、違法となっているもの=麻薬?・・・内容ではなく。それもおかしな話)
80年代終わりから90年代初め
「ダメ。ゼッタイ。」キャンペーン、一部分的に効果はあった。
偏見、スティグマを強化し、若い子たちが手を出さなくなった。
アメリカなどでも、麻薬を社会から隔離し、一般の人が麻薬に手を出さないという効果は一定程度あった。
一方で、一度手を出してしまうと、社会から抹殺される。
自己正当化してしまう(開き直り?)、自分はもうだめなんだ(悪循環)
(隔離施策は諸刃の剣)
国連で提唱されたものは
「yes to life no to drug」
「人生にイエスと言おう、薬物にはノーと言おう」
「ダメ。ゼッタイ。」は「yes to life」が抜け落ちた誤訳、その弊害は?
今の10代の子の中で一番問題となっているのは市販薬、処方薬(の乱用)である。
「ダメ。ゼッタイ。」は違法薬物に特化していることも問題。

刑罰が治療の阻害している。
「刑罰は効果がない、治療のほうが効果があるというエビデンス(根拠)をもっと粘り強く繰り返し、出していく必要がある」(松本氏)
報道に関して。
「薬物報道ガイドライン」

少しづつネット上では周知されつつあるのに、なぜ、テレビの報道内容が方向転換できないのか。
視聴率が取れる内容になってしまう(→私たちの中にも、刷り込み、洗脳的なものがあるから。ニワトリと卵みたいな感じかな?)
「テレビの仕事をして居る方々にとって視聴率は大事、私たちはその代替案としてもっといい視聴率を取れるし局としても評価されるものを提案していきたい」(松本氏)
ハームリダクション=一人ぼっちにさせない政策。
薬物使用による二次的な災害をおさえる。
清潔な注射器=HIV感染を防ぐ。
呼吸停止に対応する。
安全なヘロインの使い方を指導、ナース常駐の注射室。
効果が上がった。
死亡率は減り、犯罪もは増えず。
ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアは行っている。
アメリカは一部の地域のみ実施。
アメリカ連邦政府がハームリダクションを認めていないから、日本は変われないだろう。
医者の主観にもとづいたデータ。
ハーム(害)の度合

”社会に対する被害”ではアルコールが断トツでトップ。
(私もお酒を飲むのでこれはショック)
(でも、日本の街中での光景を思い起こせば「確かに」という思い)
(知っておくべき事実)
(戒め)
「人類がアルコールと出会うのがもっと最近だったら100%違法薬物だろう」(松本氏)
最も危険なドラッグはアルコール|英国の研究から
(故・弁護士小森榮氏のブログ)
--------------------------------------------------------------------
松本氏の記事
まちがいだらけの薬物依存症 乱用防止教育が生み出す偏見
薬物依存に陥らせるのは、薬の作用というより「孤立」