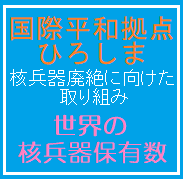第36回・憲法改正手続法その4
が更新されました。
国民投票案について。
少しずつ、現実的なものになってきているようです。
なのに私たちは、憲法改正や、その手続きについて、
現実としてきちんと情報を得る機会、考える機会を持っているでしょうか?
未だにどこか、他人事のような風潮がありますよね。
それって、誰かの思う壺、って感じにならなければいいのですけど。
誰かって誰だろう?
伊藤氏が言われているように、
国民投票が行なわれたとして、
わからないけど、まいっか、では済まないこと、
選挙に行かない人の存在をどう捉えるかという問題、
選挙運動の制限の緩和、
など、
今までの選挙とは全く違うということをしっかり意識しなくてはならないはずなのに。
わたしたちはいったい、どうすればいいのでしょう・・・
また、新しく更新され次第読んでみます。
>>バックナンバー一覧
が更新されました。
国民投票案について。
少しずつ、現実的なものになってきているようです。
なのに私たちは、憲法改正や、その手続きについて、
現実としてきちんと情報を得る機会、考える機会を持っているでしょうか?
未だにどこか、他人事のような風潮がありますよね。
それって、誰かの思う壺、って感じにならなければいいのですけど。
誰かって誰だろう?
伊藤氏が言われているように、
国民投票が行なわれたとして、
わからないけど、まいっか、では済まないこと、
選挙に行かない人の存在をどう捉えるかという問題、
選挙運動の制限の緩和、
など、
今までの選挙とは全く違うということをしっかり意識しなくてはならないはずなのに。
わたしたちはいったい、どうすればいいのでしょう・・・
また、新しく更新され次第読んでみます。
>>バックナンバー一覧