
12月はほーんと毎年スケジュールがキツキツすぎて、アップアップな状態になるのですが、やっぱり好き
 。それは、クリスマスがあるから
。それは、クリスマスがあるから 。
。ツリーを見ていると本当に幸せな気持ちになってくるし、クリスマスって「他の人の喜ぶ顔が見たい!いいことをしたい!」と思う気持ちが、そこら中にあふれてる気がして
 。
。我が家はモノ増やしたくない派なので、ツリーの購入はずいぶんと迷いましたが、子どもたちが目をキラキラさせて喜ぶ時期を逃したくないなあ、と思ってたら、友だちがツリーを買い替えるとのことで譲り受けました♪。まあ・・・男子の発想って・・・上二人は、ツリーの丸い球のような飾りは手榴弾のように投げて遊んでますけどね
 。三男はまだかわいくて、「おかあさんといっしょ~」って耳にピアスのようにぶら下げたりしてます
。三男はまだかわいくて、「おかあさんといっしょ~」って耳にピアスのようにぶら下げたりしてます 。
。さて、そんな子どもたちが大好きな楽しい絵本、ポップなクリスマス絵本がこちら↓

『おおきいツリー ちいさいツリー』ロバート・バリー作・絵 光吉夏弥訳 大日本図書
ウィロビーさんのお屋敷に見たこともないような大きなツリー(生木)が届きます。ところが、大きすぎて天井につっかえてしまうんですね。そこで、先の方をちょんぎっちゃう。ちょんぎられた先は小間使いのアデレードの元へ・・・ところが、アデレードにとっても先が大きすぎて、またちょんぎってゴミ箱に捨てておくと今度は見つけたのは庭師のチム。ここでも、先っぽはちょっといらないように感じて、ちょんぎられ外へポーン。それを動物たちが次々に見つけて・・・同じことが繰り返されていきます。さあ、最後に見つけたのは一体誰でしょう?
何がいいって、見つけた人(動物)たちが、み~んな幸せな気もちになるところ
 。繰り返しのリズムも子どもたち大好きですよね。明るくて、楽しくて、ポップなクリスマス絵本です♪
。繰り返しのリズムも子どもたち大好きですよね。明るくて、楽しくて、ポップなクリスマス絵本です♪こういうポップなのも好きですが、先日ご紹介した『ちいさなもみのき』のような地味な、厳かな絵本もやっぱり読みたいもの。私が大好きなのはコチラ↓

『聖夜のおくりもの』トリシャ・ロマンス作・絵 中村妙子訳 岩波書店
大工のおじいさんと村人たちとの温かな交流を描いたもので、手元に置いて何度も眺めたくなる美しい絵本
 。信仰深いおじいさんに、ああクリスマスってお祭り騒ぎじゃなくて、キリストの生誕を心から喜ぶ日なのよね、と思い出させられます
。信仰深いおじいさんに、ああクリスマスってお祭り騒ぎじゃなくて、キリストの生誕を心から喜ぶ日なのよね、と思い出させられます 。いままで人のための家ばかり建ててきたおじいさんが、いよいよ自分の家作りにとりかかるのですが、このおうちの素敵なことといったら
。いままで人のための家ばかり建ててきたおじいさんが、いよいよ自分の家作りにとりかかるのですが、このおうちの素敵なことといったら 。村人たちの協力がまたいいんですねえ。おじいさんがいかに人徳があったかが伺えます。そして、おじいさんがみんなに内緒で作っている木彫りの人形の美しいこと。現代っ子ボキャブラリーの次男は「ヤバイ!ヤバイ!おじいさん上手すぎ!これ、チョーやばい!」を連呼
。村人たちの協力がまたいいんですねえ。おじいさんがいかに人徳があったかが伺えます。そして、おじいさんがみんなに内緒で作っている木彫りの人形の美しいこと。現代っ子ボキャブラリーの次男は「ヤバイ!ヤバイ!おじいさん上手すぎ!これ、チョーやばい!」を連呼 。現代っこにも美しいものは地味でも静かでも響くんでしょうね
。現代っこにも美しいものは地味でも静かでも響くんでしょうね 。大人が読むと、堅実、誠実でなんて美しい生き方なんだろうとしみじみ思わされる絵本です。
。大人が読むと、堅実、誠実でなんて美しい生き方なんだろうとしみじみ思わされる絵本です。










 。
。 。外国の物語だということを忘れて思わず感情移入しちゃいます。
。外国の物語だということを忘れて思わず感情移入しちゃいます。 。こういうのやっちゃってるよね~
。こういうのやっちゃってるよね~ 。それが、同居することによって、ヨシはハっと本来のペースに気付かされるんですね。一緒にノロノロ散歩していると・・・
。それが、同居することによって、ヨシはハっと本来のペースに気付かされるんですね。一緒にノロノロ散歩していると・・・ 。子どもに対して寛容でなくなってきていて、自分たちの生活スタイルが大事
。子どもに対して寛容でなくなってきていて、自分たちの生活スタイルが大事 。ところが、ひいばあが漏らしてしまって、それを必死で隠そうとしたとき手伝いにきていた祖母がこういうんです。
。ところが、ひいばあが漏らしてしまって、それを必死で隠そうとしたとき手伝いにきていた祖母がこういうんです。


 。それはもはやDVと呼べるレベルで、もうお手上げ!!!ってなり、そのエネルギー何かほかのことにいかせないか?と探したのが武道でした
。それはもはやDVと呼べるレベルで、もうお手上げ!!!ってなり、そのエネルギー何かほかのことにいかせないか?と探したのが武道でした 。
。 。空手もいいけれど、他人さまの靴そろえるところから始めるところとか、本当の強さって相手より優位に立つことではないよね、ってことを教えてもらいたくて少林寺にしたんでした。じいじも一緒に始めて、祖父孫の絆もますます強まりました
。空手もいいけれど、他人さまの靴そろえるところから始めるところとか、本当の強さって相手より優位に立つことではないよね、ってことを教えてもらいたくて少林寺にしたんでした。じいじも一緒に始めて、祖父孫の絆もますます強まりました 。いや、だって夫が一緒に来てっていうから・・・たまには夫孝行もしないとネ。地ビールめちゃめちゃ美味しかったなあ
。いや、だって夫が一緒に来てっていうから・・・たまには夫孝行もしないとネ。地ビールめちゃめちゃ美味しかったなあ 。
。

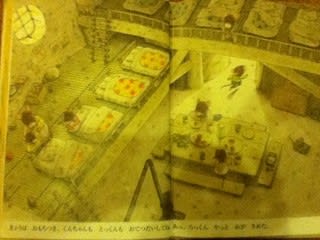
 。心に憧れの場を持てるって、いつしかそれが原風景になっていって、原点になり心強いこと。しかも、こ~んな素敵な場を選んだ長男センスいい
。心に憧れの場を持てるって、いつしかそれが原風景になっていって、原点になり心強いこと。しかも、こ~んな素敵な場を選んだ長男センスいい 。所有しなくてもいいや、図書館で借りればいいや、って。その頃は知らなったんですね~。本がどんどん絶版になっていくこと・・・
。所有しなくてもいいや、図書館で借りればいいや、って。その頃は知らなったんですね~。本がどんどん絶版になっていくこと・・・
 。
。 。
。 (こういうのがまたできるようになる日が来ただなんて嬉しい
(こういうのがまたできるようになる日が来ただなんて嬉しい 」って、まるでこの日が人生最後のような感覚を味わいました(笑)。音は色んな世界に連れて行ってくれる魔法ですね
」って、まるでこの日が人生最後のような感覚を味わいました(笑)。音は色んな世界に連れて行ってくれる魔法ですね 。明るく楽しいのも好きなのですが、キリスト教の環境で育ったためか、私にとってのクリスマスは、日本の“恋人たちのクリスマス”や“親子パーティークリスマス”でもなく、もっと静かで厳かなものなんですね。だから、こんな絵本を読みたくなります。↓
。明るく楽しいのも好きなのですが、キリスト教の環境で育ったためか、私にとってのクリスマスは、日本の“恋人たちのクリスマス”や“親子パーティークリスマス”でもなく、もっと静かで厳かなものなんですね。だから、こんな絵本を読みたくなります。↓