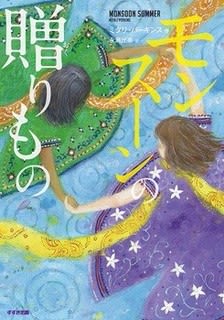
『モンスーンの贈りもの』ミタリ・パーキンス作 永瀬比奈訳
鈴木出版 318頁 2004年(原書初版)2016年(翻訳初版)小学校高学年から
これは好き!!!
瑞々しい、こういう児童文学に出会うと嬉しくなってしまう
 。
。≪『モンスーンの贈りもの』あらすじ≫
インド生まれの母とアメリカ人の父をもつカリフォルニアの15歳の少女ジャズ。
背が高くて体格がよいことに強い劣等感を抱いているところに、幼なじみに恋してることに気付いてさらに苦しむ。
弟は慈善家で素晴らしい母に似ているのに、自分は全然似ていないこともコンプレックスだったところに、自分の慈善活動において裏切り行為を受け、ジャズの心はちぢこまっていた。
ところがある夏、母が育った孤児院のあるインドのプネで、一家はひと夏をすごすことに。
自分の仲間だと思っていた父の変化、お手伝いのダニタとの友情、盲目の幼児マヤとの交流、カタックという踊りや、やさまざまな経験を経て成長していくジャズ。
モンスーンの魔法、そして、ジャズの秘密。さわやかな秀作!
時代は現代。なので、メールもあるのに、プネでは接続環境が悪くて、幼なじみのスティーブとは時間差がある手紙でのやりとりなんです。これがいいんだなあ
 。ギリギリ手紙世代の私は、自分の留学時代思い出してキュンキュンしちゃいましたよー(笑)。手紙には画面上では伝わらない思いが乗っかる気がするんです。ブログやネット記事では乗っからない思いが、書籍には乗っかるように
。ギリギリ手紙世代の私は、自分の留学時代思い出してキュンキュンしちゃいましたよー(笑)。手紙には画面上では伝わらない思いが乗っかる気がするんです。ブログやネット記事では乗っからない思いが、書籍には乗っかるように 。
。【ここがポイント】
・劣等感を抱いてる人に読んでほしい!
・人種差別&アイデンティティについて考えさせられる
・10代でも自分で小規模ビジネス立ち上げるところにワクワク
・異文化交流(食べ物美味しそう
 )&友情がさわやか
)&友情がさわやか
・幼なじみとの恋の行方にキュンキュン
 (少女漫画的?)
(少女漫画的?)どのポイントもね、それほどドラマチックに書かないんです。さらっと。でも、確かに何かが残る、種を蒔いてくれる感じ
 。
。例えば人種差別。
ジャズは白人の父に似ていて色が白く、母親やダニタは下層階級であることを示す色黒。
で、一緒にいると母やダニタは使用人と思われてしまうんですね。ジャズはこんなのおかしいと胸が痛みます。でも、“どおしてなのよおおおおおお(怒)
 ”って憤慨するほどでもないのが、かえってチクッと胸に刺さる。
”って憤慨するほどでもないのが、かえってチクッと胸に刺さる。ちなみに原書はこんな感じ↓


日本版が一番内容をよく表してるかな。ってか、眼力!!!怖すぎ(笑)。
印象に残ったエピソードはたあくさんあって(食べ物もおいしそう
 )、とてもこの物語の魅力は伝えきれないのですが、一つ思ったのはこれ読んでインドの印象変わる人多いじゃないかな?ってこと。
)、とてもこの物語の魅力は伝えきれないのですが、一つ思ったのはこれ読んでインドの印象変わる人多いじゃないかな?ってこと。インドの印象:汚い・カオス・貧困・物乞いがしつこい・喧騒・警官ですら観光客をだます
っていうイメージの人多いんじゃないでしょうか?・・・私はそう思ってました
 。
。でもね、自分自身もマザーテレサの施設にボランティアに行ったとき感じたのですが、インドには祈りにも似た静寂があるんです
 。
。『インド古代史』を書いたD.D.コーサンビーは“喧騒の中の静寂”と表現しましたが、まさにそんな感じ。
主人公のジャズは、インドには文化の中心にはおもてなしの心があってー誰もがそれを実践するすべを知っている。と述べています。
インドの美しい心
 。
。孤児院を訪ねたとき、小さな男の子が私のバンドエイドを見て(たいした傷じゃない)、“痛い?”と心配そうに聞いて何度も撫でてくれたこと
性的被害にあって狂気に陥ってしまった女性たちが収容されているところで、ある女の子が私の髪に花を挿してくれたこと、そしてくるくる踊ってくれたこと
思い出しました。
ダニタが自力で道を開いていくところは、『家なき鳥』(紹介記事はコチラをクリック。こちらもおススメ!)とも似ていますが、ダニタは雇われるのではなく、自分でビジネスするところがたくましい
 。
。慈善家で素晴らしいママのようにはいかないジャズとパパ。でも、パパはジャズより先に一歩を踏み出し、隠れるのをやめます。
「ママみたいなスケールでほかの人の人生に影響を与えられないかもしれないが、ぼくだって変化を起こす何かをしてる。それは自分にぴったりに合ったなにかだ」
ぜひジャズの目を通して見た美しいインドに触れてほしいなあ
 。
。そして、自分も自分のやり方で何か行動してみたくなる、背中をそっと押してくれる素敵な物語でした
 。
。












 。私自身のインド経験はたったの10日間(ハマる人は数か月から数年単位で滞在してますからねー)。しかもカルカッタしか行ったことがなく、そのほとんどをマザーテレサの施設でのボランティアに費やしたので、インド滞在経験があるといっていいのかどうか分からないのですが・・・。それでも、混沌とした町にあふれるスパイスの匂い、目の覚めるような色彩、日本では見られない貧富の差、むわっとむせるような熱風&土埃、衝撃の茶色の海、などなどが鮮明に甦ってきて、懐かしい思いでいっぱいに
。私自身のインド経験はたったの10日間(ハマる人は数か月から数年単位で滞在してますからねー)。しかもカルカッタしか行ったことがなく、そのほとんどをマザーテレサの施設でのボランティアに費やしたので、インド滞在経験があるといっていいのかどうか分からないのですが・・・。それでも、混沌とした町にあふれるスパイスの匂い、目の覚めるような色彩、日本では見られない貧富の差、むわっとむせるような熱風&土埃、衝撃の茶色の海、などなどが鮮明に甦ってきて、懐かしい思いでいっぱいに 。
。 。
。 (←これなかなかできないこと!)。コリーってこういう子なんです。性格はちょっと違うけれど、時代や環境の制約に負けないっていう点では、
(←これなかなかできないこと!)。コリーってこういう子なんです。性格はちょっと違うけれど、時代や環境の制約に負けないっていう点では、 。「未亡人の家」を運営しているお金持ちの夫人のように、徳の高い人もいるのも事実で希望。コリーが自立して、女性としての幸せも手に入れて、どんどん幸せになっていくラストはとっても爽やか
。「未亡人の家」を運営しているお金持ちの夫人のように、徳の高い人もいるのも事実で希望。コリーが自立して、女性としての幸せも手に入れて、どんどん幸せになっていくラストはとっても爽やか