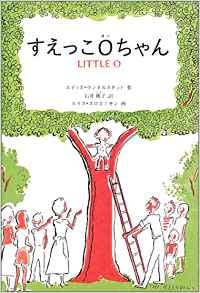『さすらいの孤児ラスムス』アストリッド・リンドグレーン作 尾崎義訳 岩波書店
今日の一冊は、小学生のころ好きだったコチラ。
『長くつしたのピッピ』でお馴染みのリンドグレーンによるもので、ロードムービーにしたい一冊
 。
。このお話は小学生当時ホーント大好きで、どのくらい好きか、って小学校の卒業文集の将来なりたいものの欄に‟『さすらいの孤児ラスムス』に出てくるような風来坊になりたい”って書いたほど。
ほかの子はケーキ屋さん
 ♪とかお花屋さん
♪とかお花屋さん とか書いていたのにね
とか書いていたのにね 。『さすらいの孤児ラスムス』知ってる人も、風来坊という言葉知ってる人もいなかっただろうなあ(笑)。
。『さすらいの孤児ラスムス』知ってる人も、風来坊という言葉知ってる人もいなかっただろうなあ(笑)。そしてね、そんなにも好きだったのに、ナント!!!・・・内容全然覚えてなかったんです
 。そんなもん。というわけで、三十年ぶり?に読み返してみました。
。そんなもん。というわけで、三十年ぶり?に読み返してみました。«『さすらいの孤児ラスムス』あらすじ》
孤児院をぬけだした少年ラスムスは、アコーディオンをかなでる陽気な風来坊オスカルに出会い、いっしょに旅をします。ところが、ラスムスがピストル強盗事件の現場を見てしまったことから、ふたりは犯人に命をねらわれてしまいます。小学4・5年以上。(BOOKデータベースより転載)
え!?待って待って?これも絶版なの~???
うーむ。でも、読むと時代を感じます。今の子たちは感情移入できないかなあ・・・?ラスムスは孤児院では問題児だったり、強盗事件に巻き込まれたりするんですけど、全体的にどこかのほほんとしてる。今の時代みたいにギスギスしていないんですね。この程度、問題児じゃなくて、愛おしいし!
小学校3年生くらいから6年生くらいまでの間、リンドグレーンの書く物語に夢中でした
 。といっても、内容をきちんと覚えているのはピッピくらいで、どれも‟なんかワクワクする!”‟おもしろかった~!”ということしか覚えてないのだけれど。
。といっても、内容をきちんと覚えているのはピッピくらいで、どれも‟なんかワクワクする!”‟おもしろかった~!”ということしか覚えてないのだけれど。子どもの頃って、作者がどんな人生歩んできた人か、どんな活動しているか、なんて興味ないですよね。だから、リンドグレーンについて知ったのは大人になってから。しかもわりと最近。2年前かな?NPO図書館とともだち・鎌倉がリンドグレーン展を展示していたのを見て、初めて熱心な平和や人権活動家だったことなど知ったんです
 。
。驚いたのは、18歳で未婚の母となっていたこと
 。当時はね、もう大スキャンダルですよ、これ。小さな村でしたし。お相手は30歳以上も年の離れた人だったとか。決して明るいだけの人生だったわけじゃないんです
。当時はね、もう大スキャンダルですよ、これ。小さな村でしたし。お相手は30歳以上も年の離れた人だったとか。決して明るいだけの人生だったわけじゃないんです 。
。子どもの頃は、「わたしたちが遊び死にしなかったのは、不思議なくらいでした」と自身で語っているように、遊んで遊んで笑い転げた、幸せな子ども時代を過ごしたリンドグレーン。まさに『やかまし村の子どもたち』ですね。ところが、10代に入ったとたん、急に「もう遊んでいられない」と気づいてしまうのです。そして、闇の時代、10代で未婚の母という苦労の時代へ。リンドグレーンにも、‟さんねん寝たろう”の時期があったんですね!
養母に預けていたラッセをようやく引き取れたのはラッセが3歳のとき。その後、職場の上司と結婚し、娘カーリンも生まれます。このカーリンがたくさんお話をねだったことから、ピッピなどが生まれてくるのです。家庭の主婦となったアストリッドは、楽しかった子ども時代を再び手に入れ、黄金期へ
 。でも、ただただおもしろおかしいだけじゃない。常に社会の弱者への温かいまなざしを忘れず、おかしいと思ったら社会に立ち向かって、闘っていったんです。
。でも、ただただおもしろおかしいだけじゃない。常に社会の弱者への温かいまなざしを忘れず、おかしいと思ったら社会に立ち向かって、闘っていったんです。幸せな幼少期ってホント大事なんだな。その後生き抜く力になるんだな。そんなリンドグレーンの子ども時代を知ることのできる、こちらの一冊もおすすめです↓












 。ぜひ図書館で。私自身は、『剣と絵筆』よりもこちらのほうが、のめりこんで一気読みだったので、読書会でみなさんが、‟なかなか感情移入できなかった、誰に共感して読めばいいのか分からなかった”という感想が多かったことが意外でした。
。ぜひ図書館で。私自身は、『剣と絵筆』よりもこちらのほうが、のめりこんで一気読みだったので、読書会でみなさんが、‟なかなか感情移入できなかった、誰に共感して読めばいいのか分からなかった”という感想が多かったことが意外でした。 。物語がどう展開していくかワカラナイ面白さもあり、個人的には、すごく好きな世界観でした。
。物語がどう展開していくかワカラナイ面白さもあり、個人的には、すごく好きな世界観でした。 。
。 。それでも、なんとか魅力を探り出してみましょう!
。それでも、なんとか魅力を探り出してみましょう! 。おまえはお情けで生かしてもらってるんだ、恥じを知るなら、さっさとどこかへ行け、死にぞこない!ってののしるんですよ?それもしょっちゅう!
。おまえはお情けで生かしてもらってるんだ、恥じを知るなら、さっさとどこかへ行け、死にぞこない!ってののしるんですよ?それもしょっちゅう! 。
。

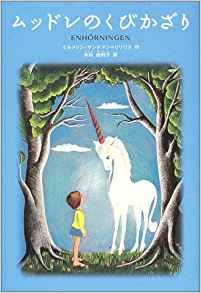
 。こ・れ・は、女の子が好きそう
。こ・れ・は、女の子が好きそう 。私自身は小学校3年生のときに読んだのですが、あまり覚えてなかったので、30数年ぶり(!)に再読でした。
。私自身は小学校3年生のときに読んだのですが、あまり覚えてなかったので、30数年ぶり(!)に再読でした。 。ただ、ふわふわっとしたファンタジーなので、夢中になるか、苦手か二手に分かれるかな
。ただ、ふわふわっとしたファンタジーなので、夢中になるか、苦手か二手に分かれるかな 。
。 。
。