
『物語の役割』小川洋子著 ちくまプリマ―新書
物語について小川洋子さんが語った講演を元にまとめたもので、とっても読みやすいです。
第一部:物語の役割
第二部:物語が生まれる現場
第三部:物語と私
という構成で、第三部には私も大好きな『トムは真夜中の庭で』をはじめとした児童文学も登場してきますよ~
 。
。小川洋子さんといえば『博士の愛した数式』しか読んだことはないけれど、あれは数字アレルギーの私に数字の世界の美しさを見せてくれたという点で衝撃的でした。無機的だと思っていた世界に、こんな美しい世界が広がっているのか、と。この『物語の役割』の中では、いかにして『博士の愛した数式』という物語が生まれたのかという、物語の生まれる裏側にも触れられていて興味深いです。
私が好きだなあと思う物語の作家さんはみな物語が「降りてきた」ようなことをいうんですよねえ。上橋菜穂子さんしかり。イメージがまず目に浮かんで、それからは何かに操られるかのように書かされて、時として自分が意図した方向とは違う結末になる、と。
「作家も現実のなかにすでにあるけれども、言葉にされないために気づかれないでいる物語を見つけ出し、鉱石を掘り起こすようにスコップで一生懸命掘り出して、それに言葉を与えるのです。自分が考えついたわけではなく、実はすでにそこにあったのだ、という気持ちになったとき、本物の小説が書けるのではないかという気がしています」
と小川洋子さんは述べていらっしゃるけれど、そういう物語が普遍性を持つんだと思います。
「作家から何かを仕掛けるというのではなく、向こうからやってきたものを受け止めただけ、ストーリーは作家が考えるものではなくて、実は既にあって、それを逃さないようにキャッチするのが作家の役目である」
と述べられてますが、テーマがありありと分かるもの、作者の意図が読め過ぎてしまうものってなんだか白けてしまうんですよねえ
 。これ書くと叩かれそうだし、私の思い違いかもしれないけれど・・・、例えばゲド戦記シリーズ4巻の『帰還』は前作3巻と比較してあれ?って思ったんです。作者の書きたいことが前に出過ぎてるって。ストーリーを拾いに行ったのではなくて、作者がしかけてるな、って。だから好きになれませんでした(はあ、ドキドキ!書いちゃった
。これ書くと叩かれそうだし、私の思い違いかもしれないけれど・・・、例えばゲド戦記シリーズ4巻の『帰還』は前作3巻と比較してあれ?って思ったんです。作者の書きたいことが前に出過ぎてるって。ストーリーを拾いに行ったのではなくて、作者がしかけてるな、って。だから好きになれませんでした(はあ、ドキドキ!書いちゃった )。
)。あと、YA(ヤングアダルト)に分類される本もどこがいけないってわけじゃないけれど、どこか狙った感が透けて見えて自分にはしっくりこないことが多いのですが、作者がしかけることが多いからなのかも、と思い当たりました。
第三部の、幼い頃小川洋子さんがどう物語から影響を受けていたかのお話も興味深いです。
「本を開くと本の世界へ行って、閉じるとまたこちらの世界へ戻ってこられる。本を開くというのは、あっちに行ったりこっちに行ったり自由に繰り返すことなんだ」
って。当時個室は与えられてなかったそうですが、本箱の中に自分だけの部屋を持つことができた、って素敵じゃありませんか
 。そして、不器用でボタンがうまく留められない自分に対して、「ボタンちゃんとボタンホールちゃん」という物語を考え、ボタンがうまくはめられないのは、ボタンちゃんが冒険に出ているからで自分のせいではないという言い訳を思いついた、と。自分の内側に物語を据えることによって、外側の現実のありようを変化させた、と述べられていますが、今の子どもたちには物語が足りないといわれる意味が分かるような気がします。自殺された息子さんに対して柳田邦夫さんの作り出した物語も印象的でした。自分の中に物語があれば、人は色んなことを乗り越えていけるんですよね。
。そして、不器用でボタンがうまく留められない自分に対して、「ボタンちゃんとボタンホールちゃん」という物語を考え、ボタンがうまくはめられないのは、ボタンちゃんが冒険に出ているからで自分のせいではないという言い訳を思いついた、と。自分の内側に物語を据えることによって、外側の現実のありようを変化させた、と述べられていますが、今の子どもたちには物語が足りないといわれる意味が分かるような気がします。自殺された息子さんに対して柳田邦夫さんの作り出した物語も印象的でした。自分の中に物語があれば、人は色んなことを乗り越えていけるんですよね。









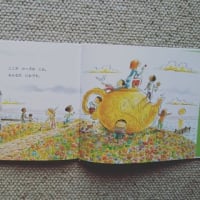

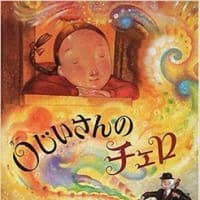
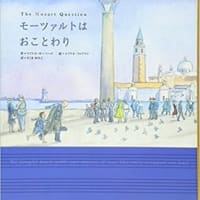
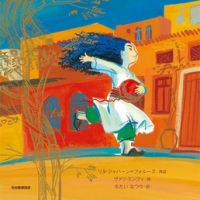
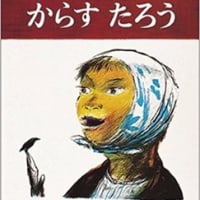
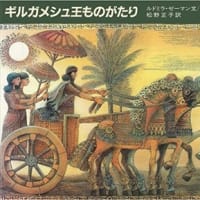



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます