2008年11月現在、日本における広汎性発達障害[PDD](広義の意)児者は、日本自閉症協会の推定で120万人と言われています。
2002年度の文部科学省の調査による軽度発達障害児は通常学級在籍児の6.3%に上ることが明らかになりました。
2008年5月1日時点での統計局による人口確定統計上、5歳~19歳児童・学生の人口は1,803万6,000人。その6.3%と仮定して、113万6,268人の小学生、中学生、高校生が何らかの問題を抱えていることになります(中高生はより人数が少なく、成人を含めると妥当な数値だと思います)。
対する児童神経科専門医のうち発達障害専門医は、2008年7月現在314人。
一人の医師が二週間に一度各々の患者を診察するとして、受け持ち患者数273人。
週5日勤務として1日あたり27人。
人口統計データの0歳~4歳の人口542万人。うち6.3%の34万1,460人を初診患者数と換算すると、一人当たりの受け持ちは1,087人。1日あたり約4人の計算となる。
一日の診察時間8時間、初診患者に30分の診察として、残り27人の診察時間は13分(かなりリアリティのある数値に落ち着きましたね)。
再診患者が一日に4人ずつ増えていくと考えると、1年後には単純計算として一日1,114人の再診と、4人の初診患者を診る事となる。
(仮に初診者を1/4にしても299人の再診)
計算上、一人当たりの診察時間:19秒(1/4で1分弱)
[あ、再々診とか考えていったら・・・ミクロの決死圏といった感じですね・・・]
(ま、そういうわけにはいかないと思いますので、何らかの調整が入ると思いますが)
(というか、通院はしなくてもいい児童が多いというのもあるかも知れませんね)
2004年度の文部科学省統計、全国の総大学生数は280万9,592人。
そのうち医学部卒医師国家免許取得者は近年約7,700人と言われています。
医師総数としては約3,500人の増加。
2006年統計の総医師数27万7,927人。うち発達障害専門医は0.1%。
年間の発達障害専門医純増加数3.5人。
焼け石に水状態ですね・・・
2005年の発達障害者支援法制定当時、5歳だった児童が成人する2019年までこの状態が続き、現在の療育・支援体制で一定の効果が得られ、年齢を重ねる毎に通院者数が減ると考えても“医師の負荷は推して知るもの”だと思います。
これは何も医師だけに関したことではないのは明白な事実で、
臨床心理士総数は、約1万5,000人。
臨床発達心心理士は重複でさらに少数(と考えてまず間違いはないでしょう)。
言語聴覚士、作業療法士、介護福祉士、ケースワーカーetc・・・
高齢化社会が目の前に迫っているのに尚かつこの状態では、皆さん相当のオーバーワークをなさっていらっしゃるでしょうね。
正直に言うと、この「発達障害」という概念は、少々いきすぎた所があるのは否めませんが、舵を切ったからには支援者にとっても当事者にとっても“無理のない”システムができることを願っています。
広汎性発達障害児の場合、医療・福祉・教育が一体となってサポートする形が望まれると思いますので、既成概念を超えた様々な分野の方の協力体制、当然としての一定の社会認知は整えていければ、と思いますね。
医療・福祉・教育分野は何かときな臭い話などがあったりしますが、いち成人当事者としては他者に余計な負担をかけず道を拓くこと、これからの子供達には健やかに日々が過ごせますように。
ちょっとショッキングな統計学的検証になってしまいました。













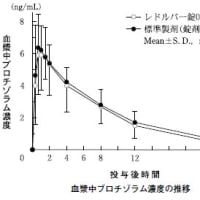

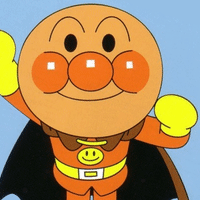
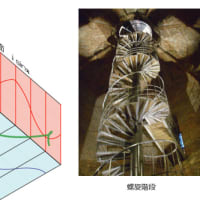

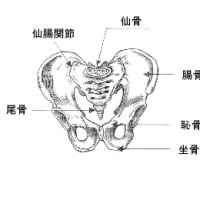
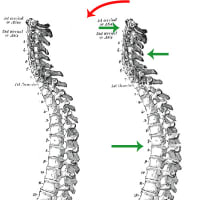
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます