長文で失礼いたします
この夏、東ヨーロッパのルーマニアとブルガリアに行ってきました。今日は、この両国で見てきたことをもとに、何を感じ、何を考えたかを中心に書いてみたいと思います。
まずルーマニアに入りました。首都のブカレストの町です。泊まったのはブカレストと、この国の第二の都市ブラショフでした。この間、避暑地でもあり、美しいペレシュ城で有名なシナイアと、もう一つ、小説のドラキュラの城のモデルになったブラン城に行きました。
ルーマニアにはいくつもの世界遺産があります。古いキリスト教の教会がいくつも世界遺産になっています。先住民ダキア人のローマに対抗した要塞もあります。首都ブカレストの町とドナウ川のデルタも世界遺産です。残念ながら、この沢山の世界遺産の中でブカレストだけしか見られませんでした。
ブカレストの町は20世紀の初めにはバルカンの小パリと言われるほどの美しい町だったといわれています。しかし実際に歩いてみると、そのような観賞に値するような町ではありませんでした。旧市街の建物は黒ずんで汚く、窓からは洗濯物がはためいていました。旧市街から少し離れると5,6階建てくらいのアパートが多く見られました。聞くところよるとチャウシェスク時代に古い建物を取り壊し画一的な高層住宅を作ったということです。私の見る限り、昔の美しい町の面影はありませんでした。町の景色を見る限り貧しい国と言う印象でした。町の景観という点ではブカレストよりブラショフの方がよかったと思います。
町の景色と対照的だったのは「国民の館」と呼ばれる建物でした。悪名高いチャウシェスク大統領が作った建物、宮殿と言ってよい建物です。建物の大きさはアメリカの国防総省ペンタゴンに次ぎ世界第二位の大きさだそうです。見るからに威圧的な建物です。中にも入ってみました。部屋は3000室あるというバカでかい建物です。公開されているのは一部だけです。その一部を歩くだけでも半日かかりました。内部は大理石をふんだんに使い、シャンデリアには一個5トンとか3トンとかいうものもありました。暖冷房設備はあまりととのっていないようですが、暖房のラジエーターのカバーが金メッキされたものまでありました。カーペット、カーテンなども絹製の特大の重厚なものが使われていました。
これらの調度品だけでなく大理石に至るまですべてルーマニアの国産材料だといわれています。絹製品のようにもともとルーマニアで作っていないものは、カイコの養殖から始めたそうです。その点だけは感心もしましたが、呆れもしました。
この宮殿「国民の館」を作るために、国民には重税が課されただけでなく、労働力の提供も国民にとって大きな負担になったようです。このような負担が1989年のルーマニア革命の原動力の一つになったとのことでした。国民生活を省みないで権勢を誇った独裁者は逆に国民から捨てられてしまいました。
ご存じのとおり、ルーマニアでは、ソ連崩壊に先だって1989年に革命がおこり、チャウシェスク大統領は夫人とともに銃殺刑に処されました。このためチャウシェスク自身は「国民の館」の完成を見ていません。
ルーマニアでもう一つ気になったのは農村風景でした。ルーマニアの南の方にあるブカレストから山岳地帯にあるシナイアに向かう途中は長時間農村を通ります。長いバス旅行の間、外を眺めていると色々なことに気が付きます。
この途中の農地をみると、そこに植えてあるのはほとんどトウモロコシ、ひまわりです。もう一つは何も植えてない土地です。この空き地には何か刈り取ったような跡があるところがあります。ルーマニアは小麦の輸出国ですから、八月と言う季節を考えると小麦を刈り取った後かもしれません。
意外だったのは、一枚一枚の畑が広いことです。どこを見ても何町歩もあるように見えました。経営規模は大きいようです。しかもどの畑にも人の姿が見えませんでした。またトラクターなどの機械もありません。牛の姿も見えません。なんとなく不思議な光景でした。
道路わきの建物は二種類に分かれました。一つはトタン葺きの古い家です。決して物置ではなく、人が住んでいるのです。もう一つの種類は新築、瓦葺の家で、日本で見かけるのと変わりありません。対照が面白くて見ていました。
帰国してから調べて分かったことですが、ルーマニアは、EU、特に中欧、東欧では主要な農業国です。しかもその構造をみると、1000ha以上の農地を持つ農家、これは全農家の0.1%にすぎないのですが、一戸当たり2100haをもち、全農地の29%を持っていることが分かりました。一方全農家の85%は5ha以下の農地しか持っていません。この85%の農家の全部でも、全農地面積の29%を持っているにすぎません。平均2.4haだそうです。大農場と小農経営の二極化しています。革命後集団化されていた農地を元の持ち主に返したとも言われています。そうだとすると市場で取引されて集中されたのでしょうか。強制的な集団化とは別の新しい問題が起こっているようでした。
ルーマニアで気になったのは今お話しした国民の館と、農村風景の二つでした。この二つは第二次大戦後、枢軸国から、ソ連の衛星国になり、革命でまた大きな社会変革を経験したルーマニアの歴史と深く結び付いているのだと思います。
ルーマニアの次に行ったのはブルガリアでした。ブルガリアで泊まった街をあげると、首都ソフィアのほかに、プロブディフ、アルバナシです。
ブルガリアで意外だったのは、キリスト教の教会が世界遺産として多数残っていたことでした。圧巻はソフィア近郊の山の中にあるリラの僧院でした。聖母生誕教会とそれを囲む外陣、修道僧たちの宿舎は見事な景観を作っていました。同じくソフィアの近くにあるボヤナ教会には中世のフレスコ画がありました。私たちを案内してくれたブルガリア人のガイドは「ルネッサンスを先取りしたものだ」「ルネッサンスはブルガリアで始まった」と得意げに話していた。ソフィアには聖ペトカ地下教会もありました。
それにしても500年近いトルコ支配の時代にキリスト教が生き延びたことに驚きました。日本では厳しい禁教令のもとで徹底的に弾圧され、わずかに隠れキリシタンという形でしか残れなかったこととの違いを考えさせられました。当たっているかどうか分かりませんが、日本で禁教令をしいたのは、強力な武器や船を持っているスペイン、ポルトガルの侵略を怖れたせいではないでしょうか。一方ブルガリアでは侵略したのはトルコの方ですから、この国で数百年の歴史を持っていた宗教、キリスト教に対して、むしろ融和的に振舞ったのではないかと考えてみました。
ブルガリアには、古代遺跡が沢山あります。首都ソフィアの中心部に何か所も遺跡発掘現場があり、どれがどの時代のものか、聞いていて混乱するほどです。ソフィアのホテルの中庭も遺跡でした。大統領府の裏も遺跡でした。プロブディフでもいくつもの遺跡を見ました。
バラで有名なカザンラクにはトラキア人の墳墓と言われる世界遺産の古墳があります。紀元前3世紀ころのものだと言うことです。フレスコ画の壁画が有名です。この国はローマ以前からローマ時代にかけてもさまざまな民族が行き交ったようです。
ここで付け加えますと、トラキア人の墓があるカザンラクはバラで有名です。バラの香油をとり世界中に供給しているそうです。ここのバラ祭りが有名ですが今回はバラの季節ではなかったので、見ることができず残念でした。
ブルガリアでのもう一つの経験を紹介します。ヴェリコ・タルノヴォというブルガリアの古い都があります。日本でいえば京都か奈良にあたるのかもしれませんが、そういう町があります。その近くにアルバナシと言う村があります。私たちはこのアルバナシのホテルに泊まりました。このホテルが社会主義ブルガリアの国家評議会議長の夏の家だったと言うことでした。このような由緒あるホテルなので、さぞかし豪華だろうと期待したのですがそうではありませんでした。なるほど外観は大理石を豊富に使った立派なものでした。しかし機能性と言う点ではお粗末でした。部屋のドアはガタピシして開け閉めに苦労しました。ドアの鍵の開け閉めも慣れるまでが大変でした。洋服ダンスも開け閉めにてこずり、使う気になりませんでした。普通の大工仕事が出来ていないのです。私だけがそう感じたわけではありません。同行者が皆そのようなことをつぶやいていまいた。
このホテルで、ルーマニアから買ってきたワインを飲もうと思って、栓抜きを探しましたがありません。添乗員に持ってくるように頼みました。しばらくすると、添乗員がベルボーイを連れてきました。彼は栓抜きを持っていますが渡してくれません。自分で開けて持ち帰るのだといいます。ホテルに栓抜きが1本しかないのでしょうか。不思議なことがあるものだと思い、添乗員と二人で笑いました。ひょっとしたら日本人に危険物を渡すのはあぶないと思ったのかもしれません。国中で最高級のところがこの調子です。昔から社会主義国の非能率と言うことが言われてきましたが、これがその実態なのかとよく理解できました。
ところで、ルーマニアとブルガリアは、バルカン半島の隣り合わせの国なので、同じだろうと考えられたのですが、トンでもない間違いでした。
まず文字も言語も違うのです。ルーマニアはローマ字、ブルガリアはキリル文字、ロシア語と同じ文字です。うっかりしていたのですが、行ってみて初めて知りました。そういえば昔、法学部の友人から聞いたことを思い出しました。東欧でもルーマニア語だけは特別な地位を占めていて、ラテン語に近い言葉だと言うことでした。ブルガリア語はスラブ系の言葉だということです。
ルーマニア、ブルガリア両国とも、数千年の歴史の間に他民族から支配を受けています。その影響をどのように感じているかということに興味がありましたが、短い旅行で簡単に知ることはできませんでした。しかしブルガリアでは少し感じ取ることができました。プロブディフの民俗博物館には生活用具や農具、それに住居の模型などが展示されていました。その中の部屋の様子を見ると西欧風とは違い、トルコ風と言ってよい作りでした。リラの僧院の司祭の部屋だった所も見ましたが、同じような印象を受けました。
どちらの国も数百年にわたってトルコに支配された国です。これに対する抵抗の歴史も伝えられているようです。ルーマニアでは山の上に要塞教会が点々とありました。世界遺産になっています。
ブルガリアでは、19世紀の露土戦争で帝政ロシアがトルコとたたかって解放されたことを記念するモニュメントが多いように感じました。ソフィアにはアレキサンダル・ネフスキー寺院と言う美しい教会があります。これは露土戦争の時に戦死した二十万人のロシア兵士を慰霊するものといいわれています。ほかにも露土戦争の激戦地の戦跡を記念することも行われているようです。ソ連時代を飛び越えて19世紀の露土戦争を記念すると言うのも面白く感じました。
もう一つはソ連や社会主義に対する感じ方です。ルーマニアでもブルガリアでもあちこちに社会主義体制からの解放を喜ぶモニュメントがありました。
私は国民の生の声が聞きたいと思いましたが、短期の旅行者には、むりでした。
この点でブルガリアのガイドが率直に語ってくれました。彼女は60歳くらいの恰幅のいい女性でした。レニングラードで日本語を学び、短期間東海大学に研修に行ったことがあるということでした。非常に上手な日本語を話しました。大学の先生だということでした。自分は共産党に入る気がなかったので教授になれなかったと言っていました。彼女は「働いても働かなくても給料が同じなのも気に入らなかった」とも言っていました。
そのガイドが案内の途中で、質問もされないのに、2度にわたって「社会主義の時代の方がよかった」といいました。理由はあまりはっきりしませんでしたが、言葉の端々から感じられるのは、社会保障の問題のようでしたし、もう一つは社会の競争が激化したことへの反発があったように見えました。彼女の他の話も加えて総合的に判断すると、今の社会の方がよいと思っているが、今の社会も辛いことがあり、昔を懐かしむこともあると受け取れました。
彼女はまた、社会主義時代の初代首相ディミトロフは、療養先のソ連で暗殺された・・・とも言っていました。これは事実かどうか分かりませんが、彼女自身はそう信じている様子でしたし、ブルガリア人に広く信じられているのではないかと感じられました。ブルガリア人のソ連に対する感情の表れかもしれません。
ルーマニアのガイドは、やはり奇麗な日本語を話す若い女性でしたが、まだ20代に見える若さで、社会主義時代のことを聞くのは無理でした。
わずかな期間でルーマニア、ブルガリアを見てきましたが、主として両国の社会を覗く旅になりました。いわゆる、ソ連流の「社会主義」を経験した二つの国を見てきての感想は、このような「社会主義」は願い下げだということです。
一言だけ付け加えて、日本の国の変革を考えると、ソ連流「社会主義」でもなく、現在の日本の「ルールのない資本主義」でもない社会、国民すべてが自分の能力を伸ばすことが出来る社会を展望したいと思います。
そのような社会をめざすために必要なこととして、一つは民主主義でしょう。チャウシェスクのような、あるいはスターリンのような独裁者を生み出さないためには国民の意思を反映できる政治制度が必要になります。特に政権交代が出来る制度が必要でしょう。











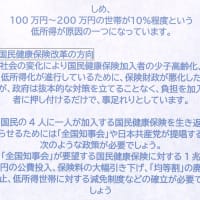
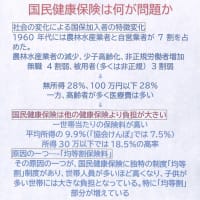
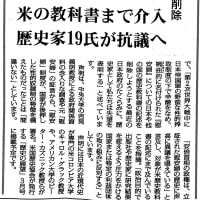





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます