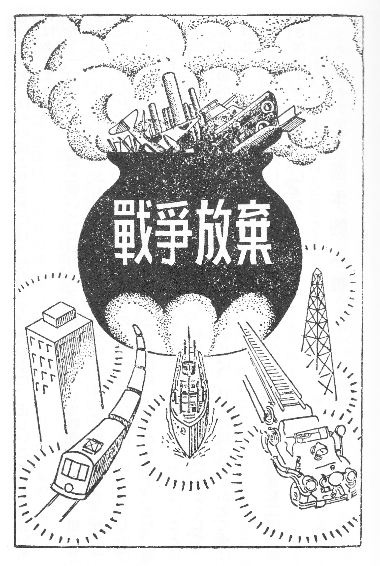韓流ブームなどで民間レベルでの交流が続いてきた日韓関係が、領土紛争の影響で、昨年来冷え込んでいます。今日はは領土紛争そのものではなく、ここ100年あまりの日韓関係、その不幸な関係を振り返って、現在の問題を考えてみたいと思います。
日韓併合まで
明治政府は、幕末以来欧米諸国が日本に押しつけた不平等条約を朝鮮に対して押しつけようとしました。明治8年(1875年)には武力を背景に朝鮮に治外法権をみとめさせ、関税自主権も奪いました。
明治37年(1904年)には第一次日韓協約をむすび、日本政府が推薦する日本人一人を財務顧問に、同じく日本政府が推薦する外国人一人を外務顧問にすることを認めさせました。
翌明治38年(1905年)には第二次日韓協約を結び、日本は韓国から外交権を剥奪しました。韓国の外交はすべて日本が行うことにしました。事実上日本の保護国にしたわけです。そうして韓国統監府(初代統監・伊藤博文)を設置しました。
さらに明治40年(1907年)には第三次日韓協約を押しつけ、高級官吏の任免権を韓国統監が掌握すること、韓国政府の官吏に日本人を登用できることなどが定められました。これによって、韓国の内政は完全に日本の管轄下に入りました。また非公開の取り決めで、韓国軍の解散・司法権と警察権の日本への委任が定められました。
このように、韓国にたいする支配力を強めていったうえで、明治43年(1910年)8月、「韓国併合に関する日韓条約」調印により日本は、韓国を廃して日本領として併呑したのです。
日韓併合により韓国の近代化が促進されたかのように言う人もいますが、武力による脅しで国そのものを奪い取って植民地にしたのです。
韓国国民の抵抗運動と日本による弾圧
こうした日本の進出、支配強化にたいして、日清戦争中の明治27年(1894年)10月頃より農民主体の義兵闘争が始まり、日露戦争中にも朝鮮半島南部を中心に義兵闘争が広まりました。1907年に韓国軍隊が強制的に解散されると、旧韓国軍の将兵たちの多くが蜂起して、農民義兵に合流し、反日義兵闘争は組織的な戦闘力を高めつつ韓国全土をおおいました。義兵の蜂起に手を焼いた日本軍は、村々を焼きはらい、ゲリラ闘争を続ける義兵を大量に殺害し、あわせて日本軍に非協力的な民衆もみせしめに殺傷しました。
日本人が間違えてならないのはこのような弾圧は日韓併合より以前から行われたということです。外国(独立国)の国内問題に対する内政干渉、軍事干渉だったのです。
三・ー独立運動
大正8年(1919年)3月1日、天道教、キリスト教、仏教指導者の呼びかけに応えて、朝鮮の人々が植民地支配からの独立をめざす運動を起こしました。3月半ばには運動は朝鮮全土に広がり、5月までの間に1.500回近いデモや騒動があり、延べ200万人の人々が参加したといいます。これにたいして日本政府は徹底的な弾圧を加えました。以後1年間で朝鮮の人々の死者は7,000人、負傷者は4万人、逮捕者は5万人近くに及びました。弾圧によって運動そのものは5月ごろには表向き終息を迎えました。
皇民化政策
1930年代半ば以降の皇民化政策は、学校教育・神社崇拝・地域支配をそれぞれ強化することを柱として展開され、創氏改名とのちの徴兵制の導入によってその極致に達したといえます。
昭和7年(1937年)10月から、朝鮮総督府は、「私共ハ大日本帝国臣民デアリマス/私共ハ心ヲ合セテ天皇陛下ニ忠義ヲ尽シマス/私共ハ忍苦鍛錬シテ立派ナ強イ国民トナリマス」という「皇国臣民ノ誓詞」を制定、学校で児童生徒に毎朝斉唱させました。また、1938年3月には第3次朝鮮教育令が公布され、「内鮮共学」と称して日本と同じ国定教科書を使い、朝鮮語を正課からなくして日本語の常用を強制するようになりました。 (註:皇国=天皇の治める大日本帝国)
国民精神総動員と創氏改名
朝鮮総督府は、日中戦争期に一面(村)一神社設置計画を推し進め、また各戸にも神棚をつくらせ、「天照大神」の御札を毎朝礼拝するよう奨励しました。京城(現在のソウル)には天照大神と明治天皇を祭った朝鮮神宮を作り参拝を強要した。7月に皇民化政策を推進する機関として国民精神総動員朝鮮連盟が発足し、地方・学校・企業ごとにも連盟支部が組織されました。
皇民化政策の創氏改名は、昭和14年(1939年)12月、朝鮮総督府によって朝鮮民事令・朝鮮戸籍令などの改正として公布され、翌昭和15年(1940)年2月11日を期して施行されました。創氏は義務(法的に強制)、改名は任意とされましたが、現実には日本式改名こそ「皇民化の指標」とみなされて、有形無形に強制されました。また、氏設定(創氏)は、法的に強制されたものであったので、届け出がない場合も、従来の「姓」を日本語読みにしてそのまま新しい「氏」とされました(設定創氏)。
創氏改名は、皇民化政策の一環であり、徴兵制導入(昭和19年(1944年)から実施)を射程に入れた上で、戸主を中心とする家観念を確立し、天皇を頂点とする家の序列の末端に植民地住民を位置づけたと言われています。
朝鮮人は「朝鮮語」という民族固有の言語の使用を禁止され、先祖伝来の「姓」を強制的に換えさせられただけでなく、日本の国家神道と天皇崇拝を強制されました。
慰安婦
このブログで以前に取り上げた「慰安婦」は、その多くが朝鮮から「女子挺身隊」などの名目で連れて来られた20歳前後の未婚女性たちでした。国家機関(軍・内務省・総督府)が朝鮮を中心とする地域で、組織的に女性を集め、軍が「慰安所」の設置と運営に直接かかわるなど、政府機関・軍が直接に関与したということが、日本における「慰安婦」問題の特徴になっています。「慰安婦」にされた女性の総数は、8 万人とも1 0 万人ともいわれ、さらに多数にのぼったという推計もあります。
朝鮮人強制連行
もうひとつ朝鮮人を強制的に連行し、鉱山などで働かせた問題があります。この問題については私の理解が浅いので、問題の存在を挙げるにとどめます。
人種差別
私自身の見聞きしたところでも、朝鮮人に対する人種差別は非常にひどいものでした。その影響は現在でも明らかに残っています。
しかし、私には、この人種差別について系統的に述べる力はありません。もし書くとすれば職業上の差別、結婚の差別などについて資料があれば書くことができると思います。またそのような客観的な資料に残る差別ではない、日常生活上の差別もあり、文学作品から読みとる方がよいのかもしれません。
日本は軍事力を背景に、朝鮮(韓国)を併合して、植民地にしただけでなく、その後も過酷な支配により朝鮮の人々を苦しめてきました。現代の問題をついても、このような背景を理解したうえで考える必要があると思います。